 |
手術部全職員(手術部所属医師6名・看護師39名・臨床工学技師3名・清掃環境整備職員8名・事務職員2名)を対象とした。医師は病院の全職員を含めると膨大な数にのぼるため、手術部専任で日常手術部の運営に関わっている所属医師6名のみを対象とした。手術部において、医師は外科系13科と麻酔科が手術に業務し、看護師は手術患者さんの看護や手術環境において専門的業務を行う。臨床工学技師は手術部内の空調・照明などの管理から大小手術機械の管理に至る専門的業務を行い、清掃環境整備職員は手術部内の日常の清掃や手術器械の洗浄・消毒などを行っている。事務職員は直接手術患者さんに関与することは多くはないが、業務部署は他の職員と共通の空間である。
手術部での業務上の安全を考える場合、①安全に患者さんが手術を受けられるための対策・②一般の北大職員としての安全対策・③手術部に特有な職員安全対策、の3つの項目が挙げられるが、今回、後者二つの普遍的業務安全と特異的業務安全について、以下の形式により全職員に業務安全上のヒヤリハット事例のアンケートを行った。 |
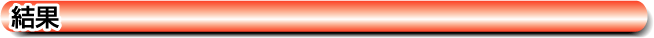 |
| 全職員58名(手術部所属医師6名・看護師39名・臨床工学技師3名・清掃環境整備職員8名・事務職員2名)にアンケートを依頼し、回答率は全体で93.1%(54/58)であった。医師以外の職員の回答率は100%であった。以下、職員機能分類を、順に医師・看護・技師・整備・事務、と省略する。 |
|


