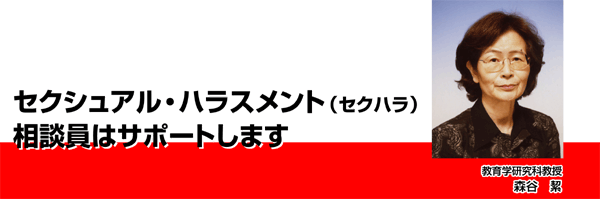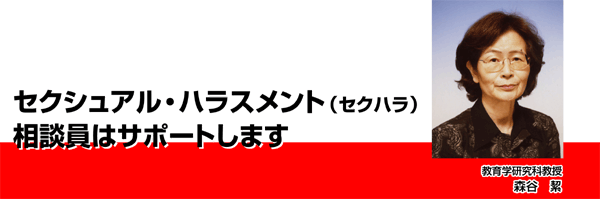皆さんは「男女共同参画社会基本法(1999年制定)」という法律をご存じですか?男女共同参画社会の実現を21世紀の日本における最重要課題と位置付け,社会のあらゆる分野で男女が共同して参画することを目指している法律です。目標(理想)としての基本法に対して,現実には伝統的で歴史的重みを持った「男女の性役割意識」が男性にも女性にも重くのしかかる過渡期を私たちは過ごしています。理想と現実の間で揺れ動いているのが現代を生きる私たちの姿であると感じています。
当然のことながら若い世代では,異性として惹かれあうことの多い男女間の問題として生じる「セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)」相談員を,私が引き受けてから4年目になります。この期間,「相談に来られた(る)方の立場に立って」を基本として,話を聞き,解決に役立つように努力をしてきたつもり−−です。相談員は原則として,複数(2人)で対応することになっています。これは,個人的で主観的な対応になったり,記憶違いを防ぐための措置です。しかし,相談に来られる方の希望によって,最初は1人でお聞きしてから,複数で対応する様にしたことも何度かあります。現代社会に根強い「男女の性役割意識」から,女性が被害者となることが多く,また体力的に劣ることの多い女性が男性の暴力的な被害者になることもあります。セクハラ相談としては女性からのものが多いのが実情であり,現在のセクハラ相談員制度の存在意義は被害にあった(と考える)女性を守ることが第一の役割です。女子学生の一部では就職の難しさ等から(?)結婚願望が必要以上に強いと感じることもありますので,生き方としての「ジェンダー学」が教養科目として必要だとも感じています。自己信頼(効力)感を高めることによって,セクハラが少なくなるかもしれないと期待しており,青年男女の自己効力感を高める課題は重要だと考えています。私は人生を長く生きてきたものとして相談員を引き受け相談にのってきましたが,やはりこの分野を専門としている方を「専任の相談員」として配置すると相談もし易くなり,併せてジェンダー教育にもあたって頂くことが北大の今後のために重要と考えています。
かくして現状では万全とは言えませんが,セクハラ相談員制度があることによって果たしうることは多様です。「男女共同参画社会基本法」が制定されても,男性に比して女性(女子学生を含んで)にかかるストレスの多いのが現代社会です。被害にあったと考えられる女性が1人で孤独に自分を責めて,精神的な後遺症に悩み,治療の過程でセクハラが浮かびあがってくることも多いのです。被害にあった女性の場合,自分を責めて自分の落ち度を探してしまうことが多いようです。どうぞセクハラ相談員を活用してください。ご一緒に考えますし,プライバシーは充分に配慮されていますので−−。 |