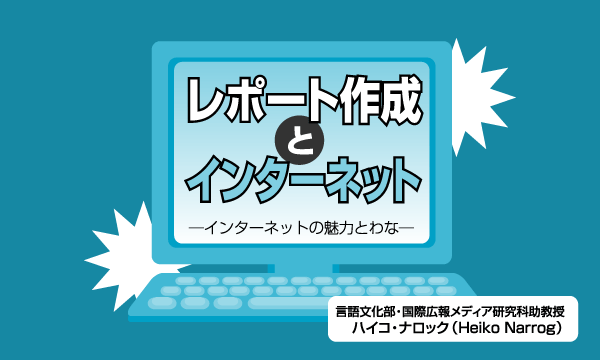
| 私は,全学教育でドイツ語を教える言語文化部の教員です。ドイツから来ましたが,今北大で6年目です。日常的な仕事をこなすのにインターネットを欠かすことはできません。文献を調べる時,翻訳する際に訳語を調べる時,外国語の表現の使い方を確かめる時,キーワードを探す時など,あらゆる場面で時間を短縮させるのに役に立ちます。5年前ぐらいはまだそれほどではなかったですが,よく考えると,今はもうインターネットに依存さえしているかもしれません。インターネットを使わない生活は,もう想像できません。 皆さんも,今は日常生活ではインターネットより携帯メールを盛んに使っているかも知れませんが,やはりインターネットを使いこなせば,勉強がより効率的に進められると思います。インターネットで私たちの一番の味方は総合サーチエンジンで,その中でも現在一番優れているGoogleです。次には,アルクの英和和英辞典をはじめとする辞典類ではないでしょうか。無料で大型辞書と同等の内容を提供してくれます。そして,北大図書館の電子ジャーナルも強力です。 どんなときにインターネットが一番役に立つかというと,これはレポート・論文作成に違いありません。あるテーマについてその概要や主な参考文献を調べるには,昔図書館を使って必要とした時間に比べて,半分以下でしょう。しかしここで,インターネットを使ったレポート作成について,2点注意したいと思います。 一つは,内容に関するもので,インターネットで提供されている情報は,必ずしも全てが信頼できる質の高いものではないし,また中立的・客観的なものでもありません。特に後者に関して,この2〜3年アメリカで見られる傾向としては,中立的な「研究所」などを装って,実はそういう形で自分の思想や価値観,信仰を広めようとする政治団体や宗教団体が急増しているようです。日本は,インターネットに関して様々な面で遅れているので,まだそれほどではないかもしれませんが,これからは注意が必要です。 もう一つは,「不正行為」のわなです。インターネットで簡単に調べた情報を,その情報源を明らかにせずに,自分のものとしてレポートなどに出すことが可能です。これは学問の根本に関わる問題で,人から借りた知識・考察と,自分自身がそれに付け加えた知識・考察を明確に分けなければなりません。様々な程度がありますが,一番ひどい場合,インターネットで見つかったエッセー,小論文などをまるごとワードファイルなどにコピーして,自分が書いたレポートとして提出するケースさえ北大で実際に起きています。これは「盗作」と言って,人の車を盗んで自分の買った車であるかのように人に見せたり,あるいは売ったりすると同じことです。ただしこの種類の盗みは,物質的な財産ではなくて,知的財産を対象としたものです。 こうした盗作は,インターネット以前にもありました。昔は,図書館である本の一部を書き写してレポートとして出すこともあったようです。書き写す分,多少勉強にもなったでしょうが,今は「コピー」「ペースト」で中身を見ないでも済みます。反面,盗作が簡単になった代わりに,その摘発も簡単になりました。盗作したものがまだインターネットに残っているので,教官も探せば,割と簡単に見つかります。 大学でよく起こる2大不正行為として,「盗作」の他に,試験時の「カンニング」もあります。不思議なことに,北大では「カンニング」だけを不正行為として正式に扱い,学生が試験時に捕まった時には停学(実質的な留年)の処分になります。私が思うに,これは甚だ不公平な対応の仕方です。カンニングには行き過ぎた処分も見られる一方,「盗作」には目をつぶっているようです。 その原因は何なのでしょうか。まず第一に,もしかしてここには少しばかり文化的な背景もあって,よく知られているように,「知的財産」や「著作権」という概念は日本を含む東洋にはもともとあまりなかったようです。私が知っている学術分野では,一時代前までの学術論文には,先行研究から借りた知識・アイデアを,それとしてあまり明確にしないで,自分の発想とも思わせる盗作気味の論文も,日本には少なくなかったように思われます。 しかし,これよりも大きな原因は,運営の都合にあると思います。個々の不正行為の重さに応じた対応をすることになれば,個別の場合をどう判断するかは,大きな組織にとってややこしそうになります。つまり,公平さを重視した柔軟・多面的な取り組みが教官・事務側には負担になることが,おそらく一番大きな原因であろうと察しています。しかし,アメリカなどではちゃんと公平な個別の対応ができているので,北大でも不可能なはずはありません。 最後に付け加えたいのですが,以上のようなことを別にしても,皆さんも北大である程度の時間を過ごせばわかりますが,大学には,学生に対しても,一般的にも,不公平なことや理不尽なことが少なくありません。また,「不正行為」に関わることの場合のように,その原因はたいてい「組織の都合」と「習慣」にあります。今の国立大学は「お役所」的な体質がとても強いように思われます。「一人歩きした組織」という感じのものです。今年から法人化すれば,「お役所」的体質が多かれ少なかれ「企業」的体質に変わるのでしょうが,大学にとって「組織の都合」「組織の利益」が第一になって,原点であるはずの学生の勉学や,教員の教育と研究が第二,第三になるという傾向は,むしろ更に強まるに違いありません。長くその組織の中にいる人たちには,その組織の「特殊性」,そしてところどころに現れる「非常識さ」が見えなくなります。皆さんはまだ新鮮な目を持っているので,ただ受身にならないで,ぜひいろいろと大学に積極的に提言してください。 |