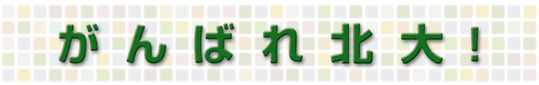|
私は現在,愛知県岡崎市にある基礎生物学研究所というところで,ショウジョウバエを使った発生遺伝学の研究をしている。基生研という名前でも知られるこの研究所は,日本でも有数の恵まれた設備と優秀な研究者を集めた研究専門機関だ。私が今取り組んでいる課題は,我々が見つけたTONASという核タンパク質が,如何にして高等生物の遺伝情報を引き出すために使われているのかを明らかにすることである。自分にとっての研究のモチベーションは「自分で見つけた何かが,自然科学の教科書の一ページに載るようなトピックの一つとなる」ことへの期待である。研究生活をしていると,日々,大なり小なりの発見がある。それらの多くは,勘違いであったり,他の誰かが既に見つけたものであったりするのだが,その過程にワクワクしたり,感動したりできることが,自分がこれまで研究を続けてこられた理由だと思う。研究は,長く続けるべきもので,自分自身の足下にこそユニークな発見が埋もれている,と信じている。自分自身の足下を気長に掘り続けられるのも一つの才能である。
私は今から24年前に北大理Ⅲ系(=生物系)に入学した。大学で野生動物の研究をしたかった私は,非公認サークル「ヒグマ研究会(以後,クマ研)」というところに入った。当時私は,河合雅雄,畑正憲,コンラート=ローレンツとか,動物行動学に関する本を好んで読んでいて,頭の中にはそれなりの動物研究のイメージが描かれていた。ところがクマ研に入ると,いきなり天塩演習林の飯場(一応,十六線研究所という名前だった)へ連れて行かれ,春の腐れ雪の上をクマの足跡を追って連日歩かされることになった。ビニール袋に飯とふりかけ,梅干しを適当に詰めて(ビニ弁と称していた)適当に握ってザックにいれ,それを昼飯にした。ハシはその辺にあるクマザサをナタで切って調達した。同期生でクマ研に入ったアウトドア少年たちは,一年後には殆どいなくなっていた。クマ研がプロの研究者の集まりかというとそうではない。一部の上級生とOBは動物学や森林生態学のプロの研究者だったが,その他多くは只の学生で,授業の合間を山歩き(=研究)にあてていた。熱心な何人かは,留年を顧みず授業をサボって活動していた。クマ研がプロの研究団体ではないというのは,いま研究者になった私の結論であるが,当時のメンバーは,研究者とは何か?ということをよく議論していた。いま考えると,クマ研には素人研究者であるが故の楽しさが溢れていた。
私が,本当の意味での研究生活のスタートを切ったのは薬学部だった。教養の成績が今ひとつで,クジ引きみたいに決められた学部だったが,神経生理学を研究しているK教授に巡り会って,卒研生として入れてもらった。K教授は懐の大きい魅力ある人物で,大学院の入学試験が終わった直後「気晴らしに山へ行ってもいいか?」と聞いたところ「いいよ」と二つ返事で,1週間程休みをくれた。卒研から博士修了まで6年間研究して,5つの論文を出すことができた。私が,気ままに実験して出したデータをK教授が形のあるものにまとめてくれた。K教授は,私に本当の意味での研究とは何かを教えてくれた恩師である。
私はその後,米国のジョンズホプキンス大学で3年間ポスドク(博士研究員)生活を送った。ポスドク時代から,研究テーマはショウジョウバエの分子発生遺伝学へと変わった。分野はまさに,遺伝子ハンティング競争のさなかで,ポスドクは常に結果を出すことを求められていた。私自身は幸運にも恵まれ,いくつかの遺伝子を見つけ,それらにオリジナルな名前を付けることができた。
最後に,研究者を目指す北大生へのメッセージを贈りたい。学部の4年間は,研究者の前段階で,本当の戦いの前の準備段階である。受験勉強で蓄積した,役に立たない知識の多くを綺麗さっぱり忘れ去ってほしい。いろいろな人に巡り会って,それまでにない体験ができるのが大学の良さである。人と知り合うための努力を惜しんではならない。自分が何をしたいのか,自分は何が得意なのか,この二つをよく考えて次のステップの選択をしてもらいたい。大学院の5年間なり6年間は,その人の研究人生を決定的に左右する大切な期間である。ある意味,研究とは一子相伝の技術習得みたいなもので,手取り足取り教えてくれる指導者が必要である。優秀な研究者に張り付いて,その人の知識の全てを会得する覚悟が必要である。これぞと思える研究者,研究室を探し出してもらいたい。研究を遂行するためには,専門とする分野の理論体系を理解して,最新の生きた知識を知ることが必要である。とても,片手間でついて行ける世界ではない。野球に例えると,高校野球レベルの選手がいきなり,メジャーリーグの下部組織の練習に参加するようなものだ。しかしながら,必死に努力する若者は必ずそのレベルについていけるようになる。また,優秀な研究者は,そのような若者の力が自分の研究の発展には必要であることを知っていて,親身に助けてくれるはずだ。Ph.Dを取った後は,北大生らしいおおらかさを武器に,シベリアなり北太平洋なり自由に飛び回って,新しい研究分野を創ってほしい。野心を持って!
|