
| 本学には化学薬品を使用している研究室が多く,学生実験でも多種類の薬品が使用されています。化学薬品には危険,有害なものが多いため,安全な取り扱いや適正な管理が「労働衛生安全法」や「毒物及び劇物取締法」等の法律で義務付けられています。使用後も,「化学物質排泄把握管理促進法」に基づくPRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度によって,354物質については環境への排泄量や廃棄物としての移動量を行政に報告しなければなりませんが,平成15年度調査によれば,本学では329分野がPRTR調査の対象になっています。また本年4月から,本学のどこに,どのくらいの毒物や劇物,PRTR対象物質があるかを常時把握するため,各研究室の端末とつながった「化学物質管理システム」が稼働しています。このように,管理面での改善が進んでいますが,薬品よる事故や健康被害の防止に大切なのは,使用者が個々の薬品の危険性や有害性を十分に把握していることです。しかし,多彩な薬品の危険有害性情報を個人的に収集するのは難しいため,薬品の購入時に危険有害性情報も提供されることが望まれていました。もちろん製造販売業者も自主的な情報提供に取り組んできましたが,ILOなどの国際機関で検討が重ねられた結果,法的ルールとしての危険有害情報の提供が始まりました。たとえば平成13年からは,PRTR対象物質に製品安全データシート(Material Safety Data Sheet:MSDS)の添付が義務づけられました。これには危険有害性や安全対策および緊急時の対策などの情報が含まれています。同様の規定は労働安全衛生法や毒物および劇物取締法にも設けられましたが,まだ対象となる薬品は限られており,その拡大が求められていました。 一方,多数の化学薬品が国際的に流通しているにもかかわらず,関連する法律,危険有害性の定義,安全データシートやラベルなどが国ごとに異なっていることも問題となっていました。このため,10年以上も前から国際的な統一についての論議と準備がなされてきました。その成果が2003年7月の国連勧告「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals:GHS)」です。これは,世界的に統一されたルールに従って化学薬品を危険有害性ごとに分類し,その情報を一目で分かるようにラベル表示や安全データシートで提供するシステムです。GHSで分類・表示される危険有害性としては,爆発性や引火性などの物理化学的危険性16項目,急性毒性,発がん性,皮膚刺激性,眼刺激性,変異原性,生殖毒性,水生環境有害性などの有害性10項目があり,それぞれの程度に応じてシンボルマークと,「危険」や「警告」などの注意喚起表示が定められています。またGHSでは対象とする化学物質の数が大幅に増えます。2003年7月の国連決議ではGHSの世界的な完全実施目標を2008年とし,アジア太平洋経済協力(APEC)では2006年を目標にしています。 GHS情報は環境省や経済産業省のホームページに載っています。化学系の学生諸君は一度アクセスしてみて下さい。皆さんにとって今後の重要な情報の一つになるはずです。 |
|
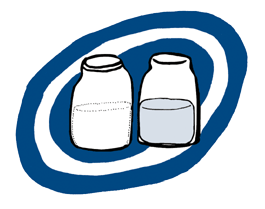 |
|
| 札幌キャンパス安全衛生委員会 三浦 敏明 |