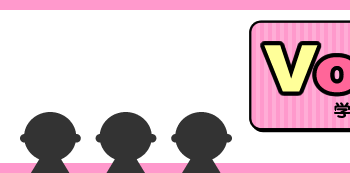 |
|
| 「高等教育機能開発総合センター」には,E棟1階の学務部事務室前とE棟2階・3階に投書箱「学生の声」を設置し,併せて「記入用紙」も備えています。 皆さんが疑問に思う事や改善して欲しい事など,この投書箱に寄せられた意見・要望は,回答(対応)を添えて,同センターE棟1階の「学生の声(回答)専用掲示板」に掲示しています。 以下,前回(第116号)以降に掲示したすべての「学生の声」を紹介します。 なお,今回の掲載に当たっては,読む際に分かり易くするため,掲示の「学生の声」(オリジナル)に,正確な表現への修正をしています。 |
| 【掲示日:平成17年6月28日】 農学部1年からの投書 Q 私は留年しているため,去年入学したときにもらったシラバスを使っています。しかし,担当教員等が昨年と今年では異なるのでインターネットでシラバスを見て今年の時間割を組みました。 ですが,オンラインシラバスは今年配布されているシラバスと内容が異なる点がいくつか見受けられます。特に対象クラスや学年が紙のシラバスとオンラインシラバスで異なっているものがたくさんありました。教務の方々は紙のシラバスの方が正しいという感じのことをおっしゃっていたので,紙のシラバスを学校に来て確認するという作業に追われて大変苦労しました。そもそも2年次以降はオンラインシラバスで確認することが多いと思いますが,このままではこれから先のことが思いやられます。オンラインシラバスは何やらミスらしきものがありますし,かといってその年度の紙のシラバスを確認するとなると,時間割を決定することにたくさんの時間を割かなくてはならないからです。 また,履修届の提出日直前はオンラインシラバスのアクセスが集中するためなのか閲覧できないことがありました。これもなんとかしてほしい点です。 そして,私はオンラインシラバスのミスについてシラバスの問合せ先である教務宛にメールしたのですが返信はおろかミスが訂正される兆しもありません。結局私が指摘した点はミスではなかったのかどうかそれすらわかりません。 今回オンラインシラバスの管理が行きわたっていないという印象を受けました。シラバスは学生生活の要の一つなのですから万全を尽くしてほしいと思います。現時点以上の対応が不可能ならば業者に委託することを望みます。現在どのようにオンラインシラバスが運営されているかもあわせてご回答願います。 |
| (学務部学生支援課からの回答) A 今回投書頂いた件,大変ご苦労とご迷惑をおかけして申し訳ありません。最初に,ご指摘頂いた問題のうち,「必要とされるシラバス冊子が渡されなかった」こと,「オンラインシラバスの不備」の2点について回答します。 まず,「必要とされるシラバス冊子が渡されなかった」ことですが,休学者・留年者に印刷シラバスを配布するかどうかは各学部によってまちまち(渡さない学部もあるようです)です。シラバスは毎年内容がまったく異なっており昨年度のものは使用できない(少なくとも昨年のシラバスを参照するようにという指示は間違い)ことから,必要な方には配布するように各学部に依頼しておきますので,印刷シラバスの件については各学部教務係に相談してみて下さい。 次に「オンラインシラバスの不備」についてですが,現在のシラバス作成の仕組みと問題点,それに対する改善の順で説明します。 まず,シラバスは授業を担当する教員が責任を持ちます。全学教育科目については例年おおよそ800人の教員が2,400科目について各々シラバスを作成します。教員はシラバスを電子データとしてデータベースに登録しなければなりません。 現状では教員のシラバスデータは種々の事情から教員の「研究業績」の一つと扱うことになっており,研究業績データベースに取り込まれます。このデータは教員本人しか編集出来ません(事務は編集できない)。またこれらシラバスデータは「研究業績」なので,時間割情報やクラス・学年情報とは連動していません。このため教員が題目や対象学年・クラス等を間違えて入力することが少なくないのも事実です。 従って,事務側ではシラバスデータを編集できませんので,例年,各教員に対し次のように正しく入力するようお願いしています。 ・個々に,シラバス入力の前に担当予定の授業に関する正しい情報(題目,対象学年,クラス等)の一覧表を送付し,それに基づいて入力するように依頼する。 ・入力シラバスの総チェックを行い,間違いについては修正を依頼する。 ・印刷シラバスは間違いを正しい情報で上書きして作成する。 以上のような状況により,教員が作成した内容を事務がチェックして作成する印刷シラバスと,編集・チェック出来ないオンラインシラバスとの間で正誤や差違が生じています。 これらを踏まえ,根本的な対応策を次のとおり検討しています。 ・シラバスデータを研究業績データベースより切り離し教員だけではなく,教務事務も編集できるようにすること。 ・サーバの増強やCD−ROM形式のシラバス配布。 これらの実現には,研究業績データベースの運用方法を変更することや,新たなシステムの構築など大学全体に関わる課題であり,改善までには少なからずお時間をいただくことになりますが,ご指摘頂いたとおりシラバスは学生生活の要ですので出来るだけ早急に改善したいと考えています。 最後に,シラバス情報システムの運用管理面とアクセス不可に関した照会事項について,回答します。 本システムの運用管理は,学務部教務課が担当しており,新年度の登録関係の業務を担当するとともに,システムを再評価のうえ,変更を要する場合には,システム管理者である情報基盤センターに依頼する業務を担当しています。また,利用者からの問い合わせの窓口にもなっています。 今回,照会いただいた「アクセス不可」については,具体のアクセス日時を確認しない限り,詳細の調査はできませんが,システム管理部署に照会したところ,長時間アクセスできなかった記録は,確認できませんでした。ただし,4月7日(木)から4月14日(木)までの期間,学内においてウイルスメールが蔓延した時期があり,それらの影響を受けて,学内のネットワークの障害が発生し,シラバスの検索に時間を要し,タイムアウトエラーにより,接続できない状態が短時間起きたのではないかと考えられます。 なお,電子メールによる照会の件については,ご照会頂いた内容の電子メールが届いていないので,調査したところ,今年に入ってからアドレスを変更した際に,シラバスに関する照会欄のアドレスを入れ替えるのを失念していたことが判明いたしました。ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。本件は,直ちに変更しましたので,ご容赦下さい。 今後は,学生の利便性を第一に考えたシステムとして改善を図る予定ですので,今回に限らず,今後とも利用者としての貴重なご意見等を頂ければ幸いです。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成17年7月4日】 理学部1年からの投書 Q 全学教育の講義に関して意見があります。例として,自分の属しているドイツ語のクラスについて述べさせてもらいます。 私は●●●●に所属していますが,この担当教員からは学生に対する配慮が微塵も感じられません。問題に対する答えをまちがえると,それだけでその学生を厳しく問い詰め,チェックし,次の授業でもしつこくその事を言い続けています。間違いを指摘するだけでよいものの,わざわざ黒板に出て人前で補習をやらせるこの授業方針にはまったく感心させられない。また,教科書の内容にまったく触れていない状況で内容に関する問題をやらされ,スペリング1つ誤るだけで上と同じことをやらされる。ドイツ語などは我々にとってまったく基礎素養のない科目で予習など不可能であり,同時に講義が唯一の学習手段であるにも拘わらずその講義に問題があるというのは,高い学費を払っている学生にとって,とても納得できることではない。毎回の講義が苦痛でしかなく,できることなら教員を変えていただきたいとさえ思う。彼の見せしめ的強制的な講義スタイルは,自由な学風を売りに出しているという北大にそぐわないであろうし,そもそも中学・高校と何ら変わらず,大学らしさすらないと思います。知人の話を聞いていても,同じ様な不満と不安は多々聞かれます。 この様な状況に置かれた学生から言えることは,大学側にはもっと「教員としての技術,資質」を持った教員を割り当てて欲しいということです。某教員は,「ここ,俺の分野外だからさ・・・」と逃げる様なことをしていましたが,これは学生の不安・不満を大きくするだけです。また,いちいちそんなチェックはできないというならば,必習科目も教員を選択できるようにすべきと考えます。 中には1年生が高校まででどの程度の知識があるものか調べてくださる方もいらっしゃいます。そこまで親切にしてほしいとは要求しませんが,もう少し初学年への講義ということをよく考えてほしいものです。少しでも学生の目から見た全学教育の現状が伝われば幸いであると同時に,大学側がこういった事態を軽視せず,学生のために具体的対応を施してくださることを期待しています。 |
| (ドイツ語担当科目責任者からの回答) A まず当該の授業に関してですが,担当教員との話し合いの結果,この授業における授業方針に関して今一度良く検討して改善すべき点は改善したいとの返答を得ました。教員側の厳しい態度は,多くの場合授業の成果を願う熱意に基づくもので,この場合はその熱意が強くなりすぎたのだと思います。ドイツ語教育系としましては,今回の問題は学生と教員とのコミュニケーションにある,つまり,教員側が学生側の意向をつかめなかったと考えます。授業の方法に関しましては,ドイツ語教育系としては一定の方式や枠組みについて申し合わせを行っておりますが,実際の運用に関してはある程度の柔軟な対応が不可欠になります。従って,実際の授業において問題が生じた場合は,その都度ケースバイケースで対処するしかありません。そのためにも今後はいっそう相互のコミュニケーションを強めるようはかりたいと思っております。もし授業に対して疑問などを抱いたなら,まず担当教員かドイツ語の科目責任者に申し出てください。 教員の自由選択制と授業チェックは,実施するとなると全科目に適用しなければならず,それには事務的な処理能力の問題ばかりでなく,基準の制定に大きな問題があり,現時点では現実的だとは思われません。授業スタイルなど具体的な基準をたてにくいことがらに不完全な基準をたて,それを全教員に強制すると,それこそ授業の硬化と北大の自由な校風に背く事態をまねくおそれがあると思います。いずれにせよこれらの問題はドイツ語教育系だけで論じられる問題ではありませんので,現時点で明確な返答はできません。 |
| 【掲示日:平成17年7月6日】 農学部3年からの投書 Q 先日の要望(シラバス配布の件)に回答いただいた者です。やはり,学部2年生の方が講義を選んだり(教科書を買ったり),実際に講義を受け始めるので,シラバスを利用する機会が多いです。 webシラバスだと,まずインターネットに接続して,その後に印刷しなければ使えないという点で使いづらいので,1年生のときに「えつらん」するのはwebで,2年で使うのはシラバスの方がいいと思うのですが,どうでしょうか。 |
| (農学部からの回答) A 前回,回答したようにシラバスを1年次に配布しているのは,新入生にその時点で農学部における講義内容全体に関する情報をまず提供することの他,2年次進級時の学科分属の際の資料として活用できるようにとの判断によります。 進級後は,北海道大学ホームページ(http://www.hokudai.ac.jp/)で閲覧する他,現在も教務係窓口において閲覧できますが,農学部図書室にも置いて閲覧出来るようにします。農学部図書室へは今年度から配置しますので,利用して下さい。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成17年7月6日】 文学部1年からの投書 Q 「日本語の歴史」の授業の進め方について 1.よいレポートの基準がわかりません。当初レポートはどんなものでもいい,と言っていたが,成績はレポートの評価だと言う。また,授業中に「いろは歌の暗号の類の記述は評価しない」と言った。設定されたテーマに関係した事柄なのに,これではレポートは「なんでも」良くないではないか。 2.授業について,6/13の授業を例にあげると,最初の20分,何の説明もなしに参考資料の解説をしていた。もっと,体系化した授業をしてほしい。(何の話をするのか,何に関する話なのか説明してから語り始めてほしい) 3.出席のつけ方。現状では,最終回だけに来て○をつけても全て出席した人と区別がつかないのではないか。 |
(歴史の視座・日本語の歴史担当 宮澤 俊雅 教授からの回答) |
| 【掲示日:平成17年7月11日】 文学部1年からの投書 Q 私は文学部の学生です。図書館の本の貸し出し冊数の上限を増やすことはできないでしょうか。あまつさえ,札幌市の図書館の最大貸し出し冊数が4冊という全国的に極めて珍しい状態―私は昨年,千葉県市川市に住んでいましたが,市川市立図書館は本の貸し出し冊数は無制限でした―である上に,社会へ頭脳集団を輩出する任を背負った大学,その図書館の本の貸し出し冊数が(学部生の場合)上限5冊とは,少なすぎやしないでしょうか。 貸し出し冊数の上限を増やすことで生じる問題点として,本のストックが減ることや,焦付きになることが考えられます。しかし,この問題は,例えば,通算で100冊以上貸りた人にのみ,一度に貸りられる冊数の上限は10冊,200冊以上は15冊,のように,たくさん貸りた人―つまり,返済能力が高く,回転率の高い人―がよりたくさんの本を貸りることができるようにすれば回避できると思います。 いろいろとまだ問題もあると思いますが,ぜひよろしくお願いします。 |
| (附属図書館からの回答) A 図書館の貸出冊数につきましてご意見いただきありがとうございます。 図書館では,教員,大学院生および学部生により貸出冊数の上限が異なりますが,開架図書に関しましては一律5冊までとしています。(ちなみに学部生の貸出冊数は本・分館それぞれ開架5冊,書庫5冊で両館あわせて20冊借りることが可能です。)これは,ご指摘のとおり開架閲覧室の所蔵冊数が10万冊ということで,より多くの学生さんにいろいろな本を提供したいという観点から5冊までとしております。実際に現状でも貸出中の図書の予約が多く,これ以上冊数を増やすと他の利用者に迷惑が掛かることが懸念されます。 また,ご提案のありました通算の貸出冊数により上限冊数を決めることにつきましては,通算の貸出冊数が少ない方にもより多くの本を借りていただきたいと考えていますので多い方のみ優遇することはむずかしいかも知れません。どうぞご理解下さいますようお願いいたします。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成17年7月11日】 水産学部2年からの投書 Q 英語の授業やTOEFL,TOEIC対策としてCall教室をよくしています。英語学習に大変便利なシステムだと思うのですが,函館キャンパスで使用できないのが残念です。他学部の学生はCall教室へ足を運ぶことは難しくありませんが,水産生はほぼ不可能です。英語力が必要なのは水産生も同じです。どうか函館にCall教室を作って下さい。 それが無理ならNETアカデミーやSmart-HTMLの使用ができるよう,せめてして欲しいです。 |
| (水産学部からの回答) A 札幌キャンパス情報基盤センター南館等に設置されている,自習・補習等へ利用できるコンピュータと同様のものが,函館キャンパス(情報処理室B)にも設置されています。 「Netアカデミー」については,授業で利用した学生(アカウントを取得した学生)について引き続き函館キャンパス(情報処理室B)設置のコンピュータでも利用可能です。 また,「Smart-HTML」については,全学年対象として函館キャンパス(情報処理室B)設置のコンピュータで利用可能です。 |
| 【掲示日:平成17年7月14日】 無記名者からの投書 Q 英語教員の●●●●さんについて申し上げたいことがいくつかあります。 1)定期テストにおいて,授業にて取り扱っていないものを試験しようとしておりますが,これは定期テストの性質,つまり授業で教えられたことの理解度の確認という目的から大きくはずれるものであり,そのような試験は許されざるものではないでしょうか。確かに定期テストにおいては,教員の側に裁量があるという意見もあるでしょう。しかし他のクラスと必修授業においての成績評価に著しい差が見られるだろうことは明らかであります。なぜなら誰もこのようなテストの性質をはき違えたテストをしないからです。 2)授業の欠席取扱いについて,他のクラス,他の学校との差があるのは,一目瞭然です。なぜなら普通は,授業の半分以上経過した時にその場にいないことが欠席となります。半分以上全部未満でも遅刻もいただけます。しかしこの人の場合だけは,かなり特殊です。たとえその場にいて名前を呼ばれた時に返事しても,本人がきこえないと,いえば欠席になります。一度その決定がなされると,出席していると本人に知らせても,その裁定がくつがえることはありません。返事をした時にたまたま,誰かのイスの音とかぶったりしても,その裁定が変わることはないのです。欠席について,このような取扱いをするのは,他の授業との間に著しい不公平が生じます。なので学校側には,この問題について早急に調査を進めることを求めます。よろしくお願いします。 |
| (学務部教務課からの回答) A まず定期試験についてですが,授業で扱った部分から80%程度,授業で扱っていない部分から20%程度を出題する旨,初回の講義で説明してあります。授業で扱っていない部分に関しては,あらかじめテキストの出題箇所を指定し,更に「辞書以外の持ち込み可」としております。 ほぼ毎回授業の最後に小テストを行い(主に学生の予習の状況を確認する内容です),これを成績評価の重要な要素としているのですが,定期試験はこの小テストで良い成績がおさめられなかった学生を救済する,という色彩が強いもので,上記の様な内容にしております。 次に出席に関してですが,返事をしているのに欠席にすることなどありません。基本的に小テストの返却が出欠確認の代わりとなっていますが,たとえ返事が聞こえなくとも,答案を教壇まで受け取りに来た時点でわかりますし,前回欠席の学生については,小テスト返却後,名前を呼び上げますし,万が一そこで呼び落としがあったとしても,学生本人が申し出るはずであり,特に問題が生じることはないと思います。 例年のことですが,何週もあとになってから,実は出席していた,などと申告して来る学生がおりますが(特に欠席の多い学生),上記の様に出席を確認しておりますので,出欠の確認に不備が起こることはないはずです。 基本的に,きちんと予習をした上で出席をし,授業に真剣に取り組んでいれば,良い成績が取れるはずで,他の講義と比べて不公平が生じることはないと思います。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成17年7月26日】 文学部1年からの投書 Q 講義でレーザーポインターを使う先生が多いが,たまにスイッチを入れたままのレーザーポインターを聴衆に向けてくる先生がいる。目に入ると危険なので気を付けて欲しい。また,講義終了後,レーザーポインターで遊んでいるT・Aがいたが,これも危険なのでやめて欲しい。 |
| (学務部教務課からの回答) A 大変危険ですので,さっそく教員とT・Aに強く文章により注意喚起しました。 |
| 【掲示日:平成17年7月26日】 無記名者からの投書 Q 試験の通知を,掲示だけでなくプリント配布でも行っていただけないでしょうか |
| (学務部教務課からの回答) A 試験掲示の混雑については,かねてより改善の余地ありとして検討を続けています。改善案としておおむね次のことを考えています。 ・掲示を増やす(別の箇所にも同じ試験日程掲示を行う) ・試験日程のプリント配布 ・日程のホームページ掲載 掲示を増やすことについては掲示場所が限られているため実現が困難です。プリント配布やホームページ掲載については,「情報の更新」が問題となります。試験日程公表後の試験追加・試験日変更について「どのように確実にお知らせするか」が頭の痛いところです。 かつて試験的にホームページに日程を掲載したことがありますが,変更を見ていない学生や見落とす学生がかなりいて,試験の実施に少なからぬ影響が出たことがあります。加えて技術的・セキュリティの問題もあって結局のところ実施に至っておりません。とはいえ,混雑しているのは事実ですし,実施する試験数も多いのでなんらかの対応をしたいと考えておりますのでお時間をいただきたく思っております。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成17年8月4日】 法学部1年からの投書 Q 休講,補講,試験情報を自分のIDからPCに入った(ログイン)段階で「あなたへのお知らせがあります」みたいに,すぐわかるようなシステムを作って下さい。それなら,前日の夜に毎日チェックができて,いちいち掲示板にいかなくていいんで。 実際,前いた関西大ではそんな感じでしたので,ムダな時間が省けて便利でした。それとじゅうたんをしいた教室を作って下さい。寝転びながらでも,先生との距離が近いんで,より活発な講義(ゼミだけ)になると思います。見た目は悪く感じますが,中身は充実すると思います。他の大学に先駆けてやることにより,又,アメリカ(カルフォルニア)のような雰囲気(のびのびとした)は,きっとクラーク博士の求めたものにも近づくはずです。 |
| (学務部教務課からの回答) A 休講については,北海道大学ホームページより閲覧できるようにしていますのでご利用下さい。補講,試験情報については教員の都合により変更等が直近までありますので,現時点ではホームページ等で閲覧できるようにすることは考えておりません。 教室へのご要望ですが,施設等の予算が限られている上に,他の設備で優先すべきものが多々ありますので,ご要望にお応えすることは今のところ無理ですが,あなたのご意見は関係する教員及び職員に伝えました。 |
| 【掲示日:平成17年8月9日】 無記名者からの投書 Q テスト期間中,カンニングを多々みかけます。先生も気づきません。私たちも,もし目ゲキしても証拠がないさらに知らない人だったりして,何もすることができない状態です。 こっちはテストにむけて勉強を一生懸命がんばっているのにもかかわらず,カンニングした人たちだけが楽していい点とっていると思うと,腹立たしくて仕方ありません。 もう少し,きびしくしてくれませんでしょうか?(テスト中はふで入れしまうなど) |
| (学務部教務課からの回答) A 投稿の件,大変残念かつ悲しく思います。試験監督の先生方にもお伝えしました。 そもそも大学とは,自ら進んで学ぶべきところです。不正によって良い成績を得ても,それが何になるのでしょうか。このような不正は,本学の教育研究の理念である「全人教育」と相容れないことは明らかです。 不正行為に関しては,掲示文及び各教室の警告文,受験者数に応じた監督員の増強等,未然の防止に努めておりますが,最終的には学生のみなさんのモラルの問題です。 また不正が発覚した場合は,必ず停学等の処分を受け留年となり,進級・卒業が延期になります。金銭面においても多大な負担がかかります。今までも不正を行った学生が留年になっています。ほんの軽い気持ちで行ったことでも,取り返しのつかない事態を招くということを充分認識してもらいたいと思います。 今後とも大学としても未然防止に一層努めていきたいと思いますが,万が一試験の際に他の学生の不審な行為に気づいた時は,その場で監督員に申し出てください。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成17年8月23日】 文学部1年からの投書 Q 第二外国語に関して,必修にする意味がわかりません。多くの学生が,第二外国語の負担のために,英語がおろそかになったり,好きな勉強が出来なくなっています。国際人を目指すためには,必要だとか,論文を読むために必要だという理由もわからなくはないです。 しかし,本当に必要だと感じる人は学べばいいわけで,全員に強制する意味はわかりません。必修ではなくて選択にすべきではないですか? |
| (文学部教務委員会委員長からの回答) A 文学部の根本的な教育理念は,わたしたちのあらゆる認識行為の基礎にある「ことば」の涵養にあります。 ことばに対する感性や深い知識・理解力は,母国語(日本語)のみならず,多様な外国語の修得過程を通してよりいっそう効果的に学ぶことができます。それは,個別の学問分野を理解するためにも,また,国際化やグローバリズムに直面している現代社会において,君自身が,積極的に自己を表現し,他者を理解していくためにも不可欠な基本的能力です。第二外国語は,たんに「国際人を目指すひと」,英語以外の「論文を読むひと」だけが学べばよい,という問題ではないと考えています。 学生時代は,時間がたくさんあると思いますので,大きな視野と度量でいろいろなことを学んでください。 |
| ▲ページトップへ |
