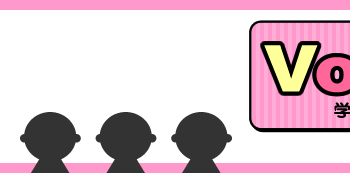 |
|
| 「高等教育機能開発総合センター」には,E棟1階の学務部事務室前とE棟2階・3階に投書箱「学生の声」を設置し,併せて「記入用紙」も備えています。 みなさんが疑問に思う事や改善して欲しい事など,この投書箱に寄せられた意見・要望は,回答(対応)を添えて,同センターE棟1階の「学生の声(回答)専用掲示板」に掲示しています。 以下,前回(第119号)以降に掲示したすべての「学生の声」を紹介します。 なお,今回の掲載に当たっては,読む際に分かり易くするため,掲示の「学生の声」(オリジナル)に,正確な表現への修正をしています。 |
| 【掲示日:平成18年2月8日】 法学部(学生未記入)からの投書 Q 1月13日に高等教育機能開発総合センターのトイレの水が急に流れなくなった原因はどうしてですか。使えないなら放送で連絡してほしかったです。トイレのジェットタオルありがとうございます。 |
| (学務部学生支援課からの回答) A この日は,午前10時頃トイレ等に使用する雑用水系の給水異常が発生しました。原因を調査した結果、午後3時過ぎに井戸水を汲み上げる水中ポンプが故障していることが判明しました。井戸用水中ポンプについては、北海道に在庫が無く取り寄せとなり、復旧には一週間程度掛かる見込みであった。(1月19日取替済み)このため、飲料水系統の井水を雑用水系統の受水槽に入れるように資材の取り寄せ、人の手配等を行い、同日午後8時頃復旧しました。 井戸から汲み出された水は、一旦受水槽に入れそれを送水ポンプで送るようになっており、水圧の低下に伴い階高の高い建物(センター付近では)情報教育館や言語文化部において、上の方から出なくなることになります。ポンプが故障してから2時過ぎまでは水は出ていましたが、どの時点で出なくなるかは、予測が付きませんので敢えて放送等でお知らせしなかったものです。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成18年2月13日】 農学部1年からの投書 Q 農学部学生自治〜や、全学連〜という団体が、講義を行う教室にビラを置いていきます。教室は公共の場であり、政治的道具に使われるべきではありません。大学側ではビラを放置していくことに対して何も措置をとらないのですか。清掃の面から言っても、片付けるのが大変である以上は、根もとを断つ必要があると思います。活動そのものを否定しているわけではありませんが、場所は選ぶべきだと思います。 |
| (学務部学生支援課からの回答) A 教室へのビラ配りについてのご指摘をいただきありがとうございます。本学では「北海道大学掲示等に関する内規」により、団体又は個人が学内において印刷物等の配布行為を行う場合はその場所を管理する部局長に届出ることとなっており、高等教育機能開発総合センターもこれにより運用しているところです。しかし、本センターの教室は授業のある期間は午前7時に開錠し、授業終了後の清掃終了まで開放された状態で、学生団体等の印刷物の配布等に対し、各教室をその都度調査することは、人的に不可能な状況にあります。 ただ,学生が講義を受ける教室を気持ちよく使用するためのルールを守ることは当然のことですので、学生の皆さんが配布されたビラを事務室(学務部学生支援課学生相談係,高等教育機能開発総合センター2番窓口)に届けていただければ、配布した団体に高等教育機能開発総合センターとして注意いたします。 |
| 【掲示日:平成18年3月27日】 薬学研究科修士課程1年からの投書 Q 就職関係の情報についておねがいしたいことがあります。現在,就職関係の情報は主にキャリアセンターで扱っていますが,求人の新着情報を学部や研究科あるいは食堂に掲示していただけないでしょうか。Web上でも公開しているとのことですが,私の研究室は自分のPCをLANに接続することができない(先生にたのみましたがダメと言われました)ので,こまめに見ることはできません。 また,学部や研究科に直接求人が来ることがありますが,これらの掲示が遅く,せっかくの札幌での説明会や学校推薦が期限切れで掲示されることが多いです(たとえば1月中旬に来ていた求人が1月31日の掲示分では載っていなくて3月1日分に載るとか。当然説明会は2月に終わっている)。このことは学生の不利益につながると思います。是非改善してくださいますよう,よろしくお願いします。 |
| (薬学研究科・薬学部からの回答) A 本学部における就職情報の提供は,掲示及び所属分野への求人票の写しによる通知により学生に周知し,キャリアセンターから送付されてくる企業説明会の案内については,掲示により学生に周知しております。 なお,平成18年度から(株)ネオリッチの「進路支援システム」(薬学系)を活用して,登録を希望する学生には,Web上で就職情報を提供する予定です。(当分の間は,従来の各分野への紙媒体による求人票の送付と併用して実施する。) 大学院生のパソコンをLANに接続することに制限があるとの件につきましては,分野ごとに事情があることから制限している研究室もあるが,今後教務委員会に諮り検討していきたいと考えております。 最後に求人情報の掲示が遅いとの件ですが,通常は1月に2回程度の割合で掲示及び各分野へ紙媒体による写しの配布による通知を行ってきておりましたが,事務担当の失念により1月31日の通知以降,3月1日までの間通知を行わず学生に不利益を与えてしまいました。今後は,1月に2度程度の通知と上述した「進路支援システム」を活用し,このような事態が生じないように努めていきたいと考えております。 |
| (キャリアセンターからの回答) A 求人情報について毎日数件以上の情報が寄せられ,キャリアセンターでは毎日更新を行っている状況ですので,求人情報について各研究科・学部及び食堂への掲示は紙媒体よりもホームページから確認していただいた方がより迅速に提供出来るものと考えております。 なお,今年からは自宅からでも求人情報はデータ検索に対応出来るように,就職支援用コンピュータシステムを更新しましたので是非,登録の上ご利用ください。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成18年3月27日】 無記名者からの投書 Q トレーニングセンターにて,一部の体育会クラブのマナーの悪さに困っています。センターには,ランニングコースがあり,その進行方向は反時計回りというルールです。しかし,一部のマナーの悪い体育会クラブは,反対方向である時計回りでランニングしています。 京都の大学で,クラブに所属する学生が,女子学生をレイプするという悲惨なできごとが先日あったばかりです。学識をわきまえていない一部のクラブによって,私の所属するクラブの,引いては体育会クラブ全体のイメージが悪化することを懸念しています。そして,それ以上に,ルール違反の危険なランニングによってケガ人が出るのでは,と不安でたまりません。車が反対車線を走るのが,どれだけ危険かは猿でもわかると思いますが。 そこで,ルール違反のランニングをするクラブ,個人の監視とペナルティを考えて実行していただけないでしょうか。私の案としては,ルール違反をするクラブでは,全ての大学施設(体育館,トレーニングセンターetc)の利用を禁止するなどがあります。 |
(高等教育機能開発総合センター・川初清典教授からの回答) |
| 【掲示日:平成18年4月12日】 獣医学部4年からの投書 Q 学生及び大学職員について要望があります。 1)北部食堂の利用 食堂の利用者が白衣を着ていることがあるが,白衣は実験中に着用することで,自身への薬品汚染等を防ぎ,かつ外部への微生物等の持ち出しを防ぐ。それを着用したまま食堂を利用するのは,モラルに反すると考えます。主に医・歯・薬の人達と思いますが,他者への配慮のない行為と感じます。同様に体育会系部やサークルの人が土の付着したジャージで共有施設を利用するのも注意指導すべきです。 2)体育会クラブについて 獣医学部前のローンは多くの人に開放されていますが,ラクロス部など一部の心無い人によって「養生中」と表示,ロープで「進入禁止」とされている間も練習を行っています。又,練習によりボール等が目の前を飛んでいくという危険な目にあったことも数度あります。クラブやサークルの人による共用部分(施設)などの専有は不適切と考えます。例)ラクロスによるローンや体育館前,教養駐輪場での練習。よさこいサークルによる中央道路の専有。 |
| (医学部からの回答) A 医学部には施設内に専用の食堂があり,昼間,北部食堂の利用はないものと思いますが,夕方の利用が若干あるものと推測されますので,本学部の教職員・学生に対し,集会等の機会を利用して注意を喚起いたします。 |
| (学務部学生支援課からの回答) A 1)北部食堂の利用について 1. 体育系サークル及びその他のサークルに対する指導については,食堂内の利用について限定した内容で文書及び掲示により,注意並びに指導します。 2. サークル以外の学生に対しては,掲示により注意します。 2)体育会クラブについて 該当サークル(ラクロス部,YOSAKOIソーラン「縁」)の代表者を呼び,今後このような行為がないように注意します。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成18年4月19日】 文学部4年からの投書 Q 文学部の今年度の学修簿配付手続きが,大変不親切だ。指定された日時に,指定された場所に行ったのに,担当者が不在で学修簿は受け取れなかった。担当者が何時なら在室しているのかも,不明だった。後期からは,前と同じように事務室の窓口で受け取れるようにしてもらいたい。 |
| (文学部からの回答) A 今回の学修簿等の配付に関しましては掲示によりお知らせしたところですが,その内容が不明確であったことによりご迷惑をおかけし,申し訳ありませんでした。 前期(4月)の学修簿配付時には,シラバスや時間割もあわせて配付することとしており,また,専修課程ごとに履修上の指導・助言などを行う場合もあることから,教務係窓口ではなく専修課程ごとに配付しています。 来年度以降,今回のような混乱を招かないよう配付の日時・場所を明確にしてお知らせするようにいたします。なお,後期(10月)の学修簿配付はこれまでどおり教務係窓口にて配付する予定です。 |
| 【掲示日:平成18年5月15日】 文学部2年からの投書 Q 文学部2年次履修コースガイダンスですが,いつどこでおこなわれるのかなどの掲示がずっとなく,3月31日に文学部の事務の方に聞いたら,4月になったら掲示すると言われました。コースのわりふり等で忙しいのであろうことはわかりますが,4月5日に行われるガイダンスの詳細が3月末日になってもわからないのは,学生としても困ります。 文学部の友人たちの間でも,一体いつどこに行けば良いのかという情報が錯綜して混乱していました。次からは,こういった掲示はなるべく早くして下さるようお願いします。 |
| (文学部からの回答) A 行事の案内や各種手続きなど学生の皆さんにお知らせすべき情報については,物理的に直前にならざるを得ないものを除き,早めに掲示等によりお知らせできるよう心がけているところですが,今回の2年次履修コースガイダンスについては,全体ガイダンス後に行われるコース別説明会の時間・場所等の調整に時間を要してしまったため,掲示の時期が遅れてしまいました。 今回はこうした事情により掲示時期が遅れてしまいましたが,必要な情報については早めにお知らせできるよう努めていきたいと考えています。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成18年5月15日】 文学部2年からの投書 Q 文学部の喫煙スペースについて述べさせていただきます。W棟の入口のところでtabacoを吸っている人をみかけますが,どうにかならないでしょうか。理由は以下の2つに集約できます。 (1)他の人の健康 喫煙所があるにもかかわらず副流煙を,しかも,人の出入りの激しいW棟の入口でtabacoを吸うことで発生させるのは,多大な迷惑である上に,tabacoの火が危険である(特に12:00〜13:00の間)。 (2)来客からの印象 北大を訪れる観光客や受験を考えている高校生にとっても,メインストリートは普通に使用するところです。その地点からW棟も視野に入る可能性は高いです。 以上が大きな理由ですが,建設的な話しをすると,1.警備員が発見したら止めさせる,2.近くにtabacoを吸うスペースを新設する,というのはいかがでしょうか。 |
| (文学部からの回答) A たとえ喫煙が許されている場所であっても,人の出入りが頻繁な場所などでの喫煙は,喫煙マナーとしては好ましくありません。ご指摘のあったW棟出入口付近ですが,出入口に向かって20mほど右側に仮の喫煙スペースとして灰皿を設置しており,本来であればここで喫煙すべきですが,そこまで行くのが面倒なのか出入口のすぐそばで喫煙する者が多いというのが実情です。 ただ,出入口にはこの場所での喫煙を禁止する旨の表示もありませんし,すぐ横に喫煙スペースが設けられていることの表示もありませんので,そうした表示をいたします。また,出入口での喫煙を見かけた場合には厳重に注意するよう警務員等への指導を徹底していきたいと思います。 |
| 【掲示日:平成18年5月15日】 農学部1年からの投書 Q 入学したての新入生ですが,サークル(部)の活動に文句があります。何か行事があれば勧誘しようとしてきて,ほとんど場所を選びません。プリントはやたらと配り,掲示板には壁が見えなくなるほどのチラシがはられて,一部は覆い隠され,一部は床に落ちていたりします。正直いって残念です。大学のあり方を疑います。企業ですら,資源節約の行動を行っているのに,そのさきがけとなる大学が過剰に紙を使い,無駄にしているとはどういうことでしょうか。 もちろん,宣伝活動が必要なのは理解できますし,広い学内のこと,積極的な宣伝が必要なんでしょう。でも効率が悪すぎます。もっとサークル(部)として一致し,情報を収約するべきです。はっきり言って,情報がちらばりすぎて入手方法が分らなくなっています。移動中に配られてもうんざりするだけですから,その効果も数名にすぎないでしょう。マイナスイメージがつきまとうばかりです。対策して下さい。 |
| (学務部学生支援課からの回答) A 4月の各サークル新入生勧誘期の教室・福利厚生会館食堂内への置きビラについては禁止しており,各学生公認団体にそれぞれ通知し,全学生公認団体メンバーが出席した「事故防止講習会」時にもアナウンスいたしました。 また,当該講習会では,音楽系・球技系等の団体間で協議し,毎回同じ内容のビラを配布するのではなく,希望者が自由に手に取ることができるよう掲示方法等を工夫するなどの改善策を取るよう注意しております。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成18年5月23日】 無記名者からの投書 Q 構内交通について,最近,構内を走る車輌について,特に運輸,配送関係の(トラック,バンなど)がかなりのスピードで走っており危険を感じます。(郵政公社,民間業者とも)中央の直線道路だけでなく,狭い道でも同様です。集配が時間との競争というのも理解できますが,構内には学生以外にも児童等が散策もしており,事故が起きてからでは遅く,業者への構内徐行るいは制限速度遵守を徹底して下さい。(入構証のある教職員・生協等の車両ではあまり乱暴な運転は見かけません。) |
| (施設部施設企画課からの回答) A 構内交通の情報提供を頂きありがとうございました。構内交通規制については,大学関係者だけでなく学外の各事業所も遵守すべきことであり,構内の安全及び良好な環境確保に重要な役割があります。 構内交通規制を遵守するよう,運輸・配送等関係車両を対象に5月12日〜5月31日まで,「注意書」を配布するとともに,正門と北13条門に注意事項を貼出し,交通規制の遵守を強化することとしました。 なお,違反車両は会社に報告する旨の警告を付記していますので,違反車両を見かけた方は,正門守衛室に情報をお知らせください。 |
| 【掲示日:平成18年5月29日】 無記名者からの投書 Q 1.S講義棟「S1教室」が暑すぎです!!! 2.年度が変わって著しく高等教育機能開発総合センターの清掃のレベルが低下している。 3.置いてある自転車を移動させないで欲しい,ただでさえ自転車が多いのに移動されると,自分の自転車を見つけるのが大変。 4.雨の日に自転車を置くときに,雨にさらさないで屋根の下とかに置けるスペースが欲しい。 5.ロッカーが欲しい。体育館の更衣室をもっとキレイに!! |
| (学務部学生支援課からの回答) A 1.S講義棟は蒸気で暖房しております。一日中蒸気を通すと室内温度が上昇し過ぎるため,その日の温度等によって調整し通気しています。しかし,設備の老朽化などにより細かな温度設定は不可能な状態であるため,手動によりバルブのメモリを開閉調節する必要がありますので,ご協力をお願いします。 2.高等教育機能開発総合センターは,毎年4月は季節の変わり目と,新入生などの出入りが多くなり,それに伴って汚れが酷くなります。一般清掃のほかに,清掃員の巡回回数を増やし,汚れの酷い場所は重点的に清掃するように指示しました。 3.多くの自転車が利用できるように,駐輪場に管理員を配置し,整理,整頓を行っています。雑然と停めている自転車,倒れている自転車は,移動させ,整理を行っています。また,駐輪場以外に停めている自転車は駐輪場に移動させています。駐輪場の整理,整頓のために自転車を移動することがあると思いますが,ご理解をお願いします。 4.駐輪場に屋根を設置,又は屋内駐輪場の設置などにはその費用が必要であり,現在のところそれらの計画はありません。 5.第一体育館アリーナ奥の男子更衣室は,本学サークルの2団体が用具置き場として使用しています。第二体育館廊下の更衣室は,第二体育館使用時のものです。その都度,内部の整理を呼びかけておりますが,再度,両団体並びに体育系団体の総括にご意見を伝え,改善するよう指導します。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成18年5月29日】 水産学部1年からの投書 Q 今週から授業が始まっているのですが,今年から前期,後期で取得できる単位に制限がついたみたいですね。そのことの話しですが,前,後期で取得できる単位の上限が23単位は少なすぎます。この単位数だと必修,選必修単位で7割強ぐらいになってしまいます。それに加えて選択であるけれど,明らかに必修に近い科目(微分積分1,情報学1etc)を合わせると,残りの単位は高々2〜3単位ぐらいになってしまいます。これだと自分の興味のある講義が複数個ありましたが進級をetcを考えて1つしか選びませんでした。これだと高校,予備校とさして変わらないです。(これは学習意欲の低下にもつながります。)来年に入学する学生のためにも単位の上限をもう少しゆるくするべきです。 |
| 法学部1年からの投書 Q 本年度から取得できる単位数の上限が設定されたのですが,授業料は昨年と同じだと思います。昨年以前の学生と比べるとわりに合わないと思います。設定の理由は聞きましたが,学生の中にはまじめにもっと授業を取りたいと思っている人もいます。2学期は上限設定をなくすことはできないでしょうか。 |
| (学務部教務課からの回答) A 本学では,学生の履修科目の過剰な登録を防ぐことを通して,教室における授業と学生の教室外学習(予習・復習等)を合わせた授業展開を行うことにより,少数の授業科目を実質的に学習できるため,単位の実質化が図られるとの判断から本年度から取り入れたものです。 具体に成績不振の学生には,履修科目を絞り込み,少ない科目に集中して取り組むよう指導する一方,成績優秀の学生には,履修登録単位数の上限を高めて,幅広い学習を奨励する制度となっております。意見として寄せられた「興味のある授業科目がとれない」「必修科目でほぼ埋まってしまう」等についてですが,2学期の履修については定められている上限を超えて登録できる制度(「学生便覧」及び「えるむ(第119号,平成18年4月号)」参照)となっておりますので,確認してください。 また,高年次においても履修が可能となっております。この制度は本年度から実施したものであり,今後この制度の内容等をさらに検証し,さらによりよい制度として運用できるように大学として検討を重ねますが,その際には「学生の意見」も参考にさせていただきます。今後もご意見をお寄せください。 ※ 参考までに単位数計算の1例を挙げると1単位は45時間と定められており,2単位の講義科目の場合は,週1コマ2時間の授業を15週教室内で行い,教室外(予習・復習等)は60時間となります。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成18年5月29日】 無記名者からの投書 Q 何故,大学の先生のこくばんの書き方が一定でなくあっちこっちにばらまくように書くのか?正直いって不快だ,授業が。追いずらい |
| (学務部教務課からの回答) A 本学では各教員に対してFD(ファカルティ・ディベロップメント)研修を通じて,「効率的な授業」や「分かり易い授業」について実践的な意見交換等を行っています。 ただ,教員個々の授業に対する「癖」という部分から,乱雑な黒板の使い方や文字となって現れるのだと推測されます。しかし,あまりにも「癖」がひどく,授業に支障をきたすと思われる場合は,教員の実名を記してご指摘願います。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成18年5月29日】 医学部2年からの投書 Q 既修得単位認定の申請の結果は第1回目の授業より前にしてほしいです。学生便覧には空いた時間は他の科目を履修するのが望ましいと書いてありますが,申請の結果がわかるまでは申請中の授業(私の場合は英語3)に出席しなければならず,他の科目を履修する機会を失うこともあります。(第1回目の授業に出席しないと履修できない科目もあります)1ヶ月近く前に申請書類を提出しているのですから,結果は授業開始前に発表してほしいと思います。 |
| (学務部教務課からの回答) A 投書の内容から,既修得単位の申請を1カ月程前の3月中旬に行ったようでありますが,この日程は各学部において定めていることから,学部間において隔たりがあります(4月から受け付ける学部もある)。ただし,全学教育科目における審査の日程は全学部統一して行っています。そのために「審査の結果の公表が遅い」との指摘になったのだと思います。既修得単位の申請は,2年生のみが申請しているわけではなく,当然,4月から入学する新1年生も申請します。また,申請科目数を比較すると圧倒的に新1年生が多い状況となっています。 本年度の場合,1年生のオリエンテーションが4月6日開催されました。各学部の大半は,オリエンテーションが開催される4月6日を締切り日としています。そして,各学部において申請科目が取りまとめられ,全学教育部に対して審査の依頼をする締め切り日を4月7日とし,全学教育部において各学部からの申請を科目別に取りまとめ,審査担当教員に4月10日(8.9日は土,日曜日)に送付しています。 「授業に出席することなく,北海道大学としての単位を認定する」という行為は容易ではなく,複数の教員が係わるのはもとより,最終的に認定を行う各学部においても,しかるべき委員会等において審議されることから,授業開始日である4月12日には必然的に間に合わないという状況となります。 では,授業開始前に認定する方法として,2年次の審査と1年次の審査を別々に行うということも考えられますが,2年生を3月中に審査するとなると,審査する教員の労力はもとより,申請者においても,授業のない期間であるにも係わらず,審査のために登校する必要性が生じます。 また,1年生の申請の締切りを早くするという方法も考えられますが,学生便覧,シラバスや時間割さえも手にしていない学生にとって無理があることと,自宅通学者は良いとしても,新たに一人暮らしを始める学生にとっては,新生活の準備等に追われる落ち着かない日(3月末から4月1日,2日等)に締切日を設けるのはいかがなものかとも考えます。 以上のような事を勘案し,現在は,新たな学園生活を始める1年生の日程を優先させていただきたいと考えております。ただし,「最初の授業にでれない」ということは,学生にとって大きな問題であると認識しておりますので,審査日程及び審査方法等については今後も検討を行う予定であります。ご理解の程をお願いします。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成18年6月9日】 経済学部1年からの投書 Q この春入学した新入生です。履修の手続きに関していくつか提案させてください。 今年から履修上限単位が20前後に設定されましたが,必修・要履修科目をとった場合,教養科目は1.2コマしか選択できなくなってしまいました。全学教育をめざす北大において,このような制限はやる気のある生徒をおさえつける,全学教育の実現を遠ざけることにはならないでしょうか。もう少し上限設定を緩和していただきたいと感じます。 また,一般教育演習や大講堂での授業は,新学期開始早々(新入生は2日め)で抽選調書が締切られており,まだ開講されていない講義は内容・自分に合うかどうかなど確かめることのできないまま,また他の科目との兼ね合い(移動の時間・時間割の都合など)がはっきり決まらないうちに駆け込みで提出した人も多いのではないでしょうか。せめて授業開始から1週間,講義を一通り体験したあとに提出できるよう,検討いただきたく思います。制度導入の目的は理解できますが,自分の取りたい講義を取りたいだけ自由に取れなくなりやや不満です。柔軟な対応を期待しています。長文失礼しました。 |
| (学務部教務課からの回答) A 履修登録単位数の上限設定制度につきましては,5月29日付けの掲示で既に回答させていただいておりますので,ここでは,一般教育演習等で実施した「抽選方式」による履修調整についてお答えします。 平成17年度までは,現在と同じ日程(二日間)で「一般教育演習」についてのみ抽選を実施し,履修者を決定してきましたが,平成18年度からの教育課程の改編,履修登録単位数上限設定制度の導入に対応した履修調整の方法を検討した結果,従前の「一般教育演習」に「外国語演習」「大講堂で行う授業(主題別・総合科目)」を新たに加え,今学期から実施しすることになりました。 ご指摘のありました「講義内容を確かめることができないまま・・」の問題については,これまでも一週間程度の余裕が持たせれないか等のご意見もあり,履修の届け出から履修者の確定までのスケジュールを関係の委員会等で総合的に検討を重ねるとともに,シラバスの内容の充実も含めて鋭意努力しているところであります。 しかし,抽選科目の決定を行った後でなければ履修届の提出ができないことを考えると,抽選の手続き等を遅らせることは履修者の確定までのスケジュールも必然的に遅れることになり,授業計画に大きな問題を及ぼすことが懸念されるとの結論に至り,本年度においても同様の抽選日程とさせていただいたものであり,事情をご理解願います。 今後におきましても,学生の皆さんからお寄せいただいた意見を参考とさせていただき,「年間行事予定」,「シラバスの内容の充実」,「履修調整の在り方」等々について検討課題として対応したいと思います。 |
| ▲ページトップへ |
| 【掲示日:平成18年6月9日】 文学部2年からの投書 Q 昨年度,ナンシー・ホワイト講師の英語1を受講した者です。ホワイト師は最初の課題レポートに住所と電話番号を明記するように指示しました。当時,私はそのことについて何も感じませんでした。しかし,今になって,あの情報がどのように使われたのか考えると不安でたまりません。単に授業のためだけであれば掲示をするか,あるいはEメールですまされる話しだと思います。(HuWebというものもあるそうですね)。そこで質問ですが,住所や電話番号は何を目的として回収したのか,何に使われたのか。ということを質問したいと思います。そして,もう一つ,ホワイト師は,講義の最終回に聖書系のチラシを配布していました。ただし,その場では見ないように指示はしてらっしゃいました。このことは,大学側としては許されるべきグレーゾーンだと考えておりますか?質問の二つ目は,一つの宗教に関するプリントを,英語の授業で配ることは許されるのか。 ということを挙げておきたいと思います。最後になりますが,私は個人的にはホワイト師の授業は好きでした。陽気なイタリア人らしい講義は毎回楽しみで待ちどおしかったです。 |
| 農学部3年からの投書 Q 昨年度,英語の授業で非常勤講師のN・ホワイトさんがご自分で通われている教会の案内を配っていた。これは問題があるのではないでしょうか? |
| (言語文化部・英語科からの回答) A お尋ねの件に関し,ホワイト先生にお会いし,話し合いを持ちました。その結果を報告します。 まず最初の質問,「住所や電話番号は何を目的として回収したのか,何に使われたのか」についてですが,ホワイト先生が学生に住所と電話番号を書かせたのは,期末試験を受験しなかった学生に(念のために)履修の意思を確認するためだということです。もちろん,これらの住所や電話番号は学期の終わりにすべて処分しているとのことですので,ご安心下さい。それでも,これは個人情報に関することですので,今後学生に連絡を取る必要が生じた場合には,教務課に問い合わせるようにホワイト先生にお願いし,承諾していただきました。 二つ目の質問,「一つの宗教に関するプリントを英語の授業で配ることは認められるのか」ですが,ホワイト先生が学生に配布したプリントは,たとえば,「クリスマス」の本当の意味(由来)や生きることの意味を一人ひとりに考えてもらうために配布した資料であり,それ以上のものではないということです。しかし,これは授業とは直接関係のないことであり,学生全員に配布するというのはあまり好ましいことではないので,先生にはこのような資料の配付は控えるようにお願いし,承諾していただきました。 |
| ▲ページトップへ |
