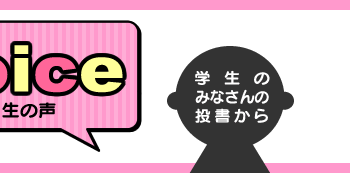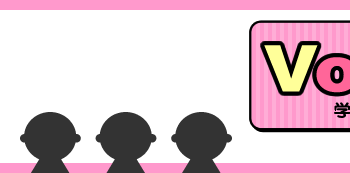 |
|
| �u��������@�\�J�������Z���^�[�v�ɂ́C�d��1�K�̊w�����������O�Ƃd��2�K�E3�K�ɓ������u�w���̐��v��ݒu���C�����āu�L���p���v�������Ă��܂��B �@�݂Ȃ��^��Ɏv��������P���ė~�������ȂǁC���̓������Ɋ�ꂽ�ӌ��E�v�]�́C�i�Ή��j��Y���āC���Z���^�[�d���P�K�́u�w���̐��i�j��p�f���v�Ɍf�����Ă��܂��B �@�ȉ��C�O��i��120���j�ȍ~�Ɍf���������ׂẮu�w���̐��v���Љ�܂��B �Ȃ��C����̌f�ڂɓ������ẮC�ǂލۂɕ�����Ղ����邽�߁C�f���́u�w���̐��v�i�I���W�i���j�ɁC���m�ȕ\���ւ̏C�������Ă��܂��B |
| �y�f�����F����18�N6��14���z ���w���P�N����̓��� Q�@���ق̃s�A�m�̎g�p�\���݂��C1�T�ԑO�ɍς܂��Ȃ���Ύg�p�ł��Ȃ��̂ł͂��܂�ɗZ�ʂ������Ȃ��B�Ă����OK�ɂ��ׂ��B |
| �i�w�����w���x���ۂ���̉j A�@���݁C�s�A�m�̂��镔�����܂ߍu�`�����̎g�p�ɂ��ẮC���p�҂���g�p���������̑O�T�܂łɐ\�����݊肢�C�w�����w���x���ی����W�i��������@�\�J�������Z���^�[3�ԑ����j������j���ɗ��T�̍u�`�����g�p�\��\�ɂ����ٌx�����ɒʒm���C���̊J�������Ă���܂����B �@����C���p�҂̕X��}�邽�߁C����18�N6��19�����C�����Ⴕ���͓��Y�T�̗��p�ɂ��Ă��\�����݂��t���邱�ƂƂ��܂����̂ŁC�������Ƃ����͂����肢���܂��B �@�Ȃ��C�g�p���@���ɂ��ẮC�S���W�ɖ₢���킹�肢�܂��B |
| ���y�[�W�g�b�v�� |
| �y�f�����F����18�N6��20���z ���L���҂���̓��� Q�@�ʊw�r���Ō���A�N�Z�T���[�ނ𗎂Ƃ��Ă��܂����Ƃ����X����܂��B�����������炩�ɖk��\���ŗ��Ƃ����Ƃ킩��ꍇ�ł����傩�狳�{�܂łȂǂP�N���ɂƂ��Ă͒T���͈͂͂ƂĂ��L���ł����C���H�����ł͂Ȃ��e�w�������Ȃ���Ȃ�܂���B���������n���̂悤�Ɉ�̌������ł����J�������Ȃ�������Ȃ��ꏊ������܂����C���Ƃ������ꂪ���G�ł�������M�d�i�͑����ɖ₢���킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ȂǂƂĂ���ςł��B���������͂Ȃ��ƉƂɋA��܂��h�Ə���S�z�ł����C�A�N�Z�T���[�͍����ł�������v�����ꂪ�������̂ł��B�����Ŗk����ɓ��ꂵ���Ǘ��V�X�e��������Ăق����̂ł��B��̓I�ɂ͂g�o��ɂł���Ύʐ^�t���ŏڍׂ������Ăق����ł��B��������������܂��Ă��闎�Ƃ�����������ɖ߂邾�낤���C�T���̂Ɏ�Ԏ���Ă��鎞�Ԃ𑼂̂��ƂɊ�����̂ł��肪�����̂ł����B�ǂ��Ԏ������������邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B |
| �i�w�����w���x���ۂ���̉j A�@�����̗��Ƃ����̊Ǘ��ɂ��āC���Ƃ���������������{���C���Ƃ������g�o��ŕۊǏ����J���Ăق����Ƃ̂��ӌ��C�v�]������܂������C���i�K�ł́C�\�Z�ʁC�l���I�ɕs�\�ȏł��B���Ƃ����C�Y�ꕨ�́C�����̉ߎ��ɂ����̂��w�ǂł�����C�����̎������ɓ�������C��t���邱�Ƃ���ł���Ǝv���܂��B���萔�ł��C�e���Ǘ��Ƃ������������ɂ��₢���킹�肢�܂��B |
| �y�f�����F����18�N7��4���z ���w���P�N����̓��� Q�@����C�w���̐��̉�p�f���Łu�����I�Ȏ��Ƃ╪����₷�����Ƃ�ڎw���Ă���v�Ƃ�����ǂ�œ������܂��B �@���w��1�N�̕����̎��Ƃ�S�����Ă��遜�����̎��Ƃɂ��Ăł����C�Ő����I���̎҂������̂ɁC����������ς킩��ɂ����C�����I���̎҂ł��������ɂ�����Ԃł��B���̏������i������Z���j�������C�������s�\���ŋ��ȏ��Ƃ��Y��������C�܂��C�h����o���Ă��Ȃǂ���Ȃ��C�������o���������m�F�ł��܂���B�݂�ȗ����ł����o�ȗ��������Ȃ��Ă�������ł��B���̂܂܂Ńe�X�g������ƁC�ƂĂ�����ɂȂ�̂��ڂɌ����Ă킩��܂��B���Ƃ����Ă��炦�Ȃ��ł��傤���H |
| ���w���P�N�̃N���X�ꓯ����̓��� Q�@���j2���́u��b�����T�v��S�����Ă��遜���搶�̎��ƂȂ̂ł����C�����̌��ۂ̐�����ړI�����킸�ɓˑR���ς̎��𗅗Ă��܂��B�܂����Ƃ̓��e���ň��Ȃ̂ł����C�����������Ɍ������āu�N�����ł����ꂮ�炢�͂킩���ˁv�Ƃ��u�킩�邩�ȁ`�킩��Ȃ���ȁ`�v�ȂǂƏ��o�J�ɂ��������������C�s���ɂ��Ă��܂��B����ɋ������R������C�_���_�����������肵�đԓx�������ł��B �@�ԓx�������͉̂��Ƃ��K�}�����Ă��܂������C���Ƃ����܂�ɂЂǂ��͉̂��Ƃ����Ăق����ł��B |
| �i�����w�ȖڐӔC�҂���̉j A�@�u�w���̐��v�̓������e���w�E�̂������搶�ɂ��`�����C���Ɠ��e�̉��P�����肢���܂����B�u�������e���l�����đP������v�Ƃ̐搶�̂��b�ł��̂ŁC����̎��Ƃɂ����Ғ��������Ǝv���܂��B |
| ���y�[�W�g�b�v�� |
| �y�f�����F����18�N7��10���z �o�ϊw���P�N����̓��� Q�@����C���C�v�]�ȖڂɎw�肳��Ă������w�̎��Ƃ̋��t�̎������ɒႭ��ύ����Ă��܂��B�O���ꓙ�̕K�C�Ȗڂ◚�C�v�]�Ȗڂŋ��t���g�n�Y���h�������ꍇ�C���k�͑I�������������ߔ����ӂ�����ł���w�̋��t�͍��Z���ƈႢ�u������́v�͎�������Ȃ���C��w�ł̍u�`�Łu�s�v�����Ă��܂����ꍇ�C���̌�ɑ傫�ȉe��������܂��B����������\���ł����ǂ�ȋ��t�ł��t������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���������������Ȃ̍u�`���J�u����Ȃ�C���k�����R�ɑI�ׂ�悤�ɂ���ׂ��ł��B��������C���t�����k�̐��Ŏ����̍u�`�̎����킩��ł��傤�B �@���鍑��w�Ƃ����������̂����w�ł��u�`�I���̃V�X�e���͂��̒��x���C�Ɛ������_���Ă��܂��B��N���ȍ~����{�I�ȃV�X�e���͕ς��Ȃ��̂ł��傤���H�Ƃ���������̃V�X�e���őS�Ă̐��k�������̂ł���u�`������قNj��t�w�̃��x���͍����Ȃ��ł��B�����̉��P��]�݂܂��B �@�NjL�E�}���ׁ̈C���ꂵ�����M�����e�͉������B |
�i�w���������ۂ���̉j |
| �y�f�����F����18�N7��10���z ���w���P�N����̓��� Q�@��������@�\�J�������Z���^�[�̋����̃C�X���������đ������܂���I�����Ə������C�X���ق����ł��B2���Ƃ�3���Ƃ��C���q�w���̂��Ƃ��l���ĉ������B |
| �i�w�����w���x���ہE�����ۂ���̉j A�@�������֎q�̐ݒu����]����Ƃ������Ƃł����C�u�`���̓��肪����C�������ꂽ�����C�ǂ̍u�`���𗘗p���Ă��邩���肩�˂܂��B�֎q����������Ƃ������ƂŁC�����߂̈֎q��z������C���邢�͑��̕�����������邽�߂ɂ��C���������ڍׂȎ�������f���ł�����Ǝv���܂��B �@����]�̂��̂�z�����Ă��C���ƒ��̊��̈ړ��C���|���̈ړ����p�ɂɍs���C�܂��C�֎q�E���̋����O�ւ̎����o�����s���邱�Ƃ�����܂��B����̌����̂��߂ɂ��C����������f���������C�ł��܂�����w���������ۑS�w������W�i��������@�\�J�������Z���^�[7�ԑ����j�ɒ��ڂ����ł��������B���N��̊F����̑̌^�̑�^���ɔ����āC�W���K�i���܂߁C�W���K�i����֎q�C�����z�����Ă���܂����C�������K�i�̂��̂͗p�ӂ��Ă��Ȃ��̂����Ԃł��B�������̒���낵�����肢���܂��B |
| ���y�[�W�g�b�v�� |
| �y�f�����F����18�N7��21���z ���L���҂���̓��� Q�@���Ȃ̂ł����i�\�������Ԓʍs�Ɋւ��Ăł��j���͕����a�@�ɂ��錤�C��i�@���j�ł����C�a�@�k���Ńp�X�J�[�h���g�p����Q�[�g�i��w�����a�@�W�҂����g�p�ł��Ȃ��ӏ��ł��j�ŁC�����炭�o���肷��i��ނ̋Ǝ҂��Ǝv���܂����j�ԂŁC�V���o�[�̃}�c�_�f�~�I�u�Ӂ@69�|64�v�Ƀp�X�J�[�h��t����Ă���Ǝv���܂��B���̎Ԃɐ���C������Ԃ̌��ɕt���Ă������܂����B�\���͏��s�����炳���͂��ł����C���̂悤�ȃ}�i�[�̈����^�]��C�Ǝ҂Ƀp�X�J�[�h�͌�t���Ȃ��ł��炢�����ł��B�܂������Ǝ҂ł���C����͂���ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�\�����S�^�]���i�̂͂��ł���C�}�i�[�̈����҂ւ͓O�ꂵ���Ή������肢���܂��B �@�܂����Ǝv���܂����C�Y���Ԃ��C��w�Ζ��҂�w���ł͂Ȃ��ƐM���܂����C�����ł���C�Ȃ������肩�Ǝv���܂��B������ɂ��Ă��F���Ă���͈̂�w�����a�@���Ǝv���̂Ō����ɑΉ����C�D�����^�]��S������҂������C�^�s�\�ɂ��Ă������������Ǝv���܂��B |
| �i��w������̉j A�@�����p���ɋL�ڂ̎ԗ��ԍ����璓�ԏ̌�t�҂��m�F���C�{�l�ɑ��{���ɂ��Ă̎����̗L���C���̐��������߂܂����B �@�{�l�̐����ɂ��C�u���̂悤�ȍs�ׂƊԈႦ���鎖�͂��Ă��Ȃ��Ǝv�����C�L���ɂ�����܂��C����͏��Ȃ��Ƃ��ԈႦ���Ȃ��悤�ɂ���ɋC��z�邱�Ƃɂ��܂��B�v�Ƃ̂��Ƃł��B |
| �y�f�����F����18�N7��25���z ���l���`�ł̓��� Q�@�g���[�j���O�Z���^�[�ɂ��Ď��₵�܂��B �P�D�u�O���R�[�X�ł̃g���[�j���O���֎~����v�Ƃ����\�莆���o�Ă܂����C���Ȃ��Ƃ����̕����̓g���[�j���O�p�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����H�����j���O��p��������Ȃ���������̂ł��傤���B���������C���̕����̓o�[�x���������Ă����v�Ȃ悤�ɉ��H���Ă���̂ł����āC�������̎g�p���֎~�����珰�Ɍ��������܂���B��ꂠ�̃R�[�X�͑S����80�������Ȃ��Cw-up������x�Ȃ炢���ł����W�c�ő������肷��̂ɂ͑S���K���Ă��܂���B�[�u�̍čl��]�݂܂��B�����Ƃ����C�ނ���R�[�X�ł̏W�c�����֎~���Ăق����ł��B �Q�D�u�������֎~�����̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤���B�u���ւ����ň�t�ɂȂ�v�Ƃ������R�͉����܂���B�m���ɂ��ł����ς��ɂȂ��Ă����Ƃ����͂���܂������C����͂���ł悢�̂ł͂Ȃ��ł����B�ނ��낢�������g���[�j���O�̂��тɏギ�������Ă���w���ɕX���͂���Ƃ����_�ŁC��������F�߂ā@���������Ȃ��ł��傤���B���������֎~���Ă���y���ŗ��p���Ă���l���ӂ����C�����܂��B �R�D�Ȃ����ʂȂ��̂���w�������̂ł��傤���B�����Ă���̂��ǂ����炩�z�u�]������Ă���̂��͕���܂��C���炩�Ɍ����̈������i�w���Ɏv���ĂȂ�܂���B���̌�������C���́u�A�C�\���g���b�N�p�v�Ƃ����ꂽ�}�V�����g���Ă���l���������Ƃ͂���܂��C�����S���g����������܂���B�܂��C�@�ŋߑ�ʂɃ_���x�����w������܂������C�O�̏�Ԃł��قƂ�ǎg���Ă��Ȃ������̂ɁC�Ȃ�����ɍw���Ȃ������̂ł��傤���C��������Ɍy�ʂ̂��̂��قƂ�ǂŁC�V�l�̃��n�r���ȂǂɎg���悤�Ȃ��̂ŁC�w���̎g�p�p�x�͒Ⴂ�Ǝv���܂��B���̂悤�Ȕ��i����̂ł���C�o�[�ƃx���`�v���X����w�����Ă������������ł��B�o�[�ɂ̓T�C�Y���Q�����āC���������͑���Ă�̂ł����C�������������Ă��܂�����Ȃ��ł��B80�L�����炢�܂łׂ͍����őΉ��ł���̂ł����C100�L�����炢�ɂȂ�Ƒ����o�[��p���Ȃ��Ɗ댯�Ȃ��߁C�F��ςɍ����Ă��܂��B�܂��C�x���`�v���X����C����3�䂠��̂ł����C100�L�����x�ōs����2��͂�����Ŋ댯�Ȃ��߁C����1�䂵���Ȃ��悤�Ȃ��̂ł��B���̂��ߊw�����\���ȃg���[�j���O���s������ύ����Ă��܂��B �S�D���L���������ł��B���炩�ɏW�c�ŗ��Ă���̂ɖ��O�������Ă��Ȃ����i�o�h�~���g���Ƃ��j������܂��B �T�D�}�i�[�̈������������ł��B�吨�ł���Ă��Ėw�ǐ�L��ԂɂȂ邱�Ƃ������ł��B�����Ƀg���[�j���O���Ă���̂Ȃ�܂������̂ł����C���ΗV�тɂ��Ă���悤�Ȋw���������C�g���[�j���O���s�����̊w���ɂ����ւ�Ȗ��f���y�ڂ��Ă��܂��B �U�D���������̃g���[�j���O�Z���^�[���\���Ɋ��p����Ă��Ȃ���������܂��B����Ȃ�{�݂̏[����Ղ݂܂��B �@�\�Z�̊W�Ŗ������Ƃ͎v���܂����C�g���[�i�[�̔z�u�Ȃǂ��������ɏ[�����C�^�����̐��ѓ������シ��Ǝv���܂��B�R�w�@��@��ł͂��������^�c���Ȃ���Ă��邻���ł��B |
| �i��������@�\�J�������Z���^�[���U�w�K�v�挤�������U�X�|�[�c�Ȋw�������傩��̉j A�@�g���[�j���O�Z���^�[�i�g���Z���j�͖{�w�ɊW����N�����̗́E���N�ƃX�|�[�c�̂��߂Ƀg���[�j���O���C�܂����̐��I�Ȏ��Ƃ��s�����߂̎{�݂ł��B���p�҂ɂ̗͑͂̋����l�����܂��B�̈�n�ۊO�����c�̂̑����͋����l�B�ŁC���p�͎��E�ʂƂ��D���ł��B�N���u�̋K�����ɂ�����Ĉ�ʓI�ɐ��R�Ƃ����g���[�j���O���ώ@����Ă��܂��B�̗͂̎ア�l�̗��p������܂��B�g���Z���ł́C���ցC�X�ߎ��C�̈�كt���A���苷�ł��B�����̗��p�҂��t���A�ł͋��ɉ������ꂽ�肵�Ȃ��悤�ɗp��̊m�ۂ₻�̔z�u�ɔz�����Ă��܂��B�ϓ_��ς��āC�䂪�܂܂�g����Ȑl�̗��p������܂��B����ɋL�����Ȃ������藘�p��C���L��Ԃ��L������C���Ƃ�u�K��̎��ɑފق̎w���ɏ]��Ȃ�������C�y�������s������C�~���[�ȂNJ��E�p��̔j����͂��o�Ȃ�������C�ƁC���̑ԗl�͎G���ł��B�g���Z���ł́C�����̑��l�ȗ��p�𗘗p�S����Ǘ��E�^�c�̒������ɂ���Đ����C�g���[�j���O���̕ۑS�ɓw�߂Ă��܂��B �@�ł́C�u���v�ɑ��Ĉȉ��ɌʓI�ɐ������܂��B �P�D�u�O���R�[�X�ł̃g���[�j���O���֎~����v�Ƃ̓\�莆���o�Ă���Ƃ��Ď��₪������Ă���܂��B�\�莆�ɂ́C�t�Ɂu�O�����H�ł̃g���[�j���O��F�߂�v�Ə����o���Ă���܂��B���̏�ŁC���҂����鎞�͑��H��������C�W�Q�ɂȂ�p����ړ�����悤�w�����Ă��܂��B���̂��Ƃ͕njŒ�p�X�|�[�c�~���[�̎���ōs���Ă���E�G�C�g�g���[�j���O�ɂ悭�Y������̂ł��̘e�ɓ\��o���Ă���܂��B �@�O���R�[�X�͖��X�m�X�Ƃ��đ��s�H�i�����j���O�g���b�N�j�ł��B�H�ʑf�ނ̓^�[�^���ł��B1968�N�̃��L�V�R�ܗւ̗��㋣�Z�p�ɊJ������C�g���Z���̃^�[�^���g���b�N��1972�N�D�y�ܗւ̑I�苭���̈�ّ��H�Ƃ��ĉ䂪���ŏ��߂Đݒu���ꂽ�R���̐ݔ��ł��B�X�p�C�N���p�ŋ��Ղł��B���Ƃ��g���[�j���O�ł͏d�ʋ������Z�Ƃ͈قȂ��ăo�[�x���𗎂Ƃ��܂���B���C�d�ʕ��̗������N�����Ă��^�[�^���͑����ɑς����܂��B��L�̂悤�Ɂu�F�߂�v���Ȃł��B��ɁC�~���[�𑽖ړI�X�y�[�X�̕ǂɐݒu���܂����B���̃X�y�[�X�ł̓~���[��O�ɂ��ăG�A���EEx�C�X�e�b�v�EEx�C�X�|�[�c�t�H�[�����K�Ȃǂ����h�g���[�j���O�C���Ƃ�u�K��ōs���Ă��܂��B�E�G�C�g�g���[�j���O���D���Ȃ̂Ń~���[�O�Ɏ����ꂪ�悭����o����܂����C���̃g���[�j���O��O���ɂ��ē��Ɉړ����~���[���Q�䐮�����Ă��܂��B����ł��C���H���Ă�����̏�̗��p��F�߂Ă��܂��B �@���̑��s�H�̓E�H�[�~���O�A�b�v���S�ʂɁC�܂����ƁE�u�K��E���J�u���Ȃǂ̃����j���O�ɑ��p����C�e�l�̃E�H�[�L���O�ɂ����p����Ă��܂��B�ϐ���}����ƁC���O��ڂ̐l�B�Ɋ|���ւ��̂Ȃ����s�H�ɂȂ�܂��B����ɁC���U�X�|�[�c�Ȋw�����ō���҂̉^���\�͌v���ł��w�����f�I�ɗ��p������܂��B���̍��Ă̗��p�\����������珑���o����Ă��܂��B���p�҂����݂ɗ����E���͂������Ďg�������K�v������܂��B �Q�D�C�I�́u�u���C�v�͂����V�����֎~�����̂ł͂Ȃ��C�]������̎w�����ڂƂ��Čf�����o���܂����B�C���̐�L�͑��҂̗��p��j�݂܂��B���́u���v�͕��u�C�����̂��߂ɕ����P�W�N�S���T���f���́u���m�点�v�Ɠ����Q�S���f���́u�C�I�ւ̒u���C�ɂ��āv�i�ʎ��j�̒ʒm�Ƀ��X�|���X���Ă���Ǝv���܂��B�@�֎~�����̏������ׂ͔������͂Ȃ��̂Œʒm�̌f�����P�����ŊO���܂��������̓��e�͐S���Ƃ��Ĉێ������悤���҂��܂��B���Ƃ���w���ɂ����q�ɂ����ւ����C�܂��O�C�̒u���ꂪ�ǂ����Ă���͍̂D�܂�������܂���B �R�D�g���Z�����p�҂ɂ̗͑͂ɗ��l����ƁE���J�u���̏��������܂��B�V�����_���x���͑S�w����S�����ǂ̋��������Ɨp�ɓ��Z���^�[�ɑ��k���Đ����������ނł��B���̐l�̗��p����������Ă��܂��B���ɁC���ۑ̈�̏]���̋������������ƂɕK�v�Ŏ�������ŌÂ��Ȃ����@��E�p�����������܂��B�ډ��C���Y���ǂ�ʂ��ĂS������p���葱����i�߂Ă���@�킪��������܂��B���ɂ͏������U�킵�Ċ����ǂ�����܂���B�����p�̃v���X�`�b�N�P�[�X���C�ٕǖʂ̌f�������ڋy�уV�����[���ł̎q�X�V�ȂǂƋ��ɒS���W�ɕ����ŗv����o���Ă����@�����̐i�ނ̂�҂��Ă��܂��B�A�C�\���g���b�N�E�X�e�[�V�����́@���a�U�O�N�ȑO�̍w���ň����p����Ă��܂��B�ؗ͑���̍��ەW���K�i������B�ł��B���́E�w�ؗ͂̂悤�ɋ͍ؗ͂����W���I�ɒ��́iKg�j�ŕ\����܂��B���̊�B�ł͂قڑS�g�̕��ʂ̋ؗ͂̍����x�̌v���ƃg���[�j���O���\�ł��B�����P�U�N�����̊�B�Ō��N�X�|�[�c�Ȋw�n�̑��_�������g�܂�܂����B�Ȋw�I�g���[�j���O�͌��������H���A�C�\���g���b�N����n�܂荡���嗬�ɂ���܂��B�j���̕s�����Ȃ��̂Ńg���[�j���O�ɂ�������܂��B�g���[�j���O���Ȃǂɂ���Ēm������l�ɐ悸�L���Ɏg���đՂ�����ł����C�@��ăg���[�j���O�u�K������{�������ƍl���Ă��܂��B �@�@Wt�g���[�j���O�p�V���t�g�̑����͂ǂ̃^�C�v���Q�W�����Ӂi�a�j�ʼn��͂ɑ��鋭�x�͋��ʂ��g���[�j���O�͈̔͂ł͏\���ł��B�u���v�ɏ�����鑾���V���t�g�Ƃ�Wt�v���[�g��ʂ���������]����d�g�݂̃^�C�v���w���Ă���Ǝv���܂����C��]�^�͏d�ʋ����̂悤�Ɏ���Ԃ�����̂��߂̉�]�@�\��L���Ă��܂��B�x���`�v���X�ȂǁC�Z���^�[�ōs����w�ǂ̃g���[�j���O�ł͎��Ԃ����Ȃ��Œ萫�\�ɗD�����]�^���L���ł��B���݁C��]�^�W�{�i�Q�{�C�����ɑݏo���j�C���]�^�P�R�{�C���̑����{��L���Ă��܂��B�g���I���̃V���t�g������̃��b�N�ɖ߂��Η��p�ɂ͕s�����Ȃ��Ǝv���܂��B�܂��C���ׂ���P�R�OKg���ŃV���t�g�����ݎn�߂܂��B���ޕ����p�t�H�[�}���X�̏�ł����̂ւ̕��ׂ̏�ł��L���ɂȂ�܂��B���邩��ɏd���o�[�x�����o�l�ŗh���Ԃ��ăg���[�j���O����p�͂�������̓I�ɂ��Ȃ�܂��B �@�}�V�[���g�ݍ��݊�������āC���݃t���[Wt�p�̃x���`�v���X�Z�b�g�U�g�i�P�g�C�ݏo���j��u���Ă��܂��B�����C�S�g���g�����C�Q�g���Œ莮�ł��B�d�̂��߂ɂ����ރZ�b�g�͂P�g������܂���B�g�����͍\���I�ɂ�������ł����C�������^�����@���O��ł���C�����ł���Ζ��͂���܂���B�����݃s������������Ƃ��ė��p���ĉ������B�Œ莮�P��ɂ͕⋭�̗]�n������܂����C���S���̏�ł͖�肪����܂���B�����̋@��̈��S����v�E�s�v�ɂ��Ă͗��p�w���̊��z���Ȃ���Ώ����Ă��܂��B�̈�ٗ��ɍŋߔp�������V���t�g��}�V�[��������悤�ɁC�X�V�ɂ��S�����Ă��܂��B �S�D�L���𑣂��悤�ɕ��S���Ă��܂��B���p�͋@�퐮���̗\�Z�z���̍����ɂ��Ȃ�̂ō���������S�����܂��B �T�D�g���Z���ł͋t�̊ώ@�����Ă��܂��B�g���[�j���O�ł͕��ׂ���̉���ł���Ǝw�����Ă��܂��BWt�g���[�j���O�͂���ɓ��ɊY�����C�����Ԃ�Z�����Ԃ����܂��B�x��ł��鑽���͂��̉ߒ��̎p���Ǝv���܂��B �U�D�g���Z�����{�݂Ƃ��̋@�\�̊g�[�ɓw�͂��Ă��܂��B���̃f�U�C���Ȃǂ���o���Ă��܂��B �@�ł́C�Ō�ł��B�g���Z���ł́C�P��N�u�����o��v�ő̈�ق��S�ʉ��C����C���̎{�݂͔���I�ɉ��P����܂����B����Ƃ���w�Ɨ��p�ґo�����ǂ��g���[�j���O���Â���ɓw�͂��C�w���E�E���̌��N�x�E�̗́E�X�|�[�c���Z�͂̈ێ��E����ɖ𗧂悤�w�߂܂��B |
| ���y�[�W�g�b�v�� |
| �y�f�����F����18�N7��25���z ���L���҂���̓��� Q�@�w���ψ���s�̍L�u����ށv�����q�ǂ��Ă��܂��B���s�サ�炭�o���Ă��c�����R�ς݂ɂȂ��Ă���̂��������܂����C�w���ɂƂ��Ă͕K�v�ȏ��邽�߂́u���Օi�v�I�ȑ��ʂ�����̂ŁC����̂悤�Ȏ����E�J���[����łȂ��Ƃ��\�����Ǝv���܂��B �@�D�y�s�̍L���o��ߌ��̂��ߎ����𗎂Ƃ��܂������C���ɕs�ւ͊����܂���B�w���̗��ꂩ��́C���������̂����Ő}���قʼn{���ł���G���E�V���E���Г��������ł�������������肪�����Ɗ����܂��B���Ќ䌟���������B |
| �y�f�����F����18�N7��25���z ���L���҂���̓��� A�@�w���L�u����ށv�ɑ��邲�ӌ��ɂ��āC�ȉ��̂Ƃ�����܂��B �@�u����ށv�́C�w���ψ���E�L�u����ށv�ҏW����Ō�������Ă���C����18�N6��14���i���j�J�Â̓�����ɂ����āC����18�N�x�i��120���`123���C�N4��j�̔��s�E�ҏW���j�������肳��܂����B������ł́C�{�N�x����C1,000���팸����4,000���s���邱�Ƃɂ��܂����B����́C�e���ǂɍ��q�̂̎��v�x�█��̎c�����̏��m�F���������ŁC���q�̂̌p���Ɣ��s���������肵�����̂ł��B����܂Łu����ށv�́C��������@�\�J�������Z���^�[1�K���r�[�ȂǂɎc�����R�ς݂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂������C���s�������팸���܂����̂ł��̉ۑ�͉����ł���ƍl���Ă��܂��B �@�u����ށv�̎������ɂ��āC�\�E�����ƒ��قǂ�4�y�[�W���̓J���[�ŏ㎿�����g�p���Ă��܂����C���̃y�[�W�͔������͓�F����̕����x�̎����ŁC�{�w�̑��̊��s���Ɣ�r���Ă����ɏ㎿�Ƃ͂����Ȃ��Ǝv���܂��B�܂��C�w���̊F����ւ̔z�t�̑��ɁC�k��𗬃v���U�u�G�����̐X�v�Ⓦ���I�t�B�X���̈�ʂ̕����K���{�w�{�݂ɔz�u���Ă��܂����C�����E��������⍑������}���قɂ����t���Ă��܂��̂ŁC���̒��x�̎��̐����͈ێ����ׂ��ƍl���Ă��܂��B �@�Ȃ��C�{�w�z�[���y�[�W�ɂ́C��81���i����9�N2���j����f�ڂ��Ă���C�����I�ɂ́C���q�̂s�����C�z�[���y�[�W�݂̂̌f�ڂɂȂ邱�Ƃ��l�����܂��B ���{�w�z�[���y�[�W�ւ̃A�N�Z�X�@�c�u�g�b�v�y�[�W�v���u�L��E���J�v�� �u�k��L�vURL:http://www.hokudai.ac.jp/bureau/populi/index.html |
| �y�f�����F����18�N8��8���z �@�w���Q�N����̓��� Q�@�Ȃ����{�i�S�w����Ȗځj�ȂɁ��������搶���u�`���ꂽ�̂ł��傤���B �@���G�u���ۊW����v����u�������̂ł����C�����搶�قǂ̕�������ȑf���炵�����Ƃ�����Ă���̂ɁC��w�̔��̐l�Ƃ��͂Ђǂ��ł��B���̎��̍��͂Ȃ�Ȃ̂ł��傤���H |
| �i�w���������ۂ���̉j A�@�����̓��e���s���m�Ȃ��߉��ł��܂���B����������̓I�Ȏw�E������������Ǝv���܂��B |
| ���y�[�W�g�b�v�� |
| �y�f�����F����18�N8��8���z �H�w���S�N����̓��� Q�@�p�\�R���𗘗p�����H���s���l�Ԃ��܂������B���������l�Ԃ͗��p��~�Ȃǂ̑[�u���Ƃ�ׂ����B |
| �i����ՃZ���^�[����̉j A�@������p�\�R���𗘗p���Ɉ��H���������ꍇ�C���H���s��Ȃ��悤�������w�����C���C�f�����Œ��ӂ����N���Ă���Ƃ���ł��B |
| �y�f�����F����18�N8��21���z ���L���҂���̓��� Q �@��������@�\�J�������Z���^�[���ɁC���{���Y�}�̎D�y�s�c�̃|�X�^�[���\���Ă���̂����܂����B�i�w�����k���̂Ƃ���̊K�i1�|2�K�̊ԁj�C����͋������̂ł��傤���H |
| �i�w�����w���x���ۂ���̉j A�@�w���̌f���́C�{�w�̌f�����Ɋւ�����K�ɂ��K�肳��Ă���C��������@�\�J�������Z���^�[�Ɍf������ꍇ�̓Z���^�[���̋����Čf�����邱�ƂƁC���̓��e�͐����I�ړI��L������́C�����͋��U�̋L�q���͖��_�ʑ��ɂ킽��悤�Ȃ��̂Ȃǂ͌f���ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���܂��B���w�E�̂������|�X�^�[�͌f���ӔC�҂Ɍ��d���ӂ̂����P�������܂����B |
| ���y�[�W�g�b�v�� |
| �y�f�����F����18�N8��21���z ���L���҂���̓��� Q�@������ł̃}�i�[�������l����������C��������H�ׂ�C�W���[�X���̂ށC���킮�C������ׂ�C�ꏊ���L����C����ł��ĐȂ��Ȃ��l������̂ɂ˂Ă���C�A�_���g�T�C�g������C���O�I�t���Ȃ��ŋA��C�t���b�s�[�𓐂ނ������A��ȂǁC�]��ɂ��ڂɗ]��܂��B |
| �i����ՃZ���^�[����̉j A�@�O��̉ł��q�ׂ܂��������w�E�̂悤�Ƀp�\�R�����g�p�����ňꕔ�̊w���̃}�i�[�����Ɉ����Ƃ̈�ۂ͖Ƃ�܂���B�E���������������ꓙ�ɏo������ꍇ�͑����d�ɒ��ӂ��C�f�����ł����ӂ����N���Ă���Ƃ���ł��B �@�܂��C�E���̖ڂ��s���͂��Ȃ��ʂ�����܂��̂ŁC�C�����悭���p�ł���悤�Ɋw�����m���݂����ӂ����Ă�����������Ǝv���܂��B |
| ���y�[�W�g�b�v�� |
| �y�f�����F����18�N8��21���z ���Y�w���P�N����̓��� Q�@�P�D�v�[���ɂ����ƁC���j������L���Ă���悤�ȏ�Ԃ̂Ƃ��������č���B�����ƕ�����Ȃ�̑�����Ăق����B �Q�D�v�[���̔r�����͑��v�ł����B |
| �i�w�����w���x���ۂ���̉j A�P�D�v�[���̈�ʊJ���̎��ԁF�u���`���j���i�j�Փ��������j��12���`19���܂Łv�ȊO�̎��Ԃ͐��j������L���Ďg�p���Ă��܂��B��ʊJ�����ɂ��C7���[���̂���1�`2���[���𐅉j�����g�p����ꍇ������܂����C�v�[���̍���ɂ���ė��K���グ�Ă��܂��B �@��ʊJ���̎��Ԃɐ��j�����i�Ǝv����j�l�B����L���C�j�����Ƃ������Ԃł���C�Ď����i���j�����j���v�[���Ǘ����ɂ���܂��̂ŁC�����b���Ή����Ă�����Ă��������B �Q�D�{�w�̃v�[���͎��̂̂������u�����v�[���i����1.6���`2.0��/�b�j�v�ł͂���܂�����h�߁E���f�ŋۂ̂��߂ɏz���v�[���ƂȂ��Ă��܂����C���j�p�̂��߁C�j���ɉe�����o�Ȃ��悤�v�[���̐��͂������z���Ă��܂��B���̋z�������@(1.26���~1.26��)�̓v�[���̒�ɂ���C���̊J���������Ł@�����{���g�ŌŒ肵�Ă��܂��B�z�������́C�z���h�ߑ��u��ʂ�v�[�����ʂɂ���14�ӏ��̏z������f�o���Ă��܂��B |
| ���y�[�W�g�b�v�� |
| �y�f�����F����18�N9��13���z ���w���P�N����̓��� Q�@�O���ɗ��C�����u���w�v�̎��ƂɊւ��Č����������Ƃ�����܂��B �@���̎��Ƃ͍w������悤�Ɏw�����ꂽ���ȏ��i�u���w����v�j����x���g�����ƂȂ��I���܂����B�Ȃ��C���ƂŎg�������Ȃ����ȏ����w������悤�Ɏw������̂ł��傤���B �@�F�l���畷�����b�ł́C���̋��ȏ��́u���K�p�v�Ƃ������ڂōw������悤�Ɏw�����ꂽ�����ł����C���ۂɂ��̖{���J���Ă݂Ă��C���Ƃ̉ۑ��i�߂�̂������ɂȂ�悤�ȕ�����Ղ��������Ă���킯�ł͂���܂���B�m���Ɏ���ϋɓI�ɃR���s���[�^�Ȃǂɂ��Ċw�ڂ��Ƃ����l�ɂƂ��Ă͂��������m��܂��C����͂����܂ł����ꕔ�̐l�ł��B��̂̐l�͖{�I�̋��ɒu�������ŁC�J�����Ƃ��Ȃ��ł��傤�B���������H�w�����łȂ�����C�A���S���Y���̋L�q�@�Ȃǒm��K�v�̂Ȃ����Ƃł����C��������������l�͎��炻��Ɋւ���{���w������Ǝv���̂ŁC�킴�킴���C�ґS���ɍw��������K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂��B �@���̂悤�Ɏg��Ȃ��{���w��������̂ɂ͉������R������̂ł͂Ȃ����Ɗ��������l�́C���̖{�̒��҂̌o�������ċ����܂����B���ҎO�l���O�l�Ƃ��k��̋����������̂ł��B����Ŗl�̋^��͔����̂悤�ɂȂ�܂����B�܂�C�l�����������̂́u���̖{�킹���͈̂�Ŗړ��ĂȂ̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������Ƃł��B �@�m���ɁC��w�̋����������̏������{�������̎��ƂŊw���ɍw������悤�Ɏw������͕̂��ʂ̂��Ƃł����C��������J���ď������u���M��v�Ȃ�Ίw���ɑE�߂����Ȃ�Ƃ����̂�������܂��B�������O�q�����悤�ɁC�����̐l���g��Ȃ��悤�Ȃ��̂𗚏C�ґS���ɍw��������͖̂��ʂł����C�l���������悤�ȋ^��i�����j������l�����Ă��d�����Ȃ��悤�ȏ��Ǝv���܂��B �@��w���Ƃ��Ă͂���ɂ��Ăǂ̂悤�ɂ��l���ł��傤���B���ԓ������҂����Ă���܂��B |
| �i�S�w���w���ψ����̉j A�@�u���w�i1�C2)�v�́C�k�C����w�̕��n�E���n�E��n�E�_�w�n���ꂼ��̊w���ŏ��Ɍg����Ă��鋳�����W�܂�C�k�C����w�ɂ�������Ƃ��Ăӂ��킵�����e���������C���E���E���ɂ�������̌�������l�����āC2�N�Ԃɋy�Ԍ������ʂ܂��C���ψ���ɂ����Ċ�悵�����e�ł���B �@���̌����Ɋ�Â��C�k�C���̍���������w�ŏ��Ɍg��鋳�����W�܂�C�k�C����w�̏����ψ����3���̋������Ҏ҂ƂȂ�C����16���̎��M�҂ɂ���āC�e�L�X�g�u���w����v��Ҏ[�����B �@����18�N�x�́C���Z�̐V����ے��Łu���v���w���߂Ă̊w�������w���Ă���Ƃ����N�ł���C��w�ɂ�������̂�����́C����ȑO�̂��̂Ƒ傫���قȂ���̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�S���̑����̑�w�ɂ����āC���̑Ή����x��Ă��钆�ŁC�k�C����w�͂��̏ɐ^���ɑΉ����������Ȃ���w�̈�ł���C���̋��ȏ��͂��̂悤�ȐV��������ے��ɑΉ��������w�������������Ȃ����ȏ��̈�ł���B �@�k�C����w�́C���痝�O�̒��̂ЂƂƂ��āC�u�S�l����v���f���Ă���C����́C���I�m�������p���邽�߂̑����I���f�͂ƍ���������������l�ނ̈琬�̊�ՂƂ��Ă̋��{������d��������̂ł���B�w�E����Ă���A���S���Y�����̗����́C����ɂ��̏��E�m���Љ�ɂ����āC�k�C����w�𑃗����C���[�_�[�Ƃ��Ċ���w�����N�ɋ��{�Ƃ��Ċw��ł��炢�����ƍl���Ă���B���̂��Ƃ���C���ψ���ł́C���E���n���킸�C�S�w���ɑ��ď��w1�C2��K�C�Ƃ��邱�Ƃ��Ă��Ă���B �@���w�́C���K�𒆐S�Ƃ������w1�ƍ��w�𒆐S�Ƃ������w1�ō\������Ă���B���w1�ł́C�z�z�����u�ۑ�E�]����ꗗ�v�ɂ���悤�ɁC�e�L�X�g�̊Y���ӏ����Q�Ƃ��āC���K���s���C���w2�ł́C���̎��K�o�������ƂɁC�e�L�X�g���ӂ܂��ču�`���s���B���w1�ł́C�Ƃ��ɁC�u���w����v�̑O�������|�m�I���L�������Љ�ւ̎Q�悷��ԓx�y�уf�[�^�E���̕\���ɂ��āC���H�I�Ɏ��グ���C�e�L�X�g�u���w����v�̓��e�����[���������邽�߂ɂ́C����ɏ��w2�̗��C�����߂�B������ɂ���C���E���E���Ƃ͈قȂ�C��w�̎��Ƃ́C��w�ݒu��ɂ��������C���Ǝ��ԊO�̎��w���K��O��Ƃ��Ă���B �@���ȏ��̈����ɂ��ẮC���N�x�́C�u�ۑ�E�]����ꗗ�v�̊e�ۑ�̖����Ɂu���ȏ��֘A���ځv�Ƃ��ċ��ȏ����ł̑Ή��ӏ������C�ۑ�ɑ��闝����[�߂邽�߂̎����I�Ȋw�K�����҂��Ă����B�������C���̓����ɂ���悤�ɁC���ꂪ�K�������w���ɗ������ꂸ�C�P�ɗ^����ꂽ�ۑ�݂̂��@�B�I�ɂ��Ȃ��ꂽ�P�[�X��������B���̓_���ӂ܂��C���N�x����͋��ȏ��Ŋw�K���邱�Ƃ��u�ۑ�v�Ƃ��Ė����I�Ɋ܂߂�ȂǁC���w���K���m���ɐ��i����悤�Ȏd�g�݂����邱�Ƃ���������B �@���w�́C���N�x����n�܂������̂ł���C���ψ���ł́C���ꂩ���������w������̃t�B�[�h�o�b�N�Ɋ�Â��āC�e�L�X�g�̗��p���@���܂߁C���Ƃ̓��e�ƕ��@�����P���Ă��������ƍl���Ă���B |
| ���y�[�W�g�b�v�� |
| �y�f�����F����18�N9��20���z ��w���P�N����̓��� Q�@�������ʂ̌f���ɂ��� �@���݂̃V�X�e���ł́C���������̍��ۋy�ђǎ����̘A���͋��{�̃��r�[�ɂ���f���f������邾���ƂȂ��Ă��܂��B�܂����̌f�����̂��C���邩�ۂ��͍u�t�Ɉς˂��Ă���̂��C�f������Ă���ȖڂƂ���Ă��Ȃ��Ȗڂ�����܂��B�P�ʂɊւ�鎎���̌��ʂ̌f���Ƃ��Ă͏����z���Ɍ�����Ǝv���܂��B����āC(1)�����̌��ʋy�ђǎ����̗L�����C������f������̂��ۂ�(2)����Ȃ�C����͂��f�������̂��Ƃ���2�_���C�������s���ۂɊw���ɕK�����m����悤�ɋ`���Â��ė~�����ł��B����Ɍ����C�ł��邾���f�����ė~�����Ƃ����̂��l�̊肢�ł��B��낵�����肢���܂��B |
| �i�w���������ۂ���̉j A�@�ŏ��ɁC�������ʂ̎��m���@�ɂ��ẮC�����Ƃ��āu�w�C��v�i18�N�x1�w���̊w�C��z�z����9��28���j�ɂ��s�����Ƃ���C�K�������f���ɂ����m����K�v�͂���܂���B �@���ɁC�ǎ����i�]�����s�ƂȂ����҂ɑ���ēx�̎����̈ӂƂ��ĉ��܂��B�j�̎��{�Ɋւ�����m��i�ɂ��ẮC�f���͂��Ƃ��C���ƒ��ł̎w���C���[���C�d�b�ɂ��A���ȂNj����Ɉ�C���Ă��܂��B �@�ȏ�̂Ƃ���C�{���ɂ��Ă͒S�������̍ٗʂɂ��s���Ă�����̂ł���C���̂Ƃ���C�v�]�̂������u�������ʋy�эĎ����̎��{�̗L���̌f���v�𐧓x������l���͂���܂���B�������̒������肢���܂��B �@�������C�^�₪�������ꍇ�́C�s���m�̂܂܂ł��߂����̂ł͂Ȃ��C�K�v�ɂ���Ă͋����ɒ��ڂ����˂铙�ɂ��m�F�̕��@���K�v�ł��낤�Ǝv���܂��B�������C�����ɘA������ꍇ�́C��߂��d�C���t�����Ȃǎ���̂Ȃ��悤�ɐS�����Ă��������B |
| ���y�[�W�g�b�v�� |