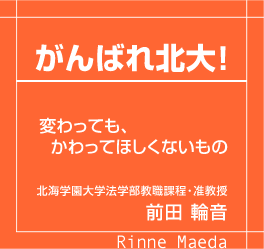某私立大学、埋め尽くされた大教室は水を打ったように静かだった。「あの、カルロス・ゴーンは、小さい頃歴史の先生になりたかった」、と始めた新入生対象の教職ガイダンスに(まんまと)触発されたK君は、予定外の教職課程履修を決意、昼には勤務、夕方から必要な講義を着々と履修し、冒頭のガイダンスの主(私)が担当する教職の演習では常に議論をリードし、教育実習を無事終え、免許取得と同時にこの春清清しく卒業した。
某日某講義のテーマは「社会科における『愛』」。戦後初の学習指導要領(試案)社会科編(1947年5月)を皮切りに、「愛」の諸相(?)について資料を作成・解説、社会科に「愛」は必要なのか?との問いかけに学生の意見が乱れ飛び、小さな教室は「愛」で溢れた。
4ヶ月前の春、教職課程ガイダンスは新入生・新2〜4年生対象および教育実習直前編(各2回)、介護体験実習・各種ボランティア関係…、と続いた。その後は随時始まる教育実習の直前・直後の個別面談、実習訪問(実習校へのご挨拶&授業実習見学)を担当した。現時点で12名分、残すところ1名。
以上が私の仕事のほんの一面である。
さかのぼることウン十年、私が入学した頃の北大には、博物館も「エルムの森」もHPも黒板消しストラップもなかったが、広い構内は今と変らず人が絶えることが無かった。建物の内外問わずよく迷ったが、勉学にも人生設計にも思う存分迷い悩んだ。当時は学生生活実態調査も授業(大学)評価もなく、精神衛生相談があったことも記憶にないが、教員研究室のドアはよくたたいた。
4年次の学校別教育実習直前ガイダンス(正確な名称は不明)は記憶に残る。なかで過去の実習のエピソードが紹介されたのだが、廊下で喫煙中に生徒と間違われ(その実習先は私服の高校)職員室で説教された人がいる、という。「反面教師」、言われなくてもスーツで実習に臨んだ。当時のガイダンスはこの他に入学時と学部移行時くらいのものだったか。
院生時代のゼミは後輩が震えるほど厳しく、研究への厳格な姿勢とガッツだけは確実に養われた(はず)。泊り込みで論文を仕上げ、提出直後に安堵したのも束の間、机上には指導教員直筆で「前田どの、次の論文作成の構想、近日中に聞かせろ」と記されたA5版の紙切れ(裏紙使用)
1枚…。今もそれはクリーム色の台紙で補強され、わが研究室のラックから私を見つめている。
普段からの話し相手だったある教員は、修士課程当時、私の学会発表に難癖をつけたので厳重に抗議して謝らせ、しばし「国交断絶」、口をきかずにらみ合った数日後、短い挨拶で「国交回復」、学会などで短いが慈愛あふれる彼の問いかけは今も続く。一院生相手によく謝ったものだと私が尊敬していることを彼は知らないが、緻密な研究には言うに及ばず。
教員や仲間との様々な語らいという名の「教育」によって学生は成長する。成果や結論に追われるばかりの風潮は教育にはそぐわない。せちがらい世の中、北大はずいぶん変わったが、この「教育」だけは変わらないことと思うし、またそう願いたい。だからそれにふれるよう後輩たちに望みたい。ドアはたたけば開かれるのだ。
…もっとも、たいして成長してない人(=私)がいうのもなんではあるが…
|