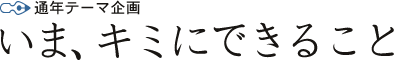 |
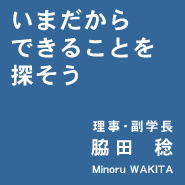 |
人生の中でも、とかく学生時代は「自由」。そして、学生時代の経験がその後の人生に大きな影響を及ぼす。自分のしたいことが思いっ切りできる反面、いろんなことがありすぎて結局何も身につかなかったということも得てしてあるもの。 本企画は、年間を通じて「いま、キミにできること」というテーマを設定、各回は、個別に設けるサブテーマに沿って、学生の皆さんにアドバイス的なメッセージを発信します。 第1回目は、この5月に教育担当の副学長に就任された脇田稔先生に寄稿いただきました。 |
| 「いまキミにできること」というタイトルのシリーズと言うことで、書き始めています。 対象は、1年生〜2年生の全学教育を履修中の学生諸君を考えています。 先日、新聞にこんな記事が載っていました。中央官庁や大企業は若手エリートクラスを、早い時期に外国に留学させるそうです。欧米の一流大学に数年間留学して、将来のために見聞を広め、それぞれ特定の分野の知識能力を高めることが目的です。ところが、途中で脱落する人が最近とみに多くなってきたのだそうです。担当教授から留年を言い渡されるものも出てきました。その理由は、授業についていけないから。 これはいわゆる専門職大学院等での話です。専門領域の知識がないわけではありません。語学とくに聞く・話す能力が標準以下という理由でもありません。一番大きな理由は、学問的基礎に乏しいのだそうです。おそらく、日本のエリートは留学先のその国の大学卒業生なら当然持っている学問的素養、歴史、文学、さらにはギリシア・ラテンの古典語の知識が水準以下だったのでしょう。日本のエリートは、大学入試と就職試験の成績で決まり、その後に当人の専門分野以外の素養(教養といってもある意味重複します)については能力を測られることがありません。大学院に行っても、専門分野のある専攻領域についての知識だけが問われて、その人の学問的背景を問うことは副次的であるようです。 その新聞記事は、これが日本の教育の欠点であると述べています。広い学問的素養の上に立脚した専門教育が不十分ということでしょう。このような考えの浸透している国々では、パーティなど人が集まる場所では、それが目的の集まりでない限り「店shopの話はするな」という暗黙の了解があります。自分の専門の話はだれでもできますが、個人の教養を示すことになりません。日本人は語学に自信がないこともあって、ついつい自分の専門に話題が片寄りがちです。自分の店の話以外に話題を求めようとするとどうしても一般的な話題になります。政治や社会情勢は難しすぎますから、自然に美術、音楽、文学、スポーツ、趣味などから、自分の「店」にないもので、自分の得意とする話題を提供することになります。ですから、話題の少ない人、無趣味の人は苦労します。 このような、話題の広さ、間口の広さ、深さを教養といい、その人の人間的な幅を測る基準になります。この点北大の全学教育は、さまざまな知識をある深みを持って育て、個性を磨く仕組みであると思います。特に、北大の特徴とされている、「一般教育演習」では、上手に科目を選べばかなりこの欠点を少なくできます。 専門教育のまだ始まっていない学生諸君には、学問の基礎体力を養成すること、これこそが「いま、キミにできること」と私は勧めたいのです。専門科目は学部に行ってイヤというほどやらなければなりませんし、分野によっては一生つき合わなくてはならない代物です。ぜひ、自分の将来と直接関わりがあるなしにかかわらず、貴重なこの期間に何かに夢中になって取り組んで欲しいのです。 学問でも、スポーツでも、芸術でも、ボランティアあるいはアルバイトであっても見聞を広め、見識を高めるのに役立ちます。同時に、交友を深め、生涯の友人を得る可能性もあります。 残念ながら、諸君がこのことに没頭できる時間は限られています。ですから、いくつも気の向くままに取り組むことはできません。いろいろ試してみることは良いことです。自分の可能性を探ることになります。ただし、無計画にまた手当たり次第に手をつけるだけでは、やったこと全部が中途半端に終わってしまう危険性もあります。また、おもしろそうだから、というきっかけは正しいと思いますが、面白半分で取り組むのは間違っています。取りついたら、真剣にやらなければ身に付きません。 さらに、一度始めておもしろくなったら、一区切りつくまで続けることも必要です。どこまでやったらよしとするかは、難しい問題ですが、スポーツでは、試合に出られる程度、語学なら辞書を引きながら簡単な文章が読める程度までが目安でわかりやすいでしょう。 学問でもいろいろ試すことはあります。将来の職業を想定してこれに必要な能力と知識、技術を抜き出し、この能力知識技術を得るために受講する科目の組み合わせと順序を考え、自分独自のカリキュラムを作成することが、いわゆるキャリアパスとして大切なのですが、全ての科目が開講されているとは限りません。自分で参考書を探して独学自習する必要のある項目もあるかも知れません。ある分野を勉強している過程で、ある項目に関連性の高いことから、別の分野がおもしろくなることもあるでしょう。ちょうど、百科事典やホームページで項目を次々と渡り歩くように。 大切なのは、自分が将来就きたいとする職業を過小評価しないことです。「この職業には、この程度のことを知っていればよいのだ」としないことです。素人が垣間見た程度では、本職の仕事とその背景全体を見渡すことはできませんから、何が必要かの判断には十分慎重でなければなりません。 |
 脇田 稔 理事・副学長 |
最後に私が教養部時代にやったこと。弓道とオーケストラ(パート・ホルン)に夢中になりました。弓道は2段をとりましたし、一度だけですが「無の境地」を経験できました。オーケストラのおかげでクラシック音楽に詳しくなりました。その他の趣味が広いこともあって後年留学したときも「店」の話をしないで済みました。落語を初めとする寄席演芸もたくさん聞きました。落語の小話は外国でも通用します。支離滅裂な教養部生活かと驚く人もいるでしょう。私にとってこれらは、ここからさらに興味を広げてゆくきっかけにもなりました。昔のことや事物の由来を知ろうと思えば、歴史の勉強が必要です。作曲家の伝記を読めば原文が読みたくなり、ドイツ語の授業に力が入ります。卒業して教師になったあとも、本職に没頭する合間の息抜きに役立っています。 いまは昔と違って興味を引く対象が桁違いに多くなりました。いくらでも選ぶ対象が有ることがよいのか、限られた中で選択して、それをおもしろくなろうと努力することがよいのか、どちらがよいことなのかわかりませんが、人の好みは十人十色、ひとり一人がそれぞれ特徴ある個性を磨いて欲しいと思います。 |
|
 学生と談笑する脇田副学長 |