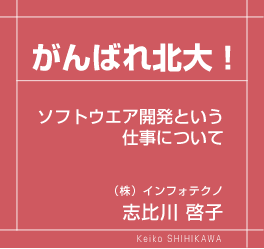社員数約60名のソフトウェア開発会社に勤務して3月で丸8年になります。
もともと「民間企業に就職する」という以外に希望する職種はなく、首都圏の就職戦線に飛び込む気もなかったので、札幌で漠然と流通系などの企業説明会に行ったり面接を受けたりしていましたが、たまたま目にした就職情報誌に文学部の先輩が載っていて、説明会に行ったのがこの会社に入ったきっかけでした。
それまでソフトウェア開発の仕事については「ゲームのプログラマー」程度の認識しかありませんでしたが、説明会で聞いた仕事の内容に興味を持ちました。
ソフトウェア開発というのは、端的に言えばコンピューターを使ってやらせたい仕事がある人と、コンピューターの間に立って、コンピューターにその仕事をさせる仕事です。
コンピューターは、命令された通りのことを、やめてもいいと命令されるまでひたすら忠実に行ってくれます。従って、命令したことに間違いがないか、発生しうるすべての状況に対応できるか、どういった条件の時に仕事をやめさせるのか、といったことはすべてソフトウェア開発者が考えなくてはなりません。
私が大学に入学したのは1996年で、パソコンをまともに扱ったのは大学の情報処理の授業が初めてでした。メールの使い方から始まり、ホームページの作り方や簡単なプログラミングなどを勉強しましたが、プログラミングにはコンピューターを思い通りに動かしたという快感があったのを覚えています。難しいなりにおもしろくて、友人の課題もやってあげたりしました。当時は、それがソフトウェア開発という職種とは結びつきませんでしたが。
専攻がドイツ語学・文学で、趣味でパソコンをいじったりということもほとんどなかったので、入社してからはけっこう大変でした。今でもパソコンの内部構造や電器・機械系統のことはほとんどわかりません(そういう人間をこの職種で採用してくれる会社の方が珍しいのかもしれませんが)。
ただ、私が就職活動を始める前に持っていたような、「1日中パソコンと向き合っている」というこの職種に対するイメージは半分合っていて半分違っていました。確かに、パソコンがないと仕事になりませんが、エンドユーザーを含めた顧客とのやりとりや、社内での打ち合わせなど、いろんな人と話すことの方がパソコンと向き合うよりも今では多くなっています。
大学で学んだことが直接的に役立つということは私の場合ありませんでしたが、異文化コミュニケーションやその他の授業で学んだ、自分の言いたいことを相手に正確に伝えたり、相手の言いたいことを理解したり、新しい言語を系統だてて学び、それをどう実践するか、また、問題が発生した際に過去の経験を踏まえて解決方法を探し、今後にどう生かすかといった、物事を学ぶ姿勢や、徹夜でレポートを書く根性など、大学での経験が現在役立っていると思えることは意外とたくさんあります。
仕事は非常に大変なことも多いですが、今後も様々な経験をしつつがんばっていきたいと思います。
|