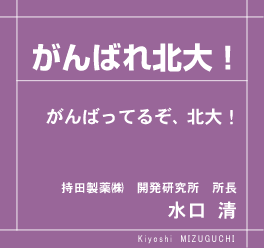現在、製薬会社の研究所に勤務しております。新薬が厚生労働省の承認を経て世に出るまでには、探索研究、前臨床研究、製剤研究、臨床研究(治験)、承認申請・承認取得という長い年月と膨大な費用を要します。新薬候補物質や目指す適応疾患の特性にも拠りますが、一般にひとつの新しい薬が患者さんのもとに届くには15〜20年、100〜数百億円を要すると言われています。国内製薬企業20社を対象としたある調査によりますと、製薬会社が新薬の候補としてこの5年間に合成・抽出した化合物の数は約50万個に及んでいました。一方、これらの会社で5年間に新薬候補物質として前臨床試験を開始したものは約200化合物、治験を開始したもの約100、さらに期待した有効性と安全性を証明できて目出度く承認取得に至ったものは32成分でした。少し大雑把過ぎるかも知れませんが、50万分の32という計算になってしまいます。2006年に国内で承認された新有効成分含有医薬品の数は20成分でした。ここ数年は10成分台で推移しています。一方、日本の製薬企業に在籍し、主に上記の探索研究・前臨床研究・製剤研究に従事する研究者の数は約1万人います。したがって、新薬承認という我々製薬会社の研究者にとっては輝かしいゴールであるイベントに見事遭遇できるのは一握りの研究者であって、不運にも遭遇できない研究者の人数の方が圧倒的に多いのです。
成就するのに長期間を要する新薬創出には先見性と研究開発力(技術と資金)が必要となります。お金のことは別として、創薬に携わる研究者には的確な創薬標的や戦略の設定(これは目利き・眼力)と確かな技術・知識、そして少しの運が必要です。大学では薬学部であっても最終ゴール達成までの創薬ストラテジーはきっと修得できないと思います。しかし、そこを目指すための研究者としての素養はきっと学べるはずです。製薬会社では薬学部出身者以外にも多種多様なバックグランドを持った方たちが沢山活躍しています。これを読まれた皆さんの中から製薬会社でチャレンジしてみたいと思う人がでればと期待しています。
昨年12月に偶々北大を訪ね、空いた時間に北大の構内を一人で散策できるという機会がありました。医学部や薬学部には仕事の関係で幾度か出かけていましたが、構内を歩いたのは二十年ぶりだったでしょうか。在学時代にもしたことがなかったクラーク像を携帯電話で写真撮影している様はまるで観光客そのものに映ったことでしょう。その日は前日まで積もった新雪も固まり、快晴。改築中だったクラーク会館から教養部まで滑って転ばないようにゆっくりと歩きました。雪を踏む時のキュッキュッと鳴る靴音と包み込むしばれた空気の匂いが学生時代を彷彿とさせ、一人懐かしい思いに耽っていました。そして、行き交う若人を見ては若かった頃の自分に重ねて活力をもらっているような気になっていました。
偶然ですが、昨夜、職場が近い社内の北大出身者有志で懇親会がありました。“北大会”と称して1〜2年に1回程度催されるただの飲み会なのですが、昨夜は20歳代の若手女性から定年間近の大先輩までの有志7名が集いました。ビールと焼酎片手に、北大時代の昔話に花を咲かせ、札幌の街の想い出を語り合いました。昔話や想い出なので話題は毎回大体同じになっちゃいます。それでも一夜のタイムトラベルは元気のモトとなり、またみんな今日も頑張っていることでしょう、きっと。まさに、「がんばってるぞ、北大!」といったところです。
|