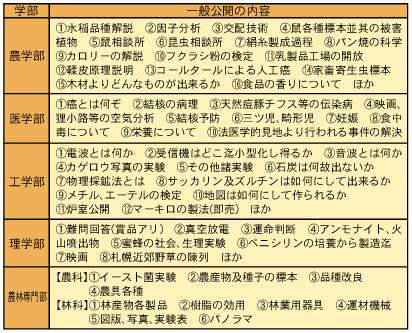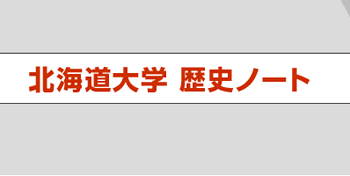 |
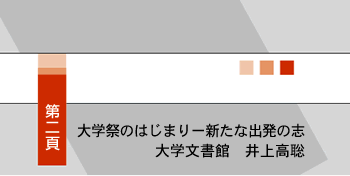 |
| 北大は最初の「大学祭」を敗戦の翌年1946年に開催した。 それ以前にも類似の行事として、札幌農学校時代から「遊戯会」という運動会を1922年まで開催していた。1929年からは全北大生が加盟する「文武会」が「文武会デー」を設けて運動会や講演会を開いた。しかし、1941年文部省の強い意向によって「文武会」は解散させられ、こうした行事も行なえなくなった。代わって、学生・教職員を戦時総動員するための錬成団体「報国会」が組織され、大学を挙げて戦争協力することとなった。 敗戦後の1945年11月に「報国会」は解散した。翌1946年7月には、大学の民主化と自治を旗印として、学生・教職員が自主参加する「学友会」を結成した。工学部生大橋智は委員長就任に当たり、「昨年8月敗戦という歴史的悲劇の痛棒は私を悪夢から現実に |
|||
|
|
||
| しかし、戦前までの大学ではほとんど例がなかった。大学はまさに「象牙の塔」であった。「学友会」は「大学祭」を通じて、こうした古い大学像を打ち破り、大学新生への意気込みを示そうとした。 「大学祭」の目玉であった教室・研究室の一般開放は、10月19、20日に実施され、多くの市民が殺到した。各学部は表のような内容の催しを行なった。見学者は、「日頃家にいて遊んでばかりいる学生さんが白い上っぱりを着て真面目な顔で難しいことをしゃべっているのを見て感心するやら |
|
| しかし、翌1947年は「大学祭」を実施できなかった。大学制度の改編、民主化運動とその反動など戦後の大学には様々な問題が山積し、学内の意思統一を図ることが難しかった。 さらに一年後の1948年には、一部の学部や団体が参加する「体育祭及び文化祭」という形式で実施した。初日10月8日にはクラーク胸像の再建除幕式を行なった。クラーク胸像は1926年に創基50周年を記念して設置したが、戦時の金属回収令により1943年に撤収され、台座だけが寂しく残っていた。クラーク胸像再建は、戦後の新しい出発の象徴でもあった。一般開放では、現在は総合博物館のシンボルとなっているデスモスチルスの骨格が理学部で初公開されたほか、医学部法医学のウソ発見器実験、工学部のロボット実験などが話題となった。 翌1949年以降も「体育祭及び文化祭」を実施した。全学統一による2回目の「大学祭」は1952年に至ってようやく実現した 。 |