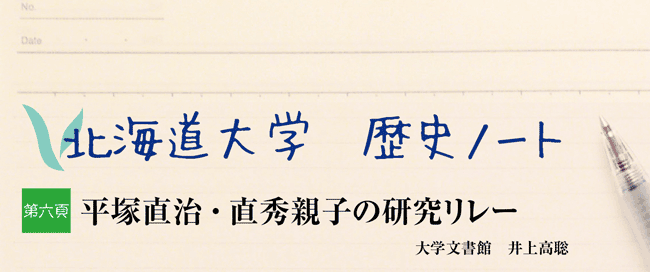鳥取農林専門学校(現、鳥取大学)教授を務める長男の直秀から「日本列島層生銹菌科誌」(一九四四年八月刊行)を受け取った平塚直治は、すぐに恩師である北海道帝国大学名誉教授宮部金吾を訪ね、同論文を進呈した。直治は重ねて一九四四年十一月十九日に宮部に宛てて長い書簡を書き送った。
平塚直治は、一八九二年に札幌農学校農学科第十四期生として入学、宮部金吾教授に師事して植物病理学を専攻し、銹菌研究を開始した。卒業後、もう一つの研究テーマであった亜麻立枯(あまたちかれ)病研究が評価されて一九〇〇年に北海道製麻株式会社に就職した(後年、取締役に就任)ため、銹菌研究は中止せざるを得なかった。その三年後に生まれた直秀は、一九二三年に北海道帝国大学農学部農業生物学科植物分科に進学し、やはり宮部教授に師事して父の銹菌研究を引き継ぎ、卒業後、研究者の道を歩んだ。
直治は宮部に宛てた書簡で、こうした親子二代にわたる銹菌研究の来し方を回想し、自身の研究テーマを息子が受け継いで完成した喜びと、恩師への感謝の念を書き綴った。
「日本列島層生銹菌科誌」を差上けまして、先生に喜んで戴きまして、深き感激と満足と光栄を感しました。……父子二代に亘り同一題目を以て先生の御指導の下に研究を遂けたなとは珍らしい事てあります。……恩師に之を捧呈し得る事は私共に取ては何事にも替へ難き喜であります。此長年月に亘り常に温情を以て激励と御指導を賜りました事に対し、深き感謝を申上くる次第であります。
宮部は十一月二十八日、直秀に書状を送り、親子二代にわたる研究成果を賞賛した。
父上が層生銹菌科の研究を御始めになられたより満五十年に相当致候由、父子二代にて纏められたる研究と言つて差支無之、我学界に於ける美挙と可申候。……一と通り目を通ふし候処に依れば、実に完全無欠と可申、唯々感嘆の外、無之候。
直秀は、後年、このときのことを次のように回想している。
この研究成果こそは、嘗て父が研究を中途で止め、私がその後を受け継いで曲がりなりにも纏めあげた感慨深いものです。……この論文が出来あがるや、直ちに、まず宮部先生と父に贈呈しましたが、御両人とも非常によろこばれ、特に宮部先生からは身に余る書簡をいただきました。(『思い出は草木とともに』、1984年)
直秀は、戦後、東京教育大学(現、筑波大学)に転任して銹菌研究を続け、一九六二年には「銹菌類に関する研究」により日本学士院賞を受賞し、菌類研究の泰斗として大きな足跡を残した。そして、銹菌研究リレーのバトンは、直秀の次男で北海道大学大学院に学んだ平塚保之博士(カナダ国立北方森林研究所)らが受け継いでいる。