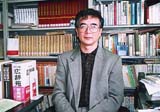
田 中 孝 彦
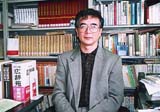
私が属している教育学部の教育臨床心理学講座では,「一人ひとりの子どもの現実から出発する」ということを,研究・教育の広い意味での方法としている。学生も教員も,相談室にやってくる子どもの事例を丁寧に検討すること,学校や地域に出かけて子どもたちの声を聴くことなどを大切にしている。したがって,学生たちが中・高校生とじかに接することもかなり多い。それは,学生たちにとっては,中・高校生の現実を知ると同時に,自分自身のこれまでの生活を見つめ,これからの自分の問題や課題を考える機会にもなっているようである。
たとえば,一昨年,学生たちと一緒に,「不登校」や「中退」の経験のある子どもたちを受け入れていることで知られる北星余市高校を訪問した。そこには,「原宿が突如北海道に出現した」と言ってもいいようなファッションの生徒たちがいた。私は「君はどこからきた?」「この学校の雰囲気はどう?」などと彼らと話し始めたが,学生たちの多くは黙ってじっとしていた。しばらくして,私のそばにいたある学生が小声で,「先生はよく話ができますね。私はこれまでああいう高校生とつきあったことがないので,どうしていいかわかりません」と言った。
今の日本社会において,高校は「偏差値ランク」で「輪切り」にされている。学校がそうなっているだけでなく,同じ時代に生きている青年たち自身の文化や人間関係も分断されている。この学生だけではなく,北大の学生たちの少なからぬ部分は,北星余市高校に通うような青年たちと深くつきあったことが本当にないのである。この訪問によって,学生たちは,北星余市高校の生徒と教育に出会うとともに,これまで自分が生きてきた世界がいかに限られた世界であったかあらためて気づかされたと語っていた。
学生たちのなかには,中・高校生の生活・文化・意識についての研究を,卒業論文のテーマにする者もいる。たとえばこの春卒業していったある女子学生は,思春期の女子生徒にとっての「群れ」(グループ)の実態とその意味を考える卒論にとりくんだ。
その過程で,彼女は,自分自身の思春期の経験をふりかえりながら,自分の問題意識を次のように確かめていた。「グループで行動することが多く,ある一つの仲良しグループに所属していなければ日常生活は送れないように感じていた。……自分というものが確立されていないがためにお互いに依存しあっていたのだと思う。」「しかし,同時に『私自身』と『グループの一員としての自分』とのギャップを感じることもあった。」そして,そのような「群れ」「グループ」のなかで,「次第に自己を模索していくことができたのではないだろうかと感じる。」
こうした問題意識から出発して,彼女はある公立高校の女子生徒たちを対象に,中学時代からどのような友だち関係を結んできたか,その友だち関係のなかで何を感じ考えてきたか聞き取り調査をした。そしてその結果を分析して,「様変わり」したといわれる今日の思春期の女子生徒たちも,やはり「群れ」のなかで依存しあいながら成長を模索しているという判断に達した。さらに中学校教師になることを目指していた彼女は,調査結果に基づいて,今日の女子生徒たちの「群れ」を問題視する教師たちの「常識」に疑問を提示し,「群れ」現象のなかに生徒たちの成長の模索の姿を感じとり,それを生徒たちとともに発展させていく教育実践の方向と教師の役割を考えた。
以上,私が直接かかわっている学生たちの姿を紹介してみた。しかし,近頃,中・高校生(広くは子ども)と向き合いながら,自分自身の過去と現在と未来を考えようとする学生たちの動きが,北大のなかでも,日本の社会のなかでも,おこりつつあるということを耳にする。これは,最近の学生たちの注目にあたいする動きの一つではないかと思い,関心をもって見守りたいと考える。
(たなか たかひこ,教育学部助教授)