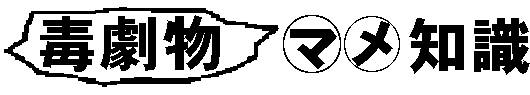 |
| 喜 多 村 昇 |
 毒を使った犯罪は歴史の中の話か推理小説の世界のこととばっかり思っていたが、「サリン事件」やヒ素化合物による「毒カレー事件」など、現実の世界で「毒」がお茶の間の話題となる恐ろしい世の中である。また、「カレー事件」以後、アジ化ナトリウムを使ったと思われる事件が、国立大学や国立研究所をもまきこんで連鎖的に起きた。多発する事件を耳にするにつけ、驚きや怒りをとおりこして、情けなく感じているのは私一人であろうか?サリンは特殊な薬品で我々が手にすることは無いが、ヒ素化合物やアジ化ナトリウムは化学実験などで薬品を取り扱う人間にとっては決して特殊ではない。化学薬品を日常的に使っている者として、それが不正に使用され、殺人にまで至ってしまったことに深い憤りを感じる。今後このような悲惨な事件やグリコの毒入りチョコレート事件などといった人騒がせなことが起こらないように、これを機会に毒物や劇物の危険性やその規制・管理体制について少し学ぶのも良いであろう。
毒を使った犯罪は歴史の中の話か推理小説の世界のこととばっかり思っていたが、「サリン事件」やヒ素化合物による「毒カレー事件」など、現実の世界で「毒」がお茶の間の話題となる恐ろしい世の中である。また、「カレー事件」以後、アジ化ナトリウムを使ったと思われる事件が、国立大学や国立研究所をもまきこんで連鎖的に起きた。多発する事件を耳にするにつけ、驚きや怒りをとおりこして、情けなく感じているのは私一人であろうか?サリンは特殊な薬品で我々が手にすることは無いが、ヒ素化合物やアジ化ナトリウムは化学実験などで薬品を取り扱う人間にとっては決して特殊ではない。化学薬品を日常的に使っている者として、それが不正に使用され、殺人にまで至ってしまったことに深い憤りを感じる。今後このような悲惨な事件やグリコの毒入りチョコレート事件などといった人騒がせなことが起こらないように、これを機会に毒物や劇物の危険性やその規制・管理体制について少し学ぶのも良いであろう。
毒物、劇物とは体重1kgあたりの経口致死量がそれぞれ30 mg以下、30〜300 mgの薬品をさす。例えば、青酸カリは致死量(ラット)2.5 mg/kgの猛毒であり、亜ヒ酸の致死量(138 mg/kg)に比べてはるかに低い。しかし、薬品によって人に与える作用が異なるので、この値だけから亜ヒ酸の毒性を軽くみてはならない。例えばクロロホルムやメチルアルコールのように、中枢神経や心臓を犯し、頭痛、めまい、おう吐、麻酔状態などを引き起こすものや、青酸カリのように血色素を溶解または機能不全に変質させて酸素供給を阻害し、呼吸困難、けいれん、呼吸停止を引き起こすものもある。さらに塩酸、水酸化ナトリウム、ホルマリンなどは消化器の粘膜や組織を犯し、おう吐、吐血、失神などを引き起こすし、ヒ素化合物は新聞報道されているように腎臓や肝臓などの器官に変質を引き起こし慢性的な種々の疾患をもたらす。このように毒物、劇物などの有害物質を含む化学物質は多岐にわたるため、対象に応じて毒物及び劇物取締法、薬事法、農薬取締法、食品衛生法などにより製造や取り扱いが規制されている。指定されている有害物質の正しい知識が必要であるだけではなく、これらの物質や類似の物質を扱うには十分な注意が必要である。
大学、研究所でのアジ化ナトリウム事件では薬品の管理も問題となった。取締法により、毒物や劇物は施錠できる専用の薬品庫に保管し、鍵は責任者が厳重に管理しなければならない。また、使用者と使用日時、使用量と残存量などを明記した記録を残し、適正に使用されているか否かを定期的に薬品の残存量と記録とを比べて管理することになっている。
今回の一連の事件を契機として、文部省から我々に対して薬品の厳重な管理を求める通知が来ており、不備がある場合には速やかに改善するよう強く求められている。今まで以上の厳密な管理を行わなければならないのは言うまでもないが、薬品を扱う人間の責任が一層重く問われることになった。しかし、最も大事なのは、我々が化学薬品に対して安易な気持ちを持つことは断じて許されないということである。犯罪という関点だけではなく、日常的に薬品を扱う人は、防護メガネやゴム手袋の使用、さらには実験後の手洗いなど、事故を未然に防ぐ努力を怠らないことも必要である。
(きたむら のぼる,理学研究科教授)
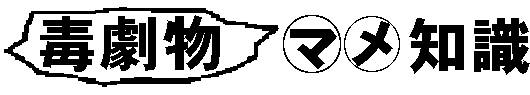
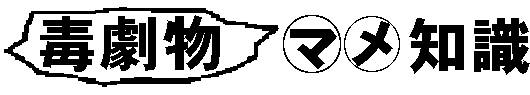
 毒を使った犯罪は歴史の中の話か推理小説の世界のこととばっかり思っていたが、「サリン事件」やヒ素化合物による「毒カレー事件」など、現実の世界で「毒」がお茶の間の話題となる恐ろしい世の中である。また、「カレー事件」以後、アジ化ナトリウムを使ったと思われる事件が、国立大学や国立研究所をもまきこんで連鎖的に起きた。多発する事件を耳にするにつけ、驚きや怒りをとおりこして、情けなく感じているのは私一人であろうか?サリンは特殊な薬品で我々が手にすることは無いが、ヒ素化合物やアジ化ナトリウムは化学実験などで薬品を取り扱う人間にとっては決して特殊ではない。化学薬品を日常的に使っている者として、それが不正に使用され、殺人にまで至ってしまったことに深い憤りを感じる。今後このような悲惨な事件やグリコの毒入りチョコレート事件などといった人騒がせなことが起こらないように、これを機会に毒物や劇物の危険性やその規制・管理体制について少し学ぶのも良いであろう。
毒を使った犯罪は歴史の中の話か推理小説の世界のこととばっかり思っていたが、「サリン事件」やヒ素化合物による「毒カレー事件」など、現実の世界で「毒」がお茶の間の話題となる恐ろしい世の中である。また、「カレー事件」以後、アジ化ナトリウムを使ったと思われる事件が、国立大学や国立研究所をもまきこんで連鎖的に起きた。多発する事件を耳にするにつけ、驚きや怒りをとおりこして、情けなく感じているのは私一人であろうか?サリンは特殊な薬品で我々が手にすることは無いが、ヒ素化合物やアジ化ナトリウムは化学実験などで薬品を取り扱う人間にとっては決して特殊ではない。化学薬品を日常的に使っている者として、それが不正に使用され、殺人にまで至ってしまったことに深い憤りを感じる。今後このような悲惨な事件やグリコの毒入りチョコレート事件などといった人騒がせなことが起こらないように、これを機会に毒物や劇物の危険性やその規制・管理体制について少し学ぶのも良いであろう。