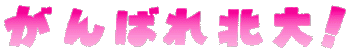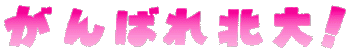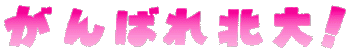 |
| 北海道赤十字血液センター 品質部 刀根 勇一 |
プロフィール (とね ゆういち)
| 1964年 | 北海道生れ |
| 1985年 | 北海道大学医療技術短期大学部 衛生技術学科卒業 |
| | 北海道赤十字血液センター入社 臨床検査技師 |
 |
| 第10回日本海オロロンライントライアスロン |
| 国際大会(1996.8.25) |
近況:鉄人への道
学生時代は、これといって運動部に所属していたわけではないのですが、社会人二年目になって初めてエントリーしたマラソン大会をきっかけに、札幌マラソン、北海道マラソン、ホノルルマラソンなどの大会に多数出場しております。さらに走るだけではなく、マスターズスイミング大会などの水泳大会、ツールド北海道などの自転車レース…はたまた、シドニーオリンピックで正式種目となった「スイム−自転車−ラン」のトライアスロン大会と止まるところを知りません。
今回も日本最長(スイム2.0km、自転車200.9km、ラン41.8km)の日本海オロロンライントライアスロン国際大会に出場すべくトレーニングに明け暮れている毎日です。(因みに、昨年は11時間30分で完走しました。)まあ、成績は別としてこれらのレ−スを経験して唯一自慢できることは、今まで出場した大会すべてに完走していることです。レ−ス中は何度となく「もうやめたい…やめようよ」と自分に問いかけているのですが、なんとか最後はゴ−ルにたどり着いてきました。
夢は、トライアスリートなら誰もが憧れるハワイ島コナで開催される「アイアンマンハワイ大会」です。いつかはトライアスロン発祥の地で真の「アイアンマン:鉄人」になりたいと思っています。
学生時代:臨床実習「職人への道」
さて、残雪残る北大構内クラーク像前で、万歳三唱記念撮影してから早十二年、学生時代の記憶を辿ることが年々困難になってきている自分が悲しい今日この頃です。
思い返せば、北大医療短大を受験したのは、将来の確固たる希望があったわけではなく、臨床検査技師という職業も「病院で尿検査している人か?」程度の知識しか持ち合わせていませんでした。三年間の臨床実習を含めたカリキュラムを終えた後の臨床検査技師像は、「いかに早く大量検体を処理する能力…職人芸」を持っていることが、ステータスであると感じていました。
卒業して現在の職場である北海道赤十字血液センターに就職が決まりました。はじめて着いた仕事は、HBV、HIV等のウイルス検査でした。
HIVについては、その頃、国民にとってAIDSがまだ「ほかの国での話」という時期でありました(因みに、私たちの臨床検査技師国家試験で初めてAIDSという文字が記載された)が、日赤は献血者のスクリーニングを導入しました。今でこそ、薬害エイズ問題が論議されてはいますが、その頃から血液センタ−職員として血友病患者の悲劇については認識していました。記憶を辿ると、医短二年生の時に、当時帝京大学教授であった阿部英氏が、医短講堂で講演したことを思い出しますが、その時に初めてAIDSという言葉の説明を聞いたのも因果を感じます。
現在、輸血用血液製剤には、PL法が適用され、さらに血液センタ−には「医薬品製造所」として法的規制がかけられており、検査の水準はウィルス感染のウィンドウ期(検査では検出できない期間)をいかに短縮できるかを探求しています。
「輸血は患者のためにある」ことは言うまでもない大前提でありますが、それゆえ血液製剤の安全性と品質を確保することは極めて重要となります。私の現在の業務は、この血液センターにおける品質をいかに維持していけるか、つまり「品質管理システム」の構築です。
この業務は、品質の均一化、すなわち検査手順を含む製造工程手順の均一化をいかにできるかがキーポイントで、誰もが同様な作業ができなければなりません。よって、特定の人しかできない「職人芸」であってはならないのです。
学生時代の臨床実習でよく、「一度しか教えないのでちゃんとメモを取りなさい」と教わったものですがメモを取らなくてもよい検査手順書(マニュアル)を整備しておくことが今、血液センターには求められています。
後輩の皆さんも今後、就職され、それぞれの職場の先輩、上司から教わることと思いますが、その際には「教える立場になって教わる」ということが重要ではないかと考えます。
皆さん、職人ではなく「鉄人」を目指してみませんか?