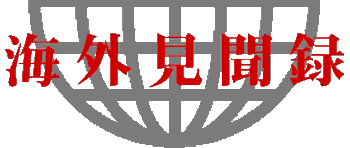 |
| 医療技術短期大学部助教授 久木田 直江 |
 ゆるやかに波うつ丘陵に牧草をはむ羊の群れが点在している。時間に追われる日常の間隙をぬって、イギリスの思い出は霧の中に浮かび上がり、私の脳裏に視像がはっきりと結晶する。1998年10月から翌年の3月まで、文部省在外研究員としてUniversity of Exeterで14〜15世紀の英文学と図像学を研究する機会を得た。イギリス文化が様々な視点から解説されているこのごろだが、イギリス中世の研究者が見たエクセターを紹介したい。
ゆるやかに波うつ丘陵に牧草をはむ羊の群れが点在している。時間に追われる日常の間隙をぬって、イギリスの思い出は霧の中に浮かび上がり、私の脳裏に視像がはっきりと結晶する。1998年10月から翌年の3月まで、文部省在外研究員としてUniversity of Exeterで14〜15世紀の英文学と図像学を研究する機会を得た。イギリス文化が様々な視点から解説されているこのごろだが、イギリス中世の研究者が見たエクセターを紹介したい。
エクセターはイングランド南西に位置するデヴォン州の古都。ローマ時代の城壁、要塞の一部が町の中心にあり、近くのダートムアには新石器時代のストーンサークルや巨石も残っている。でも、エクセターの住民たちの誇りは町の中心に立つ大聖堂だ。1066年のノルマン人によるイングランド征服後、まもなくウイリアム征服王の甥にあたる司教William Warelwastによって建立されたノルマン建築の聖堂の塔が今も聳えたっている。現在の聖堂はイギリス・ゴシック建築を代表する聖堂として名高い。ここで降誕節からクリスマスにかけて行われる様々な礼拝は確実に中世の伝統を受け継いでいる。イギリス国教会が得意とする聖歌隊の歌声が、パイプオルガンに導かれ、‘Minstrel’s Galley’と呼ばれる天使の楽隊を彫刻した身廊上部のギャラリーから、さらに内側から共鳴する時、カテドラルは荘厳と歓喜につつまれる。大聖堂のなかで繰り広げられるこのような礼拝を通して、宗教改革後も悠々と受け継がれているイギリス中世の霊性を存分に吸い込むことこそイギリス中世を学ぶ者にとって、この町ですごす醍醐味だ。中世の町は、また石造りの町でもある。エクセタ−というと、重厚、壮重、伝統などの硬い形容詞が反射的に浮かぶ。同じ時期に栄華をきわめた大陸の石作りの町、たとえば、ベルギ−のブル−ジェやイタリアのシエナのような小粋で洗練された雰囲気はまるでない。
イギリス人が、‘Typical English climate!,’‘Miserable,’‘Grey,again!’とうんざりした顔で肩をすくめる冬をすごし、ぽってりと重たい‘bread’を毎日噛み、ビールで脹らんだ重たそうなイギリス人を見ていると、時間が停止しているような鈍い圧迫感におそわれる。確かに動きがないのはここの特徴だ。階級制が根づいているイギリス社会の中にあって、エクセターは特にホワイト・アングロサクソンが大勢を占めている。伝統のしがらみが変化を妨げている野暮ったい田舎と敬遠されているかと思うや、ここは全英の住みたい町調査でナンバ−ワンになったそうだから、イギリス人の伝統への執着ぶりがわかる。
大聖堂の図書館でかび臭い本と向き合っていると、私まで伝統の亡霊にとりつかれたような感じになってくる。四旬節が始まる二月の半ば、久しぶりに晴れ上がった空に誘われ、フラットの背後にある丘を散策してみた。野草にかくれてマツユキソウ(snowdrop)が咲いている。楚々として咲く小さな白い花が美しい。イギリス人が無類の散歩好きなのも、こうした自然にいまも向き合えることができるからでだろう。伝統の重みでMentalityも体も重そうな彼らは自然との対話でどうやら、静と動、生と死のバランスをとっているのかもしれない。その中から、自然との霊的交わりを求めたロマン派の詩や中世の大聖堂に彫り込まれた‘Green Man’に代表されるおびただしい数の自然のモチ−フが生まれたと想像する。バランス感覚こそがこの島国の文化を支えているのだろう。
 カテドラル(大聖堂)
カテドラル(大聖堂)
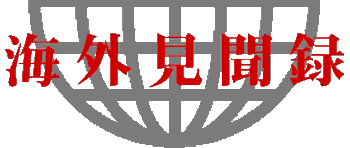
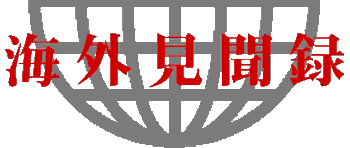
 ゆるやかに波うつ丘陵に牧草をはむ羊の群れが点在している。時間に追われる日常の間隙をぬって、イギリスの思い出は霧の中に浮かび上がり、私の脳裏に視像がはっきりと結晶する。1998年10月から翌年の3月まで、文部省在外研究員としてUniversity of Exeterで14〜15世紀の英文学と図像学を研究する機会を得た。イギリス文化が様々な視点から解説されているこのごろだが、イギリス中世の研究者が見たエクセターを紹介したい。
ゆるやかに波うつ丘陵に牧草をはむ羊の群れが点在している。時間に追われる日常の間隙をぬって、イギリスの思い出は霧の中に浮かび上がり、私の脳裏に視像がはっきりと結晶する。1998年10月から翌年の3月まで、文部省在外研究員としてUniversity of Exeterで14〜15世紀の英文学と図像学を研究する機会を得た。イギリス文化が様々な視点から解説されているこのごろだが、イギリス中世の研究者が見たエクセターを紹介したい。 カテドラル(大聖堂)
カテドラル(大聖堂)