| 大学で何を学ぶか、いかに学ぶか |
| 学生による授業アンケートについて |
| 点検評価委員会委員 阿 部 和 厚 (医学研究科教授) |
「学生による授業アンケート」が今年も行われます。どんな意味があるのでしょうか。
いま日本の大学ではさまざまな改革が進んでいます。これまでの日本の大学教育の流れのなかではほとんど革命といっていいほどです。ここで最も大きいものは教育改革です。
これまで日本の大学は、入ってしまえばあとは卒業できるというような安易なところがありました。企業は就職のとき、どこの大学の出身かが問題であり、何をどの程度学び、身につけてきたかをあまり問題にしませんでした。学生にとって教育は最大の関心事でなく、先生方も教育熱心でなくてよかった。社会も、大学にお任せでよかった。これがいま問題となっています。資源に乏しい日本は、国際競争の時代に、わたしたちの未来を大学の「知」に託さざるを得ないと、卒業生の質を問題にするようになりました。
大学は役に立っているか
大学は最終教育機関であり、教育のために社会に存在します。大学院も高度な教育を提供するところです。ここには社会的に莫大な投資があります。とくに国立大学では、学生の一人一人に授業料の何倍もの予算が投入されています。税金からです。
「大学は、その投資に値する教育をしていますか」「学生は、国民の投資に応えるように勉強していますか」。経済的に厳しいこの時代に、大学は「社会的に役に立っていますか」という問に証拠をもって答える必要がでています。
別の云いかたでは「学生が卒業時に、何を大学で学んだといえますか、何をどの程度身につけましたか」「その実力の証拠は何ですか」と説明が求められ、これにより大学が評価される時代となっています。大学改革は、こういった動きに対する大学教員の懸命の努力です。
教育の質の評価
学生の学力低下が問題とされています。こんな状況で、大学教育によって、学生が何を身につけたか、目標とするレベルの力をつけたかが問われます。先生が一方的に知識を伝える伝統的講義だけでは、もはや教育は成り立ちません。この時代の学生にあわせた教育、教育の質が問題とされ、教育の評価が必要となっています。
教育の質の評価に、多くの大学は、「学生による授業評価」をとりいれています。
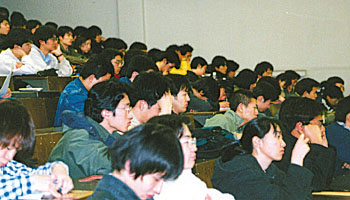 北大では、平成5年、6年に、「学生による教育指導の評価」として授業アンケートを行いました。平成7年には「この評価に対する教員の評価」、また、全学教育について「全学教育レビュー」としてアンケート、平成9年には「成績評価についてのアンケート調査」を行いました。、そして、それらを踏まえて平成10年に「教育についての教員合宿研修」を開始し、平成11年からは、「教員の教育業績評価」と「学生による授業アンケート」を毎年行うことにしました。これらの動きは、北大の教育改善への学生と先生との共同作業であり、全国でも最もしっかりしたものとして高く評価されています。だが、授業はよくなったでしょうか?
北大では、平成5年、6年に、「学生による教育指導の評価」として授業アンケートを行いました。平成7年には「この評価に対する教員の評価」、また、全学教育について「全学教育レビュー」としてアンケート、平成9年には「成績評価についてのアンケート調査」を行いました。、そして、それらを踏まえて平成10年に「教育についての教員合宿研修」を開始し、平成11年からは、「教員の教育業績評価」と「学生による授業アンケート」を毎年行うことにしました。これらの動きは、北大の教育改善への学生と先生との共同作業であり、全国でも最もしっかりしたものとして高く評価されています。だが、授業はよくなったでしょうか?
「学生による授業アンケート」の目的と内容
平成12年3月に発行された「平成11年北海道大学年次報告書ー来るべき新世紀に向けて」には、平成11年度前期授業についてのアンケート結果が詳細に記載されています。
このアンケートの目的は、第一に各先生の授業改善、第二に北大全体あるいは各学部での組織的授業改善の促進、第三に先生方の授業改善への意識改革、第四に学生の学習意欲への意識改革です。そして改善のモニターとして継続的に実施する必要があります。
アンケートは、17の設問からなります。15問は先生の授業について、最後の2問は学生の出席と授業態度についてであり、5段階評価で回答します。また、最後には、自由意見を述べる欄がもうけられ、その授業に対する生の意見や教育環境についての意見が求められています。
アンケートの結果
平成11年度には1000以上の授業がアンケートに応じました。
評価には、全体的には、文系理系学部で差がありました。文系の授業の方が、理系の授業よりも、教師の熱意が伝わりやすく、話し方が聞き取りやすく、わかりやすく、授業の進行速度や作業量は適切であり、学習意欲がわいたという結果でした。また、シラバスも整備され、授業は体系的であるということでした。一方、文系では、授業への出席状況、授業で学生参加を促すかについては低い評価でした。他方、授業におけるメディアの効果的使用法、学生参加の促進、学生の質問、発言への対応の適切さ、内容の難易度、内容の理解、学生の授業への積極的参加(質問、発言、調査、自習など)には差がありませんでした。
このような文系、理系の差異は、文系では演習が多く、クラスサイズも小さいものが多いこと、選択科目が多いこと、欠席が多く残った学習意欲のある学生による回答であったことなどから来るようです。逆に、理系では必修科目が多いことが評価点をさげていそうです。
学生は教員に対して好意的に評価していました。安心しました。一方、授業はわかりやすかったか、授業内容の難易度は適切だったか、授業の履修目標を達成できたか、授業内容と他の領域との関連について理解できたかなどには、授業というよりは、学生自身の自己評価とし、悪い点数でした。質問、発言、調査、自習などにより授業に積極的に参加したか、学生自身の理解を問われている設問には低くく自己評価しています。学生は深い理解を求められる授業、難解な理論には、一般に弱い、苦手意識があることを示します。理論を求める理系の評価が低いのはここにも理由があるかもしれません。
言語文化部の授業は、一般に好評でした。学生との相互反応のある授業を必然とする授業形態が求められ、しかもクラスサイズが小さいためとみなされます。一般の授業にもこのような授業法をとりいれると効果的なようです。
アンケート結果は、1)演習、25人以下の小人数授業、2)学生を積極的に参加させる学生参加型授業、3)理論を丁寧に展開説明する授業、4)大人数の場合にはその条件を十分に配慮した授業を求めています。また、評点にはざまざまな要素が影響を与え、教員個人評価は、評点だけでは優劣をつけられないことも明らかになりました。
自由意見
自由意見は、生の声として参考になりました。一番多い意見は、授業法に関して黒板の使い方・文字の大きさ・見やすさ・横文字を読めるようになど、OHP、ビデオ、プリントなどのメディア利用に関する意見が最も多く、ついで、発声・発音・話す速さ・声の大きさ等の、話し方に関する意見、ついで、授業の速度・内容の負担についての意見、さらに、授業の構成、学生との信頼関係についての意見などがありました。各教員は、担当の授業に対する自由意見が最も参考になります。報告書には、これらの意見をまとめて、授業の改善方法についてもまとめました。
 授業評価は、教育改善への学生参加
授業評価は、教育改善への学生参加
いま、大学は教育を大きく評価されています。また、各先生の教育も評価されます。授業評価は、教育の受け手、教育の主人公からの評価です。教育改善への貴重な資料となります。先生は学生から学ぶ。授業評価は、教育改善への学生参加ともいえます。そして、今日の大学の教育改革は、学生が大学で学ぶことで大きく発展できる力をつけてもらうためにあります。ここでは、高い学習意欲と普段の学習が求められ、学生の学ぶ責任は厳正な成績評価で測られるでしょう。教育改善は、学生と先生との共同作業です。
 授業評価は、教育改善への学生参加
授業評価は、教育改善への学生参加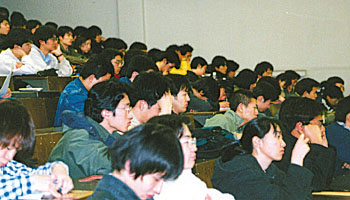 北大では、平成5年、6年に、「学生による教育指導の評価」として授業アンケートを行いました。平成7年には「この評価に対する教員の評価」、また、全学教育について「全学教育レビュー」としてアンケート、平成9年には「成績評価についてのアンケート調査」を行いました。、そして、それらを踏まえて平成10年に「教育についての教員合宿研修」を開始し、平成11年からは、「教員の教育業績評価」と「学生による授業アンケート」を毎年行うことにしました。これらの動きは、北大の教育改善への学生と先生との共同作業であり、全国でも最もしっかりしたものとして高く評価されています。だが、授業はよくなったでしょうか?
北大では、平成5年、6年に、「学生による教育指導の評価」として授業アンケートを行いました。平成7年には「この評価に対する教員の評価」、また、全学教育について「全学教育レビュー」としてアンケート、平成9年には「成績評価についてのアンケート調査」を行いました。、そして、それらを踏まえて平成10年に「教育についての教員合宿研修」を開始し、平成11年からは、「教員の教育業績評価」と「学生による授業アンケート」を毎年行うことにしました。これらの動きは、北大の教育改善への学生と先生との共同作業であり、全国でも最もしっかりしたものとして高く評価されています。だが、授業はよくなったでしょうか?