

| 工学研究科 教 授 佐藤義治(左) |
| 工学研究科 助教授 村井哲也(右) |
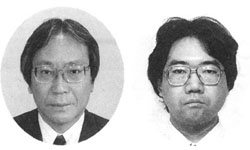
当初、インターネット社会はバーチャル(仮想的な)社会といわれていましたが、もはやバーチャルではなく現実の世界の中に、否応なしに入り込んできています。その意味において、インターネット社会のエチケットや社会常識といっても、それはわれわれの生活している社会となんら変わるところはありません。皆さんが、適正な社会常識と社会エチケットを備えているならば、ネットワーク社会においても適正な判断ができるはずです。
しかし、ここに「ネチケット(ネットワーク・エチケット)」に関して注意を喚起する理由は、ネットワークには“つい”自分ひとりだけで利用しているような錯覚に陥りやすいことや、いろいろなことが“つい”簡単にできてしまった、というように、常に自分自身を律しながら利用しなければネチケット違反になることが多くあります。そのいくつかを以下に紹介しましょう。
(1)ネットワークは自分だけのものではない。
最近は多くの学生が携帯電話を持っているようですが、携帯電話機そのものを持っていても何の意味もなく、それを通信網に登録して初めて役に立つわけです。しかし、その通信網は自分だけのものではありません。コンピュータ・ネットワークも全く同様です。皆さんが利用されているインターネットは、一般社会においても同時に利用されています。そこには重要な情報、例えば気象情報とか火山情報とかが時々刻々と通信されております。その中で自分勝手に膨大な画像情報や多数のひとに同時にメールを送ることは、大変な迷惑をかけることになります。前回も述べましたが、チェーンメールの禁止も同様の理由です。
(2)ユーザID・パスワード管理は厳重に
また、インターネットでは相手の顔が直接見えませんので、他人に成りすまして、人を誹謗・中傷したり道徳的に許されない発言をして、実際に大学から処分された例が、本特集の記事にもあります。自分のパスワードは決して人に教えてはいけませんし、またメールなどに書いてはいけません。ついでながら、個人のプライベートな情報(住所、電話番号、クレジットカード番号等)もメールで流すことは危険です。
(3)メールやWebの内容を鵜呑みにしない。
メールだけではありませんが、世の中にそう“うまい”話はありません。うまく持ちかけられても「ねずみ講」のような行為に加担してはいけませんし、また自分からそのようなことをしてはいけません。
(4)著作権に関しては慎重に。
ネットワーク上では簡単に文書や画像を取り込むことができますが、“それらを雑誌や同人誌に著作権者に無断で掲載”、“芸能人など著名人の写真やキャラクターの似顔絵などの画像データを無断で転載”、“楽曲の歌詞を転載”、“第三者が作成したソフトを許可なくネットなどへ配信すること”などは典型的な著作権の侵害で、罰せられることがあります。
(5)ネット犯罪にまきこまれない。
警察庁のまとめによると、今年の上半期ですでに昨年のネット犯罪件数の8割に達したと発表がありました。たとえば、インターネット・オークションでの詐欺事件が11件もあり、被害者が一件平均20人、被害額が一人当たり約10万円ということです。また、コンピュータ・ウイルスを電子メールで送りつけ、威力業務妨害罪に問われたケースもあります。みなさんも、むやみに、インターネット上の信頼できないサイトからソフトをコピーしますと、そこにウイルスが潜んでいることが多くあります。ウイルスの入ったメールを“つい”送ってしまい、自分自身が加害者にならないように、ウイルスチェックを常に心がけましょう。
| メニューページに戻る |