�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N2009���s�ψ���
���ےS�������E���w���@�{���@���v |
| |
�@���N��3�N�ڂ��}����u�k�C����w�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N�v�́C�����w�╪��Ɖۑ�̑��l���ɂ����āC���ɗނ����Ȃ����j�[�N�ȎЉ�v���E���ی𗬏T�ԂւƐ������C�{�w���\����s���ƂȂ�܂����B
�@�E�B�[�N��11��1���i���j�Ɏn�܂�C18���i���j�܂ł̖�2�T�̊Ԃ�28�̊�悪�W���I�ɊJ�Â���܂����B���E�B�[�N�O��ɊJ�Â����v�����ƃ|�X�g�������킹��ƁC��摍����33�ɋy�т܂��B���N�̓����́u���ʓI�ȃA�v���[�`�v�Ɓu��̓I�ȉۑ�̉�����̒v�����āu�A�g�̐[���v��3�ł����B
�@�E�B�[�N���Ɉ������ۑ�́C�C��E���ϓ���M���ɁC�Z�p�v�V�C���R�ی�C���N�C����C�l���ƕ��L���C�����̌`�Ԃ͍��ۃV���|�W�E���C�����|�X�^�[�R���e�X�g�C�f�B�x�[�g���C�s�������̌��J�u���C�W���C�f��C�J�t�F�C�t�F�A�g���[�h�ȂǁC�e�[�}�Ȃ�тɎ�@�����ŁC���ʓI�ȃA�v���[�`�����݂��܂����B���̂悤�Ȏ�@��ʂ��āC�e���ł́C�����\�ȎЉ�Â���ɌW����̓I�ȉۑ肪���グ���āC�ŐV�̌������ʂ⊈�����ʂɂ��ƂÂ��C�����ւ̓�������܂����B
�@���ꂼ��̊����x�����p�[�g�i�[�́C�C�O�̋����w���͂��ߎ����\�ȎЉ�Â���ɔM�S�ȍ����O�̑�w�C����ɂ�WHO�C���A��w�Ƃ��������ۋ@�ցC�w�p��c��e��w��Ƃ������w�p�R�~���j�e�B�[�CNPO�C�����ĕ����Ȋw�Ȃ���ȁC���y��ʏȂƂ��������{�W�@�ւȂǁC�����O�̂�����Z�N�^�[�ɍL����܂����B����6,500�l���̎Q���҂Ƌ��͎҂Ɏx�����āC���N�̃E�B�[�N���I�����邱�Ƃ��ł��܂����B
�@����͓��ɁC����Z�Ƃ̘A�g��[�߂邽�߁C2009�N4���ɂ��ׂĂ̋���Z�̊w���֏��ҏ���o�����Ƃ���C���ʓI��16����28��w����Q��������C�e�Z�̃T�X�e�i�r���e�B�Ƃ����e�[�}�ւ̊S�̍������f���܂����B���ł��C�A�W�A�H�ȑ�w�i�^�C�j�C�I�E����w�i�t�B�������h�j�C�p�����J������w�i�C���h�l�V�A�j�C�g���m�H�ȑ�w�i�C�^���A�j�C�f���T����w�i�t�B���s���j�C�W���l�[�u��w�i�X�C�X�j�C�A���X�J��w�i�A�����J�j�Ƃ́C�W���C���g�E�V���|�W�E���̊J�ÂɎ���܂����B����ɉ����C�|�[�g�����h�B����w�̊w���ɂ́C�I�[�v�j���O�V���|�W�E���ɂāu�T�X�e�i�r���e�B�����Ɍ��������g�݂ɂ�����s�s��w�̖����v�Ƒ肵�Ċ�u�������������܂����B���ɂ��C�i�C�W�F���A��w����w�����C�p���H�ƕ������w��������w�C�k����w�C�g���m�H�ȑ�w���畛�w�������E�B�[�N���Ԓ��̍s���ɎQ�����邽�߂ɗ��K���܂����B��������ɁC�����Ɍ����āu�T�X�e�i�r���e�B�v�ɌW��A�g�̂���Ȃ�[����}��ׂ��ӌ������킵�܂����B
�@�܂���N�̔��Ȃ���C�w���̎Q�����i�ɗ͂����C�I�[�v�j���O�V���|�W�E���J�Ó��i11��2���j�ɁC�u��1��k�C����w�T�X�e�i�r���e�B�w�������|�X�^�[�R���e�X�g�v���J�Â��܂����B���̃R���e�X�g�ɂ́C���߂Ă̎��݂ɂ�������炸72���̎Q��������C�����\�ȎЉ�Â���Ɋ֘A����ۑ�Ɏ��g�ފw�����������邱�Ƃ����߂Ď������܂����B�����͍�͊w���O�̐R�����ɂ���ĐR������C�u��1��k�C����w�T�X�e�i�r���e�B�����|�X�^�[�܁v��I�o���C���̖�Ɏ���������s���܂����B�܂��C�u�k�匳�C�v���W�F�N�g�v�ɍ̑����ꂽ�w�����̒�����5�c�̂��C�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N�ɎQ������ȂǁC��N�Ɣ�r���Ċw���̎Q���͊m���ɑ����錋�ʂƂȂ�܂����B
�@���Ԓ��Ɏ��{�����Q���҃A���P�[�g��q�����܂��ƁC���E�B�[�N���k�C����w�̓����I�ȍs���Ƃ��ĔF�߂����邱�ƁC�����Ă���Ȃ锭�W�����҂���Ă��邱�Ƃ�ǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B���N�̃T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N2010�́C10��25���i���j�ɃI�[�v�j���O���J�Â��C��2�T�Ԃ̓����ŊJ�Â���\��ł��B���N�̊J�Â�ʂ��Ė��炩�ɂȂ����^�c��̖��_���������C��葽���̋��͎҂ƎQ���҂āC��̓I�ȉۑ�����Ɍ������c�_�ƍs��������������������ƍl���Ă���܂��B |
| |
|
| |
����搔�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E33
�@�@�@�@�@�ۑ�ʊ�搔�E�E�E�E�E�C��E���ϓ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@19���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�m�I�v���E�Z�p�v�V�E�Љ�ϊv�@ 16���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E���R�j�E�������l���E���R�ی� �@13���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�H�ƁE���E�q���E���N�@�@�@�@�@�@�@ �@12���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E����E�l�ވ琬�E�[���@�@�@�@�@�@�@ 19���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E�l���E�����E���a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@8���
���Q���Ґ��E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E8,440�l
����w�Ԍ𗬋���Z����̎Q���@16����28��w�i2009�N11��1������24����76�@�ւƓ������������Ă���j
���E�F�u�T�C�g�K��Ґ��@25,776�l�i2009�N4��1���`12��9���j |
| |
| |
| �@ |
|
�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N2009�I�[�v�j���O�V���|�W�E���@�@�@�@
�k�C����w�u�����\�ȊJ���v���ۃV���|�W�E��
�`�����\�ȃO���[�o���Љ�Ɍ������T�ۑ�����ւ̒` |
 |
| |
| ���@���F11��2���i���j�@�@��@���F�w�p�𗬉�� |
| |
�@�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N2009�̃X�^�[�g������s���Ƃ��āC11��2���i���j�ɖ{�w�w�p�𗬉�قɂ����� �g�k�C����w�u�����\�ȊJ���v���ۃV���|�W�E���`�����\�ȃO���[�o���Љ�Ɍ�����5�ۑ�����ւ̒`�h���J�Â������܂����B
�@�`���̃I�[�v�j���O�E�Z�����j�[�ł́C������������T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N�̂���܂ł̌o�܂̏Љ����܂����B����ɁC�{�w�̓T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N2009��ʂ��Ė{�w�́C�C��ϓ��⊴���ǂ̊g��C�������̌͊��Ƃ������n���K�͂̉ۑ�̉����Ɍ����āC�����Ƌ���C��M�����ĘA�g������܂ňȏ�ɉ���������Ƃ̘b������܂����B���̌�̗��o���A�ł́C�͂��߂ɕ����Ȋw�Ȗؑ]�����ۓ���������C����̒������\�ȎЉ�̍\�z�Ɋ�^���邱�Ƃ��Ȋw�ȂƂ��đ傢�Ɋ��҂��Ă���|���q�ׂ��܂����B���ɎD�y�s�̏�c���Y�s������C�D�y���玝���\�ȎЉ�̎����Ɍ��������g�݂�i�߂čs�����Ƃ͑傫�ȈӋ`������|�q�ׂ��܂����B
�@�����čs��ꂽ��u���ł́C�Â�����̋���Z�ł���|�[�g�����h�B����w���烔�B���E���B���F���w�������������āC�u�T�X�e�i�r���e�B�����Ɍ��������g�݂ɂ�����s�s��w�̖����v�肵�����u�������������܂����B�u���ł́C�T�X�e�i�r���e�B�̎����Ɍ������|�[�g�����h�B����w�ƒn��Љ�C��ƁC�����c�̂Ƃ̘A�g�E�������Ƃɂ��āC�u�o�ρv�u���v�u�Љ�v�Ƃ����u3�̃{�g�����C���v����̃A�v���[�`�@���Љ�C����̌o�������Ɉӌ����q�ׂ��܂����B
�@���N�͖k�C����w�u�����\�ȊJ���v���ې헪�{���ݒu5�N�ڂɂ�����ߖڂ̔N�ƂȂ邱�Ƃ���C�Z�����j�[�Ɉ��������s��ꂽ�I�[�v�j���O�V���|�W�E���ł́C�����ې헪�{��������܂ŏW���I�Ɏ��g��ł���5�̈�ɂ��āC�{�w�����⍑���O�̌����҂݂̂Ȃ炸�C���ƊW�ҁC���_�ƁC�V���L�҂Ƃ��������l�ȃX�e�[�N�z���_�[���C�ȉ���6���e�[�}�ɁC�ۑ�����Ɍ��������s���܂����B�܂��C�����̒ɑ��C���Ȃ̏��ѐ�����b���[�R�c������́C������̗��Ăɂ����āC��w����̒͏d�v�ł���Ƃ̃R�����g������܂����B |
| |
| �q�k�C����w����̒r |
�E�l�b���ʊ����Ǒ�̊�Ղ̓O���[�o���T�[�x�C�����X�ɂ���
�@
�@�|���C�u�^�C�����ăp���f�~�b�N�C���t���G���U���Ɂ|
�E���̍��ۊJ�������ɑ�����{�̖���
�E���A�W�A�̊��o�ϋ��͂ɂ�萢�E�̃O���[���Z���^�[���������悤
�E�H���ƃG�l���M�[�̎����ɂ����{�_�Ƃ̎����`�k�C�����f���̒`
�E�I�z�[�c�N�C�̖����\���Ɍ��������ۃR���\�[�V�A���\�z
�E�����\�ȎЉ�Â����S����������@�ւ̃C�j�V�A�`�u |
|
|
| |
 |
 |
| ���̗l�q |
�|�[�g�����h�B����w���B���E���B�E�F��
�w���̊�u�� |
 |
 |
| �|�X�^�[�R���e�X�g�̗l�q |
�����ƋL�O�B�e�����܃O���[�v |
|
| |
�@�܂��C�w���������g��ł��錤�����u�����\�ȎЉ�Â���ւ̍v���v�Ƃ����ϓ_�Ō��ߒ����悤�������C�l�ދ��ʂ̉ۑ�����ɒ��ވ�ނ̔y�o��ړI�Ƃ��āC�{�w�Ƃ��Ă͏��߂đS�w�I�ȃ|�X�^�[�R���e�X�g���J�Â��܂����B�S�w����V�Q���̃|�X�^�[�Q��������C���ƂȂ����w�p�𗬉�ق̂P�K�z�[���͎Q���҂̃v���[���e�[�V�����ŔM���M�C�ɕ�܂�܂����B�R���e�X�g�ł́C�R�����̓��[����āu��P��k�C����w�T�X�e�i�r���e�B�����|�X�^�[�܁v���I��܂����B
�@��̈��A�ł́C�{�����v���s�ψ������C������l�ދ��ʂ̉ۑ�ɑ��ϋɓI�ɉ��������Ă����������Ă����Əq�ׂāC�V���|�W�E���͕�����܂����B
�@����̃T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N�́C����22�N10��25���i���j����J�Â���\��ł��B |
| |
| �y��1��k�C����w�T�X�e�i�r���e�B�����|�X�^�[��҈ꗗ�z |
|
| 1�j |
���w�T������ |
|
�ŗD�G�܁F |
���ā@���i�i�_�w�@�@���m3�N�j |
|
�D�G�܁F |
��|�@�T�q�i��w�����ȁ@�C�m2�N�j |
|
�D�G�܁F |
�A�@�@�j�o�i���Ȋw�@�@���m2�N�j |
|
|
�@ |
| 2�j |
�u���C�N�E�X���[���� �C��E���ϓ����� |
|
�ŗD�G�܁F |
�N���G���@�v���V���i���Ȋw�@�@���m3�N�j |
|
�D�G�܁F |
�����@��G�i���Ȋw�@�@�C�m2�N�j |
|
�D�G�܁F |
�����@�[��q�i���Ȋw�@�@���m3�N�j |
|
|
|
| |
|
| 3�j |
�u���C�N�E�X���[���� �m�I�v���E�Z�p�v�V�E�Љ�ϊv���� |
|
�ŗD�G�܁F |
�g�c�@�����i����������w�@2�N�j,�{�R�@��q�i����������w�@1�N�j, |
|
|
�d���@�����Y�i����������w�@1�N�j,��ҁ@�q�F�i����������w�@2�N�j |
|
|
�i�ȏ�4��1�`�[���Ŏ�܁j |
|
�D�G�܁F |
�I�����V�I�@�h�N���X�@�~�����X�i���Ȋw�@�@�C�m1�N�j |
|
�D�G�܁F |
���c�@�L�Ɓi���ۍL�f�B�A�E�ό��w�@�@���m2�N�j, |
|
|
�_�j�[�@�k�[�i���Ȋw�����ȁ@���m2�N�j |
|
|
�i�ȏ�2��1�`�[���Ŏ�܁j |
|
|
|
| |
|
| 4�j |
�u���C�N�E�X���[���� ���R�j�E�������l���E���R�ی앪�� |
|
�ŗD�G�܁F |
�X�@�ƋM�i���Ȋw�@�@���m3�N�j |
|
�D�G�܁F |
�����@�ڔ��q�i���Ȋw�@�@���m3�N�j, |
|
|
���@��b�i���Ȋw�@ �C�m1�N�j,�Ίہ@�ĊC�i���Ȋw�@ ���m2�N�j |
|
|
�i�ȏ�3��1�`�[���Ŏ�܁j |
|
|
|
| |
|
| 5�j |
�u���C�N�E�X���[���� �H�ƁE���E�q���E���N���� |
|
�ŗD�G�܁F |
�����@�ڔ��q�i���Ȋw�@ ���m3�N�j,���@��b�i���Ȋw�@ �C�m1�N�j, |
|
|
�Ίہ@�ĊC�i���Ȋw�@ ���m2�N�j |
|
|
�i�ȏ�3��1�`�[���Ŏ�܁j |
|
�D�G�܁F |
�O���@�`�L�i���Ȋw�@�@���m1�N�j |
|
|
|
| |
|
| 6�j |
�u���C�N�E�X���[���� ����E�l�ވ琬�E�[������ |
|
�ŗD�G�܁F |
�g�c�@�����i����������w�@2�N�j,�{�R�@��q�i����������w�@1�N�j, |
|
|
�d���@�����Y�i����������w�@1�N�j,��ҁ@�q�F�i����������w�@2�N�j�@ |
|
|
�i�ȏ�4��1�`�[���Ŏ�܁j |
|
�D�G�܁F |
�I�����V�I�@�h�N���X�@�~�����X�i���Ȋw�@�@�C�m1�N�j |
|
�D�G�܁F |
�O���@�`�L�i���Ȋw�@�@���m1�N�j |
|
|
|
| |
|
| 7�j |
�u���C�N�E�X���[���� �l���E�����E���a���� |
|
�ŗD�G�܁F |
�g�c�@�����i����������w�@2�N�j,�{�R�@��q�i����������w�@1�N�j, |
|
|
�d���@�����Y�i����������w�@1�N�j,��ҁ@�q�F�i����������w�@2�N�j |
|
|
�i�ȏ�4��1�`�[���Ŏ�܁j |
|
�D�G�܁F |
�����@��G�i���Ȋw�@�@�C�m2�N�j |
|
|
|
| |
|
| 8�j |
�O�b�h�E�R�~���j�P�[�V�������� |
|
�ŗD�G�܁F |
��@�ԁi���ۍL�f�B�A�E�ό��w�@�@�C�m1�N�j |
|
�D�G�܁F |
�O���@�O���@�q�_���b�g�i�_�w�@�@���m2�N�j |
|
|
|
| |
|
| 9�j |
���͂���|�X�^�[���� |
|
�ŗD�G�܁F |
�����@�m�q�i�_�w�@�@���m1�N�j |
|
�D�G�܁F |
���c�@�L�Ɓi���ۍL�f�B�A�E�ό��w�@�@���m2�N�j, |
|
|
�_�j�[�@�k�[�i�H�w�����ȁ@���m2�N�j |
|
|
�i�ȏ�2��1�`�[���Ŏ�܁j |
|
�D�G�܁F |
��@�ԁi���ۍL�f�B�A�E�ό��w�@�@�C�m1�N�j |
|
|
| |
| �@ |
| |
| 2009�N�A�W�A�����m�M�������A���w��A�j���A���T�~�b�g�E���ۉ�c |
 |
| |
���@ ���F10��4���i���j�`10��7���i���j�@�@
��@ ���F�w�p�𗬉�فi10��4���j�C�D�y�R���x���V�����Z���^�[�i10��5���`7���j�@
��\�ҁF���Ȋw�����ȁ@�����@�{�i�@��� |
| |
�@�A�W�A�����m�M�������A���w��iAPSIPA�j�́C�M�������_�y�я���E�ʐM�Ɋւ���w��C�Z�p�̒����C�����y�ђm���̌������s���C����ɂ��w��C�Z�p�y�ъ֘A���Ƃ̐U���Ɋ�^���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���2009�N4���ɐݗ����ꂽ�w��ł��B���ƂƂ��ĐM�������_�y�я���E�ʐM�Ɋւ���u����C���_��y�ь��w��̊J�ÁC�w�p�̒��������C�w��C�Z�p�̏���y�ѕ��y���ƁC���}���y�юG���̊��s�����s���\��ł��B
�@10��4���i���j����J�Â���APSIPA ASC 2009�́CAPSIPA�w���Â���ŏ��̍��ۉ�c�ł���C�M�������C����Z�p�C���ʐM�̍Ő�[�Z�p�̕Ƃ����Ɋւ��錤�����_���s���܂����B�����̃e�[�}�́C�����̓d�C�ʐM�ɂ�����Z�p�J���C���i�J���C�Љ�E�Y�Ɗ�Ղ̍\�z�ɂ����ĕK�v�s���Ȃ��̂ł���C���ɉ䂪���̓d�C�ʐM�ɌW��錤���E�Z�p�҂ɑ��錤�����\�̋@�����C�Z�p�����⌤���𗬂̏�Ƃ��Ă����̖������ʂ����܂����B
�@17�J�������260���̎Q���ғo�^�̂�������c�ł���C�u�M�������E����E���ʐM�v�̕���ɂ�����C�����̒����Ȍ����҂��W�܂�C�������ʂ\���܂����B2�̃v���i���[�E�L�[�m�[�g�E�X�s�[�`�C6�̃`���[�g���A���Z�b�V�����C3�̃p�l���Z�b�V�����C20�̈�ʃI�[�����Z�b�V�����C10�̃|�X�^�[�Z�b�V�������C4���ԂŎ��{���Ă���C�Ő�[�����J���Ɋւ���L�v�ȓ��_�����{����܂����B |
| |
 |
 |
| �p�l���Z�b�V�����̗l�q |
�|�X�^�[�Z�b�V�����̗l�q |
|
| |
| �@ |
| |
| ��9���T���w��ۃV���|�W�E�� |
 |
| |
���@ ���F10��12���i���E�j�j�`10��14���i���j
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF���w�����@�����n�k�ΎR�����ϑ��Z���^�[ �����@�Ζ@�� |
| |
�@�e��v����@�𗘗p���Ēn���̃C���[�W���O���s�������T���Z�p�́C�V�R�����J���C�Љ��Ր����C���C���R�ЊQ�Ȃǂ̕���ŏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���C�����\�ȎЉ�\�z�̂��߂̊�Z�p�Ƃ��Ă̏d�v���������Ă��܂��B
�@10��12���i���E�j�j����J�Â�����9���T���w��ۃV���|�W�E���ł́C�T���Z�p�ɂ���ē���ꂽ���ʂ��ǂ̂悤�ɉ��߂��邩�C�܂��C�����\�ȊJ���Ƃ����Љ�I�ۑ�ɂǂ̂悤�ɍv�����邩�Ƃ����e�[�}�ɏd�_��u���C�䂪���̌����J�����ʂ̊C�O�ւ̏�M�C�C�O�w��W�ҁC�Z�p�҂Ƃ̏������̏�����ړI�ŊJ�Â���܂����B
�@�V���|�W�E���ł́C�O���l69�����܂�193���̎Q���҂�����C�C�O����̏��Ҏ�1�����܂�3���̒����Ȍ����҂ɂ���u���y�э����O�����134���̈�ʍu�����s���܂����B����ɁC�n����T���[�Z�p��m�낤�|�����\�ȊJ���̂��߂Ɂ|�Ƃ����e�[�}�ŁC�C�O�Q���҂ɂ��e���̎��g�݂ɂ���17���̃|�X�^�[�W����C�O�w����Ƃɂ��10���̋Z�p�W�����s���܂����B�����̊w�p�I������ʂ��āC�䂪���̌����J�����ʂ̊C�O�ւ̔��M�C�C�O���ƂƂ̒m���C�Z�p�̏��������s���C�����T���Z�p�̏����֔��W�⎝���\�ȊJ���ւ̍v���ɂ��āC����I�Ȑi�����}���邱�Ƃ����҂���܂��B
�@����́C���ɍ��ۃV���|�W�E���ł͐��N�̈琬�ƎЉ�̌[�ււ̎��g�݂Ƃ��āu���āC�ӂ�āC�l����|�������������̏Z�݂��n���v�Ƒ肵�ăt�B�[���h������s�������W�����s���܂����B���ۃV���|�W�E���J�n�O����10��11���i���j�ɁC�D�y�ߍx�̏��w�Z���w�N�E���w��23���y�т��̐e18�����Q�����Č��n���w���L��ΎR�y�я��a�V�R�ŊJ�Â��܂����B����ɁC�V���|�W�E���������j���ł������̂ŁC�Љ�ɂ����镨���T���֘A�Z�p�ɑ��闝����[�߂邽�ߊ�u���⏔�W�����s���ɂ����J�������҂Ƃ̌𗬂�}��܂����B�����ɂ��C�����\�ȎЉ�����̂��߂̊�Z�p�Ƃ��Ă̕����T���Z�p���s���ɂ��L����������C������ɂ��p������邱�Ƃ����҂���܂��B |
| |
 |
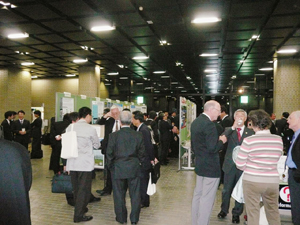 |
| ���n���w��̗l�q |
���키�|�X�^�[���\��� |
|
| |
| �@ |
| |
| �w���u�O���[���E�j���[�f�B�[���v��6��f�B�x�[�g��� |
 |
| |
���@ ���F10��24���i�y�j
��@ ���F�l���E�Љ�Ȋw�������猤����
��\�ҁF�o�ϊw�����ȁ@�y�����@���{�@�w |
| |
�@���N�ő�6��ڂ��}�����o�ϊw����Ãf�B�x�[�g���́C�e�[�}��V���Ɂu�O���[���E�j���[�f�B�[���`�k�C���ւ̒`�v�Ƃ��C���߂ăT�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N�ɎQ�����܂����B�o��`�[�������N���������C���N��13�`�[�����G���g���[���܂����B�c�O�Ȃ���V�^�C���t���G���U�̉e���ŁC�o���f�O����`�[���C�����o�[�Ɍ�����������`�[���ȂǃA�N�V�f���g������܂������C���ꂼ��̃`�[���͎����������l�������C�m�͂������ČJ��L���܂����B
�@�����́C�ŏ��Ɋe�`�[��10�����̃v���[���e�[�V�������s���C���̌�20���ɂ킽���Č݂��Ɏ��^�������C�_���W�J���܂����B������̃`�[�������N�̃e�[�}�ɂ����āC�u�k�C���͂����ɂ��Ċ������i�߂�ׂ����v�ɂ��ēƎ��̒�Ă������܂����B
�@�����͔���W��i�����������@���C�f�B�x�[�g�����o�������w�������ɖ��߂Ă��炢�܂����B�ڐ�������C���苦�c�����������Ƃ����т��тł����B�܂��C���N���炱�̋��c�̎��Ԃ��I�[�f�B�G���X����̎���̎��Ԃɏ[�āC�{�ԂƂ͂܂��ʂ̐���ŁC�����̎��₪�o��`�[���Ɋ��܂����B
�@�D���`�[���͌o�ϊw���F�c�[�~����̃`�[��UNO�B���D���͖@�w���E���w���E�H�w���̍����`�[��WOS�ł����B
�@�{�s���͊w�����Ɖ@�����ꏏ�ɍ��グ��s���ł���C���w������̏o����蒅���Ă��Ă��܂��B�{�s����ʂ��āC�w�����E�@�����҂Ƃ��R�~���j�e�B�[�\�́E�v���[���e�[�V�����\�͂������ǂ��@��ƂȂ�C�܂��C����̃e�[�}�͍��ł��v�l����������N���ׂ��g�s�b�N�Ƒ����Ă��܂��B���N���܂�����܂œ��l�C�w�������Ɏv�l�����N������s���ɂ��Ă��������ƍl���Ă��܂��B |
| |
 |
 |
| �v���[���e�[�V�������s���o��`�[�� |
�o��`�[���ƃI�[�f�B�G���X�ł̎��^�����̗l�q |
|
| |
| �@ |
| |
| CLARK THEATER 2009 |
 |
|
| |
���@ ���F10��30���i���j�`11��3���i�E�j�j
��@ ���F�N���[�N���
��\�ҁF�H�w��3�N�C�k��f��كv���W�F�N�g���s�ψ���2009�����s�ψ����@���@�G�P |
| |
�@�F�l�̂������̉��C���N��������CLARK THEATER�̃t�B�i�[�����}���邱�Ƃ��ł��܂����B���̏�����肵�č���x�����ꂢ�����������q�l�C���x�������������W�Ҋe�ʂɊ��ӂ̈ӂ�\�������Ǝv���܂��B���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���N��CLARK THEATER��10��30���i���j����T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N2009�ւ̊w�����Ƃ��Ă̎Q���Ɏn�܂�C�I�[�v�j���O�ł́w�݂��̂����x��f�C���E�L���̃A�E�g�h�A�f��Ղł���o���t�E�}�E���e���t�B�����E�t�F�X�e�B�o���̓��W�v���O������f����ʊ��u�s�s���Ȑ^���̐�ցv�ɕ\��Ă���悤�ɁC�f��قƂ��Ắu�����v�Ƃ����e�[�}�ւ̃A�v���[�`�������ł����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�@���ɖk�C����w�u�����\�Ȓ�Y�f�Љ�v�v���W�F�N�g�`�[���Ɗ��Ȗk�C���n�����������Ƃ̋��Âōs�����u�s�s���Ȑ^���̐�ցv�ɂ͑����̂��q�l�ɂ����ꂢ�������C�f��w�s�s���Ȑ^���x�̊ӏ܂ƕ����ċ����[���Q�X�g�̕��X�̂��ꂼ��̂��b�Ɏ����X���Ă�������Ⴂ�܂����B�����čX�Ɋ��������ƂɁC�A�����Ċ��Ȏ�Âōs�����u�n�����g������Z�~�i�[�v�ɂ��吨�̂��q�l�ɎQ�����Ă��������C���̃C�x���g����悵�������̖ڕW�ʂ�C�n�����g���Ƃ������ɑ��āC�f���Ƃ�����r�I����₷����������̃A�v���[�`�ň�ʂ̕��ƈꏏ�ɂ܂��́u�l����v���Ƃ���n�߂�C�x���g�����グ�邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B
�@������k��f��كv���W�F�N�g���s�ψ���́C�l�X�Ȑ���ŋ���@�ւƂ��Ă̑�w�ɏ�݉f��ق����݂��邱�Ƃ̉\�����������̊�����ʂ��đi���Ă�����Ǝv���܂��B |
| |
 |
 |
| �g�[�N�Z�b�V�����̗l�q |
�����̊ϋq���l�߂�������� |
|
| |
| �@ |
| |
| �k��f��ف~�k���Y�fPT�~���Ȓn�����g������Z�~�i�[ |
 |
| |
���@ ���F11��1���i���j
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF���Ȗk�C���n�����������@����ۉے��⍲�@���c�@���l |
| |
�@���Ȗk�C���n�����������ł́C�k�C����w��Y�f�v���W�F�N�g�`�[���C�k��f��كv���W�F�N�g���s�ψ���2009�̋��ÂāC11��1���i���j�Ɂu�n�����g������Z�~�i�[�v���J�Â��܂����B�{�Z�~�i�[�̊J�Âɐ旧���C�k��f��كv���W�F�N�g���s�ψ���2009�ɂ��f��u�s�s���Ȑ^���v�̏�f�ƃg�[�N�Z�b�V�������s���C�Z�~�i�[�̎Q���҂̑����͉f����ӏ܂��C�n�����g�����ɂ��Ă̖��ӎ�����������ł̎Q���ƂȂ�܂����B�@�@�@�@
�@�Z�~�i�[�ł͂܂��C���Ȗk�C���n�����������̒|���ꓝ�����ۑS��抯����̈��A�̌�C���Ȋ��ی��������X�N�]�������̒˖{���玁����IPCC�i�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���j��4���̓��e�ɂ��Ă̍u��������܂����B�u���ł́C�C��V�X�e���̉��g���ɂ͋^���]�n���Ȃ����ƁC20���I���Έȍ~�̐��E���ϋC���̏㏸�͂��̑啔�����l�Ԋ����ɂ�鉷�����ʃK�X�̑����ɂ���Ă����炳�ꂽ�\�������ɍ������ƁC�n�����g���̉e���͊��Ɍ���Ă��邱�ƂȂǂ��Љ��܂����B
�@�����Ėk�C����w����������w�@���C�����̐[�����m������C�����O�̒n�����g����Ɋւ��鐭��̓����ɂ��ďЉ����܂����B���̌�͖�80���̎Q���҂Ƃ̎��^�������s���C�����Ȉӌ��������s���܂����B���^�����ł͒˖{���C�[�����ɉ����Ėk�C����w��w�@�n�����Ȋw�����@���C�y�����̓��䌫�F�����҂Ƃ��ĉ����C�Q���҂���́u�X�т��L���Ȗk�C���̋��݂������߂Ɋ��ȂƗі쒡�����͂��ĐX�ыz�����̔F��J�[�{���E�I�t�Z�b�g�̎�g��i�߂�ׂ��v�C�u���N�x�ȍ~�̎����ԐŐ��͂ǂ��Ȃ�̂��v�Ȃǂ̎���E�ӌ����o����܂����B�Z�~�i�[�ɐ旧���čs��ꂽ�u�s�s���Ȑ^���v�̏�f�Ƃ����ւ��āC�n�����g�����ɂ��čl����@����Q���҂ɒ��邱�Ƃ��ł��܂����B���Ȗk�C���n�����������ł́C������n�����g�������n�߂Ƃ��������̎s���̕��X�̗�����[�߂邽�߂ɁC�l�X�Ȏ�g��i�߂Ă����܂��B |
| |
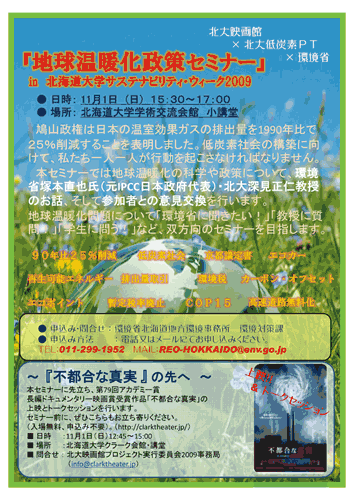 |
| �|�X�^�[ |
|
| |
| �@ |
| |
| �k�傩�琢�E�ցI�`���ۃL�����A�p�X�̓�����ց` |
 |
| |
���@ ���F11��2���i���j
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF���ی𗬎��@�����@�{���@���v |
| |
�@���ی𗬎��y�ї��w�𗬉ۂ́C11��2���i���j�ɋ����w�̃v�����[�V���i���E�C�x���g�����߂ĊJ�Â��܂����B
�@�{�s���́C�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N�w�̎Q�����@�ɗ������������w�̊w���E�������Ɏ��g�̑�w��{�w�w���ɃA�s�[������@������ړI�Ŋ�悵�����̂ł��B
�@�Q����w�́C�A�����J�E�|�[�g�����h�B����w�C���E�e�L�T�X��w���N�Ȋw�Z���^�[�C�t�����X�E�p���H�ƕ������w��������w�C�C�^���A�E�g���m�H�ȑ�w�C�����E���]��w�C�i�C�W�F���A�E�G�{�j�B����w�C���E�i�C�W�F���A��w��7��w�ł����B
�@�����́C�e��w���T�X�e�B�i�u���E�f�B�x���v�����g�iSD�j�ɂ��Ăǂ̂悤�ȋ�����s���C�w�������Ƃ���ƊO��SD�ɂǂ̂悤�Ɋւ���Ă��邩�����ꂼ��̑�w��蔭�\���Ă��������܂����B
�@�����w�̋�����������҂ɏ����Ă̗��w������͉ߋ��ɐ�����{�������Ƃ�����܂����C����̂悤��7��w���ꓯ�ɉ����͏��߂Ăł����B���ɂ́C���w�����܂�80�����̊w�����l�߂����C�M�S�ɐ����ɕ��������Ă��܂����B
�@�C�x���g�I����ɎQ���w���Ɏ��{�����A���P�[�g�ł͕]���������C�܂��Q����w�����B�����g�̑�w�ڊw���B�ɃA�s�[�����C�w���̔����Ŋ�����ꂽ���Ƃɔ��ɖ��������o�����悤�ł��B
�@���ی𗬎��y�ї��w�𗬉ۂ́C�w���̊F����ɗ��w�����g�߂Ȃ��̂Ɗ����Ă��炤���߁C������l�X�Ȍ`�ŏ��ɓw�߂鏊���ł��B���[���iryugaku@academic.hokudai.ac.jp�j�ł̗��w���k�����Ă��܂��̂ŁC���w��]�̊w���ɂ��Љ��������K���ł��B |
| |
 |
 |
| �|�[�g�����h�B����w�w������̑�w�Љ� |
�����w���w������̐��� |
|
| |
| �@ |
| |
��4��@���`yui�v���[���c�@�t�F�A�g���[�h�t�F�A
�u����u���e�B���[���ƃt�F�A�g���[�h�F�����ȎЉ�ւ̈���v |
 |
|
| |
�t �F �A�@���@���F11��2���i���j�`11��14���i�y�j�@�@��@���F�k�C����w���������g�� ������ٓX
�u����@���@���F11��10���i�j�@�@��@���F�l���E�Љ�Ȋw�������猤����
��\�ҁF����w��3�N�C���ۋ��͊w���c�́u���`yui�v�v���W�F�N�g���[�_�[�@���с@���� |
| |
�t�F�A�g���[�h�t�F�A
�@����łS��ڂ̊J�ÂƂȂ����k�C����w���������g���Ƌ��Ẫt�F�A�g���[�h�t�F�A�B���i�ɂ��Ă͋G�߂��ӎ��������i�𑽂��d����C�~�G����̃`���R���[�g�ɂ��͂����܂����B
�@�܂��C���N�̉ĂɃt�B���s���X�^�f�B�[�c�A�[���J�Â��C���̍ێ��������Œ��ڎd����Ă������i���̔��B����܂ňȏ�Ɂu��̌�����v���i�W�J�ɓw�߂܂����B���i�̔����s�������݃u�[�X�ł́C�u�t�F�A�g���[�h�̎d�g�݁v��u���`yui�v�ɂ��Ẵp�l�����ݒu�B�u�ł��g�߂ȍ��ۋ��́v�Ƃ�������t�F�A�g���[�h��C�w���Ƃ�������ō��ۋ��͂Ɋւ��銈�����s���������̒c�̂̊�������葽���̐l�ɒm���Ă��炨���Ɗ�悵�܂����B�S��ڂ̊J�Âł��邱�Ƃ�C����C���q�l�Ƃ̌𗬂���C���X�Ɂu�t�F�A�g���[�h�v�𗝉����Ă����l�������Ă���Ɗ�������悤�ɂȂ��Ă��܂����B���ꂩ����C�P�l�ł������̕��Ɂu�������v�Ƃ�������̍s�������E�Ɛg�߂ɂȂ����Ă���Ƃ������Ƃ��������Ă���������悤���̊������p�����Ă��������ƍl���Ă��܂��B
|
 | �k�吶����ٓX�ł�
�t�F�A�g���[�h�t�F�A |
|
| |
�u����u���e�B���[���ƃt�F�A�g���[�h�F�����ȎЉ�ւ̈���v
�@���i�̔���p�l���W�������ł͂킩��Ȃ������C����������ݍ���Ńt�F�A�g���[�h�⍑�ۋ��͂ɂ��Ēm��@���������C�Ƃ����v���ō�N�Ɉ�������2��ڂƂȂ����u����B����́C�ق������ǂ��s�[�X�g���[�h����z�c���a�������������ĊJ�Â��܂����B���ۂɓ��e�B���[���R�[�q�[��p�����t�F�A�g���[�h�𗧂��グ�C���݂��^�c���Ă���őO���̂��b�ŁC�^�c�X�^�b�t�ɂƂ��Ă����ɂȂ��ƂȂ�܂����B�������C�L����J�Ó����̐ݒ�ȂǏ��X�̎���ɂ���Ė����̂����W�q�͂ł��܂���ł����B����́C����̔��Ȃ����Ȃ���t�F�A�g���[�h�t�F�A���l�u����̊J�Â��蒅�����Ă��������ƍl���Ă��܂��B |
| |
 |
| �u����̗l�q |
|
| |
| �@ |
| |
| �W���C���g�V���|�W�E���u�s�s���ƌ��N�`2010�N���E�ی��f�[�Ɍ����ā`�v |
 |
| |
�� �@���F11��3���i�E�j�j
�� �@���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF��w�����ȁ@�����@�ʏ�@�p�F |
| |
�@���E�ی��@�ւ�2010�N4��7���̐��E�ی��f�[�̃e�[�}���u�s�s���ƌ��N�v�ƒ�߁C���E�e�n�ɂ����Ċ֘A�������J�n���Ă��܂��B���E�̐l���̔����͓s�s���ɏW�����C2050�N�ɂ͂��ꂪ7���ɑ�����Ɨ\�z����Ă��܂��B���̂悤�ɁC�l�X�̌��N�Ɋւ��ۑ�ɂ����āC�s�s���̎��_�͕s���ł��B
�@11��3���i�j�ɊJ�Â�������̊��́C���́u�s�s���ƌ��N�v�ɑ���ۑ�ӎ��̌[���Ɨ����鐢�E�ی��f�[�ւ̎Q��̐��i�������āC��w�����ȁE���ەی���w���삪�C���E�ی��@�_�˃Z���^�[�y�і{�w��w�ԋ���Z�ł���W���l�[�u��w�i�X�C�X�j�C�f���T����w�i�t�B���s���j�Ƃ̘A�g�ɂ��C���ۃV���|�W�E�������{�������̂ł��B
�@�V���|�W�E���́C�O���̏��ҍu�����тɁC�㔼�̉�c�Q���҂��������O���[�v���_�y�сC����Ɋ�Â��S�̓��_��2�p�[�g�ɂ��\������܂����B
�@�O���ł́CWHO�_�˃Z���^�[�C������Ȏ��ȑ�w�C�k�C����w����̍u���ɂ��C�s�s���ƌ��N�̉ۑ��2010�N���E�ی��f�[�ɂ��Ă̎�|�Љ�⊈���[�����s���܂����B
�@�㔼�̃O���[�v���_�ł́C1�j�s�s�ɏZ�ގs���̌��N���C2�j2010�N���E�ی��f�[�Ɏ��{���Ăق����C�x���g��2�_�ɂ��ċc�_���C�S�̓��c�ɂ����Ċe�O���[�v���[�_�[����̔��\���s���܂������C�u�s�s���ƌ��N�v�̋�̓I�ȉۑ�Ƃ��āC�u���v�⎩�E�Ȃǂ̐��_�I�Ȗ���C���Q���ʎ��̂Ȃǂ̊����C�����Č��N���ێ����邽�߂̃R�X�g���傽��ۑ�ł��邱�Ƃ��C�e�O���[�v����̈ӌ��Ƃ��Ď�����܂����B�܂��C����ɑ��鐢�E�ی��f�[�Ƃ��Ă̊�����Ăɂ��Ă��C�u�s�s���v�ł̎s���̍K���̊C�^���s���̉�����C�G�R�J�[�̕��y�ȂǁC����ɂ킽��s�s�̌��N���ɑ�����g�݂̂���悤�������ɒ�Ă���܂����B
�@���̂悤�ɖ{��c�́C�s�s�̌��N��S������͎s���Ƃ����ϓ_����C���G����Ȃ��̉ۑ�ɑ�����g�ݕ����Q���҂����ϋɓI�ɍl������悤��}���ĉ^�c���s���܂����B���̐��ʂ͗�����2010�N���E�ی��f�[�����������C�X�ɂ͎����\�ȎЉ�̎����̈ꏕ�ƂȂ�悤����W�J���Ă��������ƍl���Ă��܂��B |
| |
 |
 |
| �O���[�v���_�̗l�q |
�Q���҈ꓯ |
|
| |
| �@ |
| |
���A��w�O���[�o���E�Z�~�i�[�k�C���ŏI�L�O�Z�b�V����
�����\�ȎЉ�̒S����ƂȂ邽�߂�
�|2015�N�܂łɍ��ێЉ�B�����ׂ��~���j�A���J���ڕW�̌����m��| |
 |
| |
���@ ���F11��3���i�E�j�j�@�@�@
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF�u�����\�ȊJ���v���ې헪�{�� |
| |
�@11��3���i�E�j�j�ɁC���A��w�O���[�o���E�Z�~�i�[�k�C���ŏI�L�O�Z�b�V�������C�w�p�𗬉�قɂ����ĊJ�Â��܂����B
�@���̃Z�~�i�[�́C���A��w����Â�����̂ŁC���A�̖�����l�ނ����ʂ��Ă���n���K�̖͂��ɂ��āC�w����Љ�l�ɊS�Ɩ��ӎ��������Ă��炤���߁C�S���e�n�Ŏ��{����Ă��܂����C�k�C���Z�b�V�����́C��9��ƂȂ鍡�N�������ďI�����܂��B���̍ŏI�L�O�Z�b�V�������C�{�w�Ƃ̋��ÂŎD�y�L�����p�X�ɂĊJ�Â��܂����B�S�����������鉞�傪����C�{�w�w��21�l���܂�48�l�̊w�����Q�����܂����B
�@�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N2009���Ԓ��ɊJ�Â��邱�ƂƂȂ������߁C�Z�b�V�����e�[�}�́u�����\�ȎЉ�̒S����ƂȂ邽�߂Ɂ`2015�N�܂łɍ��ێЉ�B�����ׂ��~���j�A���J���ڕW�̌����m��`�v�Ɛݒ肳��܂����B
�@�~���j�A���J���ڕW �iMDGs�j�Ƃ́C21���I�̍��ێЉ�i�قɎ��g�ނׂ��l�ނ̖ڕW�Ƃ��āC���ۘA����2000�N�Ɍf�������̂ŁC2015�N�܂łɒB�����ׂ�8�̖ڕW��18�̃^�[�Q�b�g����߂��Ă��܂��B���̃Z�~�i�[�ł́CMDGs �B���͎����\�ȎЉ�̎����Ɍ����������ł���Ƃ̔F���̉��C���̒B���Ɍ����Đs�͂��Ă�����X���u�t�ɂ��}�����܂����B
�@�ߑO����2�̊�u�����s���܂����B�͂��߂ɁC�u�T�X�e�i�r���e�B��ڎw�����A��w�̎��g�݁v�Ƒ肵�č��A��w���w���̕����a�F������C���Ɂu�~���j�A���J���ڕW�F21���I�̐l�ԊJ���̎����Ɍ����āv�Ƒ肵�āC���A�J���v�擌���������̐��S�r�Ǝ����炨�b���������܂����B
�@�ߌ�ɂ́C�ȉ��̂悤��6�̕��ȉ�ɕ�����C���ꂼ��̒S���u�t�Ɗ����Ȏ��^�������s���܂����B
1�D�n���ƋQ��̍팸�cNGO�u�������������v�����ǒ��@����I��
2�D�����E��������ƒj�������cJICA�������q��
3�D�ی��E��Ác�i���j�W���C�Z�t�@�A�h�{�J�V�[�E�O���[�v�@�`�[�t����^�Վ�
4�D���E�q���cNPO�@�l���{���t�H�[�����@�f�B���N�^�[�@���q�v��
5�D���cJICA�������@�g���쐽��
6�D�O���[�o���E�p�[�g�i�[�V�b�v�c���A�J���v�擌���������@���S�r�Ǝ�
�@�A���P�[�g����́C�����̎Q���҂�MDGs�̍őO���Ŋ���l�Ƃ̎��^������ʂ��ĐV�����������������Ƃ�C����̌�������ɑ傫�Ȏh���������Ƃ��M���܂����B�܂��CMDGs�ɂ��Ă����Ƃ悭�m�肽���C���ȉ�̎��Ԃ������ƒ�������ė~���������C���̂悤�Ȍ���̐����Z�~�i�[���ĂъJ�Â��ė~�����Ȃǂ̈ӌ����������܂����B
�@�u�t�̕��X����́C�Q���҂̐ϋɐ��ɖڂ������������ƁC1�̕��ȉ��8�l�Ə��l���ɂ������Ƃ�C���l�Ȋw���E��w�@�̊w������̕��ȉ�ɓ���đ��l�ȋc�_�̏��n�o�������Ƃ������]�����Ă��������܂����B����ɁC����̊����ɂ��Ċw���Ƃ�������Ƙb���������Ƃ̂ł��邱�̂悤�ȋ@����܂��J�Â��ė~�����Ƃ̗v�]�����܂����B |
| |
 |
 |
| �c�_�ɐ���オ������������ȉ� |
�O���[�o���E�Z�~�i�[�W���ʐ^ |
|
| |
| �@ |
| |
��2��Z���`�l���E�A�[�X���ۃV���|�W�E��
�|�s�������u���C�q���f�[�^�E�q���摜�f�[�^�̍��x���p�����| |
 |
| |
���@ ���F11��3���i�E�j�j�`11��5���i�j
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF���Ȋw�����ȁ@�����@�{�ԁ@���v |
| |
�@�V���|�W�E���Q���Ґ��́C����121���C�C�O28���i10�����j�̑��v149���ł����B
�@
�@11��3���i�j�̎s�������u���ł́C�u�n�����g���Ɩk�Ɉٕρv�Ɓu�F�����猩��n���|�l�H�q���̗��p�|�v�ɂ��āC������������ŐV�f�[�^����Ɉ�ʎQ���҂ɕ�����₷���u�����s���܂����B�A���P�[�g�̌��ʁC�Q���҂�80���ȏオ�{���ɖ����Ɖ��Ă��܂����B
�@11��4���i���j�̑S�̃Z�b�V�����ł͏��Ȋw�����Ȃ�JAXA�A�g�u���̋��猤�������̏Љ���ꂽ��C�����[�g�Z���V���O�̉��p�Ƃ��ĔM�уT�C�N���g�����̃_�C�i�~�b�N�X�Ɋւ��铴�@�ƐV�����ɂ��Ă̍u�����s���܂����B����ϑ��Z�p�q���iALOS�j�Ƃ��̉��p�i�ЊQ�C�}���Ɣ_�Ɓj�Z�b�V�����ł́CALOS�̃~�b�V�����Љ�C�A�W�A�ɂ�����Z�p�ړ]�̂��߂�ALOS���p�C�n���w�ւ̉��p�CALOS�̔_�Ɗϑ��ƍЊQ���j�^�����O�ւ̉��p�C�k�C���ɂ�����n�����V�X�e���iGIS�j�ɂ��_�ƂƊ����̋��L�ƊJ���Ɋւ���u�����s���܂����B�n�����ϓ��ϑ��~�b�V�����iGCOM�j�Ƃ��̉��p�i�C�m�Ƒ�C�j�̃Z�b�V�����ł́CGCOM�̃~�b�V�����Љ�C���ƁE���Y�����ւ̎Љ�I���p�C�C�m�\�ʂ̃x�N�g�����̊ϑ��C�A�W�A�n��̑�C�����̊ϑ��Ɋւ���u�����s���܂����B
�@11��5���i�j��GCOM�Ƃ��̉��p�i����ƋɌ��j�ł́C�k�ɕ�����̐������̒����ω��C�n���K�͂̓y�됅���̃��j�^�����O�C����A���ω��C�C�X�ω��̑��������Ɋւ���u�����s���܂����B�Ō�̃Z���`�l���A�W�A�i�A�W�A�̌���Ёj�Z�b�V�����ł́C�Z�b�V�����̖ړI�ƃZ���`�l���A�W�A�̊T�v�Љ�C�Њ댯�x�w���C�Ќ��m�A���S���Y���̊J���C�Љ��ė\���ƃ��X�N��́C�Ѓz�b�g�X�|�b�g���`�B�C��i�I�ȉЂ̐���Ə��Ɋւ���u�����s���܂����B
�@�n�����̕ω��̊ϑ��ɂ����āC�l�H�q���ɂ�郊���[�g�Z���V���O�Z�p�̏d�v�����F�����ꂽ�Ɠ����ɂƍ���̐V�������p�g��ƈ�ʎs���ւ̕��y�̏d�v���̋��ʔF�����[�܂�܂����B���̂��߁C��3��Z���`�l���E�A�[�X���ۃV���|�W�E�����J�Â��C�����[�g�Z���V���O��GIS�̓�����ڎw�������ٖ��ȍ��ۘA�g�̃l�b�g���[�N�`���̎������͂��邱�ƂƂ��܂����B |
| |
 |
 |
| �V���|�W�E����� |
�u����̗l�q |
|
| |
| �@ |
| |
| �����W���F�����Ȋw���𖾂���u����E�L��ΎR�n��̉ߋ��Ɩ����v |
 |
| |
���@ ���F11��4���i���j�`11��13���i���j
��@ ���F����������
��\�ҁF���������ف@�ْ��@�n�n�@�x�� |
| |
�@�u�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N2009�v�́C�l�ގЉ�̎����\����k�C����w�������E����Ŏx���悤�Ƃ̈Ӑ}�����ɂȂ��Ă��܂��B
�@�������C�l�ގЉ�̎������l����O�ɖk�C����w�̎����\�����l����K�v������܂��B���̐��قǂ�����{�̑�w�������E����̎��ł��̂�������Ă��钆�C�m�[�x���܂�_���铌����w�C���s��w�ɑR���C�u�����Ԃ���w���X�g�v�ɍڂ�Ȃ����߂ɖ{�w����蓾���́u�����Ȋw�v�ł���C�ƍl�����k�C����w���O�̗L�u�́u�k�C����w�����Ȋw�R���\�[�V�A���v�����܂����B�����҂̌l�v���C�Ńm�[�x���܂�_���헪�ł͂Ȃ��C�����҂���������W�߁C�ٕ���̌��������邱�Ƃő���w�ƍ��ʉ���}��܂��B�l�X�Ȍ�������������œ�������ƁC�V���������̐���C������Ă������ʁC�v�������Ȃ����p�C�����̕������X�������Ă��܂��B�{�w���u�����҂̊W�ߏ�v�ł��邱�Ƃ�E���C���̂悤�ȁu�����̏�v�Ƃ��ċ@�\����C�Љ�̎������x����҂Ƃ��Ă̖k�C����w�̎��������ۏ���܂��B
�@11��4���i���j����J�Â����{���́C�u�k�哝���Ȋw�v���p�b�P�[�W�Ƃ��ēW�J���邽�߂̍ŏ��̎��݂Ƃ��āC�u����E�L��ΎR�n��̉ߋ��Ɩ����v���e�[�}�ɁC�l�X�ȕ���̌�����W�����C���̓������l������̂ł��B11��8���i���j��13���i���j�Ƀ|�X�^�[�W����ƍu������J�Â��܂����B�Q���҂͂���قǑ����͂���܂���ł������C����܂Ŋ�����킹�����Ƃ̂Ȃ��ٕ���̌����ҁC�w���C��ʐl���R�[�q�[�J�b�v�Ў�Ƀt���[�g�[�N���s���C�w�ⓝ�����牽�������Ă��邩���c�_���܂����B�u�����2��Ƃ����ԃI�[�o�[����قNjc�_������オ�鋻���[�����̂ł����B��O���X�Ȃ���u�����Ȋw�v�Ƃ��Ă̊e�w��̐ړ_�����ƂȂ������Ă����悤�ȋC�����܂����B
�@����͕ʂ̃e�[�}�Łu�k�哝���Ȋw�v��グ�čs������ł��B |
| |
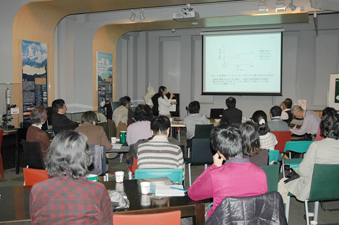 |
 |
| �u����̗l�q |
�w���E��w�@���̃|�X�^�[���\�̗l�q |
|
| |
| �@ |
| |
���ۃV���|�W�E���u�����\�Ȓ�Y�f�Љ��ڎw���āv
�`�O���[���E�j���[�f�B�[���ƃO���[�o���`�F���W�` |
 |
| |
���@ ���F11��4���i���j�`11��5���i�j
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF����������w�@�@�����@�[���@���m |
| |
�@11��4���i���j�́C���E�̃O���[���E�j���[�f�B�[������ɂ��ē����؉��Ăƍ��A���v��̌o�ϊw�҂������ču���y�уp�l���E�f�B�X�J�b�V�������s���ƂƂ��ɁC6���̖{�w����Z�̑�w�������������Ċe���̒�Y�f�Љ�Ɍ��������E�o�ϐ���ɂ��Ă��u�������������܂����B���E�e���ɂ������Y�f�Љ�Ɍ�������g����̓I����������Ȃ��疾�炩�ɂ���C��ψӋ`�[���V���|�W�E���ƂȂ�܂����B
�@����������w�@�ɂ����ẮC����Ƃ��C�Q���e���̌����҂ƘA�g�����Ȃ���C�O���[���E�j���[�f�B�[������𒆐S�Ƃ��Ē�Y�f�Љ�Â��萭��Ɋւ��钲���������p�����邱�ƂƂ��Ă��܂��B
�@5���i�j�́C�n�����ϓ��i�O���[�o���`�F���W�j�ɂ��āC1�j�C��ϓ������Ԍn�ɋy�ڂ��e���ƃt�B�[�h�o�b�N�C2�j���C�ɂ����鐶���E���w�V�X�e���C3�j�O���[�o���`�F���W�ɂ�����H�������C�y��4�j��������4�̃Z�b�V�����������J���āC8���̊C�O�����ҁC10���̓��{�����҂ɂ��u���C���_���s���܂����B���̑��C�w�����̃|�X�^�[�Z�b�V���������{���C���R�Ȋw����Љ�n�ւ̖₢�������܂w�ۓI�ȃV���|�W�E���ƂȂ�܂����B�n�����Ȋw�����@�𒆐S�Ƃ���{�V���|�W�E�����{�O���[�v�́C�ً}�ۑ���𖾂��邽�߂̃L�[���J�j�Y�������\���C�����O�̎Q�������҂ƘA�g�����Ȃ���C�n�����ϓ��̉Ȋw�I�����Ƒ�Z�p�̊m����}���Ă������ƂƂ��Ă��܂��B |
| |
 |
 |
�~�����_�E�V�����A�Y�@�x���������R��w�E
�����������ɂ���u�� |
�n�� �����l����w���w�@�@���ɂ��
��u�� |
|
| |
| �@ |
| |
| ���ۃV���|�W�E���u�C��ϓ��ɂ��n��ŗL�V�X�e���ւ̉e���v |
 |
| |
���@ ���F11��6���i���j
�� �@���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF�n�����Ȋw�����@�@�y�����C�O���[�o��COE�g�����t�B�[���h���Ȋw�̋��猤�����_�`���h���_���[�_�[�@�R���@�N�T |
| |
�@�{�V���|�W�E���ł́C�n�����g���ɑ�\�����n���K�͂̋C��ϓ��ɂ���Đ��E�e�n�Ő�����l�X�Ȋ��̕ω��ɂ��ċc�_���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��C����IPCC��4�����ȍ~�ɓ���ꂽ�ŐV�̒m���\���܂����B
�@�����ň����u�n��ŗL�̊��V�X�e���v�́C�n�����g���̉e���C���Ԍn�ω��̒��x�C��X���̕ω��C�n�����w�z�̕ω��C���n�̐l�Ԋ����̉���x�Ȃǂ��ꂼ��̒n��ɂ���đ傫���قȂ��Ă��邽�߁C�n��X�P�[���̉e���]�����K�v�ł��B���̂悤�ȗ��R����C�����P�̂��߂̑��K����́C�e�n��ɓ���������Ă��K�v�ƂȂ�܂��B
�@���\�́C�O���[�o��COE�v���O�����őΏۂƂ���C�O3�n��i���V�A�C�����S���C�C���h�l�V�A�j����̏��ٌ����҂ƁC�w���̌����ҁC�y�э����O����̏��ҍu���ɂ��\���Ƃ��܂����B���V�A����͉i�v���y�Ɩ��ڂɊW����k���т̏d�v�����w�E����C�����S������͑����̒�ʉ�����X�͒n�`�̕ω��ɂ��Ă̕�����܂����B�C���h�l�V�A����͐l�Ԃɂ��J����̐[���ȓD�Y�n�ЂƂ���ɂ�郁�^�����o�ɂ��ĕ�����܂����B
�@�܂��C�n���K�͂̋C��ƁC�e�n��̊W�m�ɂ��邽�߁C�S���C�f���̌����҂ɂ�������C�n��C��ׂ��ł̖��_��ۑ肪������܂����B
�@�������_�ł́C��L�̂悤�ȍL����啪��Ԃ̘A�g�C���f�����O��ϑ��ȂLjقȂ錤����@�C�قȂ錤���Ώۗ̈�𑍍��I�ɑ����邽�߂̋c�_���s���܂����BIPCC��4�����_�ł͋C��\���̃��f���ŕ\������Ă��Ȃ����ہi�i�v���y�̕ω���D�Y�n����̃��^�����o�j�ɂ��ẴR�����g������C�C�f���ł̕\�����@�ɂ��ẴA�C�f�B�A��������܂����B����ɁC�u�e�n��ł̐���ɗL�p�ȋC��\���Ƃ͂ǂ�����ׂ����v�Ƃ����C�C��ϓ��ւ̓K���Ǝ����\�ȎЉ�����������c�_���s���܂����B |
| |
 |
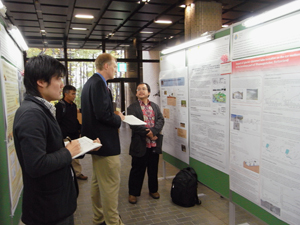 |
| ���ł̋c�_ |
�w���ɂ��|�X�^�[���\�̗l�q |
|
| |
| �@ |
| |
| ��2��@�Z���~�h������@�w�p�W�� |
 |
| |
���@ ���F11��6���i���j
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF��[�����Ȋw�����@�@���C�����@�\���@���V |
| |
�@11��6���i���j�C�D�yBio�|S�i�����Ȋw�Ȓm�I�N���X�^�[�n�����Ɓj�Ƃ̋��Âő�2��Z���~�h������w�p�W��C�O����2���̊w�҂��܂�6���̏��ҍu���ҁC19���̈�ʍu���҂ɂ��������\�𒆐S�Ƃ��ĊJ�Â���S������100�]�����Q�����܂����B
�@�C�O����̏��ҍu���̓V���K�|�[���f���[�NNUS��w��w�@��Scott Summers�搶�ɂ��u���A�a�ƐS�����ɂ�����Z���~�h�̖����v�C�č��J���t�H�j�A��w��Yoshikazu Uchida�搶�ɂ��u�畆�ɓ����I�ȃZ���~�h���q��v�ŁC���ꂼ�ꐢ�E�̍Ő�[�̌������Љ��Q���҂Ɋ�����^���܂����B
�@�܂��C�эL�{�Y��w�̖؉����N�搶�ɂ��u�A���E�y��R���̃X�t�B���S�����̐H�i�@�\���v�C�{�w��w�����Ȃ̏H�R�^�u�搶�́u�Z���~�h�͔畆�o���A�̗v�v�C����w�̐Έ�D�搶�́uS1P�ɂ�鍜�`������v�C���������H�Ɓi���j�̐Γc���Ɛ搶�ɂ��u���w�����Z���~�h�̊J���Ƌ@�\�����v�Ȃǂ̏��ҍu���C�X�ɂ͎Y�ƋZ�p�����������̓c�⋱�k�搶�ɂ�郉���`�����Z�~�i�[�u��`�q�g�����A���ɂ�铮���^�X�t�B���S�������̐��Y�v�ȂǁC�X�t�B���S�����C�Z���~�h�������Ē��ڂ��W�߂Ă���V�������������X�ɏЉ��܂����B��ʍu���ɂ������̗D�ꂽ���\������C9��������18���܂ł�������l�܂����w�p��c�ƂȂ�C���e��ɂ������Q��������C���e��[�߂܂����B
�@�ߔN�C�@�\���H�i�ɂ�錒�N���i�C�Z���~�h�̔畆�@�\���i�₪��\�h�Ȃǂ̐����@�\�ɊS�����܂��Ă��Ă��܂����C����̊w�p�W��͂��������S�ɑ��ăT�C�G���X�x�[�X�̃G�r�f���X�Ɋ�Â����W��ڎw�����̂ŁC�Q�����������̊�ƌ����҂ɂ����̕�����������ƂȂ�܂����B��������̍X�Ȃ锭�W��ڎw���āC�w�p�W��C���ېH�i�f�ށ^�Y�����W�E��c�iifia�j�ł̎��g�݁C�z�[���y�[�W��ʂ����L�������p�����ēW�J���Ă������Ƃ����߂��܂����B |
| |
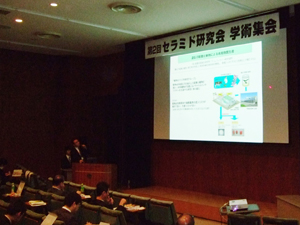 |
 |
| �M�C�ɕ�܂ꂽ���̗l�q |
Summers�搶�i�V���K�|�[�� �f���[�N
NUS��w��w�@�j�ɂ��u�� |
|
| |
| �@ |
| |
| ���ۃV���|�W�E���u�����̊C�ƐH����鐅�Y�C�m�T�X�e�i�r���e�B�w�v |
 |
| |
���@ ���F11��7���i�y�j�@�@�@
��@ ���F���Y�Ȋw�����@�}�����T�C�G���X�n��������
��\�ҁF���Y�Ȋw�����@�@�����@�A�R�@��G�C�����@�֓��@���� |
| |
| �@11��7���i�y�j�C�{���ۃV���|�W�E���́C�n�����29���l�̐l�ނ��H���Ƃ��ė��p���Ă��鐅�Y�����Ƃ��̐��Y��̂ł���C�m���Ԍn�������Ƃ��ɐ���ԍt�����Ɋ�Â��m���Ȃ��̂Ƃ���u�����̊C�ƐH�����v���߂ɁC�܂����ۓI�ȋ������Ɍ����������m�̌�������l�b�g���[�N���\�z����ړI�̂��߂ɊJ�Â���܂����B�Q���҂͉䂪�����܂�7�J���i�J�i�_�C�A�����J���O���C�����C�؍��C�C���h�l�V�A�C�t�B���s���y�ѓ��{�j�̌����ҁC�s���S���ҁC�s���y�ъw���̉���123���ɋy�т܂����B��ȓ��e�Ɛ��ʂ͎��̂Ƃ���ł��B
|
| |
1�D |
���ҍu���F
�E�b�V�E�T�~���iUBC�j�u���Y�H���ƊC�m���Ԍn�̕ۑS�̂��߂̋�Ԑ����o�ϊw�v
�������i���c��w�j�u���Ԍn�x�[�X�̋��ƕ]���Ɨ\���v
�E�B���A���E�X���[�J�[�iUAF�j�u�A���X�J�������Ƃɂ����鎝���\���v
杍^�V�i��C�C�m��w�j�u�����ɂ����鐅�Y�{�B�̌���ƍŋ߂̐i���v |
| |
|
| 2�D |
�k�C����w���Y�Ȋw�����@�̋����ɂ��u���F
������u������ւ̊C�m���Ԍn�ۑS�Ɛ��Y�H�����S�ۏ�|�m�����E���R��Y�n��̐��Y���Ԍn�A�v���[�`�Ə����I�Ǘ��Ɋւ��鎖�ጤ���v
�g���@��u�T�P�z���������Ƃɂ�����t���̌��N�Ǘ��ƈ��S�ȃT�P���Y�v
�A�R��G�u�C�m���Ԍn�ۑS�Ɛ��Y�H�����S�ۏ�̂��߂̎����\���v |
| |
|
| 3�D |
�p�l���f�B�X�J�b�V���� �R�[�f�B�l�C�^�[�Fꎓ�����i�k�C����w���Y�Ȋw�����@�j
�́@�t�g�i�k�C����w�j�u�v�����N�g���H���ރn�N�����̗{�B�Ɛ��Y�|�����ɂ���������ʋ��Ƃ̎����\�Ȕ��W�̂��߂Ɂv
�G�h�p���i�E���U���[�^�iUNU�j�u�t�B���s���ɂ����鐅�Y�{�B�C���p�N�g�y���̂��߂̊Ǘ��I�����v
���f�B�A�[�^�EI�E�j���I�[�}���i�k�C����w�j�u�����\�ȗ{�B�Ƃ̂��߂̋�ԏ��V�X�e���A�v���[�`�v
�Α��w�u�@�i�k�C����w�j�u�C��ϓ��ɉe������鑽���ԋ��L���Y�����Ǘ��̒��ʂ�����C�����āC�����I�Ǘ��Ɍ���������|���\������Pacific sardine�����Ǘ��Q�[�����͂Ɛ����v |
|
| |
| �@����̓W�J�Ƃ��āC������̂��߂ɐH�ƊC����邽�߂ɂ͏����I�Ǘ��Ɨ\�h�����Ɋ�Â����Ԍn�A�v���[�`�^���X�N�Ǘ����ł��d�v�ł���C�C�m���Ԍn�̊����e�͂��悭�������C�H�ƊC�m���Ԍn����邽�߂̐V���Ȑ��Ԋw�I���Y�C�m�w�ւ̃p���_�C���V�t�g�C�H�瓙�̋�����P����܂����B |
| |
 |
 |
| �p�l���f�B�X�J�b�V�����̗l�q |
�u���ҁE��Î҈ꓯ |
|
| |
| �@ |
| |
| �n�������ȁ|�K�C�A�V���t�H�j�[�|��ܔԏ�f�� & �����m�ē��ʍu���� |
 |
|
| |
���@ ���F11��7���i�y�j
��@ ���F�N���[�N���
��\�ҁF���Ȋw�@�@�C�m2�N�@�V��@�G�T |
| |
�@11��7���i�y�j�ɊJ�Â����{���ł͗����m�ē�i�u�n�������ȁ|�K�C�A�V���t�H�j�[�|��ܔԁv�̏�f��ƁC�����ēɂ����ʍu��������{���܂����B�u�n�������ȁ|�K�C�A�V���t�H�j�[�v�͉Ȋw�E�X�|�[�c�E���y�ȂǗl�X�ȕ���Ŋ��Ă���l�X�ɃX�|�b�g�āC�n���⎩�R�C�����e�[�}�ɔނ�̐������C�l�����𑨂����h�L�������^���[�V���[�Y�ł��B���̒��ł������f�����u��ܔԁv�́g�S�Ă̑��݂͌q�����Ă���h�Ƃ������Ƃ��R���Z�v�g�ɐ��삳�ꂽ��i�ł��B�{��i�ɂ͐D����Ƃ̐Ί_���q����C�N�w�҂ł���C���y�Ƃł�����A�[���B���E���Y���[�����o������C���R�Ɋ��Y���Ȃ��琶���邱�ƁC���ׂƂ��������O�����ɐ����邱�Ƃ�����҂ɓ��������Ă��܂��B���ɂ����F����s�m�̃��b�Z���E�V�����C�J�[�g�C14���_���C�E���}�@������o�����Ă���C���₩�Ȑ����C�L���Ȑ��E�̒a���ɔ����ɂ݁C�ꂵ�݂̈Ӗ��ɂ��Đ����Ă��܂��B
�@�����m�ēɂ��u����ł́C�n�������Ȃ��B��n�߂Ă���̌o�܂�C���ݕҏW���ł���u�掵�ԁv�̐���G�s�\�[�h�C�u��ܔԁv�̐��쎞�̋��Ȃǂ����b�����������܂����B
�@�{���́u�k�匳�C�v���W�F�N�g�v�ɍ̑����ꂽ���߁C�����ň�ʌ��J���邱�Ƃ��ł��܂����B����ɁC�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N2009�̃v���O������1�Ƃ����Ă������������Ƃɂ���X�I�ȍ��m�ɂ��C�����͊w���O��킸400�����܂�̕��X�ɂ����ꂢ�������C�����̓��ɖ����I���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�n�����₻�̎��������l������C���E�ɎU�݂��鏔�����������邽�߂ɂ͐l�̍l������S�̕ϊv�ɂ���đn�������ЂƂ�ЂƂ�́g�������h������Ǝ��B�͍l���܂��B�w�p���_�ł���k�C����w�ɂ����āC�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N��1���Ƃ��āu�l�̐S����Ă�v��悪�����ł������Ƃ͂ƂĂ��傫�ȈӖ��������Ă���͂��ł��B���ꂩ����u���ƐS�̃o�����X�v�̎�ꂽ�D�ꂽ�l�ވ琬��ڎw���k�C����w�Ƃ��Ă����ė~�����C�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N�����������ė~�����Ɗ���Ă��܂��B���B�͂��ꂩ����n�������Ȃ�ʂ��Ă�������̕��X�����₩�ȋC���������L���鎞�ԁE��ԂÂ���𑱂��Ă����܂��B�܂����N���T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N�ł��ꏏ�ł��܂����Ƃ��y���݂ɂ��Ă��܂��B |
| |
|
| |
| �@ |
| |
| ���ۃV���|�W�E���u�I�z�[�c�N�C�̊��ۑS�Ɍ����������I�̎��g�݂ɂނ��āv |
 |
| |
���@ ���F11��7���i�y�j�`11��8���i���j
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF�ቷ�Ȋw�������@�I�z�[�c�N�ϑ������Z���^�[�@�����@�]���@���l |
| |
�@11��7���i�y�j����J�Â����{�V���|�W�E���ł́C�A���[���여��ƃI�z�[�c�N�C�͕����z�Ɛ��Ԍn�A�ɂ���ĂЂƂ̂Ȃ���������Ă���Ƃ̔F���Ɋ�Â��āC�I�z�[�c�N�C�ƃA���[���여��̊����̌�����w��I�ɓ��c���C���ݐ����Ă����X�̖��ɑ��ē����I�̌����҂��������z���ď�L��w��I��b�ɑ��������c���s�����߂̍P��I�ȑ����ԃl�b�g���[�N�ł���u�A���[���E�I�z�[�c�N�R���\�[�V�A���v�̐ݗ������݂܂����B
�@���v33���̌������ʂ����{�C�����C���V�A�y�уt�B�������h�̌����҂������܂����B���̌��ʁC�I�z�[�c�N�C�ɂ����ẮC���g���ɂ��Ǝv����C�X�������C�m�̉����z���㉻�����C���ꂪ�k�����m���w���̏����Ɨn���_�f�Z�x�̌����������N�����Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ�܂����B�A���[���여��̎��n���N���Ƃ���n���S�́C���̒��w���z�ɂ���ăI�z�[�c�N�C�݂̂Ȃ炸�C�����e����܂ŗA������C���̊C��̊�b���Y���x���Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ�܂������C���w���z�̎㉻�́C�����C�S�A���ʂ̌����������N�����C�e����̊�b���Y�ɉe����^����\��������܂��B
�@����C20���I�㔼����21���I�ɂ����Đi�s����A���[���여��̎����̊��͉�����֗A�������S�̌����������N�����Ă��鎖����������܂����B
�@�܂��C�i�W����H�Ɖ�����c�̊J���ɂ��C�A���[����ł͐[���ȉ������i�s�����邱�Ƃ�������܂����B�I�z�[�c�N�C�ł́C���c���̂ɂ�鐅�������ɑ��傫�Ȋ뜜��������̂́C���݂̐����̉����x�́C����l�ȉ��ł��B
�@�A���[���여��Ő����Ă���}���ȗ��ʔ핢��Ԃ̕ω��́C�O���[�o���o�ς̉��Ő����镡�G�ȋ쓮�͂ɂ���Ĉ����N������Ă��܂��B����䂦�C���̖�����������ɂ́C�ꍑ�݂̂Ȃ炸�C�A���[���여��ƃI�z�[�c�N�C�����L���鑽���Ԃ̕s�f�̋��͂��K�v�ƂȂ�܂��B�{�V���|�W�E���̑S�Q���҂́C�A���[���여��ƃI�z�[�c�N�C�n��̎����\�Ȕ��W�Ƃ��̊��ۑS���ŏd�v�ۑ�ł���Ƃ̔F�������L���C���̕ۑS�Ɍ������w�p�����҂ɂ����������傽��ړI�Ƃ���l�b�g���[�N�u�A���[���E�I�z�[�c�N�R���\�[�V�A���v��ݗ����邽�߂̋��������Ɏ^�����C�S���̑��ӂ������č̑����܂����B |
| |
 |
 |
| ���M�����c�_ |
�Q���҈ꓯ |
|
| |
| �@ |
| |
| �����W���FLet�fs �T�C�G���X!! |
 |
|
| |
���@ ���F11��8���i���j
��@ ���F���Y�Ȋw�@�u�`��
��\�ҁF���Y�Ȋw�@�@�C�m2�N�@���q�@�D��Y |
| |
�@11��8���i���j�ɊJ�Â�������̎����W���ł́C�u�l�H�C�N������낤�I�v�Ƒ肵���������s���܂����B�C�����璊�o�����A���M���_�i�g���E�����n�����n�t�ɁC�J���V�E���C�I�����n�����F����H������ƁC�A���M���_�i�g���E���ƃJ���V�E���C�I�������w�������N�����C�����`�����܂��B���̐����𗘗p���C���Y�w���̑�w�Ղɗ��Ă������������X�Ƌ��ɗl�X�ȐF�̐l�H�C�N�������܂����B
�@��ȑΏۂ͏��w���ł������C�ی�҂̕���C�N�z�̕��ɂ����ɍD�]�ŁC�K��҂��₦�邱�Ƃ͂���܂���ł����B�P�Ɏ����������s���̂ł͂Ȃ��C���ݍӂ����\���Ŏq���B�Ɏ����̌����J�ɋ����邱�Ƃ��ł��܂����B�܂�����ɍ��킹�Đ����̃��x�����_��ɕω������邱�Ƃ��ł������ƁC���\�ґS���������������m�������L�ł��Ă������ƂȂǂ͕]���ɒl����ƍl�����܂��B�ł����l�H�C�N���̓t�@���R���`���[�u�ɓ���Ċe�������ċA���Ă��������܂����B���������̎������D�]�ł��������R�̈�ł���ƍl�����܂��B
�@����́C���������u�Ȋw�̖ʔ����v�𑽂��̐l�X�ɓ`���邽�߂̊������s���Ă����\��ł���C�����̎�ނ����X�ɑ��₵�Ă������ƍl���Ă��܂��B�����I�ɂ͔��ق̌����{�݂Ȃǂő�X�I�Ɏ������s���C�����̐l�X�ɉȊw�̖ʔ�����`���Ă��������ƍl���Ă��܂��B |
| |
 |
 |
| ��l���q���������ÁX |
| |
| |
| |
�Ȋw���Ă������낢�I |
|
| |
| �@ |
| |
| ���ۃV���|�W�E���u�ቷ�Ȋw�̃t�����e�B�A�v |
 |
| |
���@ ���F11��9���i���j�`11��10���i�j
��@ ���F�ቷ�Ȋw������
��\�ҁF�ቷ�Ȋw�������@�����@�����@�W |
| |
�@�ቷ�Ȋw���������ۃV���|�W�E���u�ቷ�Ȋw�̃t�����e�B�A�v�iILTS International Symposium, �gFrontier of Low Temperature Science�h�j�́C�ቷ�Ȋw�������̃e�[�}�ł��颊��⌗�y�ђቷ�������ɂ�����Ȋw���ۂ̊�b�Ɖ��p��Ɋւ��āC�����O�̌����҂����҂��C���������҂Ƃ��ɁC�����̌���ƍ���̓W�]�ɂ��Ęb���������Ƃ�ړI�Ƃ���11��9���i���j�`10���i�j��2���ԁC�ቷ�Ȋw�������u���ɂ����ĊJ�Â���܂����B
�@�����ቷ�Ȋw������������ �gTowards a new era in low temperature science�h�Ƒ肵�āC�{�N3���ɕ��NJԋ��͋������������A���t���b�h�E�E�F�Q�i�[�Ɉ�C�m�������i�h�C�c�j���\���� Frank Wilhelms ������ �gHow can ice science satisfy the public attention in a warmer world?�h �Ƒ肵�āC��u�����s���܂����B
�@�܂��C����E�����z�£�C���X�V�̈棁C���������C��I�z�[�c�N�����4�̍u���Z�b�V�����y�у|�X�^�[�Z�b�V��������悵�C���ҍu��20���C�|�X�^�[���\30�����s���C�����ȋc�_���W�J����܂����B2���Ԃʼn���178���̎Q���҂�����C���̓���́C�w��151���i��������138���C���O13���j�C�w�O27���i��������15���C�C�O12���j�ŁC�č��C�h�C�c�C�����C�؍�����̎Q��������܂����B |
| |
 |
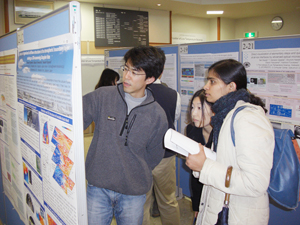 |
| �Q���҈ꓯ |
�|�X�^�[���\�̗l�q |
|
| |
| �@ |
| |
| �Y�w���Z�~�i�[�u�n����ԏ�����v |
 |
| |
���@ ���F11��12���i�j
�� �@���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF���Y�Ȋw�����@�@�����@�֓��@���� |
| |
�@�V�����f�W�^���n�}�Ƃ��āw�n����ԏ��x�����{�S���Ő���������C�w�n�����V�X�e���iGIS�j�x��w�q�����ʁx�̋Z�p�ƂƂ��Ɋ��p���邱�ƂŁC�V�����Љ��z�����Ƃ��铮���������ɂȂ��Ă��܂��B������11��12���i�j�ɊJ�Â����{�Z�~�i�[�ł́C��ƁC��w�C�����ɂ�����n����ԏ��̊��p�ɂ��ĉ�����܂����B�܂��C���̑��ɋ�ԏ��̈��Ƃ��āC1�K�z�[���̏���1976�N��2006�N�ɂ�����D�y�s�̋ʐ^�i5m�~3m�C�k��1/3,000���x�j��z�u���C����҂ɂ́C���̏�����R�ɕ����Č��Ă��炤�������{���܂����B
�@2�K��u���ōs�����u���ł́C�܂���u���Ƃ��ď����䗺�ꎁ�i���y�n���@�k�C���n�����ʕ����j����u�ŐV�̑��ʋZ�p�Ɩh�Ёv�Ƃ�������ŁC���y�n���@�̍ŋ߂̎��g�݂ɂ��ďЉ�������܂����B
�@���ɁC6�l�̉��҂����ꂼ��̐�啪�삩��n����ԏ��̊��p�ɂ��Đ������s���܂����B�܂����{�Y�ꎁ�i�k�C����w��w�@���w�����ȏy�����j���u�ϐኦ��n�ɂ����鐶���������̂��߂̒n����ԏ�p�v�ɂ��āC���ɋ��q�������i���_�w����w���V�X�e���w�������j���u�_�Ƃɂ�����GIS�̊��p����v�ɂ��āC3�Ԗڂɍ��c��V���i�k�C�����Ȋw�����Z���^�[�j���u�n����ԏ�����ւ̐V���ȃA�v���[�`�v�ɂ��ĉ�����s���܂����B�����Đԟ��������i���q���[�l�X�@��\������j���u�����̂ɂ����铝���^GIS�ƒn����̔��M�v�ɂ��āC�{�{�N�N���i�k�C���n�}���Z�p���J���S�������j���u��ԃ\�����[�V�������Ƃƌi���n�}�v�ɂ��Ċ�Ƃ̗��ꂩ��n����ԏ��̗��p��������܂����B�Ō�ɁCꎓ����ꎁ�i�k�C����w��w�@���Y�Ȋw�����@�����j���u�����\�ȋ��Ƌy�ё��{�B�Ɗ����x���̂��߂̃��r�L�^�X�ȏ��T�[�r�X�Ɋւ��錤���J���v�ɂ��Ĕ��\���܂����B�����̔��\�́C��������e����ɂ����銈�p�̍Ő�[���C�킩��₷������������̂ł���C�n����ԏ��̍��x���p�Љ�\�z�Ɍ����Ă̌[�֊����ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B |
| |
 |
 |
| �D�y�s�̋ʐ^�̏���������� |
���Y�Ȋw�����@�@ꎓ������ɂ��u�� |
|
| |
| �@ |
| |
| ���ۃV���|�W�E���u�����I�A�W�A�Љ�\�z�Ɍ����������̑����I��w�ԋ��́v |
 |
| |
���@ ���F11��12���i�j
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF�T�X�e�C�i�r���e�B�w���猤���Z���^�[�@�����@�c���@���K |
| |
�@����11��12���i�j�ɁC�k�C����w�w�p�𗬉�ّ�1��c���ɂāC���ۃV���|�W�E���u�����I�A�W�A�Љ�\�z�Ɍ����������̑����I��w�ԋ��́v�Ƒ肵�C���{�ƒ����̑�w�Ԃ̋��͊W�̂�����ɏœ_�Ă��V���|�W�E�����J�Â��܂����B�{�V���|�W�E���͓��{��y�ђ�����ɂ�铯���ʖ�ɂ���Ē���C�����͒�������̗��w���Ȃǂ��Q���҂�3����1�قǂ��߂܂����B
�@�`���C���ҍu����2���ɂ���u�����s���܂����B�܂��C���ҍu���҂̖k����w���w�������L�����ɂ��C�����ɂ������_���Y�f�r�o�ƁC���R�Đ��G�l���M�[�𒆐S�Ƃ�����_���Y�f�r�o�̌����I�ȍ팸��}����g�݂̌��Љ��܂����B�����āC�k�C����w�̋g�c���a�������C�����ł͈�@�Ȕp���������ɂ���Ĕ��Ɉ����Ɏ������T�C�N�����s���Ă������Љ��C���{������Ɉˑ����Ă������Ƃ��w�E���C�����̊W���������T�C�N���Ɋւ��l�X�����Ђɂ��炵�Ă��錻�w�E����܂����B
�@�����āC��ʍu���Ƃ��āC�����������𗬂̂��߂Ɋe���ɐݒu���Ă���E�q�w�@�̎��g�݂��Љ��܂����B���{�ōŏ��ɍE�q�w�@���J�݂��ꂽ�����ّ�w����C�E�q�w�@���̎� ���������Q������C�E�q�w�@�̊T�v�Ƌ��ɁC�����𗬂⒆���ꋳ��Ȃǂ̕����I�Ȏ��g�݂����S�ł��錻����܂����B ���������Q������C�E�q�w�@�̊T�v�Ƌ��ɁC�����𗬂⒆���ꋳ��Ȃǂ̕����I�Ȏ��g�݂����S�ł��錻����܂����B
�@��3���̃p�l���f�B�X�J�b�V�����ł́C�k�C����w�k�����������r�h�����ƎD�y��w�E�q�w�@�@�����̗Y��������C�����ɂ����ĎႢ�w���ɂ��݂��̍��ւ̊S�ቺ�����O�����|�̌x�����炳��܂����B���̎w�E���C�P�Ƀ��f�B�A���������ł͑��ݗ�����[�߂�ɂ͕s�\���ł���C�����d�v�Ȃ̂͌��n�ɍs���Ď����Œ��ڏ����擾���邱�Ƃł���Ƃ������ӌ����������܂����B�����āC���݂͕����I�Ȍ𗬂����S�ƂȂ��Ă���E�q�w�@�̎��Ƃł����C����͎����\�ȎЉ�̍\�z�Ɍ��������g�݂ȂǁC�����҂ɂ���啪��ɂ�����𗬂̉\���ɂ��Ă����݂ɊW��[�߂Ă����K�v������Ƃ��������̌𗬂̓W�]�Ɋւ��鎦���āC����̃V���|�W�E�����܂����B |
| |
 |
 |
| �p�l���f�B�X�J�b�V�����̗l�q |
���̗l�q |
|
| |
| �@ |
| |
| �V���|�W�E���u�A�W�A�E�A�t���J�J�������Ɩk�C����w�v |
 |
| |
�� �@���F11��13���i���j
�� �@���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF�T�X�e�C�i�r���e�B�w���猤���Z���^�[�@�����@�c���@���K |
| |
�@����11��13���i���j�ɁC�k�C����w�w�p�𗬉�ّ�1��c���ɂāC�V���|�W�E���u�A�W�A�E�A�t���J�J�������Ɩk�C����w�v�Ƒ肵�C���ۋ��͋@�\�iJICA�j������A�W�A�y�уA�t���J�����Ƃ̋��͊W�̂�����ɏœ_�Ă��V���|�W�E�����J�Â��܂����B�{�V���|�W�E���́CJICA�ɂ��S�ʓI�ȋ��͂čs���܂����B�p��ɂ���Ē��ꂽ�ɂ��ւ�炸�C�Q���҂̔����ȏオ�w�O����̎Q���ł���C�A�W�A�E�A�t���J�����ɑ���JICA�̎��g�݂ւ̊S�̍������M���܂����B
�@�͂��߂ɁC���ҍu����4���ɂ���u�����s���܂����B�܂��C�E�K���_���a����gWasswa Biriggwa���ɂ��C�E�K���_�ɂ�����G�R�r���b�W�̎��g�݂��Љ��܂����B�����āCJICA���2���̍u���҂ɂ���u��������܂����B�A�t���J������͉��R�a�͕������A�t���J�Œʗp����l�ނɂ��ď�����C�����Ēn�������̐X�����������C�����̊������ΏۂƂ��Đl�ވ琬�ɂ��Ă̍u�����s���܂����B�܂��C�C���h�l�V�A �p�����J������w��Adi Jaya�����ɂ́C�C���h�l�V�A�̊�����̌���ƍ���̉ۑ�ɂ��Ęb�����Ă��������܂����B
�@��2���ł́C���ƃ����S���y�уC���h�l�V�A��JICA���n���������e���r��c�V�X�e��Polycom���g���Đڑ����C���ꂼ��̍��̒��݈��ɃV���|�W�E���ɎQ�����Ă��炤�Ƃ����C���Ɉӗ~�I�Ȏ��݂��s���܂����B�͂��߂Ƀ����S����JICA���������ю��ɁC�����S���ɂ�����p���������̌���ɂ��ăv���[�����Ă��������Ƌ��ɁC����ŕK�v�Ƃ��Ă���l�ނɂ��āC���n�ɂ�����R�~���j�P�[�V�����̏d�v�����w�E����R�����g�����������܂����B�����ăC���h�l�V�A����������́C������Ƃ̃A�h�o�C�U�[�ł���D�����ɂ���āC�m�ł��闝�_�Ƌ��ɓƎ��̎��_�������Ƃ̏d�v�����w�E����C����Ɍ����c�������_��ȑΉ����\�Ƃ��邽�߂ɁC�l�X�ȍ��̎����c������K�v��������܂����B
�@��3���̃p�l���f�B�X�J�b�V�����ł́CJICA�ŃA�W�A�E�A�t���J�̃v���W�F�N�g�^�c�Ɋւ���Ă������i����C����JICA/JST�v���W�F�N�g�����{���Ă���_�w�����@��苳����H�w�����ȑD�������������C�k�C����w�̓A�W�A�E�A�t���J�ɂ�����JICA�v���W�F�N�g�ւ̍v���x���ł��傫����w�̈�ł��邱�Ƃ��w�E����C����������̒n��Ɩ��ڂȊW���\�z���Ă������Ƃ��m�F���C����̃V���|�W�E��������܂����B |
| |
 |
 |
| Biriggwa�E�K���_��g�ɂ��u�� |
�C���h�l�V�A���n���ݏ��Ƃ�
�e���r��c�̗l�q |
|
| |
| �@ |
| |
�V���|�W�E���u�T�X�e�i�r���e�B�ȎY�w�A�g�����߂�
�|�C�^���ACity State�g���m�̎��g�݂���̃��b�Z�[�W�|�v |
 |
| |
���@ ���F11��13���i���j
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF�Y�w�A�g�{���@�����@���C�@�� |
| |
�@�{�V���|�W�E���͊�u���Ǝ���v���[���e�[�V�����C�����ăp�l���f�B�X�J�b�V������3���\���Ŏ��{����܂����B�g���m�H�ȑ�w�ƃC�^���A��g�ق��瑍��6���̃Q�X�g�ɗ��Ă��������C���{�ƃC�^���A�łقړ����ōu�����܂����̂ŁC���e�͍��ېF�L���ɂȂ�܂����B�Q���҂���������̎��₪����C����ɊJ�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���e�́C�܂����c�Y�w�A�g�{�����C�}���S�[�j���g�Q�����̈��A�ɑ����C�g���m�H�ȑ�w�i���f�B���w���u�g���m�H�ȑ�w�ɂ�����Y�w�A�g�v�̊�u��������܂����B���H�ȑ�̓L�����p�X���ɃO���[�o����Ƃł���GM�C���g���[���C�}�C�N���\�t�g�Ȃǂ̗U�v�����r�W�l�X���T�[�`�Z���^�[������C���ӂ̃x���`���[��Ƃɂ��ǂ��e����^���Ă���Ƃ̐�������ۓI�ł����B
�@����v���[���e�[�V�����ł́C����w�̘A�g����iIT����j�Ƃ��āC�J���A�����C�R�{����������C�g���m�H�ȑ�w�̃��C�����X�ʐM�Z�p�Ɩk��̑S�����f�W�^���摜���W�Z�p�Ƃ�Z����������[ICT�i���ʐM�j����Ńv���W�F�N�g���Љ��C�D�y�s�C�k�C���ƃg���m�s�Ƃ̒n��Y�ƊԂ̘A�g�ւ̊��҂��q�ׂ��܂����B�܂��C�����\�ȊJ���Ɍ��������g�݂Ƃ��āC�����o���f�B��������́C�����\�ȊJ����]�����郁�g���N�X�i�]���w���j�ɂ��āC�{�w�̖{�����w������́u�I�z�[�c�N�C�̖����\���Ɍ��������ۃR���\�[�V�A���̍\�z�v���\��Ƃ��āC�n�����ɔz�����������\�ȎЉ�̓��c�Ȃ���܂����B
�@�p�l���f�B�X�J�b�V�����ł͏����I�ȋ��ʉۑ�Ƃ��āC�u����Љ�Ɍ������A�g�A�v���[�`�v�ɂ��āC�����ȋc�_���Ȃ���܂����B�C�^���A�����{�Ɠ��l�ɍ���l�����Ƃ��Ă̎��オ�ԋ߂ɔ����Ă���C���̖������ւ̋���̖����CICT�̖����C�������ʂ̎��p���ɂ��āC���ʂȈӌ����q�ׂ��C���Ɍ𗬂̃n�u�Ƃ��Ă̖k�C���ւ̊��҂�������܂����B
�i���ʁj
1�D�{�w�ƃg���m�H�ȑ�w�̘A�g����Ɋ�Â��������ϋɓI�ɍs���Ă���C�Z�p����iICT����j����C�n�����ɔz�����������\�Љ�C����Љ�Ȃǂ̎Љ�Ȋw������܂��_�ւƔ͈͂��L���ċc�_�ł������ƁB
2�D�w�O����������̎Q���҂�����C���Z�̎��g�݂ɂ��đ����̎s���ɒm���Ă������������ƁB
�i����̓W�J�j
�@����Љ�ɑΉ�������p�H�w����ł̗��Z�̋��������C����W�������������z�����Y�w�A�g�̉\���ɂ��āC�������Ă��������B |
| |
 |
 |
| �g���m�H�ȑ�w�i���f�B���w���ɂ���u�� |
�p�l���f�B�X�J�b�V�����̗l�q |
|
| |
| �@ |
| |
| �V���|�W�E���u�Ζ��s�[�N��̓��{�Ɩk�C���̂�������l����v |
 |
| |
���@ ���F11��14���i�y�j
��@ ���F�N���[�N���
��\�ҁF�T�X�e�C�i�r���e�B�w���猤���Z���^�[�@�����@�c���@���K |
| |
�@11��14���i�y�j�ɊJ�Â������̍s���́C�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N2009�̃V���|�W�E���Ƃ��čs�������̂ł��B�u�Ζ��s�[�N��̓��{�Ɩk�C���̂�������l����|�o�C�I�}�X�̗����p�|�v�Ƃ����^�C�g���ŁC��1���Ŋ�u���C��2���Ő�傩��̌������ʕC��3���Ŗk�C�����̌��ݎ����@�ւ�s�����̎��g�݂̏Љ�C�Ō�ɖk�C�����ւ̃A�s�[����錾���C�I�����܂����B�J�ɂ�������炸���ӎ��̍����s���������Q�����C�V���|�W�E���͐����ł����B
�@��u����2���̊w���҂����������C�Έ�g�����i���������Ȃ��w���j����u�Ζ��s�[�N�͐H�ƃs�[�N�C�����ĕ����s�[�N�|���{�̃v����B�|�v�C�����ĒO�ی��m���i�k�C���J��L�O�يْ��C���k�C����w�����j����́u21���I�̓��{�Ɩk�C���|�����\�ȎЉ��ڎw���ā|�v���u�����Ă��������܂����B�Ζ��s�[�N��̓��{��k�C���ł́C�l�X�͂ǂ̂悤�ɐ����l����ς��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ȃnj������Ƃ��Ă̐Ζ��s�[�N��̎Љ���ɂ��Ē��Ȃ���܂����B
�@������2���C��3���ł͊�u���̘b����C���������n��ł̌������ʂ���g�݂��Љ�܂����B�������ʕ́C�d�͒����������������ƃT�X�e�C�i�r���e�B�w���猤���Z���^�[�Ƃ̍����̌������ʕ��s���܂����B�n��̎��g�݂ɂ��ẮC�����H�Ǝ������ɒB�s�C�x�ǖ�s�C�����猤������S���҂��Q�����C����������Ȃ���̕��Ȃ���܂����B
�@�V���|�W�E���ɎQ�������s���炩��������Ȏ����ӌ����o����C�o�C�I�}�X�ւ̊S�̍������M���܂����B
�@����̓W�J�Ƃ��āC�T�X�e�C�i�r���e�B�w���猤���Z���^�[���j�Ƃ������������̋��_�̋����ƊW�@�ւƂ̘A�g���m�F����܂����B |
| |
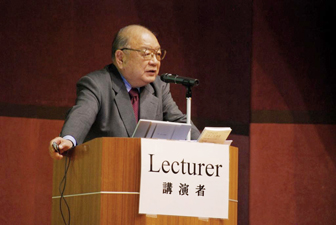 |
 |
| �O�ی��m���ɂ���u�� |
�n�������̂ɂ�鎖��� |
|
| |
| �@ |
| |
| �s�������u���u���ɂ�����_�Ƃ���݂���Y�f�Љ�̓W�]�v |
 |
| |
���@ ���F11��14���i�y�j
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF�_�w�����@�@�@���@��c�@��Y |
| |
�@�_�Ƃ���Y�f�Љ�̎����ɍv���ł��邱�ƂƂ��āC�o�C�I�K�X���Y�C�o�C�I�G�^�m�[�������C���c�̉��g���╨���z�ɉʂ��������ɂ��Ĉȉ��̉��肪���\����܂����B1�j�o�C�I�K�X�v�����g�̓��{�ɂ����錻��ƓW�]�i�k�C����w���_�������c�n�O�j�C2�j�؉X��ƐH�i�c�Ԃ̌��C�����ɂ��o�C�I�K�X���Y�i�؋���w����Chang�|Hyun Kim�j�C3�j�o�C�I�G�^�m�[�������̓��{�ɂ����錻��Ɖۑ�i�k���������t�B�[���h�Ȋw�Z���^�[�����R�c�q�F�j�C4�j���c�G���̊��ւ̑��d�@�\�i�؋���w����Tae�|Wan Kim�j�B
�@�o�C�I�K�X�ɂ��ẮC���{�Ɗ؍��̃o�C�I�K�X�v�����g�ɂ�鐶�Y���Љ��C���[���b�p�̂���Ɣ�r���Ȃ���C���ꂼ��̌���ƍ���̉ۑ肪�����ɘ_�c����܂����B�o�C�I�G�^�m�[���ɂ��ẮC�H�ƂƂȂ�앨�ł͂Ȃ��C���N�����ނɂ��Z�����[�Y�n�o�C�I�}�X�̏d�v���ɂ��Ĕ��\���Ȃ���C���̒��ŁC�X�X�L��I�M�̎��g�݂��Љ��܂����B���c�̑��d�@�\�ɂ��ẮC���g���̌y���␅�����̏y�ђ~�ϋ@�\���̑����̑��ʂ���C���̋@�\���Ȋw�I�Ɍ����邱�Ƃ��d�v�ł���Ɣ��\����܂����B�Ō�ɖ{�w�_�w�����@�̑�苳���̎i��ő������_���s���C���̒��Œ�Y�f�Љ�Ɍ����āC���{�Ɗ؍�����������F���Ɖۑ������Ă���C����͑��݂Ɍ������͂𐄐i����K�v�����邱�Ƃ����炽�߂ĔF�����܂����B |
| |
 |
 |
�����̍r�ؐ搶�i�k���������t�B�[���h�Ȋw�Z���^�[�j
�ɂ�鈥�A |
�������_���̏��c�搶�C�R�c�搶 |
|
| |
| �@ |
| |
| �ӌ�������u�n���ɗD�����Љ�ւ̑�w���s���Ƃ̋����v |
 |
| |
���@ ���F11��14���i�y�j
��@ ���F�k�C�����T�|�[�g�Z���^�[�i�ɓ��E�����r���S�K�j
��\�ҁF�n�����Ȋw�����@�@�y�����C�O���[�o��COE�g�����t�B�[���h���Ȋw�̋��猤�����_�`���h���_���[�_�[�@�R���N�T
|
| |
�@�k�C����w��w�@�n�����Ȋw�@�ł́C11��14���i�y�j�ɖk�C�����T�|�[�g�Z���^�[�ɂāC�u�n���ɗD�����Љ�ւ̑�w���s���Ƃ̋����v�Ƃ����^�C�g���ŁC�k�C����w�T�X�e�i�r���e�B�E�E�B�[�N2009�ӌ���������s���܂����B
�@�{�v���O�����̃e�[�}�́C�w�т̏�����e�[�}�ɁC�k�C����w���s���ƈꏏ�ɂł��邱�Ƃ��l������̂ł��B�y�j���̖�ɂ�������炸���͂قږ��Ȃł����B
�@�v���O�����́C�k�C����w�_�w�����@�̒������m�����̈��A�Ŗ����J���܂����B
�@�܂��ŏ��ɘb��Ƃ������ƂŁCCoSTEP�i�k�C����w�Ȋw�Z�p�R�~���j�P�[�^�[�{�����j�b�g�j�̓n�ӕێj���C�y�������u��w�Łw�Ȃɂ��x������Ƃ������Ɓv�Ƃ�����Ŋ�u�����s���܂����B�u�����������Ɓv�Ƃ��ĕ����𑨂��َ��ȃ����o�[�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̏d�v��������Ă���܂����B
�@���ɁC���{�f�[�^�[�T�[�r�X������Ђ̕��Ԕ��j�����u��w�Ɗ�Ƃɂ��l�ވ琬�v�Ƃ�����ōu�����s���܂����B���݃R���T���^���g�Ƃ��āC��w�ɂԂ牺����̂ł͂Ȃ��ϋɓI�ɃA�N�V���������ėl�X�Ȑl�ƐG�ꍇ�����Ƃ��Ă���܂����B
�@�����āCGCOE�����猤���𗬎�����́C��������C�g�����F�C���ݏ~��Y��3�������݂̎��g�݂Ɋւ��ăv���[���e�[�V�������s���܂����B��w�̓��ɂ����炸�C�A�J�f�~�b�N�ɂƂ���Ȃ��C������y��Ƃ����Љ�ł̎��H�ɂ��Ă̏d�v���ɂ��Č���Ă���܂����B
�@��2���́C�O���s��ꂽ�u�������ɂ��āC�s���̕��Ƒ�w���̊����Ȉӌ��������s���܂����B�����̕��X����C��w�ɑ��镝�L���ӌ�����яo���āC�����ȋc�_���W�J����܂����B�w���Ǝs���̊ւ����d������ӌ��������C�ӌ��𗬂͑�ϔ��M�������̂ƂȂ�܂����B�s���̑�w�ւ̊��ғx�̍������M���܂��B
�@�Ō�ɁC�O���[�o��COE�u�����t�B�[���h���Ȋw�̋��猤�����_�`���v�̋��_���[�_�[�R���N�T�y��������̈��A���s���܂����B
�@�v���O�����I������C�Q���҂͈��A�����킵�Ė��h�������s������C���z���q�����ȂǁC�F��ϔM�S�ȗl�q�ł����B
�@�Q�����Ă����������F�l�C�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B |
| |
 |
 |
�g�� ���ȊwGCOE�R�[�f�B�l�[�^�[�ɂ��
�v���[���e�[�V���� |
�R�� ���ȊwGCOE���_���[�_�[�ɂ��
��̈��A |
|
| |
| �@ |
| |
�b�b�b�u���E�̎q�ǂ����Ȃ������v��
�`�J���{�W�A�E�C���h�Ɠ��{���Ȃ��u�t�̎莆�v�` |
 |
|
| |
�� �@���F11��14���i�y�j�`11��15���i���j
�� �@���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF��w�����ȁ@�C�m2�N�@��|�T�q |
| |
�@�ċG��CCC�u���E�̎q�ǂ����Ȃ������v���s�����T�}�[�Z�~�i�[�̕��11��14���i�y�j����s���܂����B
�@�W���F�ċG�̃T�}�[�Z�~�i�[�̓��e���L�ڂ������̂�17���C�ʐ^���50�����ɓW�����܂����B
�@���F14���́u�J���{�W�A�ҁv15���́u�C���h�ҁv�ł���C�J���{�W�A�҂ł̓S�~�R�ŕ�炷�q�ǂ��̗l�q��C�J���{�W�A�̗��j�C�J���{�W�A�̐H�ו��Ȃǂ���ƌ����g���đ̌����Ă��炢�܂����B�C���h�҂ł̓C���h�̎����J�������Ă���q�������̗l�q���Љ�C���ۂɃC���h�̃}�[�P�b�g�Ŏ����J���̌������ނ����f���Ȃǂ𗬂��C�����J�����n�r���{�݁u�aornfree �`rt school�v�ɕ�炷�q�ǂ��������Љ�܂����B
�@���[�N�V���b�v�F�J���{�W�A�҂ł̓J���{�W�A�̃S�~�R�ɏZ�ގq�ǂ��B����̎莆��ǂ݁C���̓��e�ɂ��Ęb�������C�莆�ɑ���Ԏ���F���ɂ܂Ƃ߂܂����i�F���͌��n�ɓ͂���\��j�B�C���h�҂ł͎����J�������Ă����q���̐l����U��Ԃ�Ȃ���C����̐l����U��Ԃ�C�ĔF������Ƃ������[�N�V���b�v���s���܂����B
�@�W���E�̔��F�����J�����n�r���{�݁uBornfree Art school�v�̎q�ǂ��������쐬������i�̓W���E�̔����s���܂����B
�@�]���F�A���P�[�g�ɂ����Ăǂ���̕�y�у��[�N�V���b�v�ɂ����Ă��C�u�Ⴄ���E�����邱�Ƃ�m�����v�u������ŏI���Ȃ��������o���Ă悩�����v�u�����Ɓi���̂悤�ȍ��ɑ��j�x���������Ɗ������v�ȂǍ��ی𗬂ɍv���������������]�������������̂Ŋ����ړI�͂قډʂ������ƍl���܂����C����X�^�b�t�̔z�u�E�L���Ȃlj��P�̗]�n�����镪�������܂����B
�@������C����̔��ȓ_�����C�u���E�̎q�ǂ����Ȃ������v�̎��{�𑱂��C��葽���̎q�ǂ��������C�������C�������ȑ��݂ł���Ƃ����C�t����������������Ă�����ƍl���Ă��܂��B�܂��C�����O�̎q�ǂ�����������ɂ��Ă̕����ʂ��āC�����o�[�S�̂̈ӎ��̌����}�肽���Ǝv���܂��B |
| |
 |
 |
| �|�X�^�[�̏Љ� |
| �v�������߂��Ԏ���F���� |
|
| |
| �@ |
| |
| ���ۃV���|�W�E���u��Z�����Ǝ��R�����|�����I�������p�̎��_����|�v |
 |
| |
�� �@���F11��15���i���j
�� �@���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF���w�����ȁ@�����@�r�c�@�� |
| |
�@��Z�����̒m���̒��ɂ́C���Ƃ̒����Θb�ɂ���Ĕ|���Ă��������Ǘ��Ɋւ��鑽���̃q���g���Ïk����Ă���C�����̎����I���p�Ƃ����ʂő����̊w�Ԃׂ��_������܂��B
�@�{�V���|�W�E���ł́C�j���[�W�[�����h����Dr. Brad Coombes�CMr. Marino Tahi�CMr. Alex Nathan �̂R�������ق��C��Z�����}�I���̐l�X�ɂ�鎩�R�����Ǘ��̎��݁C�y�уG�R�c�[���Y���Ƃ������R�����̐V���Ȋ��p�@�ɂ��Ęb������������C�܂����{�̐�Z�����ł���A�C�k�̐l�X�̒m�����������������Ǘ��ɂ��Ă����H�����������āC����̎����I�������p�݂̍�����������܂����B
�@�}�I���̐l�X�ɂ�鎩�R�����Ǘ��ł́C�ی�n���ݒ肵�Ď��R�����́u�ۑ��v��}��Ƃ�����@�ɑ��āC�ނ炪�`���I��@�Ŏ��R�����𗘗p���Ȃ���Ǘ����s���Ƃ����u�ۑS�v���d��������@���ނ玩�g�̕ۑS�����ւ̐ϋɓI�Q���𑣂����ƂɂȂ���C�܂����{�Ƃ̋����ɂ��������Ă���Ƃ������Ⴊ������܂����B����ɂ́C�G�R�c�[���Y���y�ѓ`���I�����̏Љ�������Ɏ����ꂽ�G�R�E�J���`�������c�[���Y���̓W�J�ɂ��Ă����̉\���Ɖۑ肪��N����܂����B
�@���{������́C����L���ɂ��k�C���̃A�C�k�E�G�R�c�[���Y���̓W�J�ɂ��Ă̘b��Ɉ��������C�L�V�k�ꎁ�ɂ��X�ъǗ��̎��݁C�����ꎁ�ɂ��m���A�C�k�E�G�R�c�[���Y���̎��H�C���N���ɂ��G�]�V�J�Ɋւ�����s���C�A�C�k��������ՂƂ������R�����Ǘ��̉\�����Љ��܂����B���ꂼ��ɐ�Z�����̌����ɉۑ���c���Ă͂��錻��ł͂���܂����C�����̎��R�����̕ۑS�ɂ��Đ�Z�����ɂ��ϋɓI�Ȋ֗^�̐��ʂƐV���ȉ\�����������ꂽ�L�Ӌ`�ȃV���|�W�E���ƂȂ����ƍl���Ă���܂��B�����̎Q���҂̕��X������C��Z�����̕������w�Ԃ��Ƃ������̎����\�ȎЉ�̎����̃q���g�ɂȂ�Ƃ����ӌ������������܂����B
�@����̃V���|�W�E���J�Âɂ���āC�j���[�W�[�����h�̃}�I�������Ɠ��{�̃A�C�k�����Ƃ̋����ɂ�鍡��̎��H�E�����̓W�J�ɂ������J���܂����B������������𖧂ɍs���Ă���Ɍ𗬂�[�߂�ƂƂ��ɁC�����ۑS���݂̂Ȃ炸�C��Z���������Ɋւ��闝���E���H�E�����̔��W��}�肽���ƍl���Ă��܂��B |
| |
 |
 |
| �I�[�N�����h��w��Dr. Coombes�ɂ��u�� |
�u���҂Ƃ̋L�O�ʐ^ |
|
| |
| �@ |
| |
| ���ۃV���|�W�E���u�����\�ȎЉ�̔��W�Ɛ��E�Ɛl�̎g���v |
 |
| |
�� �@���F11��15���i���j
�� �@���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF���w�����ȁ@�����@�V�c�@�F�F |
| |
�@���ۃV���|�W�E���u�����\�ȎЉ�̔��W�Ɛ��E�Ɛl�̎g���v�́C���w�����ȁE���p�ϗ���������Z���^�[��Â̑�4�p�ϗ����ۉ�c�i11��13�`15���j�̒��j�ƂȂ�s���Ƃ��ĊJ�Â���܂����B
�@�V���|�W�E���ł́C���҂Ƃ���Michael Davis�i�}�C�P���E�f�C���B�X�j���m�i�C���m�C�H�ȑ�w�����j��Randall Curren�i�����h�[���E�J�����j���m�i���`�F�X�^�[��w�����j���}���܂����B�f�C���B�X���m�̍u���́C�薼�F�uEngineers and Sustainability: An Inquiry into the Elusive Distinction between Macro�| Micro�|, and Meso�|Ethics�i�Z�p�҂ƃT�X�e�i�r���e�B�F�}�N���E�~�N���E���\�ϗ��̊Ԃɂ���݂͂�������ʂɂ��Ă̒T���j�v�ł��B���̍u���Ńf�C���B�X���m�́C���E�Ƃ��Ă̋Z�p�҂̗ϗ���E�\�W�c�Ƃ��Ẵ��\���x���̗ϗ��ł��邱�Ƃ��`�Â�����ŁC�T�X�e�i�r���e�B�̎����͋Z�p���E�ϗ��̈ꕔ�ł���C�܂����E�ϗ��ł��邩�炱���C���̎����Ɍ����Ă̊������Z�p�҂̐Ӗ��ł��邱�ƁC�܂����i�⌚�����ȂǍL���Љ�ɉe����^���郂�m��o���Z�p�҂������C�����\�ȎЉ�̎����ɍv���o����\�͂������C���̍v�����Љ����҂���Ă��邱�Ƃ�_�����܂����B
�@�J�������m�͑薼�F�uSustainability in the Education of Professionals�i���E����ɂ�����T�X�e�i�r���e�B�j�v�ōu������܂����B���̍u���ł́C���݂̃T�X�e�i�r���e�B�ɂ܂����������ŁC���E�̑��ݗ��R�͎Љ�ւ̍v���ɂ���C���ꂪ�Љ��̐M���Ɋ�Â��Ă���ȏ�C�����\�ȎЉ���������Ă������Ƃ��܂����E�ϗ��̈ꕔ�ł��邱�Ƃ��_�����܂����B����ɃJ�������m�́C�T�X�e�i�r���e�B����͂��łɐ��E�ϗ�����̈�Ƃ��čs���Ă��邪�C���ꂩ��͂����E�ϗ�����ƈ�̉������d���łȂ���˂Ȃ�Ȃ��Ƙ_���Ă����܂����B
�@2�l�̍u���Ɉ����������^�����ł̓t���A���瑽���̎���y�уR�����g���W�߁C�L�Ӌ`�ȃf�B�X�J�b�V�������s���܂����B���ł�4�x�ڂ̊J�ÂƂȂ鉞�p�ϗ����ۉ�c�ł����C����������E�C�O�̉��p�ϗ��Ɋւ����v�e�[�}��_����t�H�[�����Ƃ��āC�T�X�e�i�r���e�B�Ɨϗ��������e�[�}�̊�ɐ����p���I�ɊJ�Â��Ă����\��ł��B����̑�5�ۉ�c��2010�N11����\�肵�Ă��܂��B |
| |
 |
 |
| �f�C���B�X���m�ɂ�锭�\�̗l�q |
���^�����̗l�q |
|
| |
| �@ |
| |
| �k�����̊������Ɋւ�����{�|�t�B�������h���������Z�~�i�[ |
 |
| |
���@ ���F11��16���i���j�`11��18���i���j
��@ ���F�w�p�𗬉��
��\�ҁF�ቷ�Ȋw�������@�y�����@���V�@�M�j |
| |
�@���g���ɂ��}���ɕω�����k�����̊��Ɋւ��āC�k�C���ƃt�B�������h���A�g���Ď�g�ލŐV�̌������茤���҈琬���ۃv���O�����Ȃǂ��Љ�C���������̌p���⏫���̌����v��̉\���ɂ��ċc�_����u�k�����̊������Ɋւ�����{�|�t�B�������h���������Z�~�i�[�v���C���b�v�����h��w�k�ɃZ���^�[�����S�ɂȂ�C����20�N9��3���`5���Ƀ����@�j�G�~�ɂĊJ�Â���܂����B
�@�{�N�x�͂��̌p���ł����C���ɁC��茤���҂��w�@���x���ł̋��猤���𗬐��i�ɏd�_��u���܂����B11��16���i���j����S�̉�c�`����3���ȉ�Ƒ������_��2�����C�x┓��ꍑ�������ł̌��n���C�Ɠ��_���2���Ԃ̓����ł����B���ȉ�1: Cryosphere & Boreal Forests��7��C2: Landscape, Land Use Changes��9��C3: Human�|Environment Relations��12��̔��\������܂����B���ȉ�1��2�͑O��̃t�B�������h�ł̃Z�~�i�[�ŋc�_���ꂽ�{�w�ƃt�B�������h�̑�w�i�w���V���L��w�C�I�E����w�C���b�v�����h��w�j�Ői�߂��Ă��鋤�������̐i����V���Ȍ����e�[�}�̒�ĂȂǂ�����C����̌p�������茤���ҁC�w���̋��猤���𗬎��ƁC�P�ʌ݊��̉\���Ȃǂɂ��ċc�_����܂����B��茤���҂�w����Ώۂɂ���Sea�|ice field course�̃e�L�X�g���������M����o�ł���܂����B�I�E����w�͖{�w�Ǝo���Z�C�A�g��w�Ƃ��Ē������Ă���C�i�w�����K��\��ł������}篎�~�߂ɂȂ�j�w�p���ۋǒ��ƍ��ی𗬒S�����������Ƃ��{�w�{�����w����\�h�K�₳��C��茤���҂��w�@�w���̋��猤���𗬂ɂ��Ĉӌ���������܂����B���b�v�����h��w�̕��w���Ǝ����ǒ��������ɕ\�h�K�₳��܂����B
�@���ȉ�3�́C���܂ł̎��R�Ȋw�n�̃e�[�}�Ɂu�l�ԂƎ��R���Ƃ̊W�v���������V���Ȏ��݂ł����B�{�w�A�C�k�E��Z���������Z���^�[�C�����H��C���b�v�����h��w�����S�ƂȂ�C�C��ϓ���l�ނ̊��������ɂ�茀�I�ȉe������k�����̊��ϓ������b�v�����h�̃T�[�~��k�C���̃A�C�k�����̐�����ʂ��āC�ނ炪�ǂ̂悤�ɉe�����C�܂��ނ炪�����Ă�����_�Ȃǂ�����ɂ��ĔM���c�_�����킳��܂����B
�@�������_��ł́C����̌p�����ɂ��āC��Z�����W�ł͖{�̋������M�̌v��C���N�x�̃Z�~�i�[�̓I�E����w������S�����ƂȂǂ��b����܂����B���C���s�ł́C���V�̃A�C�k���������ق̌��w�C�x┓��ꍑ�������Ō����Ǘ��C�ێ��C���_�Ȃǂ��w�т܂����B�t�B�������h����̎Q���҂͖w�ǃt�B�[���h�T�C�G���X�̌����҂ł���C���ɕ��ȉ�2�̊W�҂ɂ͓��{�̍��������̌�����w�ԗǂ��@��ł����B |
| |
 |
 |
| ���ȉ�ł̓��_ |
���V�A�C�k���������قł̌��C |
|
| |