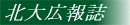1906(明治39)年、古河鉱業は帝国大学創設費として百万円を政府に寄付。そのうち約14万円が北大の前身・東北帝国大学農科大学に分配されました。 古河講堂はその時新・増築された8棟のうち現存する唯一の建物です。設計は茨木出身の文部技官・新山平四郎、施工は札幌の大工・新開新太郎が担当。建築面積127.5坪、総工費3万円余の建物は6ヶ月の工期を経て、1909年11月末に林学教室として誕生しました。 「古河家寄贈」と正面に記された白亜の洋館は、当時の建築技術の粋を集めたものになりました。フランス・ルネサンス風の緑色のマンサード屋根と両翼のドーマー窓が華麗に配置されています。  玄関を入ると仕切扉の上に「林」をデザインした欄間があり、その奥にはイオニア式円柱を手摺子にした階段が目に入ります。半円形の明かり取り窓やアーチを支えるインポストなども独特な装飾が施されています。 玄関を入ると仕切扉の上に「林」をデザインした欄間があり、その奥にはイオニア式円柱を手摺子にした階段が目に入ります。半円形の明かり取り窓やアーチを支えるインポストなども独特な装飾が施されています。 謎は柱や半円窓の台に刻まれた14頭もの鹿の線刻装飾です。「林」の欄間と共に北海道の自然を表すのか、学問の森での飛躍を願うのか、はたまた鹿鳴館的文化の発祥をここに委ねたのか、いずれにせよ明治的ロマンを感じさせます。 謎は柱や半円窓の台に刻まれた14頭もの鹿の線刻装飾です。「林」の欄間と共に北海道の自然を表すのか、学問の森での飛躍を願うのか、はたまた鹿鳴館的文化の発祥をここに委ねたのか、いずれにせよ明治的ロマンを感じさせます。 国の登録文化財及びさっぽろ・ふるさと文化百選にも指定された歴史的建造物ですが、薄い一重ガラス窓のため冬には内部も氷点下になることがあります。教官達には不評ですが、歴史を体感しながら学問を追求できるのは贅沢な悩みかも。 国の登録文化財及びさっぽろ・ふるさと文化百選にも指定された歴史的建造物ですが、薄い一重ガラス窓のため冬には内部も氷点下になることがあります。教官達には不評ですが、歴史を体感しながら学問を追求できるのは贅沢な悩みかも。竣工から90年、明治からの歴史を眺めてきた古河講堂は年末にはお色直しを終え、新世紀を迎えようとしています。 内部は文学部の研究室として使われているため、現在のところ一般公開はされていません。 (瀬名波・田島) |
|
|