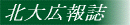|
紅葉を迎えた大野池 |
通称「大野池(おおのいけ)」は、中央道路西側の工学部とファカルティハウスの間にあります。エコキャンパス推進事業の一環として平成10年8月に整備されて以来、訪れる人々を北大創立以前の自然へ引き戻してしまうほど魅力のある場所になりました。
 雪まだ残る3月、池は水墨画のような静寂さの中にあります。が、やがて春を迎えると、池の周りには北海道を代表する様々な木々や草花が芽を出し始めます。池中央奥の噴水では、さわやかな風とともにしぶきが舞い、水中を泳ぐ色鮮やかな魚たちに誘われて、野生の鴨が飛来し翼を休めます。初夏には岸辺に白い可憐なエンレイソウ、夏には赤や白の蓮の花が咲き、秋の紅葉は人の心を和ませます。北海道の雄大な自然とは対照的に、大野池には神秘的な繊細さがあります。 雪まだ残る3月、池は水墨画のような静寂さの中にあります。が、やがて春を迎えると、池の周りには北海道を代表する様々な木々や草花が芽を出し始めます。池中央奥の噴水では、さわやかな風とともにしぶきが舞い、水中を泳ぐ色鮮やかな魚たちに誘われて、野生の鴨が飛来し翼を休めます。初夏には岸辺に白い可憐なエンレイソウ、夏には赤や白の蓮の花が咲き、秋の紅葉は人の心を和ませます。北海道の雄大な自然とは対照的に、大野池には神秘的な繊細さがあります。
 |
大野池南側水路 |
かつて、サクシュコトニと呼ばれる川がありました。それは北大植物園の北側を源泉とし、現在の北大を南東から北西に横切って琴似川に合流するきれいな流れを作っていました。大野池は、その川の泉の一つとして貴重な役割を果たしていました。現在、川の名残は中央ローンの小川と、今回大野池とともに再生された池南側の水路に見ることができます。
北大創立後の大正10(1921)年頃、大野池周辺は農学部第二農場の牛追い場の一部となり、池は牧場に遊ぶ牛馬の飲用として、また実験農場の取水源として利用されました。昭和に入り工学部等の研究施設が大野池の周りに次々と建設され始めます。昭和30年代の高度成長期に突入すると、この池にとって受難の時代が始まりました。池周辺は半ば塵廃棄場化し、どぶ臭い湿地に変わってしまったのです。
 |
故・大野教授 |
ところが昭和40年代後半、変り果てた池をもとの姿に戻そうと立ち上がったのが、当時の大野和男工学部教授です。大野教授の尽力で池は徐々に再生され、いつしかそこは「大野池」と呼ばれるようになりました。
学問の泉である大学にとって、池は象徴的な存在です。大野池の再生は21世紀に向けた北大の新たな可能性を予言しているのかもしれません。
(瀬名波) |
 雪まだ残る3月、池は水墨画のような静寂さの中にあります。が、やがて春を迎えると、池の周りには北海道を代表する様々な木々や草花が芽を出し始めます。池中央奥の噴水では、さわやかな風とともにしぶきが舞い、水中を泳ぐ色鮮やかな魚たちに誘われて、野生の鴨が飛来し翼を休めます。初夏には岸辺に白い可憐なエンレイソウ、夏には赤や白の蓮の花が咲き、秋の紅葉は人の心を和ませます。北海道の雄大な自然とは対照的に、大野池には神秘的な繊細さがあります。
雪まだ残る3月、池は水墨画のような静寂さの中にあります。が、やがて春を迎えると、池の周りには北海道を代表する様々な木々や草花が芽を出し始めます。池中央奥の噴水では、さわやかな風とともにしぶきが舞い、水中を泳ぐ色鮮やかな魚たちに誘われて、野生の鴨が飛来し翼を休めます。初夏には岸辺に白い可憐なエンレイソウ、夏には赤や白の蓮の花が咲き、秋の紅葉は人の心を和ませます。北海道の雄大な自然とは対照的に、大野池には神秘的な繊細さがあります。