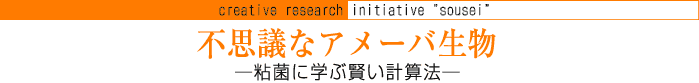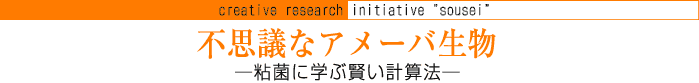|
粘菌類であるモジホコリ(Physarum polycephalum)の変形体(アメーバ状の原形質の塊で多核である)を小さく分けて、3㎝四方の迷路に置くと、広がって互いに合体し、入り込める空間すべてを埋める(図2a)。しかし、迷路の入口と出口に食物を置くと、モジホコリの変形体は「体」を行き止まりから離して、入口と出口を結ぶ最短の道をつなぐ形になる(図2b)。実に効率よく、迷路の問題を解く。細胞によるこの驚くべき解決法は、細胞レベルの材料が原始的な知性を示せることを意味する。粘菌はユニークな生物であるがゆえ、格好の研究対象である。
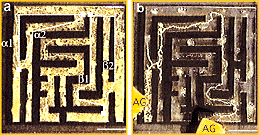
図2 迷路を解く粘菌。迷路一面に広がる粘菌(a)に餌(AG)を置くと、最短経路にだけ太い管を残した(b)。 |
|