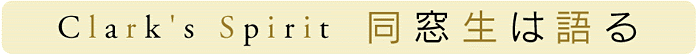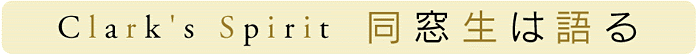|
東京湾の一角に東京都のゴミ・建築残土捨て場の中央防波堤がある。連日運び込まれる建築残土が海底から汲み入れられた土壌と混ざりヘドロ環境を常に作り出している、埋め立ての最前線である。美しい自然のイメージはないが、ここは豊富な鳥類の楽園となっている。多数のアジサシ、コアジサシ、シロチドリが繁殖し、ハヤブサ、チョウゲンボウの狩り場となる。また10年前からセイタカシギの重要な繁殖地ともなっている。私はここ東京湾岸でセイタカシギの調査を17年にわたり行っている。
セイタカシギは、1975年に、愛知県の干拓地で1つがいの繁殖が確認され、その後少数が千葉県市川市に定住し、次第に分布を広げ、現在までに200羽程に増加し、主に東京湾岸に中央防波堤を含め5カ所ほどの繁殖地がある。
中央防波堤では、セイタカシギの巣卵の多くが整地をするブルドーザーに踏みつけられ、また降雨による増水で流失する。ゴミに集まるカラスの群が卵・雛を襲う。そこは繁殖条件としては劣悪に見える。
しかし、彼らは巣卵を失えば、再営巣・産卵を何度もくり返すたくましさを持つ。栄養豊かな土砂から水溜まりに染み出した成分は初夏には豊富なプランクトン類と膨大な数のミギワバエの発生を促す。これらが繁殖期の成鳥と雛達にとって重要かつ充分な栄養となる。また草木の生えない見通しの良い環境は地上の外敵が巣卵へ忍び寄ることを難しくする。実は、ここはセイタカシギの繁殖には、大変好ましい環境なのである。
ところで鳥類は子孫を残す手段として多種多様な婚姻形態を発達させてきた。セイタカシギは一夫一妻を基本としてはいるが、私はこれまでに一夫二妻、一妻二夫、雌雌つがい、さらにより複雑な性関係のケースを見つけることが出来た。実に多様化した性関係を展開してみせるセイタカシギは、今後私に、鳥類の様々な婚姻形態がいかなる道筋で進化してきたかを解明する糸口をつかませてくれるものと期待している。
 |
抱卵交代をする
セイタカシギのつがい |
|