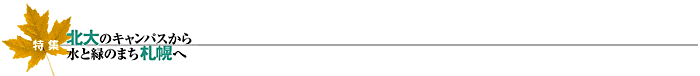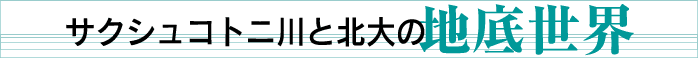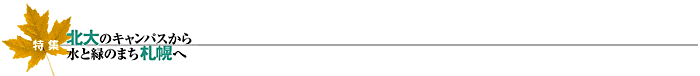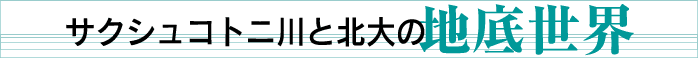|
札幌キャンパスを1〜2メートル掘り下げると、おおよそ1000年ほど前の擦文文化の遺跡に到着します。さらに1メートルほど掘り進むと続縄文文化の遺跡が顔をだしてきます。今から約2000年くらい前のものです。実は、札幌キャンパスのほぼ全域は遺跡として指定されており、K39遺跡とK435遺跡の2つの遺跡名で呼ばれています。そのためにキャンパス内で建設や土木の工事を行う際には必ず、遺物や遺構の有無を確認するための発掘調査を行わなければならないのです。「サクシュコトニ川再生計画」にともなう土木工事に際しても、その発掘調査は実施されています。しかし全域が遺跡に指定されているからといって、どこを掘っても遺物などが発見されるわけではありません。K39遺跡とK435遺跡と呼ばれるものの正体は、たくさんの遺跡が密集した「遺跡群」というものなのです。そしてそれらたくさんの遺跡は雑然と集まっているだけではなくて、そこには一定の規則性があります。それはかつて札幌キャンパスの中を流れていたサクシュコトニ川とセロンペツ川、及びそれらの前身である埋没小河川に沿うようにして分布している点です。続縄文文化と擦文文化の人々は共にサクシュコトニ川との深い結びつきのなかで生活を展開していたのです。 |