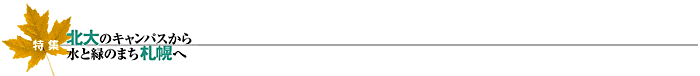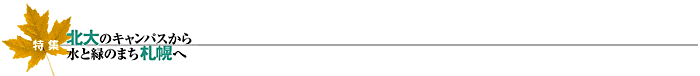北方生物圏フィールド科学センター植物園・博物館は、明治10(1877)年に開拓使が設立した札幌仮博物場を前身とする博物館で、120年以上にわたり北海道大学のスタッフ・学生の協力の下、資料・標本を収集・管理、提供し続けています。動物・歴史・考古・民族・絵画など、所蔵資料は現在約5万点にのぼり、この中には、「ブラキストン線」で著名なブラキストンが収集した鳥類標本や、絶滅したエゾオオカミの剥製など、世界的にも貴重な標本群が含まれています。このような資料は、さまざまな形で利用、紹介されているので多くの方はご存知でしょう。今回は、「キャンパスの自然」をテーマに、キャンパス内で採集された資料について紹介し、その意味について考えてみたいと思います。
所蔵標本のうち、キャンパス内で収集・採集された資料は、考古資料を除くと100点ほどになります。この10年の間に収集されたものでは、絶滅危惧種に指定されているオオタカや、エゾフクロウ、カワセミなどがあります。オオタカは営巣地の問題などはありますが、現在でも札幌付近で観察されていますし、エゾフクロウも冬季に植物園内で観察されることもありますから、それほど珍しいものではありませんが、これらの鳥たちがキャンパス内で死亡し、収集されているということは、現在のキャンパスが動物たちにとって住みやすい環境であることを意味しています。しかし、これらの多くは窓にぶつかったり、凧糸を足に絡ませた状態で木にぶら下がっていたりしたものが収集されたもので、人間と動物との共生の難しさも物語ります。
このように、北大のキャンパスは自然に恵まれたものといえますが、より古い標本を検討してみれば、周辺の環境も含めて、もっと豊かであった時代があることがわかります。 |