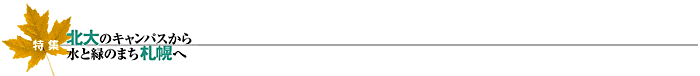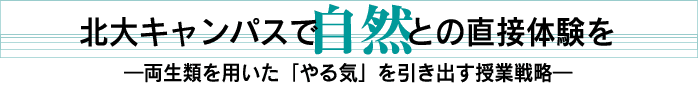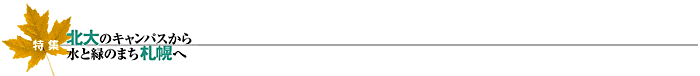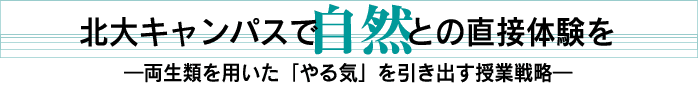「いた、いたぞ! これトウキョウダルマじゃない?」「おお?、スポット(斑紋)が独立しているから、トノサマではないな!」「背中線は綺麗に出ているじゃん。で、雌雄は?」北大のキャンパスに緑が増す頃、生物生産研究農場ではカエルを手にした学生たちの歓声がいつまでも響き渡っています。これは、全学教育の一つである一般教育演習「蛙(あ)学への招待」の授業風景です。
「昆虫採集などやったことがありませんよ…」最近学生からよくこんな声を耳にします。自然との直接体験の不足、またそれを補完する初等中等教育での実験実習や観察の不足は、私たちの想像以上に進んでいるようです。体験を通して得る情報と紙上で得る情報とでは、その量や質が圧倒的に異なります。それは、学力の低下だけでなく、学ぶ意欲の喪失にもつながる重要な問題なのです。 |