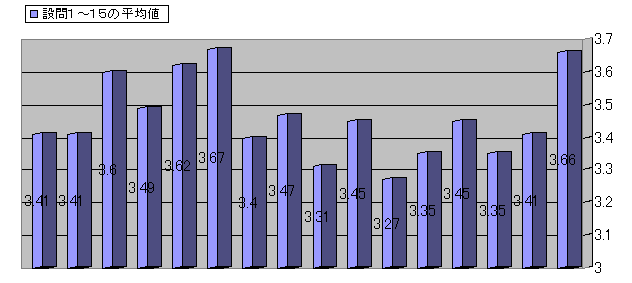
第2章 学生による「授業評価アンケート」について
はじめに
学生による授業評価は,平成4年設置された点検評価委員会において,平成5年に試行,平成6年に本実施された。この学生による授業評価は,1)学生の自己評価,2)学生による授業評価,3)教育環境の評価の3部からなっていた。また,授業に対する教員アンケートも同時に行った。平成7年には,「学生の授業評価に対する教員のレスポンス」をアンケート調査した。ここでは,学生による授業評価は,授業改善に有効であり,2から3年に1度は実施すべきであると結論された。一方,教員の教育業績評価方法が平成8年に提案された。これでは学生による授業評価も再検討された。平成9年には「学業成績評価について」アンケート調査した。ここでは,教育に関わる教官研修(ファカルティ・デベロップメント:FD)と教育業績評価の実施する方向性が打ちだされた。教育業績評価は,さらに実現にむけて内容を検討し,平成11年には管理運営と社会貢献をいれた総合評価が,これから毎年実施することになった。これは,教員の申告によるものである。したがって,学生による授業点検も並行して実施することになった。また,評価には基準の理解,合意が必要である。教育の要素,基準についてのFDが,平成10年から実施されるようになった。
「学生による授業評価」の結果は,厳正な評価,客観的評価,異なる分野の教員を比較できるような評価にはなっていない。正しい評価というには問題もあるので,「授業アンケート」と呼ぶことにした。
アンケート内容
アンケート内容は,これから毎年実施することを考慮し,必要最小限の設問とした。設問は,評価の原則にしたがって,できるだけ観察可能な内容とし,授業評価すなわち教員が担当する授業に関する設問を中心とした。後期の授業については,次年度に,ぞの前期授業とともに調査し,まとめることにした。
設問は,つぎの群に分けられた。
A「シラバスとその内容」
B「教師の授業法」
C「学生参加」
D「難易度」
E「学生の満足度・達成度」
F「出席・態度」
G「自由意見」
授業に関してAからEまでを15問とし,これに学生の自己評価的設問としてFの2問を加え,合計で17の設問とした。各設問への評価は,非常にわるい1から非常によい5までの尺度評価とした。アンケートは,講師以上の教員の前期の授業,どれかひとつ以上について調査した。
調査に応じた授業
調査に応じた授業は,合計597であった。講義と演習の比率では,80%〜90%が講義であった。全学教育とくらべ,とくに専門教育の方が講義が多い。これは,専門教育で大きな比重を占める実験,実習を調査の対象にしなかったためともみなされる。
学部別に専門科目の授業形態(講義か演習か)およびクラスサイズをみると,理系と文系で大きく異なっていた。講義は,文系では50%〜65%,理系では95%〜100%であり,演習は文系では35%〜50%であるのに対し,理系では 0%〜5%である。また,クラスサイズも異なる。文系学部では25人以下のクラスが40%〜50%である。一方,文学部をのぞいて100人以上,あるいは200人以上の大人数クラスも少なくない。とくに法学部と経済学部は,大人数クラスも特徴的である。理系学部では,理学部,農学部で25人以下のクラスも少なくないが,その他は100人クラス(51〜100人)が多い。それより大人数クラスは,水産学部が200人サイズが約30%あるが,他には少ない。これは理系での実験,実習がアンケートの対象としていなかったのに対し,文系ではゼミナール(演習)などが含まれているためと思われる。
言語文化部は全学教育を担当している。語学教育は,クラスを講義か演習かに分けることはできない,あるいは,目標が言語の運用能力にあるため,結果が別に見えるようにした。
各授業アンケートの集計結果は,全体,全学教育,専門教育,学部専門教育,講義,実習の各平均と比較できる表,および自由意見のすべてを付して,各担当教官へフィードバックされた。
アンケート結果と解析
ここでは各設問の内容,解析結果,解釈について述べる。評点は,よい方から順に5,4,3,2,1,となり,3は普通である。解析結果では,評点4と5を合計した比率を中心に解釈を進める。また,4と5の合計がほぼ半数,1と2の合計が約10%以下を高い評価,あるいは良好な評価とみなした。
A「シラバスとその内容」
シラバスと授業
・シラバスは,授業の目標,内容,評価方法を適切に示していた。
シラバスは授業の総体を表現する。各科目は各部局での必要性により存在し,必要理由は,目標として表現され,その目標到達のための授業内容,評価方法ははじめから設計されていなければならない。そしてこのことが学生につたわり,学生はこれを活用して学習できなければならない。
学部別では,4,5と回答した比率は,文系の文・法・経は高い(66.1%〜57.7%)。そのなかでは教育は低い(44.9%)。理系は文系にくらべ低い。現実に充実したシラバスをもつ学部でも,それを踏まえた回答とはなっていない傾向があった。
ここでは,シラバスを目にしていないで,感覚として答えているものが多いであろう。重要な問題は,学生も教員も,シラバスを活用しているとはいえないことである。本学ではまだ授業担当の基本,授業をうけることの基本であるシラバス観が,十分には確立されていないともいえる。
・授業は体系的に行われていた。
全学的によい評価である。本学の学生は,教員に対して好意的評価をしている。
学部別では,4,5は,文系で64.9%〜77.9%と高く,理系は55.1%〜73.0%と低かった。
評価は一般に文系で高く,理系で低かった。文系,理系の授業スタイル,学問体系の基盤の違い,センスを要求するものと正確な知識を要求するものの違いなど様々な要素が関連するのであろう。実際に,文系で演習が多いこと,クラスサイズが小さいことが関係しているであろうし,また系や学部による学術文化や教育観の違いも反映しているであろう。
B「教員の授業法」
ここでは教員のパフォーマンスについて質問した。とくに教員と学生の関係で,学生が教員から知識伝授あるいは直接の影響を受ける授業では,目の前の教員のパフォーマンスは授業法として重要となる。
B1教員と授業
・教員の熱意が伝わってきた。
授業においては,教員の熱意がみえること,熱意が学生に伝わることが最も重要な牽引力となる。
・教員の話し方は聞き取りやすかった。
これは授業法で最も重要な基本的パフーマンスである。
これらは,一般に好評であった。とくに,文系学部で理系学部よりよい評価であった。講義と演習では,演習でよかった。また,クラスサイズの小さい方よいが,200人以上の授業はまた比較的好評であった。
・授業は,難解な概念,理論があっても,わかりやすかった。
わかりやすく伝えることは授業で最も重要なことである。
全体的には評価はやや低かった。系別,講義と演習,クラスサイズでは上の2問と同様の傾向であった。 理解することを求められると,あまり自信をもてないという学生の回答心理が現れていた。
B2メディア(教育媒体)
・黒板,スライド,OHP,ビデオ,教科書,プリント等の使われ方が理解の促進に効果的だった。
授業は,教授者から学習者への情報伝達により成り立つ。広い意味では,話しことばも授業の媒体(メディア)である。ここでは,授業に用いられる話しことば以外のメディアについて質問した。
全体的には,それほどよい評価とはいえなかった。そのなかで,講義,演習では演習の方がよい。文系,理系の差は明瞭でなかった。クラスサイズでは,上記と同じで,小人数の方がよいが,大人数も悪くないという結果だった。
B3「負担」
作業量・負担
・授業の進行速度は適切であった。
一方的知識伝授,教員中心授業は授業の進行が早くなる傾向がある。
意見欄でも,これに関して学生による多くの指摘があった。
全体的には評価はよかった。学部別では,文系が理系よりよかった。演習,言語は適切であるという評価となっていた。
・授業で要求される作業量(レポート,宿題,自習など)は適切であった。
科目における単位があらわす学習時間では,授業時間以外に相当量の予習,復習が要求されている。しかし,日本の学生の自習時間は一般に極端に少ない。ここでは,自習量の適切さよりは,自習を課せられることに対する学生の満足度と関連しているのかもしれない。
全体的には評価はよかった。言語・演習は評価が高かった。
学部別では,文系で一般に適切でとくに文学部は負担が少なく,理系では負担が大きく,そのなかでもとくに医学部の負担は大きかった。履修すべき単位数も最も多い。医学部・歯学部では社会的責任をおった職業教育がおこなわれ,クラス外の作業も多くなっている。
クラスサイズでは,25人以下のクラスではよいが,クラスサイズが大きなところでも負担は大きくなっている。宿題が多いということであろう。
C「学生参加」
学生との相互反応
課題探求能力の育成など,教員と学生との相互反応,学生同志の相互反応を重視し,学生を効果的に参加させる学生中心授業が奨励されている。ここでは授業が学生参加型になっているかを問う。
・教員は効果的に学生の参加(発言,自主的学習,作業など)を促した。
全体的には参加型は多くない。
演習は講義より2倍も参加型となっている。
文系,理系の差はあまりない。教員のパフォーマンスが評価の高かった法学部は低い評価であり,一方的授業が窺える。理系はあまり参加型となっていないが,このなかで医学部は参加型が多い。 クラスサイズでは,サイズの小さいほど学生参加型となっていて,大人数クラスは参加型となっていない。
・教員は学生の質問・発言等に適切に対応した。
全体としては教員は適切な対応をしているといえる。
演習は講義にくらべ教員は学生の反応に適切に対応している。一方的にはなっていない。
学部別では,文系,理系の差はあまりない。クラスサイズでは,小さいほどよく,大きいほどよくない。大人数講義は一方通行であることが明かである。
D難易度
・授業内容の難易度は適切であった。
授業の難易度は,学生が理解できない,ついていけないほど難しいのは問題があるが,適度に難しいのもよいとされている。
全体的には難易度は,適切と評価された。一般に,文系,理系の差はないが,工学部では難しいとしている学生が多かった。
難易度と学生参加,教員との相互作用をみると,学生の参加・教員との相互作用がよいほど適切であると応える学生が多い。相互作用により授業内容の理解が得られることがわかる。
E学生の満足度・達成度
学生の満足度は,それ自体が総体的授業評価をあらわす。ここでは,学生の主観を質問している。
・授業により知的に刺激された。
一般的に,知的に刺激されたと評価している。講義より演習が高い評価となっていた。学部別では,文系が理系よりよかった。
授業法との関連
授業法がよいと答えた学生は,高く評価している。
学生参加との関連
学生参加を高く評価している学生は,高く評価している。
難易度との関連
難易度が普通と答えた学生は,高く評価している。難しいと答えた学生も評価が高い。
クラスサイズとの関連
クラスサイズが小さいほどよいが,100人以上のクラスも悪くない。
・授業の履修目標を達成できた。
達成感は,全体的にはそう高くない。このなかで,演習が効果的であることは理解できるが,一般的には,達成感を問われたときの学生の心理を想像すると,よい評価とはならないことがうかがえる。
学部別では,一般に文系がよく,理系では一般に低かった。
クラスサイズが小さいほどよいが,100人以上のクラスも悪くない。
・授業内容と他の領域との関連について理解できた。
全体的にはよくない。ここでも演習はよい。学部別では文系とは差はない。25人以下のクラスで最も効果的であった。
ここでも,理解度とその自ら内容を発展できる力がついたかを質問している。学生の心理からきてもよい評価とはなりにくい。
・授業により,新しい知識,考え方,技能を習得でき,さらに深く勉強したくなった。
全体では比較的よい。とくに演習がよい。学部別では文系でややよい。クラスサイズが小さいほどよいが,100人以上のクラスも悪くない。
F出席・態度
・この授業に対するあなたの出席率はどの程度でしたか。
全体には,多くが6割以上出席したと答えている。講義より演習が出席がよい。学部別では文系の出席は理系よりよくない。難しいとしているものほど,出席がよい。クラスサイズが小さいほど出席はよい。
・質問,発言,調査,自習などにより,自分はこの授業に積極的に参加した。
全体的に積極的に参加していないと自己批判している。学部別でみても共通して積極性に欠けていることは明瞭である。とくに理系では,積極的に参加したという学生は少ない。クラスサイズが小さいものは積極的参加が多い。
授業評価の総合評価
設問1から15までの総合評価を評価指数であらわした。
総合評価に関して,難易度については,極めて難しすぎる・極めてやさしすぎるを1,難しい・やさしいを3,適切を5として計算した。
その結果,総合点は,以下のようになった。
文系:経3.67,法3.62,文3.60,教3.49
理系:医3.47,
薬・獣医3.45,理3.40, 農・水産 3.35,歯3.31,工 3.27,言語3.66%総合点でも,文系の方が理系より評価が高い。
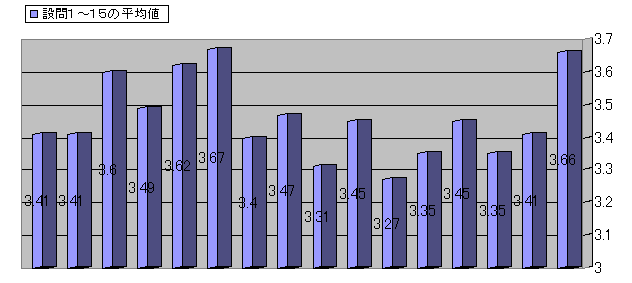
全 全 文 教 法 経 理 医 歯 薬 工 農 獣 水 専 言
体 学 学 育 学 済 学 学 学 学 学 学 医 産 門 語
平 教 部 学 部 学 部 部 部 部 部 部 学 学 教 文
均 育 部 部 部 部 育 化
平 平 部
均 均 平
均
自由意見の解析
自由意見には,1)授業法,2)授業の工夫,3)授業環境,4)この授業アンケートに関するものに大別された。
授業法に関しては,黒板の使い方・文字の大きさ・見やすさ・横文字を読めるようになどの板書に関する意見,発声・発音・話す速さ・声の大きさ等の,話し方に関する意見,授業の速度・内容の負担についての意見,授業の構成,学生との信頼関係についての意見などがあった。
授業の工夫に関しては,論理が多い難解な内容,学生との相互対応,学生参加型授業,レポート,メディア利用,プリント,出席についての意見があった。
全体の総評
結果の全体を概観する。
全体的に,文系理系で差があることに気がつく。文系の授業の方が,理系の授業よりも,教師の熱意が伝わりやすく,話し方が聞き取りやすく,わかりやすく,授業の進行速度や作業量は適切であり,学習意欲がわいたという結果であった。また,シラバスも整備され,授業は体系的であるということであった。
一方,授業におけるメディアの効果的使用法,学生参加の促進,学生の質問,発言への対応の適切さ,内容の難易度,内容の理解,学生の授業への積極的参加(質問,発言,調査,自習など)には差がなかった。授業への出席は,文系でよくなかった。とくに,学生の参加については評価が低かった。
このような文系,理系の差異はどこからくるのであろうか。ひとつの要因は,授業形態とクラスサイズによるとみなされる。すなわち,文系は,演習が多く,25人以下のクラスも多い。理系では演習は文系にくらべてきわめて少ない。いくつかの学部をのぞくと,25人以下のクラスも少ない。授業形態,クラスサイズで評価をみると,演習がよく,25人以下,50人規模,100人規模では,クラスサイズの小さいほどよい評価となっている。こうしてみると,一般に文系の授業の評価のよいのは,演習が多く,クラスサイズも小さいものが多いことによる。別のいい方をすると,演習,小さなクラスサイズの授業は,上記のように文系の授業で評価のよかった項目にみるような効果があるともいえる。
つぎの要因に,この集計ではデータはないが,一般に理系の授業は必修科目が多く,選択科目は少ない点があげられる。また,必修科目が多いために,選択科目の選択の幅が狭くなる。選択は,学習動機の強さと必ずしも一致しない。一方,文系は一般に選択の自由度がひろい。履修している科目の学習動機,意欲が強いと想像される。これが,文系,理系の評価にも反映していると推察される。
一方,文系が好評である背景には,学部による文化の違いも反映しているのではないだろうか。理系の授業は,事前に目標を明確にし,授業を設計しておくことができる。ここでは,授業を基準化でき,他の教員でもそれなりの素養があれば,シラバスにしたがって,ほぼ同様の授業を展開できる。しかし,文系教員は,科目の目標を事前には明確にしにくいという。文系では,教員自体が基準であり,それだけ自分の主張を明確に表現することが訓練されている。このようなところが,学生にストレートに伝わるのかもしれない。このことは,おそらく教員から学生への一方的授業である200人規模,200人以上の大人数講義で,評価がよい傾向がみられることにも関連するであろう。理系では100人をこえる授業があっても,200人以上の講義はほとんどない。このような授業は成立しないのである。一方,小人数の授業が多い文系では,大人数授業も多い。いわゆる講演型授業では,内容をよく整理して設計しないわけにはいかない。このような授業はわかりやすいし,現代の学生はこのような授業にならされていると思われる。
文系がよいとばかりはいっていられない現状もある。文系,理系の差のない設問では,演習,小人数であれば,よくなるはずのものが,講義型でやや大人数クラスの理系と差がないということは,これらの工夫が必要なことを示唆している。これは,学生の出席率が理系より文系が低いことにもあらわれている。
全体的には,学生は授業における教員に対して好意的に評価している。一方,学生自身が理解を問われている設問には評価が低い傾向があった。すなわち,授業は難解な概念,理論があってもわかりやすかったか,授業内容の難易度は適切だったか,授業の履修目標を達成できたか,授業内容と他の領域との関連について理解できたか,については教員の授業法というよりは,学生自身の理解度の評価ともとられ,学生は正直にあまりよくは自己評価していない。同様に,質問,発言,調査,自習などにより,授業に積極的に参加したかについても,文系,理系ともにきわめて低く自己評価している。
こうしてみると,学生は深い理解を求められる授業,難解な理論には,一般に弱い。理系の評価が低いのはここにも理由があるかもしれない。また,積極的参加の姿勢に欠けている。
言語文化部の授業は,一般に好評であった。学生との相互反応のある授業を必然とする授業形態が求められ,人数も50人以下のクラスが大部分(88%)であるためと考えられる。
以上の結果から,1)演習,25人以下の小人数授業,2)学生を積極的に参加させる学生参加型授業,3)理論を丁寧に展開説明する授業,4)大人数の場合にはその条件を十分に配慮した授業が求められる。
また,自由意見欄にのべられた授業に対する様々な意見は,授業改善方法として一般化できるものであった。ここでは,講義の改善法,成績評価の問題,学生参加型授業についてとしてまとめた。とくに,学生参加型授業は,今日の大学の教育で求められる課題探求能力の育成に重要な授業法となる。
おわりに
このアンケートの第一の目的は各授業の改善にある。設問では,授業の要素にわけて,解析した。その平均は,全体,全学教育,専門教育などにわけて示した。これより,各授業の各要素の位置づけを明確にできるようにした。ここでは授業の改善点が明らかになる。評点は,5段階尺度法によった。全体の設問に対する総評点も同様にし,授業の相対評価が見えるようにした。各授業のアンケート結果は,各担当教員にフィードバックされた。その授業改善に役立てることが期待される。とくに,学生の自由意見は,改善すべき点を明確に示している。各授業では,この総評点が少しでも上がるような努力が求められる。
今回の解析は,今後の分析の基礎となる。様々な要素が関連しているので,統計的解析は問題があるようにみえるが,今回の分析の仕方でも,授業に関してさまざまな実体がみえてきた。とくにこれまで注目しなかった学部別の比較では,文系と理系の差異という興味ある結果がみえてきた。この差が生じる要素には,クラスサイズ,演習か講義か,選択か必修かなどが影響することが考えられる。また,教育の内容や学問背景で評価が異なることは,よく話題となる「その年に最も授業評価のよかった教員」が大学全体で比較する点数だけでは問題のあることもわかる。少なくとも系別,および学部別にみなければならないことは明かである。
今回の「学生による授業アンケート」は「教員の総合業績評価」と同時に実施した。学生による授業アンケートの結果が,教員の教育業績評価にいれられるかが問われる。授業アンケートの結果は,全体での位置づけに問題があっても個々の授業では,かなり正しい評価が得られていると判断される。今回の北海道大学の「教員の教育業績」が教育に関するデータの提示としているのであれば,授業アンケートの結果は,有意義なデータである。一方,教育業績評価が教官同士の比較を目的をする評価,査定とする場合には,まだ,慎重な解析が必要となろう。
解析結果が組織的授業改善に結びついていかなければならない。意味のある解析方法をさらに検討しなければならない。次回からの授業アンケートでは,前回の授業アンケートの結果と比較が必要となる。素データは保管する必要がある。また,新たな解析に耐えるような素データの入力も必要となる。今回は,今後のデータ解析も予想して,できるだけ最小限の解析データとした。
今回と同様の分析にはつぎの点が改善される。
1) 総合評点の度数分布で位置づけを知る。
2) 各授業について,各年度の学生による評価総点,教官の認識評点を求め比較する。
3) 改善を評価する。すなわち総点の増加を評価する。
このためには,各教官のデーターおよび解析素データを保管する。
このような継続的点検評価が必要になった場合には,各年度かぎりでの点検評価委員会では対応しきれなくなろう。今後は,任務に教育評価法の研究もはいっている「高等教育機能開発総合センター・高等教育開発研究部」と点検評価委員会との連携も必要である。
北大ホームページへ