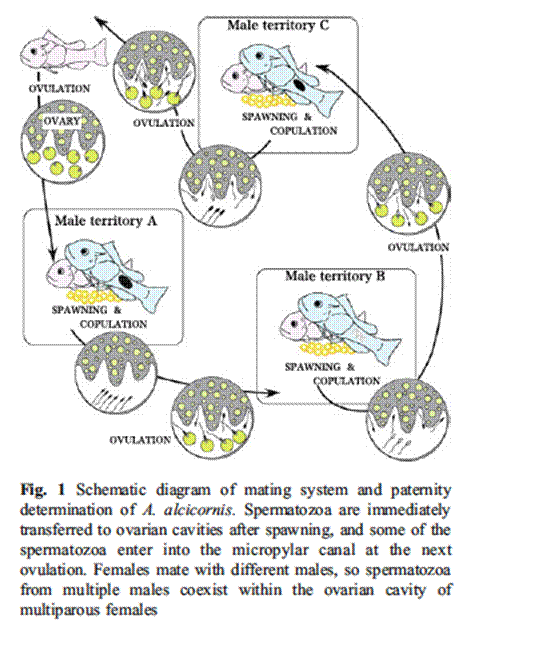
研究調査報告 21
『ドキドキする時』
生物系学部学科に進学する男子の多くは、卒業するまでには、自分の精子を顕微鏡で見るという密かな冒険をするようだ。実行に及ばなかったという人も、まだだという人も、「見たい」という欲求は、心のどこかに持っているはずだ。確かに、それを実行することは、冒険にも匹敵する勇気が要る行為かも知れない。しかし、その発想は、決して、いかがわしいことではなく、自然な好奇心であり、むしろ健全なことだと、私は思う。以下に紹介する友人の話を聞いた時も、なるほどと思ったものだ。
「自分の精子をプレパラートに採り、カバーグラスを載せ、初めて顕微鏡で観察した時のドキドキ感は今も忘れない。」と、その友人は言う。
(精子は元気よく動いてくれるだろうか?)
(変な形をした精子ばかりではないだろうか?)
(精子はたくさんいるだろうか?少なかったらどうしよう。)
「何かを観察しようとして顕微鏡をのぞく時に胸が踊るワクワク感とは明らかに違うし、誰にも見つからないように、こっそりと何か良からぬことを企てた時に感ずる、心音の強い高鳴りとも少し違う。生まれて初めて体験するドキドキ感だった。」とも言う。
「それは、おそらく自分が生物としての「人」であるかどうかが推測できてしまう緊張感が、ドキドキの正体だったではないか。」と言う友人自身の見解に私もうなずいた。
念を押すが、この話は、友人の体験談である。
では、本題の魚の研究の話をしよう。
『子を残せるどうか』。
これは、野生に生き、一瞬足りとも緩むことのない自然淘汰圧のもと繁殖戦略を進化させることにしのぎを削ってきた魚類にとっては、もっと切実な問題だろう。
魚は、自分の精子を自分で観察することが出来ない。忸怩たる思いをしているに違いない。そんな魚の雄に代わって、一回の交尾に放出する精子の量は、どれほどなのか、そして、その数は繁殖期間を通じて変化していくものかどうか。それを確かめたと云う研究が、『研究調査報告21』で報告する論文だ。
ニジカジカという魚は、雄が卵のふ化まで卵保護する。それだけでも、ほとんどが卵を産みっぱなしする30,000種近い魚類の中で少数派であり、変わり種と言える。その上、産卵の後には交尾もすると云うから、これほど奇妙な繁殖様式をとる魚類も、そうはたくさんいない。(ニジカジカの繁殖行動の動画はこちら、http://www.youtube.com/watch?v=6XnWvr6eLC8)
雄が卵を保護する一方で、雌はひと月の間、数日間隔で平均5-6回の産卵を繰り返す。産卵し交尾を終えた後は、次の排卵までに餌をたっぷりと食べなければならないので、その雄とはすぐに別れる。「薄情な雌だ。」と感情移入してはならない。なぜなら、雄だってひと月の繁殖期間中に、100回近く交尾をしなければならないのだから、「事が済んだら早く出ていってくれ。」と思っているに違いないからだ。
こんな配偶システムを持つカジカたちなのだから、雌が次に産卵する時、同じ雄を選ぶとは限らない。そのため、何回か産卵し交尾した雌の卵巣には、複数の雄の精子が混じることになる。
このカジカの精子の寿命は極めて長い。ひと月の繁殖期間中、ずっと卵巣内で授精能を維持することだって出来る。このことも、カジカに代わって精子を顕微鏡観察してやった研究から分かったことだ。
それならば、まだあまり産卵していない雌、とりわけ処女雌と交尾すると、その雌がその後に産卵する卵も授精させることが可能になるのではないか。経験豊富な雌と交尾するよりも、多くの子を残すことが出来るかもしれない。
これが本当かどうか。多くの子どもを残す戦術の開発にしのぎを削るカジカたちにとって、大いに気になる所だろう。この点も、カジカに頼まれる前に、遺伝マーカーで調べてあげた。
結果は、授精能維持期間が長いことから予想した通りで、最初に交尾した雄の精子がその後の産卵でもたくさん使われていた。これは、先に卵巣に入った精子は、授精に有利な位置をキープしているに違いないからだ。 「これで解決!」、としばらくの間、そう信じていた。
数年が経った。
「いや、待てよ。」
処女雌と交尾した雄がたくさんの子を残せるのは、もしかしたら、雄はその時にたくさん精子を放出しているためかも知れない。初めにたくさん精子を渡しておけば、繁殖期の後半になっても、その卵巣には、後から交尾した雄よりも多くの精子が残っていることだってある。ようするに、授精させた卵数が雄間で違うのは、その雌と交尾した順番だけでなく、雌に渡した精子量の違いにも影響を受けている可能性だってあることに気づいた。
こんな単純な疑問を抱くのに数年もかかってしまったのは、残念なことであったが、ともかく
「今度はそれを確かめてみよう。」と思い立った。
と云う経緯から、「繁殖期間を通じた放精量の変化、つまり『雄の精子配分戦略』を明らかにする」、という目的の研究が進められることになったのだ。
詳しいデータは、以下の論文抄録をお読み下されば、ご理解していただけると思う。
また、精子の計数や観察方法など研究の内容を「もっと知りたい!」と思って下さる方は、原著を読んで欲しい。論文請求先は、以下のアドレスです(アットは、@に)
論文請求先: hmアットfsc.hokudai.ac.jp
Sperm allocation pattern during a reproductive season in the copulating marine cottoid species, Alcichthys alcicornis.
邦題:交尾型カジカにおける繁殖期間中を通じた精子配分パターン
著者:宗原弘幸・村花 宏
出典:Environmental Biology of Fishes 83: 371-377 (2010).
要旨: ニジカジカの精子配分パターンを調べた。6個体の雄に10日間で計86回の交配をさせ、そのうち36回の交配について、偽交尾実験で海中に放精させて得た精子数を計数した。雄は早期の交配では、3?8億個の精子を放出するが、その後次第に放精量は減少した。この精子配分パターンは、“早期投資型”と表現された。なぜ、雄は繁殖早期に有意に多くの精子を放出するかについて議論した。ニジカジカの繁殖行動は、産卵後すぐに交尾をする様式である。この魚種の精子は複数のクラッチの卵を授精させる活性保持能を持ち、繁殖早期のクラッチは、精子競争のレベルが低い。加えて、雌の最初の産卵は、2回目とは異なり、海中で精子と出会う。こうした雌と出会う確率は、繁殖期が短く雌がほぼ同調し産卵を開始するため、繁殖期が進むにつれ低くなる。これらの要素は、早い時期の交配にたくさんの精子を雄が放出する形質を選択する。このようなニジカジカの繁殖生態に基づき、この精子配分パターンは、卵巣内で起こる精子競争に対応した適応的な繁殖戦略であると結論した。
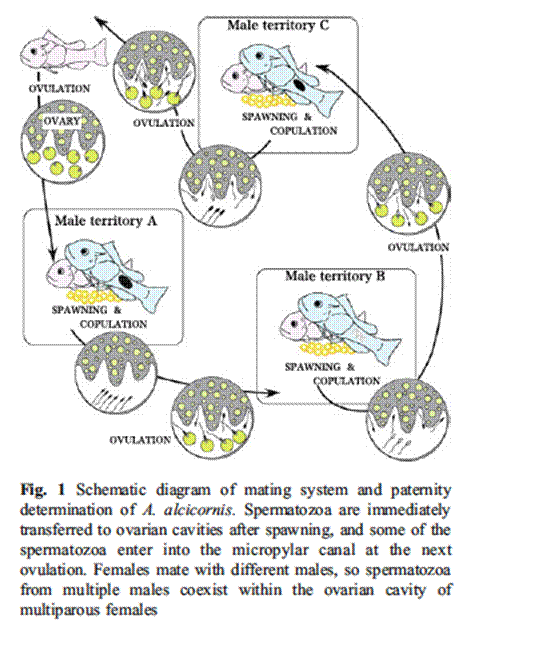
図1. ニジカジカの配偶システムと父性決定の仕組み模式図. 精子は産卵後すぐに卵巣腔内に移送され、そのうちの一部の精子は次の排卵時に卵門内に入る。雌は異なる雄と交配する。そのため、複数の雄の精子が、卵巣内に共存することになる。
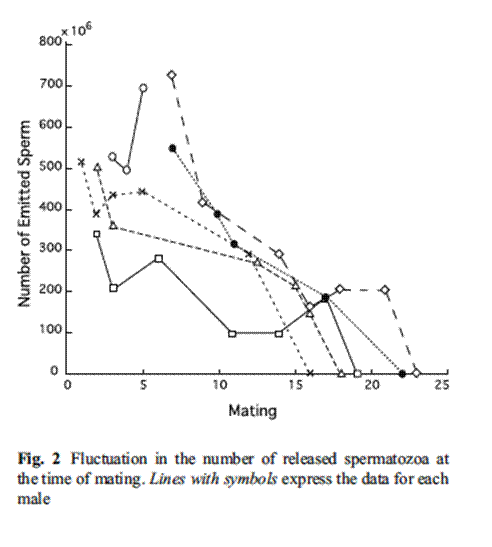
図2. 放精精子数の変動. シンボルで結んだ各線は、それぞれの雄のデータを示す。
表1. 精子配分実験に使われた雄のデータと精子配分パターンの負の相関. 雄4は、実験終了前に死亡したため、精子配分パターンの解析から除外した。
