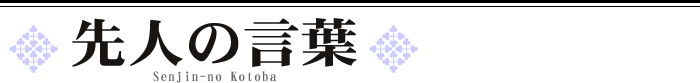
| 己を利するよりは万民のために、国益よりも国際正義のために力を尽くし、支配する側よりも支配される側の、強者よりは弱者の側の立場に立って、自らの保身を顧みず、彼らの救済と正義を堂々と主張する人々を生んできた清き精神の流れが北大にはあった。このような人々を育てた北海道大学とはどんな大学だったのか、どのような人々により、どのような教育が行われて、そのような精神を抱く人々が育まれて来たのか、まずは創設期の先人の言葉を通してその精神の源流をたどってみよう。 |
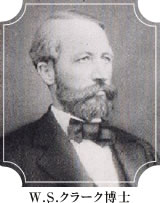 |
 |
| 「lofty Ambition (高邁なる志)」 ― ウイリアム・スミス・クラーク博士の札幌農学校開校式辞の言葉:「長年にわたり、東洋の国々を暗雲のごとく包んでおりました、排他的階級制度と、因習との暴政から、貴国がかくも見事に開放され、自由を獲得されたことは、教育を受けんとする学生一人ひとりの胸のうちに高邁なる志(a lofty ambition)を目覚めさせずにはおきません。若き紳士諸君(young gentlemen…)…」 「Boys, Be Ambitious (青年よ、大志を抱け)」 (帰国の別れの言葉) A noble ambition is among the most helpful influences of student life, and the higher this ambition is, the better. 2006年5月にイギリスの前首相Major氏がワシントン大学セントルイス校卒業式に臨んで、巣立ち行く卒業生達に送った言葉も“Be Ambitious, Aim High”(大志を抱け、高きを目指せ!) Be Ambitiousは今でも若者を励ます言葉として生きている。 |
|
|
| 注)先人が残した言葉・内容には諸説ある場合もあるので、詳しくお知りになりたい場合は、「北大歴史散歩」(北海道大学図書刊行会発行、北大生協等で販売)、その他の参考文献を、本学附属図書館等でご覧ください。 また、本学ホームページFAQに【「Be ambitious」に続く言葉について】が紹介されていますので併せてご覧ください。 http://www.hokudai.ac.jp/bureau/q/faq.html#9 |