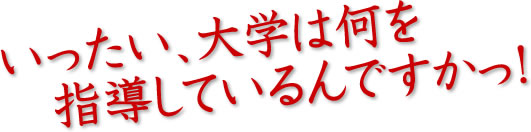 |
||
 山下先生を囲んで 留学生のみなさん |
|
|
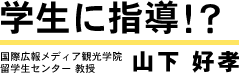 |
||
| 大学の教員になってもう四半世紀になる。しかし、「先生は学生にどんな指導をなさっているんですか?」というような質問を受けたのは今回が初めてだ。 「大学の教授が学生を指導する」という文言を聞くと、一般の人は、プロ野球のコーチが選手を指導するようなものを想像されるかもしれない。確かに大学院の専門課程にいる学生に自分の専門分野で指導するときは、細かい技術的な指導もする。しかし、普通の、一般の学部学生達に、私のような語学教師(日本語、スペイン語担当)がそのような指導らしき指導をしているだろうか? 否である。 そもそも、自分の息子の携帯電話の使いすぎを「指導」して毎月五千円以内で納めるようにさえ「指導」できない私が、北大学部学生の「指導」など出来るはずがない。 では、一体私はどのように北大の学生と接しているのだろうか? |
| 今の大学教員は主体的に指導するというよりは、様々な方面からの要求に汲汲と応えているのが現状だ。文部科学省から「英語で講義しろ」とか「外国人の教員を増やせ」とか要求されて右往左往している。そもそも日本語でもつまらない講義しかできない教員が英語で講義してどうなるのだろう。外国人の教員を増やしたらどんないいことがあるのだろう。事務の人たちの余分な仕事が増えるだけだと思うのだが…。 さて、学生達からも我々は様々な要求を受けている。これは本当です。もし疑っている人がいらっしゃるなら、北大の高等教育機能開発総合センター、つまり昔の教養部の建物にお越し下さい。その一階廊下に「学生の声」という我々(教員、職員)に対する要求が公開されている。おそらくこの「エルム」の後ろのほうのページにも我々に対する要求が掲載されているはずだ。「エルム」の中でいちばん読む価値あるページかも……。 では、学生さん達から今まで私に寄せられた要求に、どのように応えてきたか、いくつかご披露していこう。 |
| よく、このような単刀直入の要求を受ける。面白いって、我々に吉本興業のようなものを期待しているのだろうか。しかし、吉本の芸人がやってることと我々大学教員がやっていることはそれほど変わらない。「お客さん=学生」の前で、与えられた時間、「興業=授業、講義」をやってお給料をいただいているのだから。 授業が面白くないと、学生は寝る、おしゃべりをする、携帯電話でメールを送る。それなら吉本興業を参考にして面白い授業を展開しよう、と考えて始めたことがある。それは「視聴者参加型番組」を参考にした「学生参加型講義」だ。 学生を講義に強引に参加させるにはテクニックがいる。桜塚やっくんなら、「はい、そこのあんた!」と言えば済むが、こちらは最低でも半年同じ学生を相手にして講義をする。まずは受講生の名前と顔をインプットする。 語学の授業だとだいたい三十人から五十人の学生を相手にすることになる。すぐには名前は覚えられない。そこで、名前を覚えるため学生達に毎回同じ席に座るようお願いする。しかし、学生というのは曖昧なお願いには応えてくれない。で、どうするかというと、講義の最初の時期に「指定席券」を配るのである。それもくじ引きで。 くじ引きには秘密が隠されている。まず、こちらが望む位置の席を指定するのである。窓際や最後列などは除外する。全員、教室の前の方に座らせるのである。さらに、くじ引きで仲の良い学生グループをバラバラに分散させる。これで確実に私語が減る。 こうして短期間で学生の名前と顔を覚えることができる。名前を覚えたらばんばん当てる。当てたら記憶が定着する。学生側も名前を覚えてもらって指名されたら、講義に参加しているという実感が湧く。参加しているという実感があれば楽しくなる。よさこいソーランと原理はいっしょである。 |
| 授業が楽しくても、成績評価は学生達にとって妥協できないポイントだ。不公平だと感じると、確実に文句を言ってくる。何をもって不公平とするのか、学生達に耳を傾けなければならない。 まず、半年に一回のレポートや定期試験で成績をつけたりなんかすると、学生は不満を言う。試験当日、たまたま体調が悪く、いい答えが書けなかった。それで成績が下がるのは不公平だというのだ。 こういうクレームはもっともだと思う。そこで私の場合、毎回小テストをして、成績評価の回数を多くすることで対応している。そんな、じゃまくさいことをと教員の皆さんは考えるかもしれない。しかし、小テストにも秘密が隠されているのです。 まず小テストは講義の始めにする。これで確実に遅刻は減る。最期に小テストをする先生もいるが絶対に良くない。そのような場合、小テストができたら帰っていいというシステムになっている。なかなか終わらない学生が「授業が延びた」と言って文句を言う。 それでも遅れてくる学生はいる。何も言わなかったら欠席扱いとなるので、ちゃっかりと「○○、出席しました」と講義の後に言いに来る。もちろん、親切な山下先生は出席簿に「○」をつけてあげる。そして小テストを零点にする。学生は青ざめる。 そこで一言、 「○○君、入社試験の日に遅れていったら試験は零点だよね。」 これで○○君はちゃんと遅刻しないいい学生になる。 |
| 成績が不公平だという文句には、別のパターンもある。同じ科目を複数の教員が担当している場合によくあるクレームがそうだ。 今の学生は損得勘定に長けている。例えば外国語科目の△△語の講義をA教員とB教員が担当していたとする。A教員は成績評価の甘い、いわゆる「仏」の先生だとする。B先生は逆に成績評価の辛い「鬼」とする。これだけで「不公平」だと学生は言ってくる。言ってくるのはB教員のクラスの学生で、A教員のクラスの学生は決して来ない。 そこで北大を含む多くの大学では△△語の「統一試験」というのを導入することになる。同じ試験で判定すれば、どの先生に習おうとも公平だというのが理由だ。そして、△△語の先生達は「統一試験」対策の講義をすることに……。 しかし、学生はますます要求してくる。A教員の使っている教科書とB教員の使っている教科書が異なる場合、どちらの教科書のほうが「統一試験」に有利なのか損得勘定する。その結果、どちらの先生も同じ教科書を使うように要求する。これが「統一教科書」である。そして、△△語の先生達は、個性を発揮できない講義をすることに……。 これだけでは学生の不公平感はまだなくならない。A教員とB教員の教え方が異なる場合、これも不公平だと感じる。その結果「統一シラバス」を導入するはめになる。まさに中学、高校の「指導要領」を要求しているようなものだ。 以上のように、学生達の要求をどんどん吸収していくと、「画一的」「管理的」「没個性的」な講義になっていくのである。これで面白い授業を要求されたら……。 |
|
|||
| さてここまでお読みになったら、大学が中学や高校のようになっているという印象をお持ちになったのではないだろうか。 私が大学教員になってからの四半世紀で確実にこのような潮流になっている。大学は基本的に自由であるべきだ。教員も自分の信念に基づいて、担当科目の「どの部分を、どれくらい時間をかけて、どのように」学生達に指導しようか考えている。大学教員の信念はみんなバラバラである。バラバラで異質であるから学問は発達してきた。言い換えれば「多様性」が大学の研究、教育の根本にあるのだ。 ところが、「違っていること、異なっていること」が損得勘定に結びついて不満を言うのが昨今の大学生である。教員のパーソナリティ、教員の指導力の差などを笑って受け入れる余裕がなくなってしまったのだろうか。 ただ、我々教員の方も、さまざまな要求を前にして、心の余裕がなくなってきてるかもね。 |
