 |
|
 研究室の学生さんを見ても 近久先生のお人柄がわかりますね♪ |
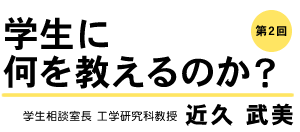 |
|
|
| 学生支援課には市民から北大生の行動に対する種々の苦情が寄せられているようです。たとえば、迷惑な家庭教師の電話勧誘がある、無灯火自転車が多くてけがをさせられた、ごみの出し方がだらしない、飲酒による器物破損をこうむったがその後の対応が横柄などなど。市民からすれば、まさに大学は何を指導しているのかと言いたくなるでしょう。しかし、大学ではこうした社会行動やマナーの教育は全く行っていないのが実態ですし、そもそもこのような指導ははるか昔から大学ではなされていなかったのです。第一、高校においてもこのような指導がなされているかどうか疑問です。 基本的に、上記の苦情内容は人間個人の行動規範に起因していることです。すなわち、社会との調和、他人に対する思いやりがあれば、このような苦情を寄せられるような行為は生じないでしょう。昔は他人の目を重視する社会でありましたので、個々人の人格にかかわらず、多くの日本人は社会と調和した行動をとっていました。さらに、大学に進学する若者の数が少なく、大学に入学する学生はおのずとエリートとしての自覚があり、また将来のリーダーになることを強く意識していました。このような状況では、おのずと社会から評価される北大生が誕生するわけです。ところが、現代は他人との関わりを極力少なくし、個人が優先される社会となりました。そして、常に他人とは半ば敵対し、緊張関係をもって接している状態となっています。たとえば、人ごみの中で他人とぶつかると、必ずにらみ合うような状況が生まれています。さらに、大学全入時代と言われるようになり、入学した学生自身にも社会をリードする人物となる自覚がほとんどありません。こうした背景が、上述したような状況を生み出しているものと思います。 |
| では、大学では何を教えるべきなのでしょうか。実務や研究を遂行する能力育成のための高度な専門教育であることは昔も今も変わりませんが、近年ではそれに加えて「総合的な人間力の向上、およびリーダーシップの自覚」を教えることが重要と思います。国家教育の視点から考えますと、国立大学は日本の将来を背負う人材を育成するために税金を投入しているのであり、これはいつの時代でも変わっていないはずです。個々の学生が良い職について将来幸せになるために教育しているのではありません。この点、我々教員側もこうした視点を持たずに、単に講義を行っているのではないでしょうか。私自身も、ごく最近まではこのような意識がなく、学生にとってわかりやすい講義をすることのみを考えていました。しかし、学科長や就職担当主任等を経験して学生に何らかの訓示めいたことをしなければならない立場になって、国立大学における人材教育について考えるようになりました。 最近は新入生に対するガイダンスや講義のはじめに、学生に対して国立大学の教育目的と各自の将来(リーダーシップ)意識について訓示めいた説明をするようにしております。自分自身の将来のために大学に入学したほとんどの学生は、このような話を聞きますと多少けげんそうな顔をした後、急に自分の使命を自覚するような顔つきになってくれます。若者のポテンシャルはいつの時代も高く、それをどちらに方向付けするかが重要です。通常、学生は社会背景に順応すべく自然に方向づけられているのですが、今一度、国家的人材教育という視点に立って、学生の自覚を方向づけする努力が教員側に必要な気がします。普段の講義の雑談の中に、こうした話を入れるなど、まず我々教員自体が教育に関する意義を自覚する必要があるでしょう。 |
| このところ、アメリカ式の教育システム(決してヨーロッパ的ではない)が日本にどんどんと導入されており、規格化された教育体制が形成されているように思います。例えば、シラバスの導入、GPAや単位の上限設定など、まさにアメリカで行われているシステムがそのまま導入されています。JABEEもそうですが、これは学生を製品ととらえ、品質保証された学生を輩出するためのシステム理念です。しかし、この品質保証は成績という一面だけの評価であり、人格や人間力(最近用いられる用語)を表しているものではありません。実際に成績が良い学生が、何度も就職のための面接試験で落ちてくる場合がよくあります。就職担当の経験から見ますと、企業は学生の成績よりもむしろ面接試験で感ずる何かをより重視しているようです。この何かとは、総合的な人間力であろうと思います。学生諸君はこの大学で、机上の勉強だけに没頭することなく、人間力の向上のためにぜひいろいろなチャレンジをし、種々の経験を積んでほしいものです。 |
| さて、この4月から学生相談室長ならびにハラスメント相談室議長を担当するようになり、メンタルヘルス等の研修会に何度か参加しています。ここで共通の認識となっていることは、「大学に入ったら大人でしょう」はもはや通用せず、実際には多様な学生がおり、教育的視点から種々のケアをしなければならないということです。学生を大人として扱い、本人の責任において学生は行動すべきであるという考えを多くの教員が持っていることと思います。しかし、「教育」という視点から見れば、相手が成人していようがいまいが、必要に応じて教員が助言をしたり、注意をしたりすべきであるのです。 近年教員の評価は主として研究業績が中心であり、競争的原理の導入以来、教員の多くは研究活動や学内業務の遂行に追われています。これに伴って、学生の面倒を教員が親身になって見ることが希薄になっているように思います。昔は先生と学生が一緒になってジンギスカン鍋を囲んで談笑したり、テニスに興じたりと言うことがよくありました。しかし、こうした学生と教員の近しい関係が近年は随分と希薄になっています。実際、教職員に対するプレッシャーの増大のため、教職員のメンタル相談が増加しているといわれています。教員の教育に対する努力をもっと評価すべきであるという意見が確かにありますが、教員人事が全国公募で行われている以上、特定大学内の教育評価はほとんど意味を持ちません。その結果として、学生を大人として扱う大義名分の一方、ケアを十分にしない状況が生まれているのではないでしょうか。 しかし、多様な学生を抱えている現在、人材形成のための教育指導は益々重要になってきています。若者の本質が昔と変わっていないと同様に、教員の資質も昔と変わっておらず、潜在的に面倒見のよい教員が多くいるはずです。こうした教員に呼びかけたいのですが、やはり学生を育て、高い人間力を持った学生を輩出する事がわれわれ教員の重要な使命ではないでしょうか。教育に多少熱心になることで、決して研究活動がおろそかになるとは思われません。研究と教育は十分に両立するはずです。 |
| 次に、学生相談関係では「発達障害」が問題となっています。自閉症など他人とのコミュニケーションがうまくできない場合や、場の空気を読めない、あるいは特定の学習が極端に苦手である等を含んでいます。大学のレベルにかかわらず、こうした学生は全体の数パーセントいるといわれています。この種の学生は大学生活になじめず、不登校となりがちなほか、就職がうまくいかないなどの困難にあい、時として自殺を選ぶことがあるようです。こうした学生に対しても多くの教員は一般学生と同一に扱い、一定の学業を修められなければ卒業を認めないという姿勢を崩さない場合が多いようです。しかし、メンタルケアを専門とする学者の間では、こうした学生に対して特別なケアをすべきであり、場合によっては卒業のための基準を緩和する、すなわち各教科の合格の基準を下げる事も必要といわれています。この是非は議論が必要ですが、障害を抱えた人間に対しても幸福な人生を送らせてあげるためには、多少の例外的配慮とケアも必要と思います。われわれ教員にとって、国家的視点に立った人材教育と同時に、個人的視点から見た学生個々のケアが重要な職務といえるのではないでしょうか。 |
|
|||
一方、相談に訪れる学生個々においても、各人の努力を期待したいと思います。学生の苦情として、先生がなかなか指導してくれないとか、先生が自分に対して特に厳しい気がする、あるいは教員と学生は対等であるなどといった不満が寄せられます。その苦情の一部はもっともであり、教員側に問題があると思われる場合もありますが、学生側に甘えと傲慢さがあるように思える場合も多々あります。やはり、自分自身を客観的に分析できる力を持つほか、自分のことは自分で解決する意識を強く持つべきです。ハラスメントやいじめにしても同じですが、いやなことをいやだと表現することが最も効果的であり、そうした力が必要です。学生相談室やハラスメント相談室は理不尽なハラスメントに対して対処する事ができますが、ハラスメントと断定できないような場合が多く、やはり問題解決は個人の対処能力によるところが大きいといえます。自身を磨く人間力の一つとして、こうした困難をはねのける力強さの養成も心がけてほしいものです。 |
| 今回、学生相談室長の立場から人間教育の必要性について述べさせていただきましたが、学生支援体制の構築が私の任務の一つですので、ぜひ学生指導に熱心な教員の輪を広げて行きたいと考えています。ご協力をよろしくお願いいたします。今後、教員と学生が一体となり、日本をリードする人材排出の拠点に北海道大学がなることを期待しています。 |
