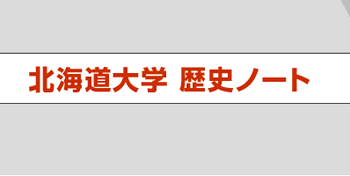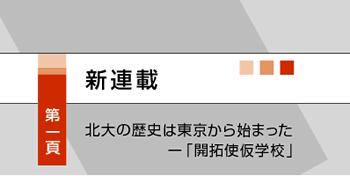|

|
今年、北海道大学は札幌農学校開校から一三三年を迎える。しかし、北海道大学の歴史はさらに四年ほどさかのぼることができる。一八七二(明治五)年、開拓使が東京に開設した「開拓使仮学校」である。
当時、北海道には箱館、江差、松前をはじめとする一部の地域にしか日本人が居住していなかった。内陸部を中心とする広大な地域には先住民族アイヌが独自の文化を営みながら生活していたが、北海道は全体として人口が極めて少ない地域であった。明治維新政府は、北海道を確固たる「領土」とするために本州以南から日本人を送り込んで定住させることが必要と考えた。そのために北海道統治機関として開拓使を設置し、北海道「開拓」事業を推進した。
開拓使は、北海道「開拓」事業の指導者や技術者を養成する学校設置を計画したが、札幌は建設が始まったばかりであったため、「仮」に東京の芝の増上寺内に開設することとした。応募者三八五名中から平均年齢一六・四歳の六四名を入学させ、開拓使仮学校は一八七二年五月二一日(旧暦四月一五日)に開校した。 |
| 開拓使仮学校のカリキュラムは、英語や基礎知識を学ぶ準備教育段階と、専門学科を学ぶ段階に分かれていた。専門学科には、(1)「化学・機械学」、(2)「鉱山学」、(3)「建築学・土木工学」、(4)「農学」の四分野を定め、アメリカ人教員が、英語のテキスト・参考書を使用して、英語で講義を行なった。四つの専門学科は、「化学・機械学」が最新の西洋科学技術の導入、「鉱山学」が鉱山資源の活用、「建築学・土木工学」が都市建設、「農学」が農業植民、というようにいずれも北海道「開拓」事業に必須な分野であった。これら専門学科を学び終えて学校を卒業した生徒には、五年間あるいは一〇年間、北海道「開拓」に従事することを義務づけていた。 |
このように開拓使仮学校は、外国人教師が外国語で最先端の西洋学問を教える先進的な学校であった。ところが実際には、それまで漢学の素読などを学んできた生徒たちが西洋式の勉強方法に反発したり、教員が頻繁に交代してその度に授業内容が変わるなどの理由から、開拓使仮学校の教育はほとんど効果を上げることができなかった。特に、生徒の語学力不足は深刻で、専門学科の講義を開くことができない始末であった。結局、開拓使仮学校は目的を果たせないまま短期間で失敗に終わってしまった。
しかし、その失敗経験は札幌の地に場所を移して生かされることになる。開拓使は一八七五年に学校を札幌に移転し、一年間を掛けて新たに準備を進めた。教育の専門家でもある農学者W・S・クラーク(マサチューセッツ農科大学学長)と契約を結び、彼の意見を取り入れてカリキュラムを編成し、専門学科を農学に限定して、生徒も少数精鋭とした。こうして、一八七六年八月一四日、W・S・クラークを教頭に迎えた札幌農学校が開校し、多くの人材を輩出することになる。
東京タワーの根元近く、都営地下鉄三田線御成門駅から直ぐの芝公園入り口の一角に「開拓使仮学校跡」石碑が建っている。北海道大学一三七年の歴史の出発点を示す記念碑である。
|
 |
|
 |