■拠点形成の背景と概要
世界人口は62億人を超えて今なお増え続け、このままでは食糧不足が地球規模で起こるものと予想されます。この危機を乗り越えるためには、これまで私たちが培ってきた農・畜産業、漁業の技術をはるかに越える、効率的でかつ生態系に悪影響を及ぼさない、持続的な食糧生産技術の開発が不可欠です。
陸上生物では、その性決定のように種々の生命機能が遺伝子により厳密に支配されています。そのため、遺伝子改変技術を用いてその生産の効率性を上げる研究が行われ、様々な遺伝子改変生物(LivingModified Organisms, LMO、カルタヘナ条約、2000年)が市場に登場しようとしています。しかし、安全性への不安から、LMOは社会的に受容され難い状況にあります。従ってLMOとは異なる、安全性の高い革新的な食糧生産システムの開発も必要です。
海洋生物は今なお未開発資源を多く持ち、また陸上生物とは桁違いの多様性と多産性を有します。このことから、海洋生物は未来の食糧資源としてのポテンシャルが非常に高いといえます。しかし、我が国では様々な水産物が大量に消費されているにもかかわらず、その自給率は既に50%以下となっています。この改善のためには、天然資源に依存している現在の水圏食糧生産システムを根本的に見直す必要があります。
海洋生物では性転換やクローン発生、ゲノムの変異(3倍体生物など)が自然に生じ(性・生殖のゆらぎ)、遺伝的な機能制御が非常に柔軟です。このような海洋生物の生命現象を解析し、それを人為的に統御することができれば、遺伝子改変技術を用いなくとも、現在の食糧生産システムを一変させ、低コスト化・効率化を達成することが可能です。これを実現するためのプロジェクトが本拠点の「海洋生命統御プロジェクト」です。
さらに、未来の技術で生産される食糧は、安全なものであるのはもちろんのこと、十分に機能性の高いものでなくてはなりません。また、BSEなどの食糧のもつ病原体や、環境ホルモンによる汚染の問題などで、国民の食の安全性への関心は高まる一方です。海洋生物におけるこれらの問題や人為的な遺伝的撹乱の影響などを総合的に評価し、対策を講じるとともに、その食品機能の高度化をすすめるのが、本拠点のもう一つのプロジェクト「食糧安全保障プロジェクト」です。
21世紀の科学は、地球生態系の一員であるすべての生物にとって優しいcomfortなものでなくてはなりません。海洋に関する21世紀型のサイエンス、MarineBio-comfort Scienceのさきがけとなるよう、本拠点では上述の二つのプロジェクトを有機的に結合した世界最高水準の研究と教育を展開します。また、本拠点の中心となる水産科学研究科が位置する函館圏では、現在、国際水産海洋都市構想が推進されています。本拠点はその中核として、学術の普及と同時に市民社会と大学および産官学の新たな関係を構築することを目指します。
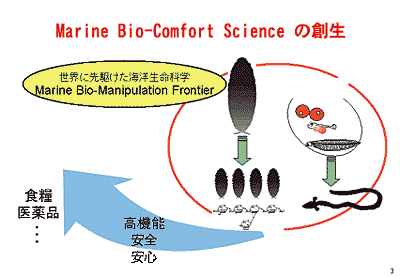 |
| 図1:本拠点形成の理念 |
■研究拠点形成計画
本研究教育拠点は「海洋生命統御プロジェクト」と「食糧安全保障プロジェクト」から構成されています。また、若手・女性研究者を積極的に養成するための「若手・女性研究者支援プログラム」を実施します。
1.海洋生命統御プロジェクト
海洋生物が持つ、性転換やクローン発生、多産等の特性を応用することで、雌雄の産み分け、不妊化、クローン集団の作成等は既に可能となっています。しかし、これらの技術ではその生産過程で「親」を養成し、それから配偶子をとることが必要になります。「親」の生産には、大型で飼育に特別な施設が必要な場合や、性成熟に長い年月を要する場合、性成熟自体が困難である場合も多く、これが海洋生物の生産を非効率化する一番の原因になっています。そこで本プロジェクトでは、「親」を使わない革新的な海洋生物生産技術を開発するために以下の研究を行います。
(1)生殖細胞の分化機構を解明する「機構解析」
(2)配偶子を他種に産ませる「借腹(仮親)養殖」
(3)配偶子を試験管の中で生産する「試験管配偶子生産」
(4)一個体から数百万個体の体細胞クローンを生産する「クローン種苗」
2.食糧安全保障プロジェクト
海洋生命統御プロジェクトで作り出された集団には、種特有の病気が異種間でも垂直感染する可能性や、遺伝的な偏りが起こる可能性があります。本プロジェクトでは、以下の観点から多角的に安全性を評価するとともに、その食品機能の高度化を図ります。
(1)種苗による病気の拡散を防ぐ「防疫」
(2)天然集団の遺伝的な撹乱を防ぐ「遺伝的管理」
(3)海域の環境汚染を評価する「汚染評価」
(4)生産される生物の食品機能を評価する「機能評価」
(5)安全性と安心感を保障する「安全管理」
3.若手・女性研究者支援プログラム
本拠点の一翼を担い、学際性と独創性、国際性に富む若手・女性研究者を養成するために、以下のプログラムを実施します。
(1)海外客員教授のセメスター制(2〜3ヶ月)による質の高い授業の提供
(2)海外大学との交換留学生制度などの拡充
(3)生命倫理、環境倫理、知的財産保護、起業家育成に関する教育の充実
(4)表彰、海外インターンシップ、研究スペース提供、競争的研究予算による支援
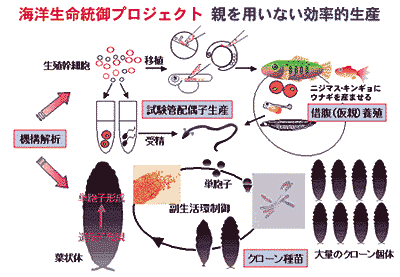 |
| 図2:「海洋生命統御プロジェクト」の概要 |
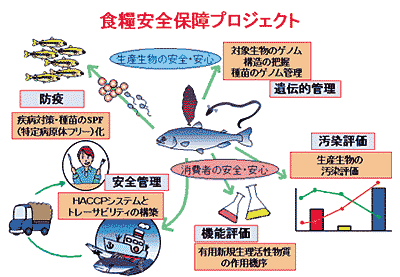 |
| 図3:「食糧安全保障プロジェクト」の概要 |
■教育実施計画
本拠点では、以下に示す教育理念や目標、計画をもって、21世紀を担う新たな人材の育成を目指します。
1.教育理念
海洋生命統御を応用した食糧生産技術開発を通じて、「次世代の食糧科学体系」を担いうる学際的かつ国際的研究能力を身につけた高度専門家を養成します。
2.本拠点が目指す理想の人材
以下の5つの項目に適う人材の育成を目指します。
(1)海洋生物の生命機能の解明からその安全性確保に関する諸問題指摘と解決策を、領域横断型の基礎知識に基づいて具体的に提案できる高度専門家
(2)「生命現象を解き明かす」技術と知識を備えた高度専門家
(3)マリンライフマニピュレーションの全体像を把握し、フロンティア精神を備えた起業家
(4)協調関係の中で発揮される、優れた独創性を備えた先端研究者
(5)強力な交渉能力を備え、国際舞台でリーダーシップを発揮できるオピニオンリーダー
3.目的達成のための教育改善計画
以下の具体的施策により、大学院教育の学際性と国際性の飛躍的向上を目指します。
(1)本拠点活動と一体化した大学院カリキュラムの創成
(2)国内外第一線研究者との積極交流
(3)国際交流の一層の推進
(4)海洋生命ベンチャー育成教育の推進
(5)文理融合型教育の実践
|