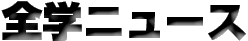
このたび,本学関係者の次の3氏が平成22年春の叙勲を受けました。 |
| 勲 章 |
経 歴 |
氏 名 |
| 瑞 宝 中 綬 章 |
名誉教授(元 工学部教授) |
石 黒 亮 二 |
| 瑞 宝 単 光 章 |
元 北海道大学医学部附属病院看護婦長 |
和 島 早 苗 |
| 瑞 宝 双 光 章 |
元 北海道大学病院診療支援部長 |
渡 邊 良 晴 |
|
| |
各氏の長年にわたる教育・研究等への功績と我が国の学術振興の発展に寄与された功績に対し,授与されたものです。
各氏の受章にあたっての感想,功績等を紹介します。 |
| |
| (総務部広報課) |
| |
| ○ 石 黒 亮 二(いしぐろ りょうじ) 氏 |
 この度,叙勲を拝受いたしましたのは,身に余る光栄です。これは永年にわたり北海道大学に勤務させていただいた結果と受け止めております。在勤中は,研究・教育に精一杯努力しましたが,必ずしも十分な成果を上げることなく,停年を迎え今日に至りましたことに忸怩(じくじ)たるものを感じております。私を推薦し叙勲の諸手続きをお進めくださった方々に,心から感謝いたしております。 この度,叙勲を拝受いたしましたのは,身に余る光栄です。これは永年にわたり北海道大学に勤務させていただいた結果と受け止めております。在勤中は,研究・教育に精一杯努力しましたが,必ずしも十分な成果を上げることなく,停年を迎え今日に至りましたことに忸怩(じくじ)たるものを感じております。私を推薦し叙勲の諸手続きをお進めくださった方々に,心から感謝いたしております。
私と北海道大学との関わりは,昭和23年4月に旧制の北海道大学予科に入学したときからです。当時は戦後の学制改革が進行中でしたので,私も2年生になる時点で新制(現在の制度)の北海道大学に編入され,教養部1年生となりました。それから1年半後にはいわゆる学部移行があり,私は工学部機械工学科に進学しました。また,学部課程を卒業する年には新しく大学院が発足し,修士課程ができましたので,私はその第1期生として入学しました。修士課程修了後2年間ほど帝国人造絹糸株式会社(現・帝人株式会社)の研究所に勤務しましたが,昭和32年に学生時代にお世話になった研究室に講師として採用されることになり,機械工学科に講師,助教授としておよそ10年間勤務させていただきました。
その後,工学部に新たに原子工学科が発足したのに伴い,私も昭和44年より,この新学科に移り,昭和45年10月からは教授として停年退官(平成6年3月)を迎えるまで,勤務させて戴きました。
退官後は2〜3の組織に所属し,原子エネルギーの有効利用,安全性向上などのPA活動のお手伝いをさせていただいております。
私の専門は熱工学で,帝人に勤務中も,機械工学科でも,原子工学科でも目的はそれぞれ異なりますが,すべてで熱工学関連の研究業務に携わってまいりました。その中でも特に伝熱学と言われる分野は戦後の宇宙開発や,原子エネルギー利用の進展と共に大変盛んに研究される工学となりました。主に,宇宙飛翔体が大気圏に帰還する際の空気力学的発熱の除去や,原子炉内の発熱を効率よく取り出して有効利用し,また炉の安全性の向上を図るのが目的です。これらの分野は,最近ではなんとか実用の域に達してはいますが,機器の性能向上,安全性の改善のためには更なる研究が必要です。
天然資源に恵まれないわが国が世界の主要国の立場を維持し,国民が豊かな生活を享受し続けるために,科学技術の持続的な発展は欠く事の出来ない要素です。その基礎的部分を担うのが大学で,役割は益々重要になりつつあります。現役で研究・教育にご活躍中の皆様には,いっそうのご発展を期待いたしております。 |
| |
| 略 歴 等 |
| 生年月日 |
昭和5年5月28日 |
| 昭和32年7月 |
北海道大学工学部講師 |
| 昭和33年1月 |
北海道大学工学部助教授 |
| 昭和45年10月 |
北海道大学工学部教授 |
| 平成6年3月 |
北海道大学停年退職 |
| 平成6年4月 |
北海道大学名誉教授 |
|
| |
| 功 績 等 |
北海道大学名誉教授 石黒亮二氏は,昭和28年3月北海道大学工学部機械工学科を卒業,同30年3月同大学大学院工学研究科機械工学専攻修士課程を修了,同年4月帝国人造絹絲株式会社に入社し研究所に勤務された後,同32年6月に同社を退社されました。昭和32年7月には北海道大学工学部講師(機械工学科)に採用され,同33年1月同助教授に昇任されました。その後,本学に原子工学科が新設されるにともない,昭和44年4月に同学科助教授,同45年10月には同教授に昇任され,原子力安全工学講座(当初,放射線安全工学講座)を担当されました。その間原子炉の熱工学,安全工学の分野の発展に努力され,平成6年3月31日限りで停年により退職,同年4月北海道大学名誉教授となられました。
昭和32年以降の本学在職中,学部においては,熱機関学第一,冷凍工学,基礎熱力学,熱輸送論などの講義を,大学院工学研究科においては,伝熱工学特論,熱輸送特論,原子工学特論ゼミナール,原子工学特別実験などを担当するとともに学部学生及び大学院学生の研究指導にあたり,多数の技術者と研究者の育成にあたられました。また,学外では室蘭工業大学,苫小牧工業高等専門学校,北海学園大学の非常勤講師として,他大学の学生の教育にもご尽力されました。
研究面においては,熱工学,特に,伝熱学の研究に取り組まれ,昭和36年8月より同38年9月までの米国留学中に行った研究結果を基礎として取りまとめた論文「不等温板の乱流熱伝達に関する研究」により同43年9月北海道大学より工学博士の学位を授与されました。原子工学科への所属換の後には,高速増殖炉の安全性と経済性に関連し,液体金属や金属蒸気凝縮の熱伝達問題を研究されました。まず,液体金属の場合には明確にされていなかった流れの構造と熱伝達の関係を明らかにする目的で,流れに直交しておかれた円筒まわりの熱伝達の挙動を,当時では先駆的なナトリウムループを建設して実験を行われました。その際,装置に工夫をこらして,局所の熱伝達率の分布を初めて測定して,非粘性場の計算結果が実用上の精度で適用可能とされていた従来の定説を修正されました。これは,高速増殖炉システムの重要機器である蒸気発生器や中間熱交換器の伝熱特性の基本として極めて重要な結果であり,また,高速増殖炉の炉心冷却性能と密接な関連のある二重管内の熱伝達問題を取り上げ,内外管の偏心の度合いが及ぼす影響の大きいことを明らかにされました。このことは炉心が稠密に組み立てられている高速増殖炉の安全性の評価にとって特に重要な成果であります。さらに,この実験においては液体金属に使用可能な特殊な温度プローブを開発して温度場の詳細を測定し,液体金属流れにおいて特異な挙動を示すとされていた乱流プラントル数の詳細を明らかにし,工学基礎の進展に多大の寄与をもたらしました。また,昭和48年のオイルショックに端を発して予算化された文部省の科学研究費補助金,エネルギー特別研究の一環としてカリウム蒸気の凝縮熱伝達の問題を取り上げ,従来明確でなかった凝縮係数に関する精度の高い測定値を得ると共に分子運動論的な考察によって金属蒸気凝縮のメカニズムに明解な説明を与えられ,平成元年4月この成果に対し機械学会より論文賞が授与されました。
学内においては,放射性同位元素等管理委員会委員,アイソトープ総合センター運営委員会委員,学生部委員会委員,留学生委員会委員,国際交流委員会学生交流専門委員会委員,発明委員会委員を歴任され,平成元年6月より同3年5月までは北海道大学評議員として大学運営の枢機に参画されました。工学部においては,大学院制度委員会,広報委員会,企画委員会,研究開発相談室運営委員会,エリアモニター施設運営委員会,加速器研究室運営委員会の各委員長のほか多数の委員会の委員を務められました。
学外では,文部省学術審議会専門委員,日本学術会議原子力研究連絡委員会,同熱工学研究連絡委員会,同原子力基礎研究連絡委員会の各委員,科学技術庁高レベル放射性廃棄物地層処分推進検討会,同原子力研究開発支援技術高度化検討委員会の各委員,日本学術振興会審査員などとしてわが国の学術・技術の全般にかかわる委員を歴任され,また,日本伝熱学会会長,日本原子力学会理事,同編集委員長,日本機械学会評議員など国内の学協会委員を歴任されました。また,北海道総合開発委員会委員,日本原子力学会北海道支部長,日本機械学会北海道支部長などとして地域の学術技術の発展にも大きく寄与されました。
以上,学生の教育,学術研究の発展及び本学の運営に対する貢献は極めて大なるものがあり,その功績は誠に顕著であります。 |
| |
| (工学院・工学研究院・工学部) |
| |
| ○ 和 島 早 苗(わじま さなえ) 氏 |
 この度,平成22年春の叙勲で瑞宝単光章の栄に浴することが出来ましたことは,誠に身に余る光栄に存じます。この様な栄誉ある章を私ごときが頂戴できましたことは,偏に長きにわたる諸先輩方々のご指導,同僚の皆様方のご支援の賜物と心から厚くお礼を申し上げます。 この度,平成22年春の叙勲で瑞宝単光章の栄に浴することが出来ましたことは,誠に身に余る光栄に存じます。この様な栄誉ある章を私ごときが頂戴できましたことは,偏に長きにわたる諸先輩方々のご指導,同僚の皆様方のご支援の賜物と心から厚くお礼を申し上げます。
顧みますれば,昭和53年から勤務しました登別分院は,国立競技場に類似した材質で造られた屋外トラック・温泉水を利用した室内プール等温泉療法研究を兼ね備えた施設として平成9年本院統合まで地域特性を活かしたリハビリ医療を行っておりました。この間,営林署と提携した振動病患者,本院からの術後患者のリハビリ目的,地域の患者のなかでは糖尿病患者が血糖コントロールを図るための運動療法を中心としたリハビリテーション看護充実に努めてまいりました。リハビリテーションは日々継続することで結果がでるもので,それには時間が必要とされます。そのためには目先を変えた看護が必要とされ,当時まだ馴染みのなかった“糖尿病教室”を確立し,恵まれた自然環境を利用した継続的運動療法として “集団森林浴”を定着させました。これには,看護スタッフが中心となり当時の阿岸教授,大塚助教授,事務の方々など分院上げての年間行事として糖尿病患者の運動療法に大きな効果をもたらしました。これらの,成果については看護学会や,チェコで開催された“第33回世界水・気候治療国際学会”にて報告させて戴きました。平成8年地域の方々に惜しまれながれの閉院は心が痛む思いをしました。
北海道大学病院は “教育”“研究”“臨床”を柱とした国立大学病院の使命を担っていることを看護部から享受され,臨床現場に発生する問題を25年間の在職期間,常に念頭におき“おや・なぜ・どうして”から始まる研究手法を活用しながら,看護スタッフ,医師,理学療法士,作業療法士とのチームが一丸となって取り組むことができたこと,また,国内の研修はむろんアメリカ,ヨーロッパ(スウェーデン・オランダ・ベルギー),中国への海外研修は,本院に新設されたリハビリテーション科開設準備に活かすことができ微力ながら貢献できました喜びは今でも忘れることが出来ません。このような環境で育てられ,支えられて仕事をさせて戴いたことに幸を感じる次第です。
平成9年,本院に新設されたリハビリテーション科は,国立大学病院として全国的に先駆的なことであり,故真野教授(初代教授)のご享受,看護スタッフとともに研鑽を重ね北海道大学病院におけるリハビリテーション看護の専門性を構築するために苦慮したことが懐かしく想い出されます。
平成14年定年退官後は,財団法人黎明郷弘前脳卒中センター(青森県)の急性期から回復期リハビリテーション看護に携わり,更なるリハビリ看護の専門能力を高めるべく看護部長として指導育成にたずさわっております。
最後に,今回の受章の労をお取り下さいました皆々様にお礼申し上げますと共に,北海道大学の益々のご発展を祈念申し上げます。 |
| |
| 略 歴 等 |
| 生年月日 |
昭和16年10月19日 |
| 昭和53年4月 |
北海道大学医学部附属病院登別分院看護婦 |
| 平成元年4月 |
北海道大学医学部附属病院登別分院看護婦長 |
| 平成9年1月 |
北海道大学医学部附属病院看護部看護婦長 |
| 平成14年3月 |
北海道大学定年退職 |
|
| |
| 功 績 等 |
和島早苗氏は,昭和16年10月19日室蘭市に生まれ,昭和46年3月日本製鋼所病院看護学院を卒業,昭和53年4月当院登別分院に文部技官として採用され,昭和61年副看護婦長,平成元年看護婦長に昇任しました。平成9年1月本院と統合し,新設リハビリテーション科の初代看護婦長になり,平成14年3月31日定年退職されました。
その後,嘱望され平成14年5月より財団法人黎明郷リハビリテーション病院(青森県)看護部長,平成17年7月より同法人弘前脳卒中センター看護部長として勤務,現在に至っています。この間,日本看護協会において認定看護管理者として認定されました。
登別分院では,温泉療法研究施設を兼ねていた環境と地域の特性を活かし,看護の質向上に貢献しました。平成4年「地域に密着した継続的運動療法を考える-糖尿病患者の登山を試みて」を日本看護学会に発表,平成10年チェコで開催された第33回世界水・気候治療国際学会において「糖尿病患者に行った集団森林浴の評価」を発表しました。
リハビリテーション科では,医師,理学療法士,作業療法士とのチーム医療の推進やリハビリテーション看護専門性の確立及び看護職の育成に尽力しました。さらにスタッフとともに研鑽を重ね,平成11年「ADL自立に向け,“まつこと”を基本とした障害患児の看護」,平成12年「両手機能を失った障害患者の在宅療養をかなえた看護-ビデオカンファレンスの有効性」「脳血管障害患者の移乗自立に関するFIM得点からの検討」を日本看護学会に発表等多数の研究発表を行いました。こうした努力は北海道のリハビリテーション看護をリードし発展させました。
さらに,看護管理の視点から看護師の疲労度に着目し,平成2年北方産業衛生学会に「当院における看護婦の業務と運動量に関する検討」,平成4年日本看護研究学会に「三交替看護勤務における自覚症状と血中ホルモン値について」等発表しました。
また,質の高い看護サービスの保証にむけて,業務調査及び業務改善を積極的に実施し,平成12年「看護助手業務再編成による外注化システムの構築」を日本看護研究学会に発表しました。患者に必要な看護量の構築を推進し,平成12年「看護度分類北大版改訂に向けての検討」を日本看護学会に発表しました。
同人は,社会的活動を精力的に行い,とくに北海道看護協会においては,室蘭支部長他の委員を14年間,社会経済福祉委員を4年間及び研修会の講師等を歴任しており,これらの功績が認められ,平成12年5月北海道社会貢献賞(優良看護職員)を受賞,さらに平成14年5月日本看護協会長賞を受賞しました。
以上のように同人は,リハビリテーション看護の専門性を確立し,看護体制の整備及び後輩指導・育成に尽力をした功績は誠に顕著であります。 |
| |
| (北海道大学病院) |
| |
| ○ 渡 邊 良 晴(わたなべ よしはる) 氏 |
 この度平成22年度春の叙勲の栄に浴し,身に余る光栄と思っております。私がこのような機会に恵まれたのはひとえに諸先輩,同僚など多くの皆様方のご指導,ご支援の賜物と感謝し,心から厚くお礼申し上げます。 この度平成22年度春の叙勲の栄に浴し,身に余る光栄と思っております。私がこのような機会に恵まれたのはひとえに諸先輩,同僚など多くの皆様方のご指導,ご支援の賜物と感謝し,心から厚くお礼申し上げます。
私は昭和50年の卒業と同時に北海道大学医学部附属病院放射線部に採用されました。職場は,現在は既に無くなった病院建屋の南病棟地下にあった放射線治療部門に配属になりました。放射線部長は故入江五郎先生,技師長は千田昌美技師長でした。
当時,放射線治療室には,コバルト-60の装置,ベータトロン,ラルストロンの装置があり,昭和50年度にはリニアックが設置され,これらの装置で放射線治療を年間2,000人以上の患者に行っていたと記憶しています。治療医は入江先生,後に放医研に行かれた辻井先生,溝江先生らが居られ,忙しい中でも一緒に山や川に出かけた記憶があります。当時放射線治療はまだ手作りの部分が多く残っている頃で,週1回のカンファランス等で入江先生,辻井先生には多くの教えを頂き,当時の糧が以後の仕事に繋がっており深く感謝しております。また大学の大型計算機センターの端末,ミニコン,当時出始めたパソコン等を使用する機会に恵まれ,線量計算,装置のモニタ,制御等に使用が始められた時期でもありました。
北大病院は平成元年から10年間をかけて建て替えられ,今や昔の病院を知っている方も少なくなりました。放射線部では,平成9年,10年の移転時に多くの新しい装置と共に新たに放射線情報システムを構築し導入しました。これは,病院情報システムで発生する放射線検査のオーダ情報を元に放射線部内の業務を行うためのシステムで,多くの部員と一緒に業務に合わせたシステムを作り動かしました。
その後,医科・歯科附属病院の統合,平成16年の法人化に併せて診療支援部が設立され,前任の北村部長の退職に伴い平成19年4月から診療支援部長に就任しました。診療支援部は,臨床検査技師,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,臨床工学技士,歯科技工士,視能訓練士,言語聴覚士,歯科衛生士等多くのコメディカルスタッフが所属しています。各部員は院内の各部門で専門職種の業務を行っており,病院機能のインフラ的な役割を担っておりこの機能なくしては病院機能が止まってしまう重要な部門と考えています。
一方で,社会の医療を取り巻く環境の変化と共に北大病院も大きく変化しているのを実感しています。北大病院は,北海道地区の基幹病院として診療と共に教育・研究を行うことが求められております。しかし,我々の働く臨床現場では業務の効率化と共に高度化した専門技術への対応,医療安全への取り組みなど多くの事が求められており,最近の10年間はこれらの対応に追われた日々でした。
振り返りますと,北大キャンパスの自然の中で四季折々の景色と共に過ごすことができ,無事に定年を迎えることができましたのは,病院長を始め関係各位のご協力とご支援のたまものと心から感謝いたしております。
最後に北海道大学,北海道大学病院の更なる発展をご祈念申し上げます。 |
| |
| 略 歴 等 |
| 生年月日 |
昭和24年11月17日 |
| 昭和50年3月 |
北海道大学医学部附属診療放射線技師学校卒業 |
| 昭和50年4月 |
北海道大学医学部附属病院放射線部エックス線助手 |
| 昭和50年7月 |
北海道大学医学部附属病院放射線部診療放射線技師 |
| 平成2年7月 |
北海道大学医学部附属病院放射線部主任診療放射線技師 |
| 平成12年4月 |
北海道大学医学部附属病院放射線部副診療放射線技師長 |
| 平成15年10月 |
北海道大学医学部・歯学部附属病院診療支援部副診療放射線技師長 |
| 平成16年4月 |
北海道大学病院診療支援部副診療放射線技師長 |
| 平成17年4月 |
北海道大学病院診療支援部診療放射線技師長 |
| 平成19年4月 |
北海道大学病院診療支援部長 |
| 平成22年3月 |
北海道大学定年退職 |
|
| |
| 功 績 等 |
同人は昭和24年11月17日に北海道常呂郡佐呂間町に生まれ,同43年3月北海道立遠軽高等学校を卒業,同50年3月北海道大学医学部附属診療放射線技師学校を卒業,同年4月1日北海道大学医学部附属病院に採用され,主任診療放射線技師,副診療放射線技師長を経て平成17年4月北海道大学病院副診療支援部長,兼診療放射線技師長に就任され,同19年4月北海道大学病院診療支援部長に就任し,同22年3月定年により退職されました。
同人は放射線診療業務に従事すると共に大学病院の使命でもある学生教育,臨床実習に携わり,また,院外では放射線技術,特に放射線治療分野に於いて北海道地区の放射線治療技術の進歩に大きな貢献をされました。同人は,放射線部では放射線治療技術の開発と共に放射線治療のシステム化に取り組み,放射線治療医と共に治療患者のデータベースの構築,治療計画へのCT画像の導入など現在では各施設で広く行われている治療技術の開発に多くの貢献をした。
放射線部では平成元年から放射線画像の電子化に取り組み,同人の主導でウェブベースの放射線情報システムを日本で初めて導入しました。また,画像情報の規格化,ネットワークの整備も進め,放射線部全体の画像情報の電子化を達成しました。これは高い評価を得て,他施設,他大学等から多くの見学者がありました。その後,平成14年の病院情報システムの更新では全病院の画像システムを導入し,同16年からは国内の病院に先駆けてフイルムレスの診療に移行しました。
北海道大学病院診療支援部は,臨床検査技師,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,臨床工学技士,歯科技工士,視能訓練士,言語聴覚士等の医療技術職員約170人を統括し,診療を支援する部でありますが,同人は業務分析を行うと共に人員の配置を見直し,手術部の業務,救急部・ICUの業務,血管造影検査,超音波検査等について複数の関係する職種が共に業務を行う体制を確立しました。
一方,同人は北海道大学医学部附属診療放射線技師学校,北海道大学医療技術短期大学部放射線技術学科,北海道大学医学部保健学科を通じて,非常勤講師として診療放射線技師の教育,臨床実習におおよそ30年間携わり,診療放射線技師の養成に大きく貢献しています。
院外では,社団法人日本放射線技術学会の専門委員,評議委員などを歴任し,同北海道部会の理事に16年間就任し,この間多くの研究発表,教育講演などをおこない放射線技術の発展に寄与してきました。その他,各種委員,評議委員など歴任すると共に,多くの学会発表をしています。また,北海道地区の放射線治療担当者で構成する北海道放射線治療研究会を主催し,平成12年からは代表世話人として,北海道内の放射線治療担当者の教育,研修に多大の貢献をしてきました。
同人はこれら約35年もの永きにわたり,放射線分野,医療情報分野の向上と進歩に寄与し,後進の育成に尽力したその功績は誠に顕著であると認められます。 |
| |
| (北海道大学病院) |
| |
|