10月7日(日),学術交流会館小講堂を会場に,国際シンポジウム「フィルム/コンテンツ・ツーリズムと地域社会 Film/Contents Tourism and Local Communities」を開催しました。
「フィルム/コンテンツ・ツーリズム」とは一般に耳慣れないテーマ(概念)かと思いますが,映画やテレビドラマ,アニメやゲームなどのメディアコンテンツが,その舞台となった場所に新たなイメージを付与し,それが現地への旅行行動を生み出す,そういった新しい形で進展している観光・ツーリズムを指します。
なぜ人はそういったメディアコンテンツの舞台を訪れる旅を行うのか。また地域社会ではこうした現象をどう受け止め,いかなる動きが展開されているのか。今回の国際シンポジウムでは,国際的に第一線で活躍している国内外の研究者が集い,オーストラリア,ニュージーランド,日本の事例を読み解きながら,フィルム/コンテンツ・ツーリズムの本質に迫るべく研究発表と議論を行いました。
具体的には,オーストラリア国立ラ・トローブ大学のスー・ビートン准教授による基調講演「場所と想像力――ファンタジーからリアリティへ」に続き,須川亜紀子先生(関西外国語大学),フィリップ・シートン先生(本学国際本部留学生センター)の研究発表,さらに山村高淑先生(本学観光学高等研究センター)も加わっての計4名によるパネルディスカッションが行われました。
基調講演でビートン先生は,映画やドラマなどをめぐるツーリズムの様々な展開を,テーマパーク等とも結びつけながら紹介されました。某超大作映画の「架空の続編」の予告編上映(いくつものハリウッドの大ヒット映画の場面をパロディ化して織り込んだ,いわゆる二次創作)なども織り交ぜてのスピーディな議論に会場は盛り上がりました。その後のシンポジウムでも,アニメやテレビに触発されての戦国ブームと「歴女(れきじょ)」たちの観光行動(須川先生),あるいは大河ドラマとツーリズム,地域振興との関連(シートン先生)など,観光・ツーリズムと地域社会とを結ぶ最先端の現象について,旧来的なアカデミズムの狭隘なイメージや枠組みを突き崩すような,清新でダイナミックな研究発表が続きました。最後のパネルディスカッションも,ディスカッサントの山村先生が複雑多岐にわたる論点をクリアに整理し,フロアからの熱心な質問も相継ぎ,充実した討議が実現されました。
また,翌8日(月・祝)にはメディア・コミュニケーション研究院において,ビートン先生のレクチャーを主軸にした国際ワークショップ「Making the Most of the Movies: Tours and other Business Opportunities/映画の活用:観光ツアーとビジネスチャンス」を開催しました。前日に引き続き,映画やドラマなどのコンテンツに誘発された観光を,ビジネスの側面から光を当て直して議論し,いっそう多面的にフィルム/コンテンツ・ツーリズムのおもしろさと可能性を検討することができました。
メディア・コミュニケーション研究院,国際広報メディア・観光学院,
観光学高等研究センターが国際シンポジウム
「フィルム/コンテンツ・ツーリズムと地域社会」を開催
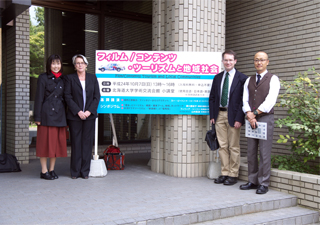 パネリストの4氏(会場看板前) |
 ワークショップでの討論の様子 |
(国際広報メディア・観光学院,メディア・コミュニケーション研究院,観光学高等研究センター)