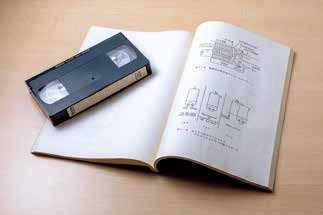|

株式会社サンブリッジ代表取締役会長兼CEO
小野 裕之
ONO Hiroyuki
| 工学部卒業、工学研究科修士修了 |
※2021年4月から株式会社ユナイテッド・バス代表取締役社長に就任
「文系と理系のど真ん中」から考え実践する
〜時代の変化を見極め、先を読む〜
クラウド(インターネットを通じてシステムを利用する方式)を活用し、顧客情報を一元管理するしくみを導入することによって、企業の売上と生産性向上を図るビジネスを展開している小野裕之さん。その独創的な考え方やアクティブな行動力の背景を、今までの企業活動や学生時代を振り返りながら、語っていただいた。
―まず、現在のお仕事について教えてください。
一昔前の企業による営業活動は、展示会の開催や広告、担当者によるセールスが一般的でした。ところがインターネットの普及が状況を一変させました。顧客はホームページにアクセスして商品情報を得ます。そこで、マーケティング・オートメーションという手法を導入し、顧客の行動パターンや購買意欲の情報を一元管理し、自動的に分析することによって、一定のレベルを超えた顧客に対してのみ働きかけを行う営業活動に移行していきます。その結果、企業の売り上げと生産性は格段に向上します。企業の営業は精神論ではなく、計算可能な予測に基づいた科学なのです。私たちは、こうしたマーケティングのしくみを提案し、企業活動をサポートしています。

―大学時代はどのように過ごされていましたか。
学部は工学部の応用物理学科で光センサーの基礎研究をしていましたが、大学院では生体工学の分野に興味を持ち、人工臓器を開発するという未開拓の分野に挑戦しました。修士論文提出の直前で、アメリカの大学病院との共同研究が打ち切られてしまい困惑しましたが、なんとか論文としてまとめることができました。自分自身で研究の論理展開を考えることは、非常に良い経験になりました。
勉強以外では、ラグビー、旅行、テニスなどのサークルのほか、軽音楽のバンド活動にも力を入れていました。当時は、偏った人間にならないよう、コミュニケーション・スキルを高めようと何でもやりました。いろいろなアルバイトも経験しました。一番力を入れていたのは塾講師のアルバイトでした。担任制ということもあり生徒の進路に責任を持つため、講義の準備や夜遅くまでの補講など長時間労働で大変でしたが、働いた成果が実感でき、今の仕事をする上でのベースになっています。
―理系とは全く異なる分野に就職されましたね。
博士課程への進学も考えましたが、リクルート社に就職し、その後、ベンチャー企業に転職しました。ビジネスの世界は属人的な要素が多くを占めますが、これを科学的に再現可能性のあるものとして構造化ができると考え、実践しました。私が昔から使っているキーワードは「アナログ⇔デジタル変換」。顧客との対人関係の世界は文系的であり、アナログです。一方、技術の世界はデジタルであり理系的です。お客さんに対して、技術をどうやって使えば課題を解決できるかを提案するマッチングが必要であり、ビジネスチャンスを生むと考え、実践してきました。アナログの世界はどんなに頑張ってもデジタル一辺倒にはなりませんよね。だからアナログとデジタルの変換をいかにスムーズに行うかが重要です。これからの時代は「文系と理系のど真ん中」で活躍できる人材が求められます。
―独創的な視点を持つために日頃から心がけていることは。

有事となった時に何が起きるかを見ています。例えば2011年の東日本大震災。ITの世界では、クラウドによるサービスが一気に増えました。既存の方式よりも安いことと、災害時に企業活動をいかに継続させるかという安全面の重要性に対する認知が高まりました。コロナ禍では、DX(デジタル・トランスフォーメーション)という言葉が一般的になるなど、世の中の価値観が一気に変わりました。例えば、通勤からリモートワークへと働き方が切り替わり、さらに非対面式での営業活動やプロジェクト作業、企業セミナーのオンライン化が当たり前になりましたが、この変化にあわせたサービスを提供することで、弊社では生産性が向上し、売上高も大幅に伸びました。
―北海道の可能性をどのように見ていますか。
広大な土地とともに、地理的、地勢的に有利なポジションにあり、経済面で中心的な役割を担えるのではないかという期待値がありますので、そこに携わり、恩返しをしたいという思いは強くあります。食料自給率は200%とダントツですし、寒い土地でおいしい米を作る技術を持っています。また、すでにITと農業を融合した新しいビジネスモデルが生まれています。食と健康は、個人的にはこれからの時代に一番重要なテーマだと考えており、新しいイノベーションを起こしてくれるのではないかと北大に期待していますし、一緒にやれたらいいなと思っています。
―最後に、学生へのメッセージをお願いします。
学業では自律的に考えて自走しなければならないこともありますが、そうした場面で様々な実践ができる環境があるということが大学の良いところです。学業以外の諸活動にも同じことが言えます。ぜひ、オープンなマインドで新しいイノベーティヴなことにチャレンジしてください。
|
|
PROFILE 1964年北海道出身。1987年に北海道大学工学部卒業、1990年に同大学工学研究科修士課程を修了し、株式会社リクルートに入社。新規事業担当マネージャーとしてインターネットサービスの事業化に着手。その後、国内ITベンダーにて数多くの新規事業創出に携わる。2009年からサンブリッジグループの経営に参画。2020年7月から現職。独自のアプローチかつ企業に寄り添う目線でのサービス展開は常に高い評価を得ている。 |
| 前のページへ | 目次へ | 次のページへ |