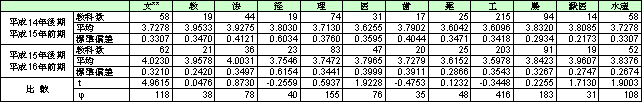
アンケート全体の平均 (拡大表示,別ウィンドウが開きます)
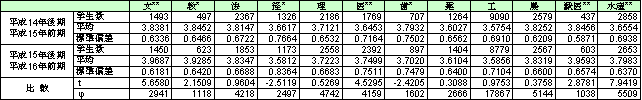
**:p<0.01, *:p<0.05
今回の授業アンケート(平成15年度後期および平成16年度前期)から,公表媒体がこれまでの年度報告書(印刷物)の一章としての公表及び報告書のPDF化によるホームページへのアップから,独立したホームページ形式の公表のみになった。これにより公開性が増すことが期待される。また,別の情報へのリンクなど印刷物とは異なる表現ができるため,それを利用してわかりやすくするよう心がけた。
分析の内容についても昨年までの手法に加えて以下のような新たな試みを行った。
1)調査対象を非常勤講師まで拡大した。
2)回収状況に関する数値をより正確にした。
3)大きな変化が推測される部分について統計学的な検定を適用した。
前回までの報告書では,回収率を(回答教員数)÷(講師以上の全教員数)としていた。ところが,同一教員が複数の授業についてのアンケートを提出していることがあり,この算出方法は実情にそぐわない場合があると考えられる。そこで,今回は新しい指標として実施率を計算した。実施率は(実施者数)÷(講義,演習の担当教員数)で算出し,同一教員が複数の授業について実施した場合は1名とカウントした。新しい指標の実施率の平均は従来の指数(過去4年間の平均69.5%)よりも低く,65%である。依頼者数(部局における授業担当者数)の少ない部局での数値は低めに出ているが,大きな部局の数値は信頼できる。依頼者数が10名以上の部局では,実施率は41.94%〜83.33%の範囲にあり,多くは6割台である。授業アンケートの重要性を鑑み,実施率のさらなる改善が期待される。
総合平均の年代別変化をみると,多くの学部で第1回目の調査から総合評価は徐々に良くなり,ここ数年はほとんどの部局で平衡に達しているように思われる。そこで,前回との比較のため,学生の全アンケートに対して平均値の差の検定(t検定)を行った。そこから,文学部,教育学部,経済学部,医学部,歯学部,獣医学部,水産学部が統計学的に見て意味ある(有意な)変化を示していることが判明した。この中で経済学部と歯学部で昨年よりも総合評価が0.08以上低下しており,少々懸念される状況である(別図「学部別評定平均」参照)。
ところで,これまでの表記は学生アンケート全体の平均を算出していたが,そうすると人数の多い科目の評価に偏る可能性があるので,授業ごとの平均値を算出した後,それらの平均を計算し,それを利用したt検定も行った。その結果,経済学部も歯学部も前回との有意な差異は認められなかった。歯学部は昨年度に比較して演習と講義の比率を見ると講義が増加しており(88.2%→95.5%),その影響が考えられる。両学部ともアンケート全体の評価が有意に下がっている一方で授業平均の差は認められないことから,大人数講義の評価が低下していることが推測される。両学部での原因の究明と解決が望まれる。参考までに,平均値でも明らかに改善の傾向が認められたのは文学部だけである。
設問別に上位二項目「強くそう思う」と「そう思う」の合計比率を算出すると,13「授業の履修目標を達成できた」,8「教員は効果的に学生の参加を促した」,17「自分はこの授業に積極的に参加した」が50%以下である。達成感が低いことや,参加型授業とはなっていない講義が多いことは,学生の学習動機の低下にもつながるので継続的な努力が必要である。FDなどで,参加型授業の手法をさらに広める努力が必要である。さらに,上位二項目の合計が60%以下であるものをあげると,1,5,6,7,9,10,11,14,15の9項目に及び,まだまだ改善の余地のある講義が多いことが推測される。
自由意見は,昨年度と同様,学生評価の総合点が優れている授業を抽出し,その授業についての意見を紹介することにより,授業を評価する学生の視点や,高い評価を受ける授業の特性を明らかにするよう配慮した。授業名と学生のコメントからだけでは授業の内容が推測できない場合もあるので,シラバスの一部を掲載した。抽出した意見が伝えているのは,学生は教員の総合的授業実行方法(授業への熱意,教育媒体・負担の適正さ)と授業への満足感・授業における達成感を特に重視しているということである。抽出した意見の多くがこれらの点を指摘し,評価していた。
本年度から北海道大学は法人化すると同時に「評価室」を設置した。「学生による授業アンケート」については,中期目標・中期計画において,「引き続き実施するとともに,その結果への教員の対応を学生に公開する」ことが明文化されている。授業アンケートの実施に関するノウハウは,すでに十分な蓄積がある。したがって今後は,いかなる方法で学生に公開するかというのが1つの重要な検討事項になるものと考えられる。ホームページ形式での公開はその第一歩である。
なお,評価室では授業アンケートと成績との関連性を検討するために,平成16年度後期授業において,例数を絞って,個別学生の成績と授業アンケートの数値が対応するようデータを回収し,分析する試みを行っている。また,高等教育開発機能総合センターでは全学教育について授業ごとの成績分布と授業アンケートの関係を分析している。これらの検討結果が公表されれば,さらに詳しい状況がわかるようになり,教育の質の改善に寄与するものと期待される。
学校教育法の改正により,大学は7年に1度認証評価を受けることとなった。認証評価機関の一つである大学評価・学位授与機構が平成16年2月に公開した「大学機関別認証評価」の大学評価基準は11項目で構成され,その9番目は「教育の質の向上及び改善のためのシステム」である。このなかで,大学が学生の意見を的確に聴取し自己点検評価に反映するとともに,【評価結果を教育の質の向上・改善に結びつけ,具体的かつ継続的な方策を講じる】ことが求められている。
本授業アンケートの大きな目的は,結果を各教員にフィードバックすることにより,各教員が自らの授業の課題等を見つけ,授業を改善することにある。過去の数値の経緯が示すように,各教員の努力により授業改善は進んできているが,授業アンケートの結果が平衡に達したことは,これまでのように各教員の努力のみに頼っていたのでは,これ以上の改善が望めない可能性を示唆している。
本学では早くから全学FDを実施するなど,教育改善に力を入れてきた。各学部でも学問分野に応じたFDを実施するところが増えてきており,水産学部では学部FDにおいて,本授業アンケートで高い評価を受けた者による講義の後に授業改善に関するグループ討論を行うなど授業アンケート結果を組織的に活用する取組も始められている。これらFDの実施だけでなく,TA制度の効果的利用法や教育業務のサポート体制など,ますますの積極的かつ組織的な教育改善の取り組みに期待したい。