 |
|
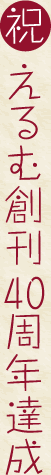 |
『えるむ』創刊四十周年、おめでとうございます。
この記念すべき節目に今一度、「なぜ『えるむ』にはつい見入ってしまうおもしろさがあるのか」ということを考えてみたく、筆を執らせていただきました。
結論を先に言ってしまいますと、タイトルにもありますように、『えるむ』には近くて遠い「お隣さん」のことが書かれているからだと私は思います。北海道大学は敷地、構成員ともにとても大きな組織です。集団が大きくなればなるほど個人として繋がっているという実感が希薄になるのは自明のことであり、そのためメインストリートですれ違ったり講義の教室で隣り合う学生が、同じ場所を共有しているのに知らない人、「近いのに遠い」人となってしまう。あるいは学内で行われる諸々の催しがどこか気疎いものとなってしまうという具合です。
あるコミュニティのなかの「近くて遠い」を「人」にできるだけ近付けていくこと。当然といえばその通りではありますが、広報に求められるのは実にこのような機能ではないかと思うのです。ここで述べる「近くて遠い」は「ひと」にのみとどまることではありません。行事であったり、お店であったり、あるいはモノであることも可能です。
私は現在大学院の映像製作実習で、JR北海道発行IC乗車券「Kitaca」のPR映像をグループで製作しています。(ご存じの方も多いとは思いますが、Kitacaとは改札機に触れることで通過できる機能のついた、札幌近郊で利用可能なプリペイド乗車券です)
Kitacaが利用可能な区域に居住しており、更に通学にJRを利用している私にとって、この北海道初のIC乗車券はまさしく上述したような「近くて遠いもの」、つまり「十分自分に関係しているが、よくわからないもの」でした。そのような印象を持つ人は少なくないと感じ、まず自らkitakaについて知り、そこで得られた情報を広く伝えたいという思いから、この企画に参加しました。
作品はインタビューを主とするドキュメンタリーです。Kitaca製作者(Kitaca事業室室長、イメージキャラクター「エゾモモンガ」作者)のみでなく利用者のインタビューも盛り込みました。製作者側から提供される情報だけでなく、利用者の意見、いわば「クチコミ」的な要素を加えることで、Kitacaが作品の視聴者にとってより身近なものとなると考えた上での工夫です。
広報のあり方について考えさせられること多々あり、難儀しつつも1月末の上映会に向け奮闘しております。『えるむ』には遠く及ばないものの、「近くて遠い」を「近い」にするということの、ひとつの試金石となればよいと願っております。 |
 |
|
|
 |
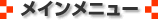 |
|
 |