 |
 |
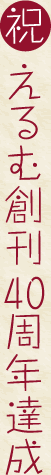 |
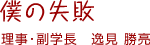
|
◇最初に出会った北大の教員は阿部保(1910〜2007年)、僕も一員となった1962年文類1年3組の担任である。入学式後に教室に参集した僕らに「下駄を履いて来ないように」とだけ述べると退出した。生協総代の司会で自己紹介を行い、僕も出身地・志望学部をぎこちなく話した。誰もが僕より長じており、予備校・恵迪寮での顔見知り同士は既に打ち解けてもいて、気後れするしかなかった。僕の北大最初の日はこうして始まった。
◇毎朝クラス毎に出欠を確認しないと理解するにはやや時間を要した。講義は高等学校とは根本的に異なっていた。講義では常に新しい知識を得た。同時に既得の知識が統合されていくことに興奮した。
いくつかの講義の記憶を記しておく。
人類学(名取武光)は概論。英語(鈴木重吉)はナサニエル・ホーソン『緋文字』。講義は余談(19〜20世紀前半のアメリカ文学史)に徹した。憲法(深瀬忠一)は比較憲法史。国史(北村文治)は古代日本奴隷制。東洋史(佐久間重男)は中国土地制度史。地学(浦島幸世)は鉱床学。化学(堀内壽郎)は錬金術にはじまる近代化学史。漢文講読(近藤光男)は蘇軾の詩を通読。国語講読(和田謹吾)は近代日本文学史。生物(青戸偕爾)はアフリカツメガエル。国文学(藤岡忠美)は『源氏物語』「宇治十帖」の「橋姫」を通読。一般数学(中島甲臣)はギリシャ数学史。政治史(矢田俊隆)は、マルクスからローザ・ルクセンブルグにいたるドイツ社会民主党史。法学(今村成和)は行政法。政治学(小川晃一)はホッブス論。
◇人類学では、歯の後退と相関する「頤(おとがい、下顎の先端)」、ボーラ(小石・紐で造った狩猟道具)を知った。鈴木重吉が訳した『緋文字』があると知って「英語」の予習を放棄したが、アメリカ文学史を聴いたのは、後にも先にも彼の余談が唯一であった。小学校以来3度も教わった「主権在民」「戦争放棄」「三権分立」を、国家権力の制限と市民の権利保障の歴史過程に位置づけて理解できたのは、確かな成長であった。初めて聴く地質学は新鮮であり、黒鉱に驚き、「鉱床形成要因はわからない」との結論から僕は勇気を得た。高等学校「化学」で教わった錬金術と有機化学の歴史を知った。蘇軾ひとりの作品を詩人の閲歴と重ねながら読むのも、『源氏物語』の一帖を読むのも、高校の授業ではあり得ない。高校では中国の詩人は政治家とは教えなかった。自然主義文学にあらかたの時間を費やしたが、二葉亭四迷『浮雲』を手始めに、作品を読みながらたどる文学史はその後の読書への姿勢を規定した。
◇別の収穫は、講義している教員は学者でもあると知ったことである。例えば、『緋文字』は鈴木重吉の、蘇軾は近藤光男の、自然主義文学・島崎藤村論は和田謹吾の、アフリカツメガエルの再生は青戸偕爾の研究テーマそのものであった。「課題意識と方法・実証」に精魂傾けた講義に惹かれた。そして、博覧強記に圧倒されながら聴いた堀内壽郎の有機化学史を、後に彼の学長就任講演で「個体発生は系統発生を繰り返す」と聴いたこととともに思い出す。僕らは教養教育を通じて、「学問の仕方」を教わったと言い換えてもいい。
◇僕は入学式当日の「気怠い挨拶」に失望したまま、阿部保の「西洋文学史」を受講しなかったことを後悔している。阿部保は、『アリストテレス詩学(芸術論)』(碓氷書房、1949年)を訳出し、「エドガァ・アラン・ポウの詩とその美的理念」(『東京経大学会誌』第2・3号、1950・51年)を著した美術史家・英文学者であり、『ポオ詩集』(新潮文庫、1956年)を訳出し、『紫夫人』(1953年)、『冬薔薇』(1955年)、『蝶』(1958年)など詩集を編んでいる象徴詩人でもあった。僕には象徴詩を鑑賞する能力はないが、韻律は快い。阿部保が学生の時に詠った「太陽と薔薇と苦悶と」(『夢の画廊で』1985年)から韻律の美しさを確かめておこう。
吹きみだれる胸の血潮と、/吹きみだれる薔薇の花と、/吹きみだれる秋の日差しと。
彼がわれわれのクラス雑誌『曙光』巻頭に寄せた「石狩の海」からも引いておく。
ここには書かれたことのない文字がある。/ここには描かれたことのない絵がある。/ここには歌はれたことのない悲しみがある。
阿部保は「ああ、青春は空しく夢みて過ぎる。」(『ポオ詩集』「あとがき」)と記すような人である。そして、『アリストテレス詩学(芸術論)』には、「ものを学ぶということは(中略)たといその人々のものを学ぶ能力がいかに小さくとも、この上ない悦び」とある。
彼の講義を受けなかったのは僕の失敗である。 |
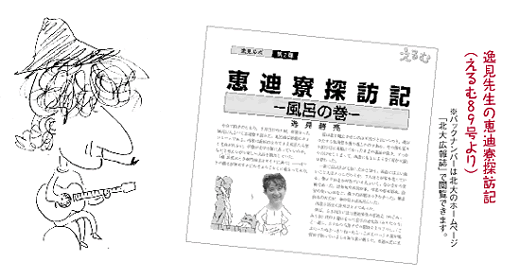 |
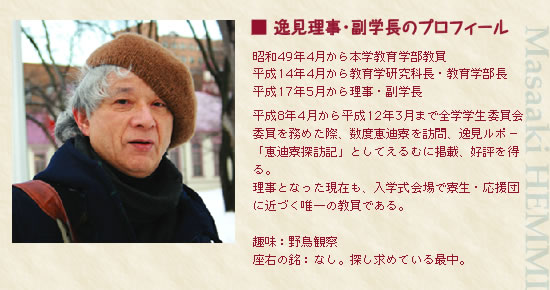 |
|
|
 |
 |
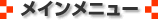 |
|
 |