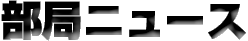
| 21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」総括シンポジウム「スラブ・ユーラシア学の幕開け」を東京で開催 |
スラブ研究センターを核とした21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築:中域圏の形成と地球化」は平成19年度で終了します。5年間の事業の締めくくりとして,その成果を社会的に開かれたものとするため,普段の札幌における英語ないしロシア語によるシンポジウム開催ではなく,会場は東京に,そして言語は日本語による報告を主とするものを企画しました。
1月24日(木)から26日(土)のシンポジウム当日,会場となった神田の学士会館,そして東京大学本郷キャンパスには朝から100名以上の参加者が詰めかけ,学士会館では160名分用意した席がほぼ埋まるパネルディスカッションも出るという盛況ぶりでした。
5年間の事業目的をあえてひと言でまとめると,「旧ソ連」,「旧ソ連東欧」,「旧社会主義圏」という後ろ向きの言い方をやめ,現実に相応しい名前をつけること,そして,現実の動向に相応しい分析方法を確立することでした。それが「スラブ・ユーラシア学の構築」であり,学術的にも社会的にも,これからは「スラブ・ユーラシア」という名前でこの地域を呼びましょうと提案を行っています。
欧米ではこの地域を,学問的に,「移行諸国」と呼ぶことがいまだに多いのですが,これは事実上,「スラブ・ユーラシア諸国は欧米型の政治経済体制へと移行するはずだ」という含意で用いられています。しかしロシアのように,独自の改革路線を歩む国も少なくありません。つまり単なる社会主義から欧米型資本主義への「移行」では捉えきれない現実があります。その現実を出発点として受け止め,そこから相手を見る目を鍛え直していく必要があります。
ではその現実を見つめる目とは何か,ということになります。まさにそれが今回企画した三日間にわたるシンポジウムの目指した主題でした。第一日目である1月24日(木)の「地域をつくる,くくる,えがく」と題された三つのパネルディスカッションは,これからのスラブ・ユーラシア研究の方法論を提起するものでした。
一つ目は地域を生み出す主体の問題,あるいはどのように地域を設定するのかという問題です。これが第一パネルディスカッションの主題である「地域をつくる」という問題領域です。
二つ目はそうして出来上がったいくつかの地域がさらに大きな単位として括られていく問題,つまりスラブ・ユーラシアが多様な地域の複合体であるということを踏まえて,全体としてどのように広域的統合がなされるのかという問題領域です。これは近年において注目を集めている「帝国論」的手法でスラブ・ユーラシアを分析する方法です。
三つ目は「えがく」がテーマです。これは少し硬く言えば,心象地理といわれる分析視角です。つまり物理的な山とか川とか海の形状から地理的な,あるいは空間的な認識を行うのではなく,人々がある空間,ある地域をどのように思い描いてきたのかという問いかけです。スラブ・ユーラシア研究では文学や言語に係わる分析が特段に重要な位置を占めていますが,このパネルディスカッションではそれが意識的に追求され,言語学研究における地域研究の可能性にまで話題が広げられました。
二日目の25日(金)は「次世代の挑戦」と題され,若手研究者が主役でした。現役の大学院生,大学院を終えたばかりの新進気鋭の研究者たちがパネルを企画し,運営しました。つまりこれから10年後,20年後のスラブ・ユーラシア研究を担う世代がどのようにこの地域を捉え,分析しようとしているのか,それを若手研究者自身の企画として打ち出してもらったのです。
三つの若手企画パネルディスカッションをキーワードでまとめますと,一つ目は「社会主義時代における学知」を問うものでした。二つ目は「跨境」がテーマでした。つまり国境などの境界線を分断の視点からではなく,接点として見なおす方法です。そして三つ目の主題は「宗教」でした。今日,宗教がもつ重要性は改めて言うまでもありませんが,このパネルディスカッションではテーマの現代性を念頭に置きながら,歴史研究としてイスラーム,ユダヤ,分離派正教徒に関する報告がなされました。今回の21世紀COEプログラムでは「全国を結ぶ若手研究者の育成」という目標を掲げましたが,この総括シンポジウムでも南は九州から始まり,関西圏,中部圏そして首都圏の大学で研究に従事している第一線の若手研究者をパネリストに迎えた企画が用意されました。シンポジウム終了後,多くの来場者から,「若手企画の報告や討論が非常に高いレベルだった」,「テーマとして,とても興味が持たれた」など,主催者としてうれしい評価をいただきました。
三日目の26日(土)は会場を東大本郷に移し,東大の「イスラーム地域研究」プロジェクトと共催で,国際シンポジウム「ロシアと中東の間のコーカサスとその住民たち」を開催しました。スラブ・ユーラシアと中東,西アジア,ないしイスラーム世界との接点であるコーカサス地域が取り上げられ,多様で複合的な「狭間の世界」が描きだされました。海外から招聘した第一線の6名の専門家は,会場に集まった100名近い聴衆に感激し,コーカサスという特殊なテーマでこんなに多くの聴衆が集まるとは予想していなかったと,歓声をあげました。
コーカサス・シンポジウムは札幌そして京都でも開催され,全体として日本におけるコーカサス研究の本格的幕開けを告げるものとなりました。「コーカサス」プログラムはイスラーム研究との連携を目指すという意味で,とても重要でした。「スラブ・ユーラシア学」はスラブ・ユーラシア地域だけで閉じてしまう学問ではありません。隣接する地域や関連する研究分野との共同作業を日常化する,という問題提起がこのシンポジウムに込められていました。今後も他地域の研究者との連携や共同を不可欠なものとして,スラブ・ユーラシア学を鍛えていこうと考えています。
今回のシンポジウム開催に合わせて,スラブ研究センター監修による三巻本シリーズ『講座スラブ・ユーラシア学』も刊行されました。
|
|
|
| (スラブ研究センター) |
|