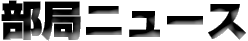
| 「地質の日」記念展示「支笏火山と私たちのくらし」を開催 |
去る4月28日(火)から5月31日(日)に北海道大学総合博物館1階「知の統合」コーナーにおいて,本総合博物館企画展示「支笏火山と私たちのくらし」が開催されました。
本展は昨年開かれた企画展示「ライマンと北海道の地質―北からの日本地質学の夜明け―」展に引き続き,5月10日の「地質の日」を記念するもので,今年は日本地質学会北海道支部・日本応用地質学会北海道支部・北海道地質調査業協会・札幌建築鑑賞会・札幌軟石文化を語る会・北海道大学総合博物館の共催で行われました。
約4万年前の支笏火山噴火は我が国でも最大級の巨大火山爆発であり,その火砕降下物は遠く知床半島まで到達しています。また,厚い火砕流堆積物は支笏カルデラ周辺から札幌市・恵庭市・千歳市・苫小牧市を含む低地を埋め立てて,その広大な火砕流台地は後カルデラ火山活動である恵庭岳や樽前山の軽石や火山灰とともに優れた自然景観を作っており,また市民生活とも密接に関わっています。さらに,支笏火山およびその後の火山活動は温泉や金属鉱床などの恵みももたらしています。
展示では,火山活動の災害と恵みの両面を市民の皆さんに知っていただくことを意図に,支笏カルデラ噴火と後カルデラ火山活動の様子や火砕流堆積物の特徴と分布,支笏湖周辺の温泉や金鉱床などの地質学に関わる事柄とともに,札幌市の建築遺産といえる札幌軟石のかつての採掘の様子などをパネルや実物展示,DVD映像により紹介しました。また,火山災害の防災・減災への意識や備えの重要性も市民にアピールしました。NPO法人環境防災総合政策研究機構と(財)自然公園財団支笏湖支部に提供していただいた有珠火山や支笏湖のDVD映像,および(財)資源・環境観測解析センターに提供していただいた衛星画像による支笏湖周辺の立体写真はたいへん好評を博しました。
今回の目玉の一つは,明治期以降において札幌の重要な建築材料であった「札幌軟石」(溶結凝灰岩)でした。札幌軟石は,開拓使の御雇い外国人技師であった米人アンチセルにより発見されたともいわれていますが,粗末な住居のため火事が多かった明治初期に開拓使により耐火建築資材として使用を奨励され,そのため,明治から大正初期の札幌には日本では珍しい石造建物の建築文化が見られました。それらの一部は,現在でも使用され,また保存されています。札幌軟石建築物の調査を市民グループが行っており,来年の展示はそれが中心になる予定です。
関連の土曜市民セミナーとして,5月16日(土)に若松幹男氏(北海道地質調査業協会)と瀬戸静恵氏(財団法人自然公園財団支笏湖支部)による講演会「支笏火山と支笏湖よもやまばなし」が行われ,多くの市民に参加していただきました。 |
|
|
| (総合博物館) |
|