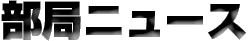
10月24日(土)から11月23日(月・祝)まで総合博物館で開催された「疋田豊治ガラス乾板写真」展は,文学研究科芸術学講座と総合博物館が主催し,水産科学研究院が共催した展覧会で,総合博物館の10周年記念の催しの1つです。
本学函館キャンパス内にある水産科学館(総合博物館分館)には,疋田豊治の撮影による約6,900点のガラス乾板が残されています。疋田は,現在の水産学部で,明治末から昭和初期までの40数年の間,教官を務めた人物で,シシャモの学名の命名者として,また北方産カレイ類の研究者として知られています。この「疋田写真」は「北海道開拓写真」と並ぶ本学の所蔵する貴重な資料ですが,これまでほとんど紹介されてきませんでした。今回の展覧会では,ガラス乾板をスキャンし調整してプリントした108点をご紹介すると共に,ガラス乾板数点と,疋田のメモが記されたその包装紙,疋田のオリジナルプリント,疋田による魚類のスケッチ,オショロガレイの液浸標本やオヒョウの骨格標本,同時代のカメラなどを展示しました。
「疋田写真」の約半数は魚類の写真で,他の半数は本学のキャンパスや函館の学生生活,あるいは調査旅行で訪れた択捉や色丹の風景などの写真です。魚類の写真には,研究目的とは別に,疋田がその形体の美しさや表皮の質感のおもしろさを強調したり,遊び心をもって配置したと思われるものも見受けられます。風景写真には,現存しない建物や,かつての漁業の様子と人々の暮らし,また時局を反映した情景が写されており,今日では歴史の重要な記録であると言えます。展覧会では「疋田写真」のごく一部ですが,その多様な側面を紹介し,疋田の膨大な仕事を概観することを試みました。
展覧会には,北海道大学教育GP「博物館を舞台とした体験型全人教育の推進」の一環として本学の大学院生・学生20名が主体的に関わりました。そもそも本展のきっかけとなったのは,文学研究科芸術学専修の博士課程に在籍する廣田理紗さんの研究でした。展覧会の構想,作品調査,パネル・キャプションの制作,カタログ編集,展示作業,ポスター・チラシの作成と広報活動,そして会期中のギャラリートーク,シンポジウムの開催など,準備全般と運営に,廣田さんを中心にした大学院生と学生が参加したことは,大学博物館らしい取組であったと言えます。学生達はギャラリートークに対応するだけでなく,会期中毎日,会場に詰めて,来場者に対応致しました。
本展の基調となるカラーは銀杏色でした。博物館入り口の垂れ幕やポスター,チラシ,ポストカードなどに配された銀杏色は,キャンパスの美しい秋の色にもマッチしていました。新聞やテレビなどでも広く報道され,多くの来場者をお迎えしました。関連して開催した市民セミナー「疋田写真の魅力」(本誌別掲。83頁参照 )やアートトークにも多くの参加者をお迎えしました。来場者との対話やアンケートの回答から,細部まで鮮明に写し出すガラス乾板写真への興味,撮影者疋田への関心が高いことを確認できました。疋田写真の研究を進めてその成果が公開されていくことへの期待も多くお寄せいただきました。 |
| |
 |
 |
| 展覧会会場風景 |
総合博物館入り口 銀杏色の垂れ幕 |
|
| |
| (総合博物館) |
| |
|