北方生物圏フィールド科学センターでは,8月19日から23日までの4泊5日の日程で「野外シンポジウム2013〜森をしらべる〜天塩・中川編」を開催しました。野外シンポジウムは,本センターが管理する広大な森林や渓流で行われている森林研究を現場で見て,調査を実際に体験しながら,何がどこまで解明されたのか,そしてこれから何を明らかにする必要があるかについて考える場です。参加者は全国の大学の学部生を対象としており,様々な大学・専攻・学年に所属する学生が集います。
16年目となる今年の野外シンポジウムは,天塩・中川編と道外では初めての南紀−古座川編(和歌山研究林)のダブル開催となりますが,天塩・中川編には北大生を含む全国各地の国公立8大学から森林研究に興味を持つ11名の学生が道北の天塩研究林・中川研究林に集まり,研究林スタッフや大学院生たちから森林研究の最新の成果や研究の進め方について学びました。プログラムの基本スタイルは,日中に野外で実際の調査を経験するフィールドセッションと,詳しい解説や質疑応答を中心とした夕食後の室内でのポスターセッション,そして,参加学生が学んだことを利用して「仮想」の研究を考え,それを発表するアンビシャスセッションの3段構成になっています。
フィールドセッションでは,高さ30m以上のタワーを利用した炭素循環研究,窒素循環,サンショウウオとオタマジャクシの食う−食われる関係,2000万円もする機械を使った葉っぱ特性の測定,尾根と谷でミミズの数はどれだけ違うかなど,様々な分野に関するセッションが行われました。このような多様な研究を間近で見ることが出来るのは,広大なフィールドで研究活動が活発に行われている本学の研究林ならではです。
夜のポスターセッションでは,現場でのセッションをより深く理解するために,ポスターを使ったプレゼンテーションが行われました。参加学生からは時間を惜しむように活発な質疑応答が繰り広げられました。多くの参加学生にとっては,初めての学会形式のポスターセッションで研究の楽しさや難しさのほか,研究者たちの苦労話や試行錯誤の裏話などを聞く良い機会となり,毎日夜遅くまで楽しい交流の時間が続きました。このほかにも,早朝の森でのネズミ採りや,自動撮影カメラによる野生動物の観察(今年はなんと,ヒグマが写っていました!)など盛りだくさんのメニューが用意され,雄大な自然を対象とした野外研究の楽しさを満喫しました。
全てのセッション終了後にあるアンビシャスセッションでは,興味あるテーマに分かれたチーム別にプレゼンテーションが行われました。発表されたテーマは,「スズメガとシャクガとダケカンバの危険な三角関係」「温暖化によって森林はメタボ化するのか?」「シカの樹皮剥ぎが窒素循環に与える影響」の3つでした。準備する時間は半日弱と大変短かったにもかかわらず,前夜遅くまでチーム内で議論を重ねた甲斐があり,とても魅力的で興味深い仮想研究が発表されました。最終日のエクスカーションは「ヤマベ釣り」を行い,参加者は胴長を着て渓流を歩き,多くのヤマベを釣りあげました。釣ったヤマベは早速天ぷらにして,大変美味しく頂きました。
参加した学生たちは「参加することを実は迷ったけど,来て本当に良かった」,「これまであまり興味のなかった根っこがとても面白いテーマであることに気づくことができた」,「北大大学院に来たくなった」など,新鮮で濃密な5日間の感想を語ってくれました。森林研究の面白さを満喫した参加者の中から,大学院に進学して新しい研究テーマに取り組む学生が現れることを願いながら,野外シンポジウムは閉会しました。今年はさらに,9月末に野外シンポジウム和歌山編を開催します。初めての和歌山での開催で北海道とは違った魅力を伝えることが出来そうです。事業の概要は本センター森林圏ステーションのホームページに掲載しています。是非ご覧になり,来年のシンポジウムにもお越しください!
北方生物圏フィールド科学センターで「野外シンポジウム2013
〜森をしらべる〜」を開催
 野外セッションで |
 野外セッションで |
 ポスターセッションの様子 |
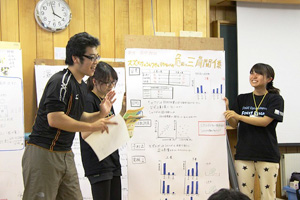 アンビシャスセッションの様子 |
 最後に全員で記念撮影 |
(北方生物圏フィールド科学センター)