サステナビリティ・ウィーク2014の開催
10月20日(月)〜11月3日(月・祝) 会場:附属図書館正面玄関ロビー
学術成果のオープンアクセスとHUSCAP
主催:附属図書館/実施責任者:附属図書館学術システム課 課長 片桐和子
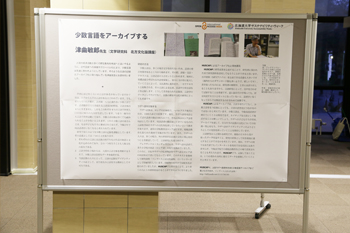 |
|
 |
| 展 示 風 景 | ||
10月31日(金) 会場:国際本部2階大講義室
留学希望者向けセミナー SD on Campus: Invitation to Study Abroad Program
主催:国際本部長 上田一郎/実施責任者:文学研究科 教授 瀬名波栄潤
イベントでは,各大学がサステイナブル・ディベロップメント(SD:持続可能な開発)についてどのような教育を行い,学生が授業や授業外でSDにどのように関わっているかを発表し,それぞれの特徴的な取り組みを紹介しました。
本イベントは今回で6度目の開催ですが,参加した学生に実施したアンケートでも「協定大学への留学について興味を持てた」,「北大生の活動も協定大学の取り組みにならって盛んになれば良い」などの回答が見られました。また,発表した留学生も自らの大学を直接アピールできる貴重な機会ととらえて十分な準備を重ね,当日も満足感を抱いていたようでした。参加学生のアンケートでは,来年度に講演してほしい大学の希望についても聴取することができたので,可能な限り希望を取り入れていきたいと考えています。
 国際本部からの説明 |
 参加者の発表風景 |
10月31日(金) 会場:学術交流会館小講堂
市民公開シンポジウム「都市でも農的生活−植物の面白さと豊かな生活」
主催:北方生物圏フィールド科学センター/共催:北海道園芸研究談話会/実施責任者:北方生物圏フィールド科学センター 教授 荒木 肇
東京農工大学の藤井義晴教授は「植物同士で成長を制御するしくみ」について話され,化学物質が植物相互の生育を阻害または促進させているアレロパシーという現象を紹介しました。この関係を上手に活用すると雑草抑制になり,有機農業や農作業効率化や新規生物農薬の創出につながると説明されました。
中国江西省花野菜研究所のザン・ユーピン助教は,「中国上海市における農業テーマパーク」について説明され,そこでは植物工場,バイオテクノロジーや近代庭園等による中国における農業発展と将来像を展示し,毎年30万人が見学に来ていると報告されました。
さとみらいプロジェクトグループの奥山 誠副施設長は「サッポロさとらんどにおける農的生活の支援活動」と題して,サッポロさとらんどが「人と農業・自然とのふれあい」や「都市と農業の共存」をテーマに,市民が農業や自然を身近に感じながら憩い・楽しむことができる魅力的な緑地空間の提供を理念に運営されており,平成7年のオープン以来,来園者が1,000万を超えたと報告されました。園内で農業体験の場を提供し,市民農園は194区画設置したものの,4倍の競争率となり,農業のある暮らしに関心が高まっていると説明されました。
市民農業講座「さっぽろ農学校」の吉岡宏直主任講師は「定年後にめざす農業活動」として,農業へ一歩進みたい人を対象に,4月〜11月上旬までの毎週土曜日に農業実習(栽培技術の実践)と講義(農業全般基礎知識)を開講し,50代の受講生が多いと報告されました。また,市民農業講座「さっぽろ農学校」の卒業生が,さっぽろ農学校倶楽部やグリーンライフさっぽろのNPO法人を設立して,北大生も参画している事例を報告されました。
討論では,多様な農業へのふれあいについて意見が出され,講師の吉岡氏から札幌市の「いきいきファーマー育成事業」が平成26年度から始まり,中高年世代が農業技術を習得し,農的活動を通じて生きがいのある暮らしを実践できるために研修ほ場を設置する計画(1人が約10aを耕作)も披露されました。
 会場の様子 |
 質疑応答時の様子 |
11月25日(火) 会場:学術交流会館
サステイナブルキャンパス国際シンポジウム2014
主催:サステイナブルキャンパス推進本部,施設部/共催:一般社団法人国立大学協会/
実施責任者:サステイナブルキャンパス推進本部 プロジェクトマネージャー 横山 隆
最初に,京都大学経済学研究科の植田和弘教授の講演があり,Human development(人間発達)を促す場としての大学の役割を強調されました。特に,持続可能な社会の担い手育成には,地域との協働を含む社会的学習が不可欠であり,従来の大学キャンパスもそのための場として変化していく必要性を示されました。
続いて,ルクセンブルク大学のアリアネ・ケニック博士は,そのような変化が,海外の大学でどのように起きているか,実際の例を交えた講演をされました。ルクセンブルク大学では,まさにHuman developmentを目指し,学生自らが太陽光発電組合のビジネスモデルを検証する等,地域課題に根差した教育プログラムの実践例を紹介されました。
その後のパネルディスカッションでは,文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課の森 政之整備計画室長,札幌市の生島典明副市長,本学の吉見 宏経済学研究科長らがパネリストとして加わり,地域連携のためにキャンパスがどのように活用されうるか,その可能性について議論しました。ブリティッシュコロンビア大学のCIRS(Center for Interactive Research on Sustainability)やルクセンブルク大学のベルバル新キャンパスにおける計画手法が,海外のキャンパス計画・開発の事例として紹介されました。これらの事例は,様々なステークホルダーを巻き込んで計画の改善を行っているという点がこれからの日本のキャンパス計画・開発において新しい切り口となる可能性の示唆がありました。
 集合写真 |
 植田教授による講演の様子 |
 ケニック教授による講演の様子 |
12月10日(水) 会場:農学部4階大講堂
新しい農業生産のやり方 ―エコロジー農業の日仏交流―
主催:アンスティチュ・フランセ日本,札幌日仏協会/札幌アリアンス・フランセーズ/共催:農学研究院,国際本部/
実施責任者:農学研究院 教授 大崎 満
フランスからは,農村環境の様々な変化等を中心に40カ国以上での研究経験を持つ農学者エティエンヌ・アンズラン氏と,国土総局にて持続可能な農業の実践を指揮されるエリック・ジリ氏をパネリストとしてお招きし,日本からは,電気柵等による革新的な放牧システムをはじめとするニュージーランドのローコスト・ファーミングの導入に長年取り組まれるファームエイジ株式会社の小谷栄二代表取締役と,現役の畑作農家である北海道十勝地区農協青年部協議会の前多幹夫副会長,農学研究院の久田徳二客員教授,北方生物圏フィールド科学センターの三谷朋弘学術研究員がパネリストとして参加しました。
農学研究院の林美香子客員教授による司会進行と,同研究院の内田義崇助教によるファシリテーションのもとパネルディスカッションが開始されました。エコロジー農業の定義について,単独の農業技術ではなく農業生産に関する考え方の変化自体であることや,エコロジー農業を普及していくために必要な政策や消費者の理解などについて議論がなされました。最後の質疑応答では,時間いっぱいまで多くの質問が行われ,また,終了後も来場者が個人的な質問をパネリストに直接行っている様子がしばらく見受けられました。
 参加者の集合写真 |
 質疑応答の様子 |
12月19日(金) 会場:フロンティア応用科学研究棟レクチャーホール
日露共同で行う教育プログラム開発プログラム
−極東・北極圏における持続的発展を未来につなぐ−
主催:北海道大学/実施責任者:文学研究科 教授 望月恒子(副学長)
本シンポジウムには,RJE3プログラムのロシア連携5大学である極東連邦大学,北東連邦大学,イルクーツク国立大学,サハリン国立大学,太平洋国立大学の学長・副学長・教員等15名を含む90名が参加しました。
はじめに山口佳三総長から挨拶があり,当プログラム事業推進責任者である望月恒子副学長,及び本学と長期にわたり様々な共同研究実績を持つロシア科学アカデミー極東支部太平洋地理学研究所のピョートル・バクラーノフ所長に基調講演をいただきました。望月副学長は,RJE3プログラムで育成する人材のビジョンと体制,及び本学の戦略との関係性などを含め概要について紹介しました。バクラーノフ所長からは「ロシア太平洋地域:長期的視点で見た開発,国際共同のための地理学的・地政学的な強みと課題」として,本プログラムが対象とする地域における様々なデータを元に,その可能性と課題についてお話しいただきました。
続くパネルディスカッション第1部では,本プログラムのコンセプトにご賛同いただいている日露の学術,産業,経済各界を代表する方々(北海道庁経済部経営支援局国際経済室 小玉俊宏室長,北海道銀行国際部ロシア室 中川文敏調査役,在北海道サハリン州政府代表部 クトヴォイ・アンドレイ代表,北東連邦大学 プリシヤズニ・ミハイル副学長,本学工学研究院 瀬戸口剛教授)にご登壇いただき,各氏の経歴等とともにプログラムに対する期待や可能性についてお話しいただきました。
パネルディスカッション第2部では,RJE3に関連した研究を行う日露の学生(理学院博士課程2年 岩波 連さん,文学研究科修士課程1年 岩渕真由子さん,国際広報メディア・観光学院研究生:サハリン国立大学出身 オレグ・パンコフさん,北東連邦大学経済学研究科修士課程2年 アニシア・ラザレワさん)による自己紹介の後,パネラー全員でディスカッションを行いました。育成される人材に求められること,これまでの交流と今後の展望,また学生の立場からの質問や希望等について,会場も巻き込んで活発な議論が行われました。
 山口総長による開催挨拶 |
 集合写真 |
12月20日(土)・21日(日) 会場:学術交流会館小講堂
先住民文化遺産とツーリズム 文化的景観と先住民遺産をめぐる諸問題
主催:アイヌ・先住民研究センター/共催:観光学高等研究センター,WAC Japan(世界考古学会議日本)/
実施責任者:アイヌ・先住民研究センター 教授 加藤博文
先住民の文化的景観もしくは先住民に関わる考古学に携わる大学の研究者,博物館業務従事者,埋蔵文化財行政従事者の方々に,講演者としてご登壇いただきました。スウェーデンのウプサラ大学のニール・プライス教授とカール=ゴスタ・オジャラ講師は,サーミと考古学あるいは考古学遺跡から読み取れる先住民の景観利用について講演されました。また,ワシントン大学バーク博物館のスヴェン・ハーカンソン准教授とアバディーン大学のリック・ネヒト上級講師には,アメリカ北西海岸で出土したネイティブ・アメリカンに関する考古学遺物などを活かした博物館活動についてご報告いただきました。北海道の事例としては,旭川市と平取町の埋蔵文化財行政に従事されてきた旭川市の友田哲弘学芸員と平取町の吉原秀喜主幹にご登壇いただき,地域内にあるアイヌ文化に関わる資源をどのように再発見し,継承していくかについてご発表いただきました。白老町のアイヌ民族博物館の八幡巴絵学芸員からは,白老町の景観にまつわる口承伝承をご紹介いただくとともに,自然と深く関わりを持ちながら発展してきたアイヌ文化の継承に関する博物館の取り組みをご報告いただきました。
最後に,講演者全員によるパネルディスカッションが行われ,アイヌや先住民の文化遺産を特徴づける景観の保護とその適正な活用を,まさに現代及び未来の課題として考えることの重要性が確認されました。
 プライス教授による講演の様子 |
 文化的景観をめぐる総合討論の様子 |