|

北海道大学大学院保健科学研究院
保健科学部門 リハビリテーション科学分野
寒川 美奈 准教授
SAMUKAWA Mina
博士(理学療法学)。専門はスポーツ理学療法学、運動療法学。札幌医科大学衛生短期大学部卒業。札幌市内整形外科での勤務、カナダのアルバータ大学への留学などを経て、札幌医科大学大学院保健医療学研究科博士後期課程修了。2003年に北海道大学医療技術短期大学部助手に着任。2008年から大学院保健科学研究院の所属となり、2013年から現職。理学療法士として東京オリンピックの運営に携わるなど、スポーツ現場の最前線で活躍している研究者である。
安全で効率的な運動を探求するスポーツ理学療法学
病気や怪我、加齢や障害などの様々な理由によって運動機能が低下してしまうと、私達は体を自由に動かせなくなり、日常生活に支障をきたしてしまう。そのような状態にある人や、その恐れがある人に対しては、自立した日常生活のための基本的な運動機能、歩くこと、座ることや立ち上がることなど、の回復を目的とした治療(リハビリテーション)が必要となる。このための治療法を「理学療法」という。また、理学療法によって運動機能の回復や維持などの支援を担う専門職が「理学療法士」である。
理学療法は、リハビリテーション対象者の身体を理学療法士の手や器具などを用いることで動かす、あるいはリハビリテーションの対象者自身が動くことで治療を行う「運動療法」、リハビリテーション対象者に物理的刺激(温めることや振動を与えることなど)を加えることで治療を行う「物理療法」、テーピングなどの「装具療法」の大きく3つに分けられる。このうち、1つ目の理学療法に関する「運動療法学」を基盤として、スポーツ傷害の予防、運動療法の有効性に関する検証、ウィメンズヘルスを中心としたヘルスプロモーションに関する研究に取り組んでいるのが、保健科学研究院の寒川美奈准教授である。

研究室のゼミ生との一枚。スポーツジムで
一緒にトレーニングをしながらそれぞれが
研究している運動の重要性やその効果を体験。
幼少の頃からアルペンスキーに親しんでいた小樽市出身の寒川准教授。小樽潮陵高等学校に入学したが、スキー部はジャンプ選手と2人だったため、市内の強豪校と一緒に練習をしていたという。「その当時、私と一緒に練習や競技に参加していた選手達が怪我をすること、特に膝の靭帯を痛めてしまい、競技を辞めざるを得ない状況に追い込まれることが度々ありました」と寒川准教授。「その様子を見ていて、スポーツによる怪我の治療や予防をサポートするような仕事はないのかと漠然と思ったのが、理学療法の道に進むことになったきっかけです」。
札幌医科大学衛生短期大学部理学療法学科に進んだ寒川准教授。スポーツ理学療法が進んでいる海外への留学を希望していたが、当時の指導教授から、まずは日本での臨床経験を積んだ方が良いとのアドバイスを受け、理学療法士として札幌市内の整形外科への就職を決めたという。「そこでは、スキージャンプやサッカーなどの競技でトップレベルの選手を診る機会が多くありました。その貴重な経験を通して自分の目指すリハビリ像が明確になり、海外でスポーツ理学療法を学びたいという意欲が高まり、大学時代の恩師に紹介を受けてカナダのアルバータ大学に留学しました」と当時を振り返る。
留学後、札幌医科大学大学院での研究活動などを経て、2003年から本学教員となった寒川准教授。現在は、スポーツ理学療法学研究室で、怪我の発生要因を解明して予防に役立てるといった、スポーツ現場の課題解決を図るための研究に取り組んでいる。また、北海道大学COI「食と健康の達人」拠点の健康コミュニティプロジェクトに参加し、運動を通じて岩見沢市民の健康づくりをサポートするなど、地域貢献にも力を入れている。
さらに、寒川准教授は、全日本スキー連盟のモーグル代表チームの理学療法士としてワールドカップや世界選手権、オリンピックなどに帯同し、競技時の怪我の予防と治療に携わってきたことに加え、本年開催の東京オリンピックにおいても、選手村に設けられた理学療法室のコアスタッフとして国内外の選手達の支援にあたるなど、多方面で活躍している。こうした活動で得られたことを教育に還元し、日本では比較的新しい分野であるスポーツ理学療法学の発展に必要な人材を育成しているのだ。「ゼミ生には、自由な発想を持って研究に打ち込んでほしいですね。そして、スポーツや臨床の現場との橋渡しとなるような研究成果を積極的に発信していきたいです」と今後の意気込みを語る寒川准教授。これまで経験してきたスポーツ現場での様々な事例をもとに、競技の特性を考慮した予防法の構築を目指し、学生と共に日々研究に励んでいる。
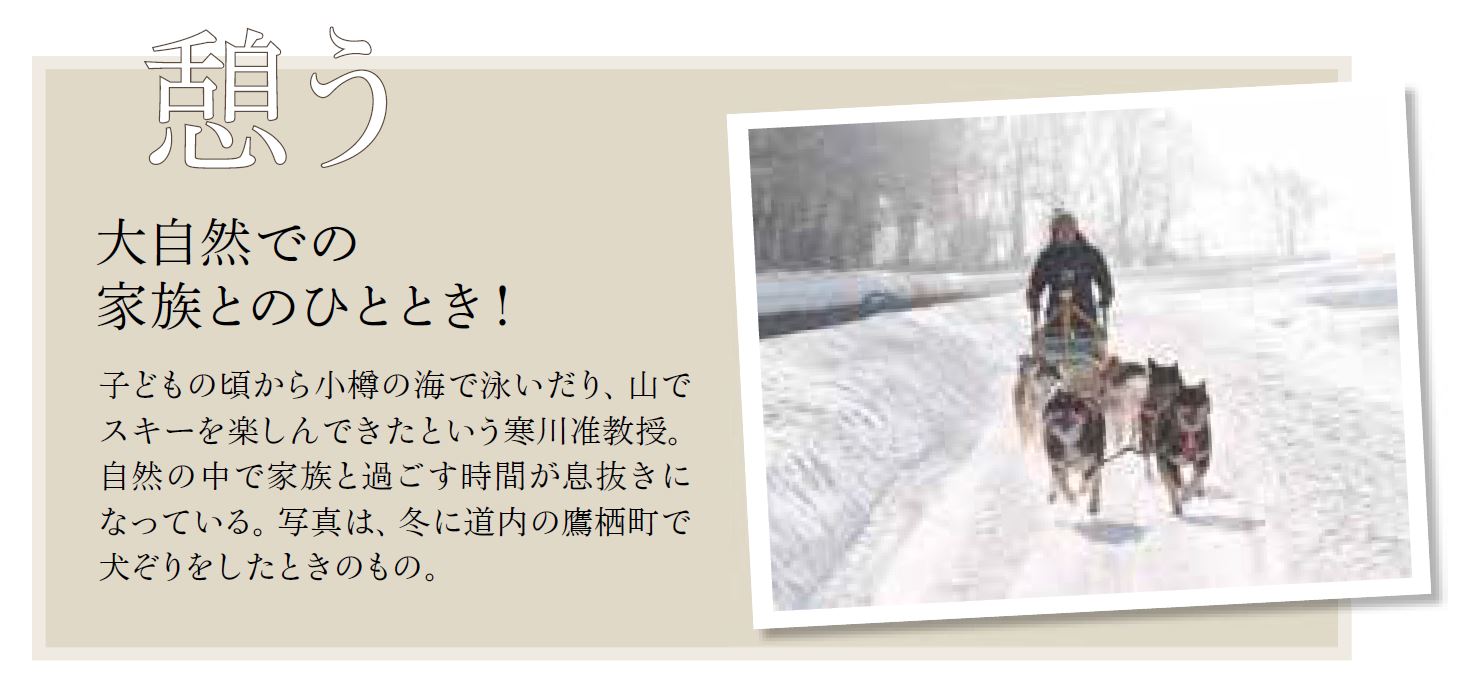
| 前のページへ | 目次へ | 次のページへ |