|
音とインターネットの可能性を追求し
地方で活動するクリエイターを応援

ゲスト
伊藤 博之 氏
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 代表取締役
今や世界中にファンを持つバーチャルシンガー・初音ミク。その始まりは、札幌の会社が開発した、音楽制作ソフトウェアだ。生みの親として知られる伊藤博之氏は、この7月に自著『創作のミライ「初音ミク」が北海道から生まれたわけ』を上梓。今年、会社設立30周年を迎え、デジタル音楽業界のトップランナーとして活躍を続けている。
比類なき大学を目指して改革を進める寳金清博総長が、北海道大学での勤務経験が人生の転機となったという伊藤氏に、コンピュータとの出会いや起業するまでの経緯、地域とクリエイターへの思いなどについて話を伺った。
寳金 伊藤代表は、北海道標茶町のご出身なんですね。どのような子ども時代をお過ごしでしたか。
伊藤 僕は、ごく普通の子どもでした。可もなく不可もなく。
寳金 部活動などはされていましたか。
伊藤 高校は一時間半かかる汽車通学だったので、帰宅部でした。音楽が好きで、一人でギターを練習していましたね。
寳金 伊藤さんとはこれまで二度ほどお会いしていますが、非常に控えめな方だなという印象を私は持っています。このような業界で成功されている方として、もっと別の人物像を描いておられる方もいるのではと想像するのですが、ご自分ではどう思われますか。
伊藤 目立ちたくないんです。「すごいですね」などと言われると気恥ずかしくて。何事もひっそり黙々と、自分の中で消化したい性格です。
寳金 高校卒業後は公務員の道を選択されて、北大の職員になられたのですよね。
伊藤 僕の田舎では大学に進む人がそもそも少なくて、就職するのが自然でした。北大工学部の研究室に事務職の枠があって、そこに採用していただきました。
寳金 今の職業からすると、むしろバックパッカーで世界一周のような、アバンギャルドな生き方を想像されがちかと思いますが、公務員は堅実な選択ですよね。
伊藤 自分が普通の公務員になっていれば何の変哲もない人生で終わったと思うのですが、配属された研究室が少し特殊だったんです。職員もゼミや研究に参加しなさいと言われ、僕の前任者も後任者も、学位を取っています。
寳金 それはすごい。今はあまりない環境ですね。そこでコンピュータと出会われたのですね。
伊藤 はい。精密工学科で機械設計を主にやっていたので、周りにコンピュータがたくさんありました。それまで触ったこともなかったのですが、コンピュータを使えないと仕事にならないと感じまして。とりあえず勉強して情報処理の資格を取りました。そこでプログラミングを学ぶ機会があり、英語の論文を読むために不得意な英語も勉強しました。
寳金 相当異例な話ですよね。伊藤さん自身のポテンシャルもあって、そこに環境が加わり化学反応が起こったのだと思いますが、今の大学の状況では普通、ないことです。
伊藤 当時の先生が京都の方で、「君も大学行ったらええよ」と勧めてくださいました。そういう選択肢もあるのかと気付き、夜間で北海学園大学に通い始めました。昼間は北大で働き、17時になったら自転車で学園大に行って、大学を行ったり来たりの生活でした。

寳金 その時に学んだことは、今の仕事にも役に立っていますか。
伊藤 2つの大学を行き来して思ったのは、大学は単に勉強するだけではなく、知見を広げて引き出しをたくさん作るところだということです。「学び方を体得するところ」でもあって、その経験がすごく大事なんだなと。普通の公務員で終わったら体験できなかったと思うので、とても貴重でした。
寳金 その後の起業の上で、大学に通って学ばれたビジネスモデルは、知識としても重要だったのでしょうね。
伊藤 僕が卒業した高校は、商業高校ではないのになぜか簿記の授業があって、簿記3級を取っていたので、経営について学ぶ下地はできていました。大学で経営に関する授業を受ける上で、それはすごく助かりました。
寳金 職場が工学部で、職員も勉強しやすい環境だったこと。高校で少しビジネスに触れ、それを北海学園大学で勉強したこと。ある種、ミラクルな組み合わせだなと思います。起業されたのはどのようなきっかけだったのでしょうか。
伊藤 1985年から10年間、北大職員としてお世話になる中で、インターネットの存在を比較的早い時期に知っていました。当時、僕はプライベートでギターを弾いていて、海外のクリエイターと趣味でコラボレーションしていました。自分で作った曲をフロッピーディスクに入れてエアメールで相手に送るのですが、そこに相手が音を入れて送ってくるまでに何カ月もかかるんです。そうするともう、創作のパッションが思い出せなくなって続かないんですよ。でも、インターネットなら瞬時に送れる。「このインフラが世の中を変えていくんだ」と衝撃を受けました。これは公務員をしている場合ではないぞと。
寳金 私も1986年にカリフォルニア大学でインターネットと遭遇しました。論文をワードのファイルにして、それを送ると届く。今では当たり前ですが、やはり衝撃的でしたね。しかし、退職は大きな決断だと思いますが、何か先の当てがあったのでしょうか。
伊藤 辞めてから始めたというより、始めてから辞めた形です。自分で作った「音」のライブラリーが結構な量になったので、アメリカの音楽雑誌に広告を出して販売したのがスタートでした。当時はコンピュータが出始めた頃で、電子機器をつないでシステムを自分で作り、世の中にある音をマイクで録音しまして。作った音をフロッピーディスクで郵送していました。
寳金 それは英文の雑誌ですよね。コンピュータミュージックに特化したアメリカの雑誌とは、それ自体がレアですよね。
伊藤 80年代後半で、まだインターネットがなかったので、3行50ドルの個人広告を出して音を輸出していました。そのうち海外から「音を作っているんだけど日本で売ってくれないか」という逆オファーが届くようになって。90年代初めに円高が進んだので、日本にいる僕が、海外から仕入れた音を日本の雑誌に載せて販売すればいいと思いつき、輸入販売に切り替えました。それが現在の会社の原形ですね。
寳金 音に特化した仕事をされていた中で、初音ミクが誕生したいきさつをお聞かせいただけますか。
伊藤 「自分で音楽を作るためのソフトウェア」の販売を、会社設立の1995年から今も続けています。初音ミクは、キャラクターのように認知されていますが、「コンピュータに歌を歌わせるソフトウェア」です。当時、ドラムやギターなどあらゆるソフトを販売していましたが、唯一、「歌を歌うソフト」はなかった。ヤマハさんがその技術を開発したと聞き、それを基に当社で商品化したのが2004年の「MEIKO」という初代のソフトです。初音ミクは、2007年に開発した3番目のボーカロイドなんです。
寳金 なぜ爆発的にヒットしたのが初音ミクだったのでしょうか?
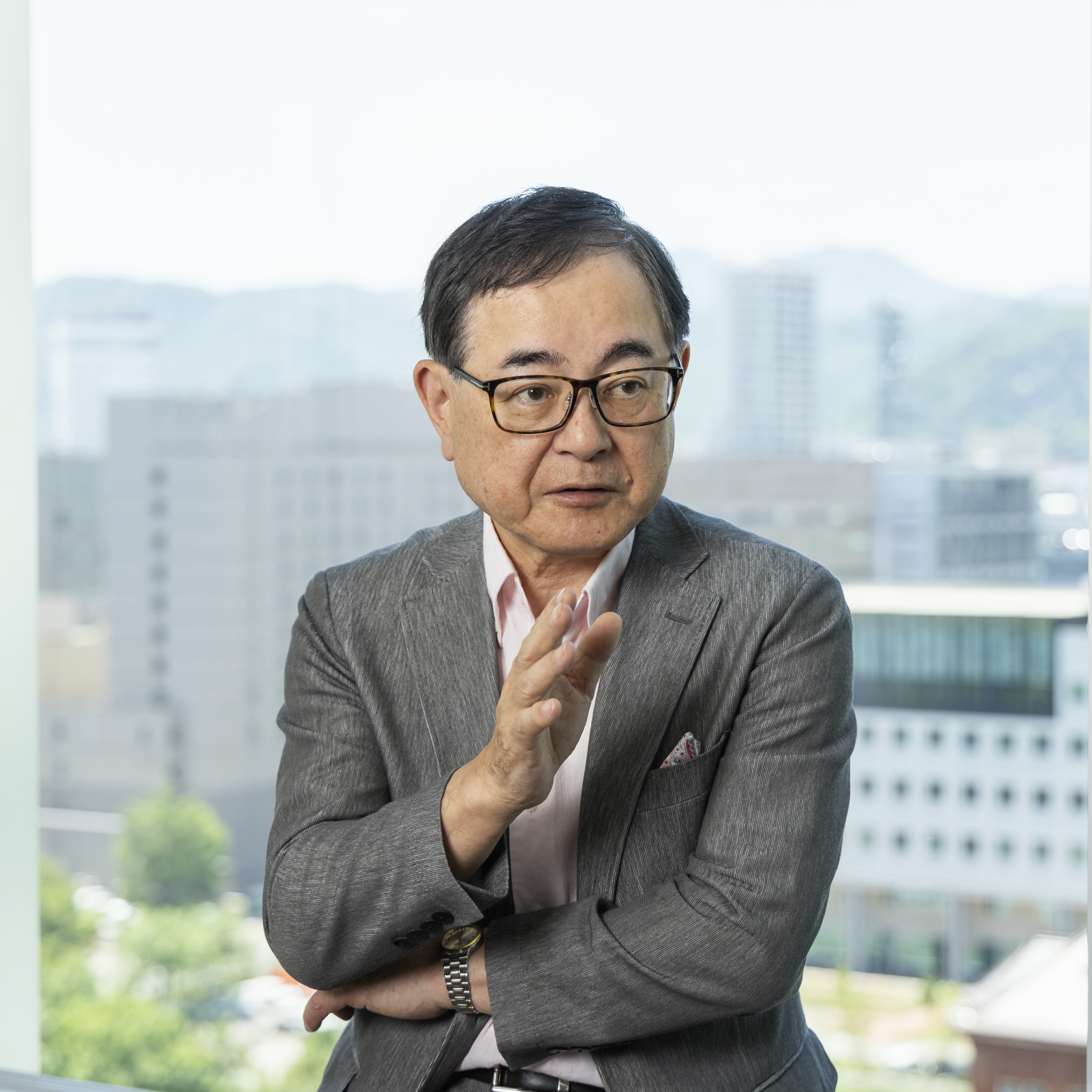
伊藤 いくつか要因がありますが、大きいのはYouTubeやニコニコ動画の登場です。こうした動画共有サイトでクリエイターが作品を発表できるようになり、初音ミクはブレイクしました。それから、アニメ等で活躍している声優さんの声を初めて起用したことですね。キャラクターのイラストも、発売に合わせてクリエイターの方に描いていただきました。
寳金 初音ミクを使った二次創作をフリーで認められていますよね。
伊藤 初音ミクは、音楽を作るソフトウェアなので楽器といえます。ピアノで曲を作ってリリースするのに、ピアノメーカーに許諾は取らないですよね。インターネット上で利用してもらうことで存在も広がりますし、クリエイターの皆さんに委ねようと思っていました。
寳金 初音ミクは地域連携においても活躍していますが、札幌に本社を置くことも含め、地方との関わりはどのようにお考えですか。
伊藤 インターネットが出てきた時、その可能性を高く感じて、音楽のビジネスでも出版でも、地域のハンディキャップを埋めるのではと思っていました。札幌に本社を置くのもそうした理由からです。クリエイティビティにおいて、地方で活動を続ける人たちを応援したい気持ちがありますし、インターネットを使って札幌を盛り上げていきたい。そのような思いから、雪まつりに「雪ミク(初音ミク)」の雪像を作り、雪ミクが北海道を応援するフェスティバル「SNOW MIKU」を開催しています。
寳金 これもぜひ伊藤さんに伺いたかったのですが、生成AIについてはどのような展望をお持ちでしょうか。
伊藤 今後どのように進化するのか興味深いですが、文明の必然だと思っています。電気が特別だった時代があり、現在はインターネットがインフラの前提にあります。それと同じで、AIの存在を前提に文明が進歩していくはずです。大昔、イメージが壁画で具現化され、その後、紙と筆記具が普及したのと同様、AIは新しいペンのように使われていくものではないでしょうか。
寳金 今は、AIにできない事を皆が探している気がします。
伊藤 AIにできない事というより、AIが人と調和する世界が理想かなと思います。鉄腕アトムのように日本は早い段階からフィクションという形でそのような世界を描いてきましたよね。
寳金 AIと調和する社会を日本は先行して実現できるかもしれないですね。7月に出版された著書も、ぜひ拝読します。本日はありがとうございました。
|
北海道大学総長
寳金 清博 HOUKIN Kiyohiro 1954年、北海道出身。北海道大学医学部卒業。医学博士(北海道大学)。1979年北海道大学医学部附属病院等に勤務。米国カリフォルニア大学デービス校客員研究員等を経て、2000年北海道大学大学院医学研究科助教授、2001年札幌医科大学医学部教授、2010年北海道大学大学院医学研究科教授に就任。2013年北海道大学病院長・北海道大学副理事、2017年北海道大学病院長・北海道大学副学長を歴任し、2020年10月から現職。 |
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 代表取締役
伊藤 博之 ITO Hiroyuki 1965年生まれ、北海道出身。高校卒業後、北海道大学事務職員として勤務しながら、北海学園大学を卒業。1995年にクリプトン・フューチャー・メディア株式会社を設立し、効果音やBGM、携帯電話の着信メロディなど音に特化した事業を展開。2007年に発売した歌声合成ソフト「初音ミク」が大ヒット。2008年より北海道情報大学情報メディア学部客員教授、2013年より京都情報大学院大学教授。 |
| 前のページへ | 目次へ | 次のページへ |