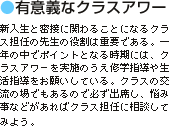 |
 |
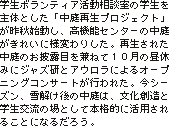 |
 |
 |
| 近年、大学生に対して、社会に巣立っていくうえでの基礎学力や専門知識の習得に加えて、コミュニケーション能力や実行力、積極性など「人との接触の中で仕事をする能力」が重視されつつあります。(参考・社会人基礎力研究会〔経済産業省〕中間とりまとめ) また、厚生労働省における「若年者の就職能力に関する実態調査」の結果によれば、企業が採用に当たり重視する能力に関して、半数以上の企業が「コミュニケーション能力」「基礎学力」「責任感」「積極性・外向性」「資格取得」「行動力・実行力」「ビジネスマナー」を重視していることが明らかになっています。 社会人基礎力などと称されるこうした能力は、元来、自然と身に付く能力と考えられていましたが、昨今の若者には、その能力が低下していると指摘されています。 古くから学生の自主的活動は、人間形成の上で有益であるとされ、正課活動と両輪として課外活動が奨励されてきました。しかし、近年では学生が大学祭を自主開催できない大学が増えてきたり、厳しき伝統を避けたエンジョイサークルが多いと言われています。 はたして北大生はいかに! 幸い本学の大学祭実行委員会の奮闘ぶりは言わずもがなであり、体育系、文化系サークルもまだまだ活発な動きが見られます。さらに、2001年度から、当時の総長の発案で、学生の意欲を応援すると銘打った「北大元気プロジェクト」が始まり、財政支援等を受けてユニークな活動を行っています。 今後も北大生らしいユニークな発案で、大学の活性化や地域連携につながるような活躍を期待しています。 |
| 去る11月2日(日)、札幌コンサートホール「キタラ」(以下「キタラ」)において、北海道大学交響楽団(以下「北大オケ」)の第116回定期演奏会がありました。 当日開場15分前には、多く北大オケのファンがキタラにつめかけ、長蛇の列ができていました。 私自身がキタラで北大オケの演奏を聴いたのは今回が初めてでしたが、17年前に札幌市民会館ホールでの演奏会と比較すると、劇的に演奏技術が向上しており、特に透明感のある繊細な弦楽器の響きに驚きました。 キタラの音の響きについては、国内外のプロの演奏家から素晴らしいと絶賛されていますが、学生(北大オケ)の話でも、キタラのホールを使用すると、心地よい残響に包まれて、自分達の演奏が上手に聞こえるそうです。 今回のプログラムの前半は、モーツァルト「歌劇『魔笛』の序曲」、正指揮者川越氏の作品「合奏曲小品二題『静』と『動』」、ドヴォルザーク 「交響詩『野鳩』」の小品であり、プログラムの後半は、パイプオルガンとピアノを使用する豪華で華麗なサンサーンスの「交響曲第3番ハ短調『オルガン付き』」でした。 特に、サンサーンスの交響曲については、気合いの入った完成度の高い演奏で、冒頭の流れるような弦楽器のアンサンブルから、一気に「音楽の世界」に引き込まれました。 終盤、キタラが誇るパイプオルガンの荘厳で重厚な響から音楽が始まり、弦楽器が刻む行進曲風の旋律から、凱旋パレードのような大団円を迎える終楽章は、パワフルで圧巻でした。 鳴り止まんばかりの拍手は、社交辞令ではなく、多くの観客が音楽に感動して、満足されたことを示していました。(H) |
| 最初は気が重かった。サラリーマンにとっての土曜日は仕事のストレスを癒すために欠かせない休日であるはずなのに…、昼から晩まで学生行事に付き合わされるのはごめんだと思った…。 10月18日(土)、今年で2回目となる「北大大集合2008 vol.2」を見に行かされた…。「北大大集合」は、文字通り、本学学生サークルが一同に集まってステージ発表を一般向けに行うイベントで「北大生の活動を一度に鑑賞できる絶好の機会」というのが売りになっている。しかし、如何せん時間が長い。午前11時から夜の20時過ぎまで延々と続く。中には興味のあるサークルもあるが、途中途中でうるさいバンドが何度も登場するのをプログラムで知った時は気が滅入った…。 しかし、そのイベントに教育熱心な佐伯総長が出席されると聞いて、事態は急展開!行かない訳にはいかなくなった…。第2部の開始前に行われる総長挨拶に合わせて着席。最初からいたような顔をして、第2部の開始を見守った。 第2部は、いきなり軽音バンド「青空教室」の演奏で始まった。普段、サークル会館に響き渡る絶叫を十二分な心構えで待ち構えていたせいか、高校時代の同級生で構成された「青空教室」の歌声は上質で耳に心地よく、女子学生のドラムさばきも格好良かった。続く映画研究会も玄人はだしの自主映画を上映。ステージ発表の合間には、今年のミス日本「空の日」に選ばれた女子学生が特別ゲストとして小気味良いコメントを添えた。MCの軽快な進行も相まって、知らないうちに自分の中で受け入れ体制が整っている…。ひょうたんを使ったアフリカの楽器「バラフォン」という木琴の演奏を目をつぶって聴き入ったときは、頭の中に象やライオンが駆け巡るアフリカ大陸が広がった。音楽系サークルに対抗して「奇術研究会」は、純朴そうな学生が巧みなトークで客席を沸かせた。そして、長い縄の両端にボールがついた「メテオ」という道具を操り、見事なジャグリングを披露した。練習では何度もボールをメガネにぶつけて壊したという。コンタクトで臨んだ本番の姿は実に凛々しかった。終わってから「素晴らしかった」と声をかけた時のハニカミ加減がまた学生らしかった。 最早、自分の中でここまで盛り上がってくると帰るタイミングを逸してしまう。 第3部では感動の度合いが一段と増した。竹でできたインドネシアの打楽器「アンクルン」を使った留学生たちの「涙そうそう」を聴いたとき、そして、知的発達障がいのある子どもたちと一緒に元気一杯に踊るYOSAKOI学生のはつらつとした姿を見たときは、ついウルルンとなってしまった。けれども、留学生たちのリードでステージと客席が一体となって「マカリナ」を踊りだした時は、逃げ腰になった情けない自分もいた。 こんなはずではなかった。 そんなこんなで第4部まで見入ってしまった。義務感で出かけた学生イベントであったはずなのに、学生それぞれの才能と思いの強さに感化されてしまった。 この感動をうまく伝えて来年の誘いにつなげようとするつもりはない。ただ、物事には、いってみなきゃ、やらせてみなきゃわからないことが大いにあるということだけである。(K) |
 |
| 1月17日(土)、18日(日)に実施された大学入試センター試験の期間中、「北海道水環境ユースWACCA(ワッカ)」の学生たちが、本学の中央ローンにたくさんのスノーキャンドルを設置し、受験生に激励の灯をともした。 センター試験期間中は、平穏無事に終わることを優先しているため、受験生への激励活動はいろいろな制約を受けることになるが、前年の小規模な取組が成功裏に終わったこと、また、水をテーマに活動しているだけあって、彼らの純粋(水?)な気持ちが伝わった。 企画代表の青江翔太郎君以下12名の学生たちは、前夜の寒空の中で準備を進めた甲斐あって、受験生に見てもらえたことを喜んでいた。 昨今の学生支援は、学生の思いを理解し、実現にあたっての問題点を示し、時には解決策を一緒に考えてあげることも必要であるが、今回は、責任ある立場の思い切った判断と、その信頼に気持ち良く応えた学生たちの奮闘ぶりが「灯」となった素晴らしい取組であった。(K) |
 |
| 第2学期は、どこのサークル・団体等でも幹部交代の時期だ。いままで普通の部員だった学生に役職なんかがついたりして、新たな責任感が培われるとともに、どんどんとリーダーシップを身につけていくのだ。 さて、年末・年始の時期に新幹部になった学生が窓口にやってきた。 「よう、元気?」と顔なじみの福間健君(水産1年)に声をかけると、「このたび、北大祭全学実行委員会の委員長になりました。」「そうでしたか…。」月見草を好む自分にとって、肩書きのある人には声が改まってしまう…。同行してくれた山口しおりさん(医学1年)と永見俊也君(法学1年)とともにご挨拶をいただき、ちょうどクリスマスの時期ということでクッキーのプレゼントまでいただいた。 ※ ナガミ君は恥ずかしいとの事で写真なし また、年始めには、全学新入生歓迎実行委員会の委員長になった道林千晶さん(理学2年)が来てくれた。今年は成人ということで、栃木県の実家に帰省していたとか。まさしく受験シーズン到来のいま、「受験生応援パックやクラオリパックの準備に余念がない」とのことで、いろいろなプレッシャーで満杯だという。普段は、ニッコリメガネの元気な道林さんだが、写真撮影の時だけは、メガネをはずしておすまし顔になる。よーく見ると美形の成人に様変わりしており、1年生の頃からはやっぱり身も心も成長しているんだと実感した。2団体の来訪に感謝した次第♪(K) |
 |