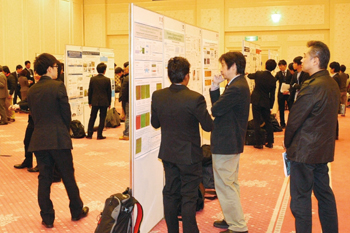12月16日(火)・17日(水),シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロにおいて,第15回RIES-Hokudai国際シンポジウムを開催しました。このシンポジウムは,電子科学研究所が中心となって毎年開催し,その年毎に漢字1文字でテーマを設定しています。今年度は,「振動(oscillation)」,「共鳴(resonance)」,「調和(harmonization)」,「協調(connections)」,といった意味を持つ「響」という漢字をテーマに選びました。本学をはじめ,国内では東北大学,東京工業大学,大阪大学,九州大学,筑波大学,沖縄技術大学院大学から,海外ではローレンス・バークレー国立研究所(アメリカ),精華大学(中国),国立陽明大学(台湾),及び企業からの総勢130人を超える大学院生,ポスドク,研究者などの参加者が集いました。本学は,電子科学研究所のほかに理学研究院,先端生命科学研究院,情報科学研究科,工学研究院から参加がありました。
このシンポジウムでは,5セッションで国内外の14名の招待講演者と,1名の基調講演者が「響」という漢字をテーマに講演を行いました。各セッションのテーマは,「生物機能における協同性」,「機能性物質における調和現象」,「スマート材料の集団相運動の振動界面」,「フォトニクストと光科学における振動と共鳴」でした。さらに,今年度は「新しい共同研究を目指して」というセッションを新設し,電子科学研究所が主催する「北海道大学ニコンイメージングセンター」及び「ナノテクプラットホーム事業」に関する講演を行いました。また,東京工業大学応用セラミック研究所の細野秀雄教授が基調講演を行い,「響」にちなみ,新規機能物質の創成において,基礎から応用を見据えた学際的研究の重要性を,とてもわかりやすく発表いただきました。
電子科学研究所で研究する大学院生の参加者に加え,他部局の大学院生の参加を募った結果,9名の参加がありました。ポスターセッションでは,昨年度に引き続き,素晴らしいポスター発表を行った若手研究者を表彰するポスター賞を授与しました。ポスター発表の時間以外にも,懇親会及び懇親会後の時間を利用して,招待講演者の先生方と,自身のポスターの前で熱心に研究の紹介をする大学院生の姿がとても印象的でした。今回のポスター賞の特徴は,年長の研究者の投票によって受賞者が決定するところにあり,受賞 者が関連する分野の科学者や専門家との連携を持ち,自身の科学者としての新分野の共同的な創造につながる機会が持てるようになっています。
2日間のシンポジウムを通じて,学際的な議論の促進や,将来の共同研究につながる新たな「ネットワーク」が構築できました。電子科学研究所以外の学内参加者を含む大学院生,ポスター賞受賞者の多くから,「様々な研究者や学生から直接指摘等をいただくことができ,研究活動を続けていく上でとても参考になった」とコメントがありました。
このシンポジウムは,電子科学研究所が,ファイブスター・アソシエーション(北海道大学電子科学研究所,東北大学多元物質科学研究所,東京工業大学資源化学研究所,大阪大学産業科学研究所,九州大学先導物質化学研究所),及びナノマクロ物質・デバイス・システム創製アライアンス,物質・デバイス領域共同研究拠点との共催により,開催したものです。ここにご協力いただきました関係機関各位に心より感謝いたします。
このシンポジウムでは,5セッションで国内外の14名の招待講演者と,1名の基調講演者が「響」という漢字をテーマに講演を行いました。各セッションのテーマは,「生物機能における協同性」,「機能性物質における調和現象」,「スマート材料の集団相運動の振動界面」,「フォトニクストと光科学における振動と共鳴」でした。さらに,今年度は「新しい共同研究を目指して」というセッションを新設し,電子科学研究所が主催する「北海道大学ニコンイメージングセンター」及び「ナノテクプラットホーム事業」に関する講演を行いました。また,東京工業大学応用セラミック研究所の細野秀雄教授が基調講演を行い,「響」にちなみ,新規機能物質の創成において,基礎から応用を見据えた学際的研究の重要性を,とてもわかりやすく発表いただきました。
電子科学研究所で研究する大学院生の参加者に加え,他部局の大学院生の参加を募った結果,9名の参加がありました。ポスターセッションでは,昨年度に引き続き,素晴らしいポスター発表を行った若手研究者を表彰するポスター賞を授与しました。ポスター発表の時間以外にも,懇親会及び懇親会後の時間を利用して,招待講演者の先生方と,自身のポスターの前で熱心に研究の紹介をする大学院生の姿がとても印象的でした。今回のポスター賞の特徴は,年長の研究者の投票によって受賞者が決定するところにあり,受賞 者が関連する分野の科学者や専門家との連携を持ち,自身の科学者としての新分野の共同的な創造につながる機会が持てるようになっています。
2日間のシンポジウムを通じて,学際的な議論の促進や,将来の共同研究につながる新たな「ネットワーク」が構築できました。電子科学研究所以外の学内参加者を含む大学院生,ポスター賞受賞者の多くから,「様々な研究者や学生から直接指摘等をいただくことができ,研究活動を続けていく上でとても参考になった」とコメントがありました。
このシンポジウムは,電子科学研究所が,ファイブスター・アソシエーション(北海道大学電子科学研究所,東北大学多元物質科学研究所,東京工業大学資源化学研究所,大阪大学産業科学研究所,九州大学先導物質化学研究所),及びナノマクロ物質・デバイス・システム創製アライアンス,物質・デバイス領域共同研究拠点との共催により,開催したものです。ここにご協力いただきました関係機関各位に心より感謝いたします。